
・マランダン・バレエ・ビアリッツ「パストラル/田園」
・ジョアニー・ベール「un lieu à soi」「Au Pouvoir !」
・アントニー・エゲア「ミューズ」
・シルク・プリュム「最後の季節」
・ザ・バンビエスト「フェイント・メモリー」
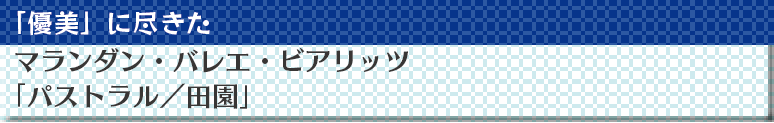
ティエリー・マランダン。大西洋側のスペインとの国境近く、バスク地方にあるビアリッツを本拠地とするバレエ団の芸術監督兼振付家で、2019年にはフランス芸術アカデミーの振付家に任命された。マランダンはクラシックバレエをベースにしているが、創作する作品はコンテンポラリーで、他のバレエ団には見られない独特の踊りと美学が高く評価されている。また、音楽に対する分析のセンスに優れていて、作曲家が意図したイメージがまさにこれだったのではないかと思わせるような振り付けで、視覚化された音楽、そして生きる美術作品を思わせる作風が特徴だ。
今年の新作は、ベートーベン生誕250周年を記念して、ベートーベンの生まれ故郷であるドイツのボンのオペラ座からの依頼を受け、ドイツ公演の前にパリのシャイヨー国立舞踊劇場での世界初演を迎えた。

ⒸOlivier Houeix
「パストラル/田園」は、交響曲第6番「田園」をベースに、「アテネの廃墟」と「カンタータ112番 静かな海と楽しい航海」を加えた3部構成。金属の櫓が組まれ、四角い升の中で何かを求める人は、黒いしっかりした素材のドレスを身に纏っている。現れた4人のミューズが彼を支えるように踊り、一瞬にしてドレスを剥ぎ取ると、白い軽やかなワンピース姿になるが、櫓から落ちて力尽きた。現世のしがらみや悩みから解放されて精霊となった男は、美を求めて旅をする。アテネの古代ギリシャから現代の街中までのイメージが交差するシーンが繰り広げられる。そして最後は、肌色の全身タイツになったダンサーたちが輪になり、ユートピアを描く。書いてしまえばこれだけなのだが、ひとつひとつのシーンが絵になっていて、過去から現代まで、そして世界のあちこちを旅しているような、見る側の想像を刺激してくれる作風に引き込まれた。そして何よりメインを踊ったユーゴ・レイヤーの美しこと! 彼は男だが、柔軟でしなやかな踊りは、男とも女ともつかない不思議な雰囲気を醸し出していた。昔は、女性がたくましく、「体操選手のようなダンサーたち」と言われていたが、近年は動きがずいぶん柔らかくなった印象を受けていたのだが、この作品に関しては完璧なユニセックス。男女ともロングドレス、ワンピースなどの揃いの衣装で、振付もしなやかな中に力強さがあり、男のようで女、女のようで男という中世的な雰囲気が、ベートーベンが描いた「田園」のイメージをさらに膨らましている。これは、マランダンの想像力の豊かさだけでなく、音楽を分析する感性の鋭さによるものだ。古典バレエ作品のように美しい構成と、20人のダンサーが織りなすコンテンポラリーダンスの動き面白さに魅了された。
「美は世界を救う」というマランダンの信念が、確固たる形で現れた作品だ。(2019年12月17日シャイヨー国立舞踊劇場)

ⒸOlivier Houeix
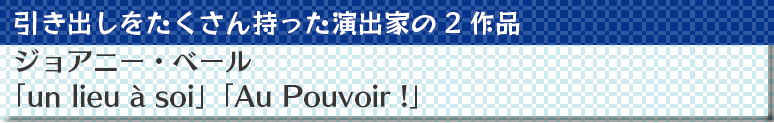

「un lieu à soi」ⒸJohanny Bert
ジョアニー・ベールは演出家、マリオネティスト(人形師)。でもダンス作品も作る。最初に知ったのはアビニヨン・オフ。どうしても都合がつかずに見に行けなかったが、運良くこの作品「Le petit bain」はオペラ座アカデミーで取り上げられて、バスティーユオペラのアンフィテアトルへ見に行った。(2018年5月の記事)子供向け作品といえど、たくさんのアイディアがあって、おしゃれで美しくて、大人も子供も顔をほころばせて会場を後にして行ったのが印象に残っている。
今回は、演劇とマリオネットの2作品を所見。期待通り、いやそれ以上で、作品を作る意図がはっきり見えることが素晴らしい。特にマリオネットの「un lieu à soi」は、多くのことを考えさせられた。un lieu à soiとは、自分の居場所のこと。流れ行く時の中で、自分はどこにいるのだろう。流されているのか、それともその流れに乗っているのか。現在クレルモン=フェランのコメディ劇場は、その隣に新しく2劇場を建設中で、この建設現場をテーマに作成された短編映画という触れ込みだったが、実際は人形劇+映像のスペクタクルで、古いものが壊されて新しいものが生まれる過程を語っていた。
かつては長距離バスの発着場として賑わった建物は、伽藍堂の箱となり、錆が出ている。ここが新しい劇場として生まれ変わるための工事が始まった。この映像が消えると、舞台に置いてあった木の棒が動き始めた。とことこ歩いて消え去ると、ブーという音と木屑が落ちてきて、「僕」が出来上がった。そして「僕」は工事現場にいる。瓦礫を動かしてみる。開いた壁の穴から工事の様子を伺う。丸く開いた穴から出ようとしたけれど、力尽きて落ちてしまった。隣の人が思わず「あ、死んじゃった」と声を出した。まるで生きているように人形が動くものだから、つい感情が入ってしまったのだろう。しかし、「僕」は死んでいなかった。瓦礫をゆっくりと動かして、なんとか自由になれた。すると僕の生みの親のベールがやってきて「僕」を起こしてくれた。彼に操られて発着場のモザイクタイルの周りを歩く。昔の建物の床は手が込んでいた。手作業で敷き詰められたタイル張りの美しい床。これも壊されてしまうのだろうか。天井も美しい絵が描かれている。 クレーン車に乗ってみる。まだコンクリ剥き出しの廊下を飛んでみる。工事の人に話しかけたら踊り出した。コーン・アウギュスティンとロザルバ・トーレス・ゲレーロではないか! どうりで踊りがうまいと思った。アマチュア壮年舞踊団のリフティングの面々もたくさんの「僕」を持って踊っている。時は流れ、古いものは新しいものに代わっていく。ノスタルジーもあるけれど、新しい劇場がかつての発着場のような活気を取り戻してくれるだろう。そして「僕」は、操ってくれた紐を切って自由になる。未来へ!
こんな物語は、舞台上半分がスクリーン、下半分でマリオネットの二重構造で語られる。ベール自身が人形を操り、彼の足と人形のコラボレーションや、ベルトコンベアーを使った演出、また映像の中で飛んだシャボン玉が、実際に会場に降って来るというサプライズなど、小さな空間からたくさんのアイディアが飛び出す。そして、アイディア倒れにならず、これからさらにクレルモン=フェラン市の舞台芸術が豊かになるという希望を見せてくれたのがいい。ベールは2年間この劇場をレジデンスとしていて、そこで感じたことを作品にしたのだ。
その前に見たシーガールズという4人の歌って踊れる女優と3人の演奏家のグループの「Au Pouvoir ! 権利を!」という作品の演出もよかった。ベールはたくさんの引き出しを持っていて、ひとつのシーンから思いもかけないような小道具が飛び出したり、想像を膨らませてくれたりする。ベールの作品の振付担当が、コンテンポラリーダンスの若手振付家ヤン・ラバランドで、センスのあるアーティストと長年にわたって起用していることで、安定して作品を作ることができるのだろう。振付家ではないけれど、注目に値するアーティストだ。(Au Pouvoir ! 11月20日、un lieu à soi 12月19日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)
(注:以前の批評では名前表記をジョニーとしていましたが、ジョアニーの間違いでした訂正してお詫びします。)

シーガールズ
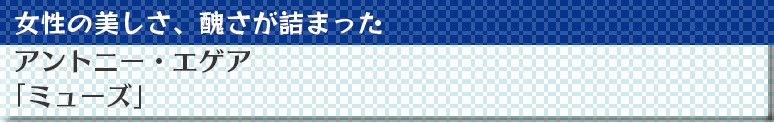
ピアノの繊細な音色がヒップホップとこんなにうまく融合するとは思ってもいなかった。薄暗い明かりの中に、2台のグランドピアノが柔らかい照明の中に浮かび上がった。ふたりの女性がそれぞれのピアノにすわり、ゆっくりと、そして優雅に持ち上がった手が鍵盤に静かに降りて作品は始まった。
「牧神の午後」のプレリュードが静かに響くのに呼応して、グランドピアノの下に不思議な形が現れた。ゆっくりと動くその姿は、人のような、虫のような。次第に明かりが入ると、それは鏡のような床に映ったふたりのダンサーだと分かった。なんともミステリアスな始まりは「牧神の午後」にふさわしい。ふたりのピアニストとふたりのダンサー。共に女性で、まさにミューズが奏で踊る作品だった。ビゼーのカルメン、スレイマン・ディアマンカの「恋するミューズ(Muse amoureuse)」、サン=サーンスの「死の舞踏」と続き、最後はラヴェルの「ボレロ」で締めた。「牧神の午後」でのミステリアスなイメージと打って変わって、「カルメン」では現代の若々しい女性を、グランドピアノをぐるりと回して、恋するミューズは衣装を着替えた。女はいつも優しいのではない。嫉妬もするし、悪戯もする。「死の舞踏」というより死の対決-ダンサーVSピアニスト、ダンサーVSダンサー及びピアニストVSピアニストの闘い、やっぱり女は怖いかも。最後のボレロで女性パワーを見せつけて、お茶目で優雅に終わった。
アントニー・エゲアの女性をみる目は鋭い。良いところも悪いところも承知の上で、女性の多面性をヒップホップのテクニックを使って見せる。時に男性は女性より女性を知っているのではないかと思う。女性に限らず、人を冷静に観察して、良いところを引き出すのがうまい振付家だと思う。そこがエゲアの作品が好きな理由。ストのせいか客席に空席が目立ったのが残念。(12月13日大学都市劇場Théâtre de la Cité)

Ⓒpierre-planchenault


Ⓒbenoit dochy
20年ぶりに見たシルク・プリュム。やっぱり楽しい、やっぱりポエム。寒い季節に身体がほくほくする公演だった。
赤い花びらがハラハラと舞う舞台。でも夜になればここは怪しい森になる。煙が出る大きな籠を背負った旅人の一行、牧師は一瞬にして服を剥がれ、身体がグネグネの人が踊り、ケンタウロスとは程遠い(失礼)太っちょのおじさん(腹回りがまん丸で、まるでドラム缶)の演技には驚くやら吹き出すやら。騎乗の人を演じながら足は馬のステップで馬の鳴き声を発し、突如人間の声で話し出す。人かと思えばいきなり寝転んで、馬が背中を掻く様子。かと思うといつの間にかゴリラになっている。この珍芸は一見の価値あり。開脚した人をモップに見立てて床掃除など、笑いと驚きが次から次へと出てくる。よくまあこんなにアイディアがあること! さっと降りた幕の前での寸劇の間に場面転換するから、約2時間の公演中、休憩も暗転もなくシーンが変わる。ほんの数分でこれだけ装置が変わるとは、まるで手品のようだった。
ここにはなんでもある。アクロバット、ダンス、演劇、音楽、笑いと驚き、そしてポエム。一方通行の演技ではなく、観客とのやりとりもあって、アドリブ対応がうまいから知らないうちに作品に入り込んでいる自分がいる。それがシルク・プリュムの魅力だ。日常の雑多を忘れて心から笑える公演って、素晴らしい。
創設して35年になるというカンパニーの人気は衰えることなく、フランス各地を回っている。それだけリクエストが多いのだ。パリでも毎年ラ・ヴィレットで公演している。(12月20日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

Ⓒyves petit
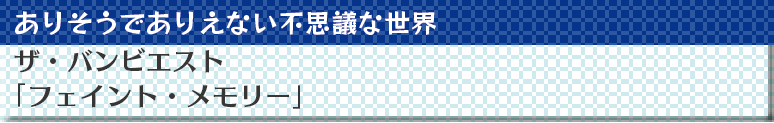
菅沼伊万里率いるザ・バンビエストがパリのエスパス・ベルタンポワレで上演した「フェイント・メモリー」は、石壁の小さなスペースを生かした作品に仕上がっていた。
食べる、飲むという日常の行為が壁に映し出された。ん? なんか変。編集によって人物がすり替わっているのと、不規則な石の模様が微妙な味を出している。4人のダンサーは揃いの服とカツラをつけて、人形ぶりのような動作が繰り返されるが、少しずつ変化していく。アンドロイドっぽいけれど、脚を高くあげたりしているから、人間なのだと妙な納得。
短いシーンが次々と流れ、脈絡がありそうでない夢を見ているような気分になる。現実なのか幻想なのか。実際に見ているのだけれど、時々現実離れしているような錯覚に陥った。
ベルタンポワレの独特な空間をうまく利用した演出がいい。(11月27日エスパス・ベルタン・ポワレ)

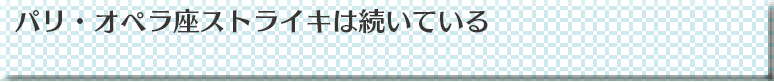
12月5日から続く年金改革に反対するストライキのため、パリ・オペラ座の年末公演「ライモンダ」と「ル・パルク」は、5日以降31日まで全て公演中止となった。23日に予定されていたエレオノーラ・アバニャートの引退公演(ル・パルク)や、オペラ座バレエ学校のデモンストレーションも中止となったのは残念な結果だった。
パリ・オペラ座のダンサーは、ルイ王朝以来の契約で、一般より早い42歳での引退が認められている。他にも優遇が認められている職業があるのだが、現政府はこれを全て廃止して一本化し、全ての職業に就く人を64歳定年にしようという計画だ。これに対し、オペラ座のダンサーは、バレエが怪我と隣り合わせで肉体を酷使する職業であり、64歳まで踊り続けることは不可能だと反対。ダンサーだけでなく、パリ管弦楽団もストをしているので、オペラ公演も中止。
ボルドー国立バレエ団もストライキをしており、装置なし、一部の照明なし、あるいは公演中止という状態があったことも付け加えておこう。
というわけで、パリ・オペラ座の「ライモンダ」と「ル・パルク」の公演批評はありません。
https://www.youtube.com/watch?v=57ouCoN1Su8
https://actu.orange.fr/france/videos/greve-54-annulations-de-spectacles-a-l-opera-de-paris-CNT000001mqmwh.html#plmAnchor
https://actu.orange.fr/france/videos/greve-le-coup-d-eclat-des-danseurs-de-l-opera-de-paris-CNT000001mlUaw.html
|

