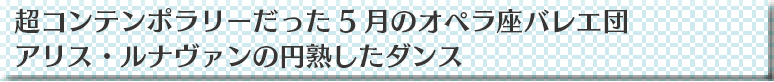
今月のパリ・オペラ座は、アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルのソワレと、ジェームス・ティエレ、ホフェッシュ・シェクター、イヴァン・ペレス、クリスタル・パイトの4本立てという、コンテンポラリーが2演目だった。この全く違うテイストの5人の振付家作品をどこまで踊りこなせるか、そこに興味津々で見に行った。

「弦楽四重奏第4番/Quatuor N°4」 ©Benoite Fanton/Opera national de Paris
まず、4月27日から5月12日まで11回上演されたアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルのソワレは、「弦楽四重奏第4番/Quatuor N°4」「大フーガ/Die Gross Fuge」「浄められた夜/Verklärte Nacht」で、3作品とも非常によく踊りこなされている。欲を言えばかなりお上品で、ローザスカンパニーとは異なるけれど、カンパニーを真似すれば良いというものではなく、いかにダンサーが作品を理解して個性を発揮するかが作品の良し悪しとなる。
「弦楽四重奏第4番/Quatuor N°4」は、4人の若い女性が、青春を謳歌するがごとく、楽しくおしゃべりをして、悩みを話したり、色気を出したり大人ぶってみたりしながらはしゃぐ姿が魅力的な作品だ。オペラ座のダンサーは少し優等生的なところもあるけれど、古典作品が好きだと言っていた藤井美帆が、ショートカットでお茶目な笑顔を見せながら踊っていたのが印象的だった。表情豊かで爽やかで、汚れのない乙女たちの無邪気な会話が微笑ましい。

「弦楽四重奏第4番/Quatuor N°4」 ©Benoite Fanton/Opera national de Paris
「大フーガ/Die Gross Fuge」では、紅一点のアリス・ルナヴァンが7人の男に負けないキレのある踊りで、圧倒的な存在感を見せた。さすがエトワールは貫禄が違う。ピタリと形に入るから、動きにブレがなく、メリハリのある振り付けを楽しみ、パートナーを組む相手との無言の会話が見える。まさにこの舞台に生きている! という感じが素晴らしかった。男性では、アンドレア・サリとタケル・コストがノリの良い動きをしていたのが印象に残った。期待のポール・マルクは、まだ体の芯から振り付けを楽しんでいるようには感じられなかったのが残念。もう一つ気になったのが照明だった。以前にクレテイユのMACで見た時には、サイドからの強い光のコントラストによって、ダンサーの動きが見えたり隠れたりするのが面白かったのだが、今回はそこまでの照明のコントラストがなく、全体がほぼ均等に見えていたのはなぜだろう。MACでできたことがガルニエ宮でできないはずはないのだが。

「大フーガ/Die Gross Fuge」 ©Benoite Fanton/Opera national de Paris
そしてラストの「浄められた夜/Verklärte Nacht」。下手奧が森の入り口なのだろうか、木立の間に立つ男のシルエットが、月光の微妙な移り変わりにゆっくりと浮かび上がっては暗闇に紛れる。背中を向ける男に寄り添う女。振り向いてくれない男への失意を表すかのようにうなだれ、落ち葉の舞う土にひざまづき、背中を丸める。この静かな悲しみを演じたのは、アリス・ルナヴァン。先ほどの「大フーガ」とは全く違う面を見せるルナヴァンの演技の厚さに再び感心。レオノール・ボーラック、アリス・カトネ、リディ・ヴァレイエス、セヴリーヌ・ウエスターマン、エミリー・ハズブーン、カトリーヌ・ヒギンス、アワ・ジョアネ、アルチュール・ラヴォー、ニコラ・ポール、マチュー・ボット、アレクサンドル・カルニアト、アントニオ・コンフォルティ、ジャック・ガストウトがそれぞれの愛の形を見せる。求める者、去る者、愛し合う者。夜の闇に紛れる様々な感情が交差する。
3作品とも、ローザスカンパニーとは異なる風味だが、こうして踊る人によって作品の印象が変わるのも悪くない。(5月3日オペラガルニエ宮)

「浄められた夜/Verklärte Nacht」 ©Benoite Fanton/Opera national de Paris
圧巻だったクリスタル・パイトの「The seasons’canon」

「The seasons’canon」©Agathe Poupeney/Opera national de Paris
5月後半に見たのが、4人の振付家によるソワレで、ジェームス・ティエレの「Frôlons」、ホフェッシュ・シェクター「The art of not looking back」、イヴスァン・ペレス「The Male dancer」、クリスタル・パイト「The seasons’canon」 と、コンテンポラリーファンには、非常に興味のある演目。

「Frôlons」 ©Agathe Poupeney/Opera national de Paris
客席に着くと、係員から最初の作品はホールと大階段と大広間で行われると説明された。道理で廊下に人が多いわけだ。ブリキのバケツを叩くような激しい音がして、髪ボサボサで黒いロングコートを着た男が、大声で叫びながら、せわしなく廊下を歩き回っている。すると、黒っぽい金色の全身タイツに黒い仮面をつけた人たちが、観客の間を縫うように現れた。黒いコートの男たちは、観客から彼らを守るようにして道を作り、見学場所を探してうろうろする客にあっちに行けこっちに来いと指示している。ダンサーたちは数人が固まって踊ったり、絡んだりし、そして散っていく。上ばかりを気にしていたら、足元の黒い物体にヒヤリとした。平たい台の上に体を乗せた黒く輝く蜂たちが、足元をすり抜けていったのだ。人が素早く動いてできたスペースに、黒光りした四つ足動物が現れた。尻尾を振り、顔の前のふたつのろうそくの光に導かれるように、のそのそと、しかしものすごい威厳を持って這い回っている。すると地下から頭上にたくさんの白く光る球体をつけた人が現れた。女王蜂だ。この女王を導き、導かれるように黄金の威厳を持った蜂の群は、会場に勢いよく吸い込まれていった。舞台では大きな布が風に吹かれて舞い、中央の円形の穴からひとりずつ消えていく。女王と獣たちは、ゆっくりと見送り、バイオリンとチェロ奏者は、オケピットの中で仰向けに倒れている。怪しげな歌と音楽と、不気味なダンサーたち、そしてそれらを管理する怪しい男。ガルニエ宮は蜂の巣の中だったのだ。

「Frôlons」 ©Agathe Poupeney/Opera national de Paris
ジェームス・ティエレのちょっと不気味な世界観に覆われたガルニエ宮の雰囲気を一転させたのが、ホフェッシュ・シェクターの「The art of not looking back」。オニール八菜をはじめとする女性ばかり9人が、シェクター独特のムーブメントをこなしている。スモークが煙る中、軽く膝を曲げて足踏みしながら、太陽の光を浴びるような仕草や、体をくねらせる早い動きが、強いパーカッションとがなり声の中で綴られ、トランスにも似た感覚を感じた時に突然やってくる静寂。そして写真のように動かないダンサーたち。あるいは、機械仕掛けの人形のようにタンデュを繰り返す無表情な人たち。唐突にやってくる音楽と踊りの静と動の強烈なコントラストに目眩を覚える。

「The art of not looking back」 ©Agathe Poupeney/Opera national de Paris
それにしても、ガルニエ宮の美しさとは対照的なしゃがれた男の怒鳴り声とその内容は下品とも言えるもので、唾を勢いよく吐き捨てた音には、頭の上から唾をかけられたように感じたし、それはまるでガルニエ宮をこき下ろしているようにさえ感じた。思わずわざわざこの作品を選んだシェクターを思い浮かべてしまった。

「The art of not looking back」 ©Agathe Poupeney/Opera national de Paris
これに対して、男性ばかり10人の作品を作ったのが、イヴァン・ペレス「The Male dancer」。中世の貴族を思わせるようなマントや、ドレス、あるいは風変わりな服を着た一団が、踊りながら列をなして進んで行く構成で、絵画を見ているような印象を受けた。そこに何か物語や特定の感情があるわけではなく、ひとつの集団の中のそれぞれの思いが短く綴られている。深く関わらず、距離をおきながらも、1本の絆で結ばれている集団。ダンサーの個性を生かした振り付けで、ステファン・ブリヨンの存在感、フランソワ・アリュのダイナミックな踊り、ヴァンサン・シャイエのキレのいい動き、パブロ・レガサの伸びのある踊りが目を引いたが、ここでもシモン・ル・ボルニュが良い踊りをしていて、年末に上演された「プレイ」(アレクサンダー・エクマン振付)での経験が十分に生かされているように思った。コンテンポラリー系の作品で彼はこれからもっと伸びるだろう。

「The Male dancer」 ©Agathe Poupeney/Opera national de Paris

「The Male dancer」 ©Agathe Poupeney/Opera national de Paris
クリスタル・パイトの「ザ・シーズンズ・カノン」は、圧巻だった。2度目の所見だったが、新鮮な興奮を持って見終えた。大群舞によるマス的なムーブメントは、それ自体がダイナミックだが、今回はソロやデュエットのシーンが印象に残った。見る位置によって受ける印象が違うのかもしれない。稲妻のような光の線がホリゾントを移動する中、大海原の波を彷彿するような、あるいは大地が呼吸するように波打つ群舞。その塊の中から生まれた生命が、絡み、語る。自然の中で生きる生命の強さと、生きる歓びが地の底から湧き上がるような作品に、観客総立ちのカーテンコール。マリー=アニエス・ジロ出演日に当たったはラッキーだった。やはり彼女は素晴らしい。(5月26日オペラ座ガルニエ宮)

「The seasons’canon」©Agathe Poupeney/Opera national de Paris
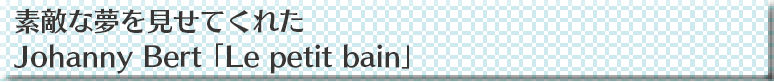
ジョニー・ベールは、フランス人の演出家。この作品は、昨年のアヴィニヨンで見逃していたので、こうしてオペラ座のアカデミーによる、最良の環境で見ることができたのは幸運だったとしか言いようがない。
触っちゃダメ、入っちゃダメとでもいうかのように、高い柵の中いっぱいに白い泡が詰まっている。学校帰りの道草か、蛍のように光るリュックサックを背負った男がやってきて覗き込んでいる。こんなところに閉じ込められていちゃ可哀想だ、一緒に遊ぼうよ、とばかりに柵を開けて、泡の塊を手に取って、丁寧に形整えて、大事そうに光るリュックにしまい込む。今度は泡の中にかがんでみる。まるで泡のかまくらに入っているみたいだ。泡を切って道を作って、隠れてみたり、浮かんでみたり、今度はオブジェを作ってみよう。雲にもなるね。雪も降ってきた。あらら、雪だるまならぬ、泡の人形が話しかけてくるじゃないですか。話して遊んで、その人形もリュックにしまって、柵を閉めて、今日の道草はここまで。泡でこんなに沢山のイマジネーションが湧くなんて、素敵! カーテンコールが終わって、席を立とうとしたら、キラキラ輝くものが舞台に。それは天井から降ってきた無数のシャボン玉だった。その綺麗なこと!
子供向けの作品とはいえ、大人だって十分に楽しめる。夢を与えてくれてほっくりした。朝の会を見たから、今日は1日気持ちよく過ごせそうだ。ガルニエ宮やオペラ・バスティーユでの大舞台も良いけれど、オペラ座のアカデミーは良質の作品を見せてくれるので、オススメ。今シーズンのダンスは終わってしまったので、9月下旬以降に来シーズンの上演演目がネットに発表される予定なので、要チェック。(5月19日バスティーユ・オペラ座アンフィテアトル)

©Jean Louis Fernandez
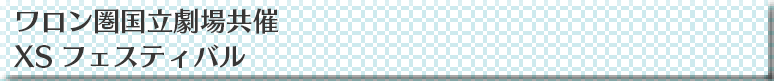
お気に入りの劇場MACクレテイユで、ブリュッセルのワロン圏国立劇場共催のXSフェスティバルが行われた。30分ほどの作品8本のうち、6本を自由に選んで見るという企画で、演劇、人形劇、ダンスが見られる。この中で圧巻だったのが、マリオン・レヴィの「トレーニング」。さすがもとローザスのメンバーで、 舞台で演じることを知っている。
興奮しているのか、息を切らして、勢い良くドアを占めて椅子に座ったものの、何が気に入らないのか、もう一度ドアを閉め直した。笑ったり泣いたり、大声出したり、踊ったり。コロコロ変わる感情を、ひとりの同じ人間が演じているとは思えないほどの勢いで進めていく。可愛いらしかった乙女がいきなり鉄製のバーを掛け声も勇ましく、重量挙げ選手のごとく持ち上げたのには、あっけにとられて吹き出した。客席との距離を取りながらも、しっかりその場の雰囲気を掴んで作品を進めていくから、全体がひとつになれる。そこがうまいと思った。
ハナ・マ振り付けの「スワン」は、ドイツ在住の三原慶祐とフランス在住の石川勇太の日替わりのソロ。私が見た日は石川勇太だった。白鳥の湖の曲の一部が流れる中、ボックスパンツ姿の石川は白いチュチュの布の塊を床に叩きつけ、駆け回り、白鳥の湖などくたばれとでも言いたいかのように、勝ち誇ったように両手を挙げる。その姿がボクシングのチャンピオンみたいだが、さて、だから何を言いたいのかが掴めなかった。白鳥になりたいのになれないのか、白鳥クソ食らえなのか、後半にもう少し発展性があると良かったように思った。(5月24日MACクレテイユ)

「スワン」 ©Boshua
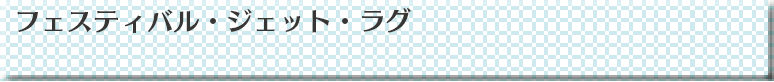
若手の発掘に貢献しているエトワール・デュ・ノール劇場。今回のフェスティバル・ジェット・ラグは、ジャグリングとヒップホップ特集。大道芸と思われがちなジャグリングは、立派な舞台作品なのだ。
ルノー・ルエの「Versatile」は、ジャグリングしながらのコント。タイトル通り「無節操な」始まりだった。ジャングラーは普通3つのボールで演じるんだよ。でも、4つもあれば、6つもある。スポーツなんだよ。と言いながら、わざとボールを落としたり、ジャンプしながらボールを飛ばしたり、目をつぶってボールを取ろうとしたり。でもハイレベルなテクニックをさらりと見せて、あっと言わせるところが憎い。サッカーボールで遊ぶように、足技を見せたり、ヘッドキックまで見せて、小さなボールでここまで遊べるのかと、感心。

「Versatile」
ボリス・クティとマイシム・サレの「ありがとう、すみません/Merci, Pardon」には、完全にはめられた。ノイズ音の中でヒップホップ系の動きをするふたり。しばらくしたら、ひとりが「こんなの耐えられない、俺は出ていくぞ」って、本当に舞台から降りてしまった。もうひとりは黙々と踊り続けている。しばらくすると、先ほど出て行った男が戻ってきて、「音を止めろ!」。相棒を捕まえて、「お前本当に楽しんでいるのか?」「嫌気がさしているに決まってるだろ、こんなノイズ音は耐えられん」。あらま、好きで踊っているのではなかったのね。こんな調子で、その後のふたりの会話と動きに笑っているうちに、スタッフが客席の階段を走り降り、何か雰囲気が怪しい。すると、「あのー、大変に申し訳ないのですが、機械の故障でこのまま公演を続けられなくなってしまいました。以前にもあったんですが、今日もまた同じところで同じような問題が起こって…直るまでもう少し待ってください」まあ、機械の故障はあることなので、仕方ないかと思っていたら、「待っている間、何もしないのもなんなので、この機会に自分のことを話します。」と、ひとりが身の上話しを話し始めた。「この職業では将来が不安で、実を言うとこのまま続けるかどうかわからないんです」。この言葉を聞いた相棒は驚いて、やけくそになったのか、ホリゾントの壁を叩き出し、穴をあけるどころか壁自体を壊している。だが待てよ、何かが変だ。奴は壊れた壁の向こうで踊っている。つまり、全ては演技で、機械の故障はシナリオの一部だったのだ。リアルな演技に観客全員が見事に騙されたのだった。途中で客電がついた時にさっさと席を立ち、ふたりが止めるにもかかわらず、「機械の故障がいつ直るのかわからないのなら、待つ気はないわ。あなたたち、運が悪かったわね」と言って帰った年配の女性。全てが演技だったと知ったらさぞかし悔しがるだろうなあ。何があっても辛抱強く待つことが肝心と言うことですね。出演者からは、「ストーリーをあまり詳しく話さずに、宣伝してね」って。ダンスに演技にジャグリング(スリリングなシーンもある!)ミックスの、充実した1時間。(5月18日エトワール・デュ・ノール)

「Merci, Pardon」 ©Jouni Ihalainen

噂には聞いていたが、驚くほどよく鍛えられた、身体能力の高いダンサー集団による3作品のソワレ。
最初のエドワード・ロックの「ザ・シーズンズ」は、ものすごく早い腕の動きに、目を奪われる。ひとつの丸いスポットの中の男。左右からのスポットの変化で、体の影がミステリアスに変化する。すると、その横にパッとついたスポットの中に、別の男がいた。3つのスポットの中の3人の踊りが、一瞬にしてソロに戻る。そのスポットから飛び出した先にピタリとつくスポットの中での、キレの良い動き、あるいは、そこから離れたところにスポットがつけば、そこにはまた別のムーブメントがある。一瞬のうちに変わる構成は、LEDの効果を最大限に生かしている。鋭いスポットの変化と、スピーディな動きのリズムに圧倒された。

「ザ・シーズンズ」©Arthur Wolkovier
2番目の「GEN」は、Cassi Abranchesの振り付けで、黒っぽい体にフィットした衣装の女性のソロで始まる。上手から下手に向かって歩く女性、そして下手から上手に向かう集団。暗い照明の中に鈍く光る衣装と、ハードボイルド的な振り付けが、社会の憂いをイメージさせる。集団でいても、デュエットでも、お互いをけん制しながら存在しなくてはならない現代社会を表しているように感じた。

「GEN」 ©Arthur Wolkovier
ナチョ・デュアトの「Gnawa」は、民族的、土着的というか、宗教的な感じで、民衆の感情のかけらが散りばめられている。それは日常のものなのだけれど、ジェスチャー的な表現と、流れるような動きが小気味好く混ざっている。最後はろうそくを持って踊り、聖なる一夜は静かに幕を下ろした。(5月4日MACクレテイユ)

「Gnawa」 ©Alceu Bett

2011年に作られた初期の作品だが、今だに世界をツアーしている超人気作品。2017年にはNYのベッシー賞にノミネートされている。これまでにも何度もフランスで上演されているのに、ずっと見逃していて、やっと見れた。
男女が出会って、お互いに気になるも、向こうがしかけりゃ、こっちが引くで、なかなかうまくいかない。タンゴを踊っても、ダメ。タンゴは男がリードするものなのに、ふたりが主導権を取ろうとするからだ。「ホンジはドイツ女だからね。」
ドイツ育ちとフランス育ちは、隣国でも気質が全く違う。そんなふたりが客席に向かって話し始めた。
ホンジ・ワン「ドイツではね、全てがきっちりしているの」
ラミレズ「ホンジは韓国人で、ドイツで育った。親は韓国語しか話さず『アンニョンハセヨ』って言われてもね」
ワン「彼はフランス人というけれど、生まれたのはスペイン国境近くの町だし、親はスペイン人よ」
これじゃあ息が合わないわけだけれど、それぞれがふたつの文化を持っているから合わせて4つの文化があるわけで、それはリッチなこと。これがこのふたりの魅力なのだ。そしてやがてふたりが、意気投合していく様子を綴っている。ところで、モンチッチは日本の会社が製造した人形なのだが、ドイツでは男性のシンボルという裏の意味もあって、韓国人のワンはモンチッチと呼ばれてからかわれていたと作品の中で語っていた。そのモンチッチは、世界を飛び回るアーティストになった!
ふたりの歴史をベースにした作品に、ほっくりしたこともあるけれど、私は彼らのダンスそのものにも惹かれた。ラミレズの羽のように軽いダンス、ヒップホップだけれど、スルスルと形が変化して、そこには重力がないと感じさせるように軽い。そこにワンのキレのいい動きが入り、まるで手品を見ているかのようにふたりの体の位置が変わっていく。そして、ふたりが指先を合わせて波を打つような動きは、それが人の腕とは思わせない、雲が流れるようにしなやかなのだ。ソロありデュエットあり芝居ありの、アイディア詰め込み型の構成だけれど、ふたりの存在そのものが素敵なのだ。この作品は、「We are Monchichi」として若い二人のダンサーに引き継がれる。
今年1月に見た2017年初演の「Dyatopian Dream」での最新技術を駆使した作品も強く印象に残っているが、初期の作品も悪くない。こうして短期間に初期と最新の作品が見られたのは、彼らの成長ぶりが見られて、非常に収穫だった。今後の活動に期待したい。(5月14日ラ・コメディ・ドゥ・クレルモン=フェラン)

©Morah Geist, courtesy of Jacob’s Pillow
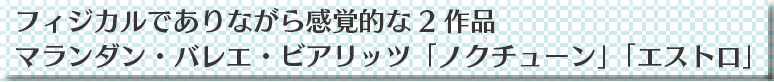
ダンサーは高度なテクニックで、力強い動きをするのに、その背景が非常に抽象的で、独特のニュアンスが魅力のティエリー・マランダン率いるCCNバレエ・ビアリッツ。パリ郊外のジェモー劇場で、「Noctune/ノクチューン」と「Estro/エストロ」が上演された。
「ノクチューン」(2014年)は、上手から下手に人が流れる中、デュエットや、ソロで様々な人生や感情が綴られる。ショパンの美しい曲に合わせた動きと、時折混じるコミカルなムーブメントがアクセント。バレエ団はクラシックバレエを基礎としているけれど、作品は完全にコンテンポラリー。毎回ダンサーのレベルの高さには感心する。ここ数年でバレエ団の中心的存在だったダンサーたちが引退して、若返ったように思う。そのせいか以前の体育会系のようなイメージは薄らぎ、まろやかになったように感じた。特に女性ダンサーの、男性並みの筋肉には圧倒され、気持ち良いほどの力強さが作品によっては気になることがあったが、現在のダンサーたちからは、それは感じなかった。それもよいけれど、マランダン・バレエ団の特徴が薄らいだような気がして、少し残念、というか、ノスタルジーかな。

「ノクチューン」 ©Olivier Houeix
「エストロ」(2014年)はヴィバルディに曲に合わせた、生と死を描いた作品。男の死を悲しむ女に、思い出が蘇る。楽しく遊んだこと、友人との会話、死を見送る思いが交差する。ひとつの感情が20人のダンサーによって増幅され、大群舞ならではの構成に見入った。光りを放つランタンが美しく、灯籠流しのようにも見え、悲しみの中にも、死を慈しむ思いが、生きることの美しさを語っていた。(5月23日Les Gémeaux)

「エストロ」 ©Olivier Houeix

すっかり遅れてしまいましたが、マルセイユのフェスティバル開催中です。

http://www.festivaldemarseille.com
|

