Philippe Decouflé 「Shazam」
Johanny Bert 「Hen」
Hofesh Shechter 「Double murder-Clowns/ The Fix」
パリ・オペラ座 「Le Rouge et le Noir」
Angelin Preljocaj 「Deleuze/ Hendrix」
Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi 「Ara!Ara !」
Alice Laloy 「Death Breath Orchestra」
伊藤郁女 「Chers」
Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi 「Ara! Ara !」
中間アヤカ 「フリーウエイ・ダンス」
Alexandre Fandard 「Très loin, à l'horizon」
Rebecca Journo 「Whals」
秋にはコロナ禍による外出禁止令が出るのではないかという憶測ゆえか、今年のシーズンは例年より早く始まった感がある。前シーズンに上演できず、延期となっていた作品をなんとしてでも上演したいということもあったのかもしれない、9月早々から注目すべき作品が名を連ねた。ヴッパタール舞踊団はピナ・バウシュの「緑の大地」をクレルモン・フェランで、パリのシャイヨー国立舞踊劇場ではダミアン・ジャレと名和晃平の「プラネット[Wanderer]」が、シャトレ座ではディミトリス・パパイオアヌーの「Transverse Orientation」など、ダンス作品が開幕演目となった劇場があった。パリ・オペラ座バレエ団では恒例の「ガラ」が9月24日に、そしてアレクサンダー・エクマンの「プレイ」でシーズンを開幕した。
待ち侘びた開幕ではあったが、コロナ禍による長期の劇場閉鎖ゆえか、再び外出禁止令が出るのではないかという懸念か、衛生パスなしでは入場できないゆえか、満席にならない会場があったことが惜しまれる。外出禁止令中のネット配信は、多くの人に舞台芸術を広めた一方で、劇場離れを進めたのではないかと懸念する。舞台は瞬間芸術ゆえに毎回違う。そして、そこにいた人にしか得られないものがある特別な時間と空間なのだということを忘れてはいけないと思う。そんな中で、小劇場のエトワール・デュ・ノールでの公演はほぼ満席に近く、しかも若い層の観客がほとんどだったことに、ダンスの将来は明るいという感を得た。
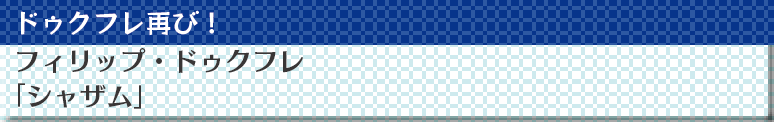

ⒸSigrid Colomyès
楽しい作品は何度見ても楽しい。1998年初演ということは、23年間ツアーし続けているロングランだ。この作品は早めに行って客席で待ってはいけない。なぜなら、劇場外での行進で始まるから。この日も開演30分ほど前に劇場前に着いたら、ちょうど楽屋口からの行進が始まったところだった。その後ホールで一回りしてから場内に消えていった。
「僕はこの作品の初演当時はまだ子供で…」と語るダンサー。そうよね、20年以上前の作品だもの。おや、年配のおじさん達は、当時のダンサー?! 昔のビデオが流れて、そこに若かりし頃の姿を見つけた。年月の流れを感じるけれど、50歳近くなっても踊っているということが素晴らしい。若いダンサーに替えた方がキレがあるだろうけれど、古参ならではの味がある。さすがドゥクフレ。
今から20年前は、映像技術は今ほど発達していなかったし、映像を使う作品は少なくて、驚きの連続だったのを思い出した。そして今回同じ作品を見て、やっぱり驚きの連続だった。何度見ても面白いのだ。カメラや鏡の使い方でこんなにも不思議な場面になるのかと、改めて驚いた。当時にこんなアイディアを出したアーティストが他にいただろうかと、ドゥクフレの才能に感心する。しかも今見ても新鮮。ダンスあり、笑いありの楽しい作品は元気をくれる。ドゥクフレマジックは衰えず!(9月29日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

ⒸSigrid Colomyès
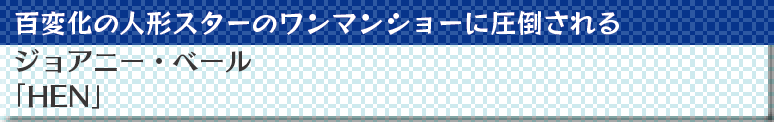

ⒸChristophe Raynaud de Lage
人形だと分かっていても、まるで生きているかの如くに動くショーの主役に、完全にイニシアティブを取られた。ぎょろりとした目、熱い唇、髪は剃り上げ、どう見ても男なのだが、大きなおっぱいがある良性具有の「ヘン」が観客に向かって叫べば、ウイィィィ! と歓声が上がる。彼は百変化、司会者になり、コワモテの悪になり、娼婦になり、セレブな婦人になって、歌い、踊り、喋りまくる。セクシーで、ワルでナイーブな「ヘン」。パリのキャバレーのリドやムーラン・ルージュ負けじのワンマンショーに盛り上がる。大量のペニスが出てきたり、おっぱいが引きちぎられたり、社会風刺もあって過激な部分もあるけれど、人生なんてこんなもんでしょと、一笑する。
公演の後のトークには、夜遅い時間にも拘らず多くの客が参加した。「みなさんのほとんどは、僕のことを知らなくて、たまたまこの日が空いているからって見にきたんじゃないの?」との鋭い質問に、「その通り!」との返答が客席のあちこちから飛んだ。多くの人が今日から彼のファンになったのだ。
彼の人柄通りの和気藹々としたトークでは質問が絶えない。ここで分かったのは、しゃべりと歌は全てベールによるライブで、人形が自分の顔を隠してくれれば怖くないのだそうだ。アイディアが浮かんで人に話したら、多くの人が曲を提供してくれて、それで歌うことになった。舞台で歌を歌うのは初めてだったけれど、歌ってみたら気持ちが良いので、歌のレッスンに通って、こうして初日を迎えたのだと。一人一人の質問に丁寧に、そしてユーモアたっぷりに応えるベール。彼の人柄と才能が輪を広げている感じだ。マリオネットというけれど、生きているかの如くに動き、話し、歌う「ヘン」。機会があったら是非と勧めたい。この作品はベールともうひとりのアシスタントが人形を担当し、チェロとパーカッションの生演奏が伴う。チェロも弦を弾くだけでなく、ギターのように爪弾いてあらゆる音を出す。パーカッションも、太鼓だけでなく、シンセサイザーやウインドチャイムで的確な効果音。ベールの一人舞台に見えるけれど、共演者の心がひとつになっていたことが、成功の要因のひとつだろう。作品の面白さだけでなく、人間的な暖かさを感じた公演だった。(9月30日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

ⒸChristophe Raynaud de Lage
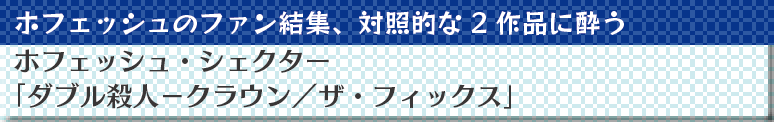
ホフェッシュのファンは、この日が来るのを待っていた。マイクを持って現れた男が「1年半ぶりに戻ってきました! では、いつものを行きますか? ピピっ」すると客席から「イェーイ」という大歓声。この合言葉を知らなかったのは私だけだろうかと周りを見回すうちに、オッフェンバックの「天国と地獄」の「カンカン」に合わせてのお祭り騒ぎとなり、「クラウン」は始まった。
この明るい音楽の後の暗転の後は一変する。音程の低い音楽に合わせて、小さなスポットライトのシルエットになって現れた人たち。単純なステップを揃いで踏んでいたかと思うと、激しい動きになり、薄いスモークが煙る中、少人数の集団が上手、下手に現れては消える、まるで映画を見ているようだ。暗転にならずとも、人が走り去り、全く別の状況がぱっと浮かび上がる。そして始まる殺戮。白い衣装につけられた真っ赤なチーフは血の象徴か。さまざまな殺し方が描かれる。暴力的だったり、見せしめだったり、優しく抱きしめて気を許したところで一発とか、殺しては殺され、殺されては生き返る。これでもか、これでもかと人を殺して歓喜する姿に嫌気が差す。これはまるで殺人ゲームだ。しかも赤いカーテンと丸い電球というサーカス小屋定番の装置が、楽しいイメージを不気味なものに変え、残虐性を強調する。時に一列になって無表情でステップを踏む姿に背筋がゾクっとする。映画「クラウン」や「ジョーカー」を思い出した。道化の笑みを讃えた化粧の下の残虐。規則的に刻まれるリズムが冷酷な世界を支配しているかのようだ。

「クラウン」ⒸTodd MacDonald
これに続く「THE FIX」は、Tシャツにズボンという普段着で、7人のダンサーが入り混じりながら絡むコンタクトムーブメントで綴られる。ゆっくりとした動きと激しい動きが繰り広げられ、やがて座禅を組むかのように静かに座った。トランスに入り、叫び暴れる男を押さえつけ、なだめ、静かに客席に送り出す。やがてダンサー全員がマスクをつけて客席に降りて、観客とハグするというラスト。「クラウン」のバイオレンスとのギャップに戸惑ったが、これがあるからバランスが取れているのかもしれない。今、この世に欠けていること、そして人々が望むことは「希望を持つこと」だと。(10月6日シャトレ劇場)

「THE FIX」ⒸTodd MacDonald
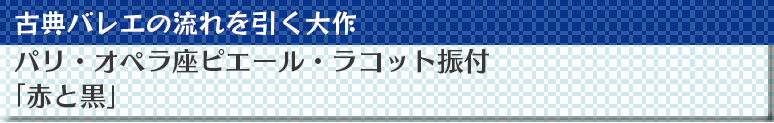

ⒸSvetlana Loboff/Opera national de Paris
スタンダールの長編小説「赤と黒」。登場人物が多く、欲と愛と嫉妬が複雑に絡む、決して単純ではない小説を、どうのようにバレエ作品に仕上げるのかと注目されていた。コロナ禍により延期となっていたが、ここにようやく初演を迎えた。
主人公のジュリアン・ソレルと町長の妻レナール夫人を中心にした恋愛劇を、2回の休憩を入れた3時間15分の大作にまとめ、わかりやすいゆえに長さを感じさせず、綺麗に仕上げていた。
簡単にあらすじをまとめると、まず第1幕はジュリアンの家庭環境を描く短いシーンで始まり、シェラン神父の擁護の元、家庭教師として行った町長のレナール家で夫人と出会う。一目惚れしたのはレナール夫人だけでなく、召使いのエリザも同じだったが、相手にされず、夫人との関係に嫉妬したエリザがレナール氏に密告し、怒った夫は彼を解雇する。
2幕では、神学校の生活に馴染めず、レナール夫人のことばかりを考えるジュリアンが、懺悔をして信仰ある態度を取ったことで、晴れて学校を出て、ラ・モール伯爵の家に秘書として雇われることになり、そこで伯爵の娘のマチルドとの出会いを描く。自分に興味がないことが面白くないマチルドは、自らジュリアンを誘う。
3幕はマチルドの寝室から始まる。一夜を共にしたものの、高慢な娘は翌朝にはジュリアンを罵り一変する。感情が激しく変わるマチルドだったが、ふたりは結婚を決めた。なんという運命か、レナール家を辞めた女中のエリザが、この屋敷で働いていたのだ。エリザの嫉妬は最高潮に達し、ジュリアンを不幸に導くべく策略を練る。密告。懺悔に訪れた教会で神父に強要されて、レナール夫人はこれまでの出来事を書かされ、これが大問題となった。これを知ったジュリアンは教会のミサに押しかけ、レナール夫人に発砲する。
監獄に送られたジュリアンを見舞うシェラン神父とルナール夫人に別れを告げ、彼はギロチン台へと向かった。そしてレナール夫人はジュリアンの涙を拭いたハンカチを握り締めながら倒れるところで幕。
ピエール・ラコットの振り付けはクラシカルで、恋愛劇としての物語を重視したバレエ作品に仕上げている。それゆえ、高度なテクニックや派手なムーブメントを前面に出さずにさりげなく組み込み、優雅で流れるような振り付けを印象付ける。そして、登場人物の感情の変化を見せることに重点を置いたことで、物語の流れを明確に伝えている。また、紗幕の後ろにぼんやりとその人物を登場させ、現実と夢想を同時に対比させたり、映像を使った演出が時空間の移り変わりをを端的に見せている。ただ、場面転換に時間を要することがあり、特に3幕では転換が多く、その度に暗転となることが流れを止めているように感じた。幕前でのシーンを入れた場面もあったが、場面転換が幕前シーンより長く、音楽も動きもない時間があったのが気になった。
ラコット自らデザインした装置は豪華で見応えがあり、衣装も役柄を表すに十分な、気品とセンスのあるものだった。

フロリアン・マニュネⒸSvetlana Loboff/Opera national de Paris
さて、主な配役は、ジュリアンにユーゴ・マルシャン、マチュー・ガニオ、フロリアン・マニュネ、ジェルマン・ルーヴェ、レナール婦人にはドロテ・ジルベール、アマンディーヌ・アルビッソン、リュドミラ・パリエロ、オニール八菜、マチルドにビアンカ・スクダモア、ミリアム・ウルド=ブラーム、レオノール・ボラック、エリザにロクサーヌ・ストヤノフ、ヴァランティーヌ・コラサント、ナイス・デュボスク。
直前のキャスト変更はよくあることだが、今回は特に多かったようで、所見した日もマルシャン+ジルベール版だと思って行ったら、マニュネ+アルビッソン版に変わっていた。
この日の配役は、ジュリアンにマニュネ、レナール夫人がアルビッソン、レナール氏にステファン・ビュリヨン、マチルドにボラック、エリザにナイス・デュボスク、シェラン神父にオドリック・べザールで、どの役も適役だった。

ナイス・デュボスクⒸSvetlana Loboff/Opera national de Paris
マニュネは、お人好しの好青年を演じていたが、スタンダールの小説のように、恋は出世の手段と考えるずる賢さをもう少し出せば作品が深まったのではないかと思う。優しい顔立ちなので、ずる賢い表情が見えにくいのかもしれない。とはいえ、テクニック的にも演技の面でも非常に良く踊りこなしており、近い将来エトワールに任命されるのではないかと期待する。
アルビッソンは、表現力がさらに身についた感じだ。初めてジュリアンを見た時の胸のときめき、悪とは知りながらも情事を重ねる罪の意識、そしてジュリアンへの思いを断ち切ることができないもどかしさをよく表現していた。
ビュリヨンが白髪が混ざる壮年の父親役を演じたことに驚いたが、親として、町長としての威厳があり、それは踊り自体にも現れていた。
高慢な娘を演じたボラックも、瞬時にして変わる感情の変化を的確に表していた。
ラコット版では、召使いのエリザが流れの要となる重要な役だ。白羽の矢が立ったスジェのナイス・デュボスクは、フロアの動きが少し固いのが気になった以外は非常によく踊りこなし、若さゆえに暴走し、感情をむき出しにする役柄をよく演じていた。
レナール家での家庭教師のレッスンは、オペラ座バレエ学校からの3人の男の子が好演。先生のバレエのパを真似して、一生懸命踊る姿が愛らしく、演技の面でもよく演じていた。

アマンディーヌ・アルビッソンとステファン・ビュリヨンⒸSvetlana Loboff/Opera national de Paris
古典作品でもアクロバット的な動きが目を引き、ダンサー個人の活躍が印象に残る作品があるが、今回のようにストーリーに重点を置き、物語の中の登場人物としてのダンサーを浮き立たせる作品は、いつまでも心に残るものだと思う。この作品が長く上演されることを願いたい。(10月23日パリ・オペラ座・ガルニエ宮)
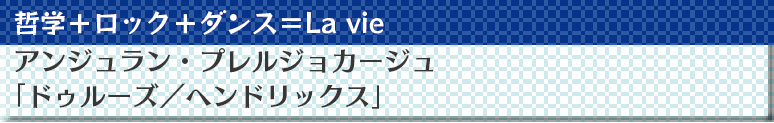

ⒸJC Carbonne
タイトルを見て、身を構えた。ジル・ドゥルーズはフランスの60年代の哲学者。その哲学者とジミー・ヘンドリックスの音楽がどう結びつくのだろうか。哲学が苦手でドゥルーズの本など読んだこともない私には想像がつかず、ビクビクしながら見にいったのだが、心配することなかれ、明るい哲学に明るい音楽だった。
80年代にパリ8大学でのドゥルーズの講義を録音したものと、ヘンドリックスの音楽をバックに、日常の物語を組み込んだ踊りだった。ジョン・ケージの講義を録音したものを使った「エンプティ・ムーヴス」のような感じだが、踊りの内容は異なり、そこに生きることの希望が見えた。
体操選手のように懸垂をするシルエットがブルーの光に浮き立つ。この後は黒のぴたりとしたズボンにベージュのシャツ姿のダンサーたちによるいくつかのシーンとなる。ロックに合わせて激しく踊ったり、動きや構成の面白さだけを見せる場面の後には男女の官能的なデュエットを見せるなど、豊富なボキャブラリーのプレルジョカージュワールドに目が離せない。そして、シンプルな衣装ゆえに全てがクリアーだ。ドゥルーズの「存在ってなんだろう」「永遠とは?」などという講義に現実に引き戻されながら、踊りと言葉の間を旅するような感覚だ。シリアスで、時に笑いを誘う講義と、ヘンドリックスの時に激しく、時に優しいギターの音色は80年代を思い起こさせるが、それを古く感じさせない振り付けとダンサーのエネルギーには生きる喜びが感じられる。横たわった人の形をチョークで描き、そこにいた人がいなくなれば、人型だけが残る。それが過去と現在、そして存在することの意味を表しているように感じた。そして最後の場面の、ダンサーが歌に合わせて歌いながら踊る場面で、今、ここに存在して、今を楽しんでいるのだと気づかせる。哲学とロックとダンスは、とても近いものなのかもしれない。(10月21日104/ソン・キャトル)

ⒸJC Carbonne
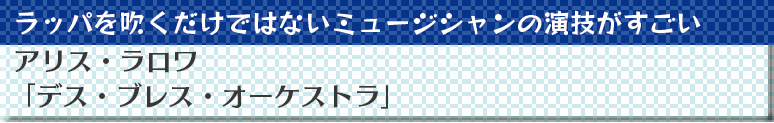

ⒸJean Louis Fernandez
アヴィニヨンで「ピノキオ/ライブ♯2」を見て、すっかりファンになってしまったラロワの公演を見に行った。それは、演奏と人形とオブジェのフィジカルな舞台だった。
ゴーという鉄パイプを吹くような音がして、スモークが蔓延している。スモークを客席に流さないためなのか、舞台前面に布がかかっている。ぼんやりと白く見えるものは、煙の渦だろうか。と、布がバサリと落ちて始まった。荒い呼吸音が聞こえ、椅子に座った人形を背負う4人。自分を模した人形を背負っているのだ。
ここは現実と非現実が入り混じる密室だ。壁には何本もの太いパイプが口を開け、彼らの行動を監視し、威嚇するかのように煙や音が飛び出す。彼らも戦いを挑むけれど、どうやら相手の方が優っているようだ。人形のシャツのボタンを外せば、その腹にはホルン。彼らの武器はトランペット、トロンボーン、チューバ、テナーチューバの菅楽器で、これで壁の向こうの見えない怪物に立ち向かう。プラスチックのチューブがこの密室に空気を送っているのだろうか、それを引き出して呼吸したり振り回して音を出したり。人形の腹に突っ込んだら、お腹がどんどん膨らんで破裂してしまった。するとそこから男の子が出てきた。
何が飛び出すかわからない密室の壁が突然崩れ、窓が吹っ飛び、物が飛び、演奏者たちは大きな透明のビニールに楽器ごと包まれ、それでも演奏をやめない。瓦礫と化した部屋で元気に走り回る子供は、臨機応変でポジティブだ。そんな彼が、決して上手くないけれど大人の真似をしてトランペットを吹く姿が愛らしい。ようやく密室から脱出できる開放感と、これから新たに始まる新しい道。そんな希望が感じられるラストがいい。
ミュージシャンの演劇団。言葉はほとんどなくて、会話は楽器と身振りだけ。ラロワの言葉のない演劇作品に興味が湧く。(10月9日 Nouveau Théâtre de Montreuil)

ⒸJean Louis Fernandez
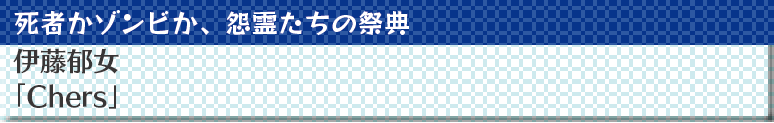

ⒸJosefina Perez Miranda
ここ数年の伊藤の活躍がめざましい。休むことを知らずに作品を作り、そして踊り続けている感じだ。パリ郊外のMACクレテイユ・メゾン・デザールでは、昨年の新作「Chers」と、今年の新作の子供向けの「Le Monde à l'envers/逆さまの世界」が同時期に上演された。両作品ともこの後の上演予定がぎっしり詰まっているという売れっ子ぶりだ。
今回は「Chers」を所見。薄暗い舞台にふらりと現れてポーズを取るダンサーたち。その合間で年配の女性が男に向かって名前を叫び続けている。しかし彼はするりとすり抜けてしまう。ふたりが出会った時、男は息を大きく吐いて崩れるように倒れた。「死んだの?」死んだ息子の亡霊を見ているのだ。そして話しかける、思い出とともに。
この年配の女性、女優のデルフィーヌ・ランソンが飛び抜けていい。伊藤と共に作った台本も良いし、ダンサーと踊っても引けを取らない。その存在感が圧倒的なのだ。
ここでは、死者の思い出が語られ、死者が生き返ったかのように動き踊り、様々な出来事が描写される。出産を連想させる女の叫び、赤ん坊みたいなギャン泣き、白鳥の湖にJポップスでのショーダンス、そして暴力。6人のダンサーの見事な踊りと異なる個性に目が離せない。ただ、冒頭の死者を弔う儀式の厳かな雰囲気から、ラストの服を脱ぎ捨てて踊りまくるシーンへの繋がりが見えなかった。あまりにもたくさんのことがありすぎて、焦点が薄れたように思う。日本人のように霊魂を語らないフランス人には、新鮮な視点の作品と写ったようだ。(10月20日MACクレテイユ・メゾン・デザール)

ⒸJosefina Perez Miranda
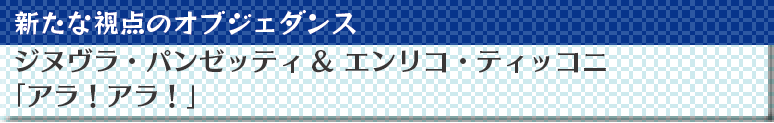

Ⓒvalerio figuccio
タイトルが日本語みたいなので、勝手に「あら、あら!」と驚きと笑いの作品かと思ったら、とても真面目で、大きな旗を持っての踊りです。
旗は止まることを知らず、縦になったり横になったり、8の字を描いたり、床を這うようになびいたりしながら動き続け、身体もそれに合わせて変化していく。音楽は規則的な太鼓の音と細かくシンバルを打つ音だけ。ひとつの旗がふたりの間を行き来し、ひらひらと靡いていた旗は、時折大きな音を立てて風を切る。四角い布が捩れることもなく、常にたなびき揺れ続けさせるのは容易なことではないと思う。専門家について旗の振り方を研究したそうだ。後半はそれぞれが旗を持ち、立ったり座ったり、足を振り上げたりと、動きが大きくなった。
旗が止まれば暖簾になり、ラストはふたりが重なってダビンチのウィトルウィウス的人体図になった。ここに行き着くとは、なかなかのアイディアのラスト。
オブジェを使ったダンス作品を追求しているふたり。この作品は、振り付けコンクールのポディウムのファイナルに選出されている。(10月7日テアトル・ド・ラ・シテ)
振り付けコンクールポディウムは11月19、20日に行われる。ファイナリストを見れば、以前に見たいくつかの作品が並んでいる。「ゼッペリン・ベンド」「ザ・パッション・オブ・アンドレア2」「ミュイット・メーカー」そしてこの「アラ!アラ!」。審査結果はいかに。
アドレスはこちら。

Ⓒvalerio figuccio
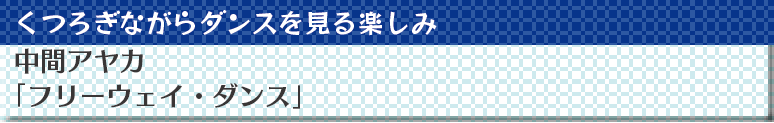
会場に入ると、そこは庭だった。木のチップスが敷かれた通路にはたくさんの花が咲き、木が植り、灯籠があって鹿威しが打つ竹の根が響く。謡曲からJポップスまで多彩な音楽に合わせて中間は自由に踊っている。それを見ながらリズムに合わせて皆の体が揺れている。彼女が自然体で踊っているから、こちらも自然体でいられるのだ。本棚にある本を広げたり、飲み物をもらったり、あら、ガチャまである。2ユーロでバッチが出てくるらしい。子供たちはブランコで遊んでいるし、霧吹きで植木に水分を与える人、チョークで床に絵や文字を書く人など、自由にダンスを楽しめる庭なのだ。
中間は衣装を何度も変え、次に何が出てくるか分からないダンスがいい。メロディが掴めない歌も面白い。彼女が着替えている間が休憩時間となってトイレに行ったり、飲み物を飲んだりできるけれど、4時間は長すぎたかもしれない。中盤以降に動きが少なくなったことと、19時半のたったひとりの観客との糸電話でのトークの間に、することがなくなった客が離れてしまった。子連れの家族の夕食時間でもある。その前の映画タイムと合体するとか、別のアニメーションをするなどの工夫があっても良かったのではないかと思う。また、客との対話はあるものの、もう少し踏み込んでも良かったのかもしれない。後半のダンスシーンでは、クラシックバレエで鍛えたしなやかで強靭なムーブメントが、それまでの流れを変えたのが新鮮に映った。そして木の周りを回りながら踊る姿(ポールドブラの美しいこと!)が、とても自然で見ている方まで心地よくなる。最後まで全ての観客を維持できなかったのが惜しまれる。(10月24日ポンピドゥセンター)

ⒸHideto Maezawa
ポンピドゥセンターで10月8日から24日まで催された5回目のフェスティバル・ムーヴ/MOVE。ダンスパフォーマンス、映像、展示、ロングランのビデオダンスがあり、中間アヤカの「フリーウェイ・ダンス」もこの一環で上演された。

新人に場を与える劇場はいくつかあり、エトワール・デュ・ノール劇場(旧18区劇場)もそのひとつだが、その多くがほぼ無名の新人たち。だから面白い。
アレクサンドル・ファンダールの「Très loin, à l'horizon」は、ミニマルに徹したダンスだった。フード付きのジャケットを着て、手で顔を隠したまま頭を振り続けるふたり。ゴーという音の中のリズムに合わせて、頭を激しく振る。時にゆっくり時に早く激しく、肘が円を描き、空を切り、左手を横に伸ばして竹とんぼの様に回転しながら移動する。呼吸音、赤い光が回り、クネクネと体を捩らせて動く姿は異生物のようだ。右手を固定した状態という拘束の中の自由が面白かった。

「Très loin, à l'horizon」
レベッカ・ジュルノの「Whales」は、鯨の鳴き声をバックに、3人の女性が体をくねらせながら移動する。時々赤く、時々白く浮き上がる体。肩が動き、それとは逆方向に腰がくねり、暗闇に消えては浮かび上がる。深海をイメージさせる照明が美しく、未知の世界がミステリアスに浮き上がる。ただ、最後までトーンが変わらなかったことが少し冗長に感じられたように思う。(以上2作とも10月8日エトワール・ドゥ・ノール)

「Whales」ⒸMehdi Baki
|

