
 日本でも公演しているので、彼の名を知っている人はいると思う。最初に見たのが、サシャ・ワルツの作品で、その後がジョセフ・ナジ。そう、今年1月に世田谷パブリックシアターで、ナジの「遊ぶ」に出ていたはずだ。人形のように身体が自由自在に動いてしまう人。それはそれはただ目を見張るばかり。そんな彼が数年前から振付家としても活動を始めていて、ポップでキッチュなのはよいが、どこか煮え切らないところがあった。それが、この作品では彼のユーモアが見事に結晶した感じ。初演のアビニヨン(昨年)を見た人が「良くない」と言っていたが、やっぱり作品は生きている。7か月経ったらブラボーものになっていたようだ。タイトルの「ペプロス」とは、古代ギリシャ・ローマ時代の女性用寛衣、もしくは古代を題材とする時代映画とある。全くその言葉の意味通りの作品。ギリシャ・ローマ時代風の彫刻と、門番。槍を持っていかめしく立っている。寛衣をまとった人が通り過ぎたかと思うと、突然タイムスリップしたかのように現れる現代人。このごちゃ混ぜの混乱の中、聞こえてくる古い時代映画の男女の会話。生の映像と映画、生演奏と録音された音楽の組み合わせなど、アイディア豊富な総合マルチメディア作品。でもこれがちっとも鼻につかず、うまくまとめているところが気に入った。生きた蛇も出てくる、彼らしいジョークがふんだんの作品。動けるダンサーばかりだったのも、作品の質を高めるには効果的だった。(4月4日テアトル・ド・ラ・ヴィル)(文中写真(C)LAURENT PHILIPPE) 日本でも公演しているので、彼の名を知っている人はいると思う。最初に見たのが、サシャ・ワルツの作品で、その後がジョセフ・ナジ。そう、今年1月に世田谷パブリックシアターで、ナジの「遊ぶ」に出ていたはずだ。人形のように身体が自由自在に動いてしまう人。それはそれはただ目を見張るばかり。そんな彼が数年前から振付家としても活動を始めていて、ポップでキッチュなのはよいが、どこか煮え切らないところがあった。それが、この作品では彼のユーモアが見事に結晶した感じ。初演のアビニヨン(昨年)を見た人が「良くない」と言っていたが、やっぱり作品は生きている。7か月経ったらブラボーものになっていたようだ。タイトルの「ペプロス」とは、古代ギリシャ・ローマ時代の女性用寛衣、もしくは古代を題材とする時代映画とある。全くその言葉の意味通りの作品。ギリシャ・ローマ時代風の彫刻と、門番。槍を持っていかめしく立っている。寛衣をまとった人が通り過ぎたかと思うと、突然タイムスリップしたかのように現れる現代人。このごちゃ混ぜの混乱の中、聞こえてくる古い時代映画の男女の会話。生の映像と映画、生演奏と録音された音楽の組み合わせなど、アイディア豊富な総合マルチメディア作品。でもこれがちっとも鼻につかず、うまくまとめているところが気に入った。生きた蛇も出てくる、彼らしいジョークがふんだんの作品。動けるダンサーばかりだったのも、作品の質を高めるには効果的だった。(4月4日テアトル・ド・ラ・ヴィル)(文中写真(C)LAURENT PHILIPPE)
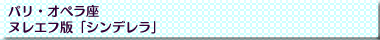
 この作品を最初に観たのが80年代のニューヨーク。パリ・オペラ座がリンカーンセンターで上演し、まだ20歳そこそこのシルビー・ギエムという天才ダンサーが踊るとの評判を聞いて観に行ったのを思い出す。あいにく私は舞台近くの席を買うお金がなく、当日の朝並んで、安いチケットを手に入れたものの、最後尾の列、しかも立ち見で、ギエムはマッチ棒のごとく細く小さくしか見えなかったが、当時は驚きの新解釈と評され、シンデレラのカボチャがスポーツカーになった瞬間は、ひえーっと思わず声を上げたものだ。それから20年。時代の流れを感じずにはいられない。ヌレエフが亡命して、見た自由の国。そして華やかなハリウッド。全く正反対の世界に飛び込んだ驚きと喜び、そしてそれまでの風習を破ろうとする意欲が感じられる。しかし正直なところ、テクニックの見せ場は少ないし、現代の私たちにはハリウッドの華やかさは当たり前の事になってしまったし、これといった感動はなかったが、それでも人気なのは、出演者のキャラクターだと思う。目を見張ったのが、意地悪な母親役を演じたステファン・ファヴォラン。いまいちぱっとしないダンサーだったが、女装役をやらせたらめちゃうまい! トウシューズも難なくこなし、意地悪度、嫉妬深さ度、夫を馬鹿にする態度、何をとっても演技力抜群で笑える。これに意地悪姉さんのメラニー・ウエルとナタリー・リケがからみ、この3人の演技には目が離せない。シンデレラのアニエス・ルテテューは美しすぎ、王子役のジョゼ・マルティネズは当たり前にかっこ良く、ちょっと印象が薄くなってしまったほど。オペラ座ファンの友人に言わせると、レティティア・プジョルの意地悪姉さんが最高だとか。このバージョンでは、ジョゼ・マルティネズが意地悪母さん役を演じるので、これはやっぱり見比べなくちゃあダメだなあ。(4月17日パリオペラ座ガルニエ)(文中写真(C)Laurent Philippe) この作品を最初に観たのが80年代のニューヨーク。パリ・オペラ座がリンカーンセンターで上演し、まだ20歳そこそこのシルビー・ギエムという天才ダンサーが踊るとの評判を聞いて観に行ったのを思い出す。あいにく私は舞台近くの席を買うお金がなく、当日の朝並んで、安いチケットを手に入れたものの、最後尾の列、しかも立ち見で、ギエムはマッチ棒のごとく細く小さくしか見えなかったが、当時は驚きの新解釈と評され、シンデレラのカボチャがスポーツカーになった瞬間は、ひえーっと思わず声を上げたものだ。それから20年。時代の流れを感じずにはいられない。ヌレエフが亡命して、見た自由の国。そして華やかなハリウッド。全く正反対の世界に飛び込んだ驚きと喜び、そしてそれまでの風習を破ろうとする意欲が感じられる。しかし正直なところ、テクニックの見せ場は少ないし、現代の私たちにはハリウッドの華やかさは当たり前の事になってしまったし、これといった感動はなかったが、それでも人気なのは、出演者のキャラクターだと思う。目を見張ったのが、意地悪な母親役を演じたステファン・ファヴォラン。いまいちぱっとしないダンサーだったが、女装役をやらせたらめちゃうまい! トウシューズも難なくこなし、意地悪度、嫉妬深さ度、夫を馬鹿にする態度、何をとっても演技力抜群で笑える。これに意地悪姉さんのメラニー・ウエルとナタリー・リケがからみ、この3人の演技には目が離せない。シンデレラのアニエス・ルテテューは美しすぎ、王子役のジョゼ・マルティネズは当たり前にかっこ良く、ちょっと印象が薄くなってしまったほど。オペラ座ファンの友人に言わせると、レティティア・プジョルの意地悪姉さんが最高だとか。このバージョンでは、ジョゼ・マルティネズが意地悪母さん役を演じるので、これはやっぱり見比べなくちゃあダメだなあ。(4月17日パリオペラ座ガルニエ)(文中写真(C)Laurent Philippe)
100 dessus dessous
何年か前から、このシリーズの名前を目にするも行った事がなく、今年初めて行ってみた。ダンステアトル風、或はパフォーマンス風の作品を提供しているように思った。だからダンスだけを期待すると外れるが、今時の若者のアイディアの豊富さには驚かされる。そんな意味で非常に楽しめた。あいにく今年は1日3作品しか見られなかったが、来シーズンはもうちょっと覗いてみようと思う。

「食べる」という行為を客席からじっと見るのはなんか妙。しかも相手がちっとも楽しそうに食べていない。まさに「食べる」行為を見るだけなのだ。無表情で、林檎はまだしも、ジャガイモをほおばったり、靴下を食べたり。与えるほうも与えるほうで、無表情。茶色の紙袋を持ち、ポケットからおもむろに出し、歩いて所定の場所に置く。そして元の場所に戻る。二人の格好のダサさがまた、作品に味を添えている。人間はなぜ食べるのだろうか? 生きるためなのだが、口を動かすと、これに関連して顎が動き、こめかみも動く。これが食べるという行為か。と改めて思ってみたりする。それにしても、大幅飛びをしながらパンを食べるのには、ハラハラ。のどにつかえちゃったらどうすろんだろう、などと余計な心配をしてしまった。最後にバケツからばら撒かれた沢山のグレープフルーツ。むいたとたんにツンとくる匂い。これがたまらない。でも彼らは無表情にほおばっている。このアンバランスさがおかしい。無機質な空間で演じるのも面白いけれど、松根君が言っていたように、お店、特にスーパーマーケットでこれをやったら絶対に面白いと思う。(4月18日CND)
そうそう、言うのを忘れたけれど、この公演は一晩に3作品ほど見られて、たったの10ユーロ! お買い得です。しかも専用バスで会場を移動するのだ。まず、松根君+スバル君の公演をCNDで観て、それからバスでメゾン・ド・ラ・ヴィレットに移動。たった5分の移動だけれど、得した気分。

(C)matsune et subal

この作品もなんだか、まじめなんだか不真面目なんだか、ダンスがうまいんだか下手なんだか、わかったようなわからないような、でもその混ざり具合がよく出来ていて、吹き出す場面も多くて面白かった。アイディアが豊富で、かといって多すぎず、程よく流してくれた。(4月18日メゾン・ド・ラ・ヴィレット)

これまたユーモラスな作品。3人が斜めに並び、真ん中の人がマイクを持つ。一番後ろにいる人が好き勝手に動き、それをマイクを持った人が実況解説し、一番前にいる人が、その言葉から後ろで踊っている人の動きをイメージして真似るというもの。つまり、この人には自分の後ろで踊っている人が見えないので、解説を便りに想像して動くしかない。「両足を平行に開いて、手は右手が左胸の前、左手が後ろの左側で、、、」。理解の仕方によってここまで原型が変わるものかと感心すると同時に吹き出してしまう。また、解説者も瞬時に動きを言葉で表現しなくてはならないので、これもどんな言葉が出てくるか想像もつかない。「アンヌ・テレサ・ド・ケールスマイケルとインド舞踊を交互に」と言われて、一瞬目が点になるダンサー。「フォーサイスの動きとマイケル・ジャクソンステップ」といわれて直ちに想像がつく人がいたら私は感心してしまう。この言葉と動きの時差に爆笑。その後のディック・ウオンの踊りは、しなやかで、シャープ。でもなぜか蛸を思い出してしまった。特徴ある腕の動きのせいだろうか? とても不思議なダンスで好きだった。(4月18日メゾン・ド・ラ・ヴィレット)
 (C)Dick Wong (C)Dick Wong
3作品の傾向が全く違い、それぞれがとても個性的で、とても満足した一夜でした。
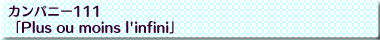
昨年から「カンパニー111は絶対に観るべき!」と言われていて、やっとお目にかかれました。コンセプトは、オーレリアン・ボリーとある。ああ、あのピエール・リガルと組んで、めっちゃ面白い作品を創った人か! 演出はフィル・ソルタノフ。期待を裏切らず、面白い公演だった。最初は光の祭典、蛍光灯が踊る踊る。マスゲーム的に規則正しく、なおかつ自由自在に空を舞う。それに伴う影の効果もちゃんと演出されている。やがて人が出て来て自由自在に舞台を駆け巡る。人も長い棒もまるでベルトコンベアーに乗っているかのように舞台を滑り、得意のアクロバットで見せる。たった6人の出演者なのに、その倍の出演者がいるかのように次々と人が出入りし、映像を交えて、ユーモアあり、驚きありのあっという間の1時間15分。サーカスは演劇のジャンルに区分けされている事もあるので、プログラムを見たらサーカスという文字を探してみるべき。こっちのサーカスはアクロバットダンスなのだ。(4月19日テアトル・ド・ラ・ヴィル)

(C)Aglaé Bory
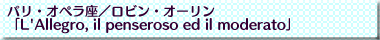
 何かと話題の多い作品を創るロビン・オーリンがオペラ座に何を振り付けるの? 期待は膨らみ、多くのジャーナリストが詰めかけていた。しかし、正直なところ、……。オーリン得意の小型カメラでの投影と、ビデオ編集。ヘンデルの曲をオペラ歌手が歌い、ニコラ・ル・リッシュ始めとする、そうそうたるメンバーが踊る。企画とアイディアは面白い。が、最近のオーリンの作品に見られる、即興の面白みが全くなかった。与えられた動きをいかにこなすか、という事においては長けていても、イメージから動きを生み出し膨らませる事が、オペラ座のダンサーには欠けていたように思う。この2つの事は全く質が違うからだ。オペラ座のダンサーはすばらしと思う。身体の使い方が全く違うクラシックバレエとコンテンポラリーを見事に踊り分けられるバレエ団となった。これはセーヌ65号でも書いたし、本当にそう思う、ただ、即興ダンスにはまだ慣れていないようだ。例えば、リッシュがブラジャーを着けてお尻を振るのも、大きなアヒルの映像と戯れるのも、アリス・ルナヴァンが動物の仕草をするのも、それなりにこなしている。しかし、それ以上のものは感じられなかった。ヴェラ・マンテロがオーリンの作品を踊った時の様に、まるでそのとき初めてハプニングが起こってしまったかのように演じ、観客とあたかも会話をし、次に何が起こるのかわくわくするしながら見入るような雰囲気は、あいにく感じられなかった。ただ、オペラ座のダンサーは選ばれた人たちばかり。数年後には、この作品を踊りこなしているだろうと確信する。(4月23日オペラ座ガルニエ)(文中写真(C)Maarten Vanden Abeele) 何かと話題の多い作品を創るロビン・オーリンがオペラ座に何を振り付けるの? 期待は膨らみ、多くのジャーナリストが詰めかけていた。しかし、正直なところ、……。オーリン得意の小型カメラでの投影と、ビデオ編集。ヘンデルの曲をオペラ歌手が歌い、ニコラ・ル・リッシュ始めとする、そうそうたるメンバーが踊る。企画とアイディアは面白い。が、最近のオーリンの作品に見られる、即興の面白みが全くなかった。与えられた動きをいかにこなすか、という事においては長けていても、イメージから動きを生み出し膨らませる事が、オペラ座のダンサーには欠けていたように思う。この2つの事は全く質が違うからだ。オペラ座のダンサーはすばらしと思う。身体の使い方が全く違うクラシックバレエとコンテンポラリーを見事に踊り分けられるバレエ団となった。これはセーヌ65号でも書いたし、本当にそう思う、ただ、即興ダンスにはまだ慣れていないようだ。例えば、リッシュがブラジャーを着けてお尻を振るのも、大きなアヒルの映像と戯れるのも、アリス・ルナヴァンが動物の仕草をするのも、それなりにこなしている。しかし、それ以上のものは感じられなかった。ヴェラ・マンテロがオーリンの作品を踊った時の様に、まるでそのとき初めてハプニングが起こってしまったかのように演じ、観客とあたかも会話をし、次に何が起こるのかわくわくするしながら見入るような雰囲気は、あいにく感じられなかった。ただ、オペラ座のダンサーは選ばれた人たちばかり。数年後には、この作品を踊りこなしているだろうと確信する。(4月23日オペラ座ガルニエ)(文中写真(C)Maarten Vanden Abeele)

池田扶美代はやっぱりいい。さらに奥が深くなった。踊りも、演技も、存在感も。ただ、この作品は、台本自体がきつかった。アフリカの内戦。子供兵士の話。その上、ベンジャマンの意気込みがすごくて、叫んだり暴れたりわめいたりするのが、見ていて辛かった。そんな時に、池田の動きだけを見ていると、救われたような気になる。乱暴に扱われてもきょとんとしている。ベンジャマンがわめき散らしても、それにおかまいなく彼女は自分の世界を保っている。時には無垢な子供、時には年頃の女性、そして母。その微妙な変わり様がなんとも良いのだ。作品に関係ないようでいて、ちゃんと作品の中の人になっている。その距離の置き方が素晴らしかった。ただ、アラン・プラテルがどのように作品に関わっているのかが最後まで見えず、聞いたところ、演出家として、作品がはみ出さないように統制していたという事だが、プラテルと池田がどう関わり合うかを来期待していた私にとっては、彼らしい色が出ていなかったような印象が残り、ちょっとがっかり。(4月24日アベス劇場)

(C)HERMAN SORGELOOS
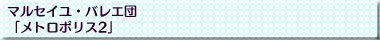
機械のようにハイテンションで、正確に動くダンサー達。そして目を見張る大掛かりな装置。完璧故に感じる冷たさが気になっていたのだが、この作品はちょっと印象が違った。バレエ団の芸術監督であり、振付家のフレデリック・フラマンは頭の良い人だと思う。自分のやりたい事と、置かれた環境を見事に交えて行く。彼は、シャルロワダンスというコンテンポラリーカンパニーから、南の港町マルセイユのバレエ団という、全く環境の違う場所への移籍した。しかも、ローラン・プティ、ピエトラガラと、大物が仕切ったバレエ団を、いきなりベルギーのコンテンポラリー振付家が仕切るわけだから、そう簡単にいくわけがないはず。それを、着実に自分のカラーに染め(もちろん、遠藤康行をはじめ、何人かのダンサーを移籍させたが)、しかもバレエ団の特徴も取り入れいれている。前作は、どこか躊躇しているところがあったのだが、今回はそれがない。今後は、フランス版フランクフルト・バレエ団(フォーサイス時代の)、或はNDTになるのではないかという予感までさせる。ザハ・アディの装置はシンプルだが、ダンスと装置の必然性が見え、何より融合していたのが良かった。フラマン作品の装置は、美術というより建築に近いことで有名で、いつも目を見張るものばかりだったが、余りにも出来すぎていて、ダンスより装置に目が行ってしまう事もあった。が、この作品は全てがバランスよくまとまっていた。また、遠藤が中心的役割を果たしていたのは、日本人として嬉しかった。

なお、この作品の開演前に、カンパニーのダンサー、カタリナ・クリスティがホールでソロ作品を上演。赤いヒモに仕切られた空間を、身体が空間に切り込むようにシャープに動く。踊りのうまい人だ。最後はバリカンで実際に髪をそり落としてしまうという、ちょっとびっくりパフォーマンス。でも思わず、明日の公演ではどうするのだろう、もう剃る髪もないし、と余計な心配をしてしまった。彼女はこのあと出演した「メトロポリス2」では、さらにきれいに剃り上げて、ほとんど坊主頭。本公演前にあれだけ激しく踊って、メトロポリスでも過激にエネルギーを発散し、その体力には圧倒された。(4月26日メゾン・デ・サール・クレテイユ)
|

