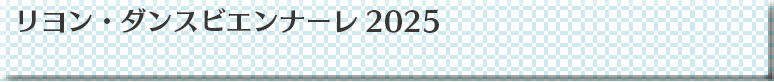

第21回目を迎えたリヨンのダンスビエンナーレが9月6日から28日まで開催された。40公演のうち24作品が新作で、14カ国からの参加と、やはりリヨンの規模は大きい。ギ・ダルメが定着させたダンスビエンナーレを、ドミニク・エルヴュが独自の視点で開拓を進め、現在の芸術監督ティアゴ・ゲデスが若い世代を巻き込んで新たな方向性を打ち出しているという印象を受けた。前回から始まった「クラブ・ビンゴ」で、朝まで踊りまくるイベントは大盛況だ。
Yuval Pic ''Into the silence''
Leïla Ka ''Maldonne''
Luiz de Abreu & Calixto Neto ''O samba do Crioulo Doido''
Collectif A/R ''Dancing''
さて、所見した作品の紹介の前に、新たなダンス賞を紹介したい。
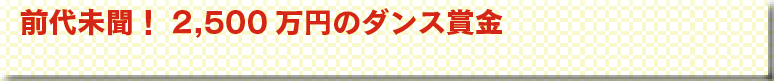

芸術部門では真っ先に不況の煽りを受けるのがダンスと言われている中、なんと15万ユーロ(約2,500万円)の賞金が与えられるダンス賞が創設された。
Salavisa European Dance Awardで、ポルトガルのカルースト・グルベンキアン財団によるもの。非常にレベルの高かったグルベンキアン・バレエ団はあいにく2005年に解散してしまったが、芸術への支援は常に行われていた。そんな中、1977年から1996年までグルベンキアン・バレエ団のダンサー、指導者、そしてバレエ団の芸術監督を務めたジョルジュ・サラヴィサJorge Satavisaへのオマージュとしてこの賞が創設され、その第1回目の受賞者二人が発表された。
ドロテ・ミュニャネザ(Dorothée Munyaneza、ルワンダ/イギリス/フランス)とイディオ・シシャヴァ(Idio Chichava、モザンビーク)だ。
ドロテ・ミュニャネザは、ルワンダ生まれでイギリスとフランスに住む、ダンス、演劇、音楽に才能を発揮しているマルチ・アーティストで、今年のリヨンのダンスビエンナーレでは、パリのポンピドゥセンター一推しのアーティストとして4日間にわたるイベントを開催した注目の若手アーティストだ。
一方のイディオ・シシャヴァは、モザンビークを拠点に活動する振付家で、その振り付け・演出の才能には多くの期待がかかっている。今回上演された「Vagabundus」は、昨年のジュン・イヴェンツ/June Eventsでの印象が強く残っている若手振付家だ。
2023/24年のインプレッション、下記リンク先のでも触れています。
https://office-ai.co.jp/_edi/_edi-history/edi-20240602.html
2年に一度与えられる賞の賞金は、なんと15万ユーロ。日本円にして2,500万円(1ユーロ166円計算)という破格の金額。欧州では「芸術への投資」も盛んで、この賞金で シシャヴァはダンススタジオを建設して、祖国でのダンスの普及に努めるという。
作品に対する賞金はあっても、長期間のプロジェクトに対してこれほどまでの高額な賞金を出す機関は珍しい。厳選な選考のもとに才能に投資するという考え方が定着している欧州ならではの賞だ。なお、この章は2年に一度与えられ、全世界のアーティストを対象としている。
では、所見した作品についての感想を。
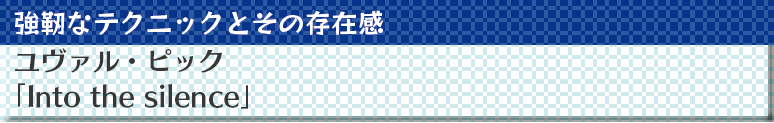

©Sébastien Erôme
CCNリリュー=ラ=パプを離れての最初の作品は、女性二人のデュエットと男性のソロの小規模ながら見応えのある作品だった。
前半は女性のデュエットで、バッハのゴルトベルグ変奏曲に乗って、ゆっくりとしたステップを踏みながら体を捩らせる動きがメインだ。付かず離れずの二人は、時折同じ振りをしたり呼応しながらも、それぞれの世界観を持ち続けている。
デュエットが終わると男性のソロが始まった。同じバッハのゴルトベルグ変奏曲だが、印象は異なる。どっしりと地についた動き、何にもせずに一点を見つめて立っているだけなのに空間が広がる。スピーカーを持ち運ぶことで音源が変わり、また別の世界が広がる。
ピックは長年共に活動しているダンサー3人を選んだというだけのことはあって、3人ともピックのメソード、そしてその思想が深く体に刻み込まれていると感じた。ダンサーの一人小林円香は最も古く、2011年にピックがCCNリリュー=ラ=パプのディレクターに就任して以来ずっと活動を共にしている。男性ダンサーのギヨーム・フォレスティエは2018年からだが、舞台に現れた瞬間にピック自身の踊る姿と重なった。私が最初にピックの踊りを見たのは、1996年のパリ・コンテンポラリーダンス国際コンクールでの、どっしりと土から湧き出るような踊り。細身で柔軟性があり、スルスルとテクニックを見せるダンサーが優勝すると思っていたのに、そのイメージとは異なるピックがグランプリ。多くの人がその存在感を讃えていたが、当時の私には「それまでに見たことがないもの」であり、舞台に存在する意味を考えさせられたコンクールだった。その当時の衝撃が今、この作品を見て蘇った。
なぜ舞台で踊るのか。何を以って舞台に存在するのか。
この3人はその意味を知っている。そのピックの思想を表現するだけの確かなテクニックがある。テクニックに関して言えば、例えば、足をふり上げると同時に上体を倒してから上に持ち上げる動きや、力強いジャンプと歩幅のある移動などで、地面を感じさせるムーブメント、これがピック節なのだろう。私ごとで恐縮だが、理想のダンスを求めて渡仏した私にとって、もしかしたらこれが長年求めていたものかもしれないと、心が震えた。
フリーランスになって新たな方向性を見つけるのか、今後も個性的な思想を持つピックを応援したいと思う。
そして、小林円香。欧州人に比べて決して優れた体型を持っているわけではないが、ふとした瞬間に彼女の持つオーラに引き込まれる。いつ見ても変わらぬエネルギッシュなダンサーだが、今回はその中にきらりと光る優しさが特に印象に残った。ピックと共にフリーランスとなったことを一つの起点として、更なる活躍を期待したい。(9月24日Théâtre de la Renaissance/ Biennale Danse Lyon 2025)

©Sébastien Erôme

©Sébastien Erôme
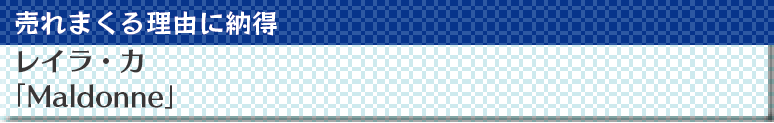
今私が注目している新鋭の振付家。ダンサーとしても素晴らしいが、振付家としても才能を発揮している。2023年に作られたこの作品は売れに売れ、今シーズンが終わる来年6月までツアースケジュールはびっしりだ。2026年2月には、なんとパリのオランピア劇場での公演が予定されている。
5人の女性がじっと佇む。涙を拭いたり、ひたいの汗を拭ったりするような動作がゆっくりと繰り返される。悲しみを携えた女たち。その動きが次第に激しくなるとともに、呼吸音と倒れる音がリズムを作る。倒れては起き上がり、また倒れては起き上がり、今度は着ていた服を脱ぎ捨てて床に叩きつけ、怒りをぶつけながら床を擦るような動作。 タイトルのMaldonneは、「トランプの配り違い」とか、「誤解」「間違い」という本来の意味と「マドンナ」を合わせたイメージでつけたということから、女性を蔑視する社会を批判したものだろう。ちょっと古めかしい服が、こき使われる家政婦を連想して重いなあと思い始めたのだが、「私は惨め〜、私は悲しい〜」などという歌詞に合わせて口パクで歌い始めたあたりから、あら? ヒステリックに怒りをぶちまけ、八つ当たりに取っ組み合いの喧嘩が漫画チックに描かれた場面には、これはパロディだったのか? と吹き出してしまった。臨月の妊婦の腹から出てきたのは大量の布。これを投げ合い、いがみ合うなり助け合うなり忙しい。そして最後は重ね着していた服を脱ぎ捨てながら床に叩きつけて、でもそれは女性の勝利を仄めかす。見事な展開だった。
ダンスのレッスンを受けたことも、ダンス学校に通ったこともなく、バスケットシューズでストリートからダンスを始めたというレイラ・カ。マギー・マランとの出会いがコンテンポラリーダンスの世界に入るきっかけだったという。今後どこまでブレイクするのか、注目に値する新鋭。(9月25日Toboggan, Décines/ Biennale Danse Lyon 2025)

©Monia Pavoni
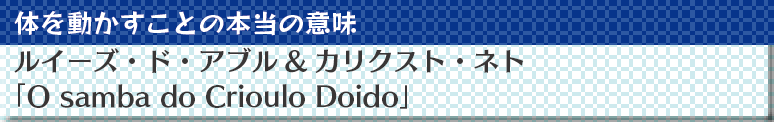

©Gil Grossi
ホリゾントいっぱいにブラジルの国旗。その前でシルエットとして浮かび上がる男が、クネクネと体をくねらし踊っている。ズーンズズン、ゆったりとしたリズムとそれをつき破るかのような叫び声の中、高いヒールのブーツを履いた男はしなやかに、そしてセクシーに腰や腕を動かしている。舞台の前面に出て立ち止まった時、突然照明がついた。彼は全裸で正面を見据えて立っている。ただじっと立っている。すると胸や腹の筋肉を動かし始めた。後ろ向きになって肩甲骨を動かす。尻を細やかに早く揺らす。顔の表情を変える。激しく動いているわけではないのに、汗で体が光っている。体のあらゆる部分の筋肉が動いている。体の芯から動きが出ているのだ。
今度はブラジルの国旗が印刷された布を纏ってのファッションショーだ。この布の数箇所に穴が開いていて、そこに手足や顔などの体の一部を通して纏えば、一枚の布が百変化するのが面白い。最後は布を振り回しながら舞台を走り回る。
ここまで見て、いまいち作品の趣旨が見えなかったのだが、この後の練習風景の映像を見て全てを納得した。ダンススタジオとは思えない、ガレージのようなコンクリート剥き出しの場所でのリハーサル。振付家のルイーズ・ド・アブルが カリクスト・ネトを指導するが、彼は視力を失っている。それなのに見えている。「そうじゃない、こうだ」。ポーズを見せ、時に体に触れて位置を直す。
「動きを作るな! 呼吸が自然に動きを導く」
この言葉が刺さった。意図的に作られた形だけの動きは心に響かない。体の内面から自然と吐き出された動きが必要なのだ。この時この作品の意図が見えた。この作品は当時のブラジル社会への痛烈な批判だったのだ。性、ジェンダー、表現の自由、本音と建前…。冒頭のゆったりとしたリズムの中の叫びは「肉!」だったのだ。痛烈な批判をしながらも、愛国心は忘れない。
2004年に初演された作品とはいえ、現代にも通じるものがあるから、再演され続けているロングランなのだ。ルイーズ・ド・アブルの舞台作品に対する強い信念に唸らされた。(9月26日TNG-Les Atellier Presqu'ile, Lyon 2)

©Marc Domage
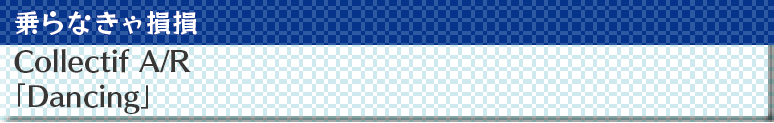

©Noémie Lacote
以前は国鉄車両の修理場だった巨大な建物が文化施設となり、そこで行われたCollectif A/R の「Dancing」。中央に組み立てられた台の上にミキサーとドラム。客席はないから、台を囲むようにして皆座っている。暗くなるとともにネオンが輝き、ダンサーたちが登場して台の上で軽く踊ったあとは、ダンサーたちの指示に沿って客は移動し、できたスペースやお立ち台のような台の上での踊りが始まる。カンパニーダンサーは5人だけれど、アマチュアダンサーたちが踊りながら参加している。シンプルな動きなので、こうなったら一緒に踊っちゃえ〜! というのも勿論あり。もうここはハウス、ダンシングルームなのだ。乗らなきゃ損! 楽しまなくちゃ損! まさに「ダンシング」。音楽はライブでミキサーしたりドラムを叩いたり。客のノリとダンサーに合わせての即興も交えている感じだ。ふと横を見ればダンサーが隣にいて笑っている。微笑み返して一緒に踊って、彼女はまたどこかへ消えていった。そして気がつくと5人のダンサーたちは客が入れない場所で見事なパフォーマンス。ここはハウスでもあり、ロフトな劇場でもあるのだ。ダンサーと共に楽しむ一夜。乗ったが勝ち!(9月26日Les Grands Locos, La Mulatière)

©Noémie Lacote

©Noémie Lacote
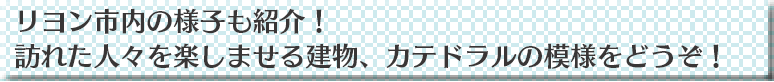

©Masumi
今年のビエンナーレは、グラン・オテル・デュー内のシテ・アンテルナシオナル・ド・ラ・ガストロノミー・ド・リヨンに事務局を構えた。

©Masumi
ローヌ川沿いに立つオテル・デュー。この広大な建物は、病院、そしてホスピスとして機能していたが、2019年に大改造され、高級ホテルやショップ、レストランが入り、中庭も整備されて市民の憩いの場となっている。
Cité International de la Gastronomieと書かれたドアを入ると、売店があり、軽食を取れるようになっている。2階に上がれば広い明るい空間になっていて、

©Masumi

©Masumi
たくさんの薬の陶器の入れ物が、昔は病院だったことを窺わせる
この場所はシテ・ド・ガストロノミーだったが、コロナ禍以降閉鎖している。ビエンナーレの間は、コンファレンス会場や、ダンススペースも用意されていて、歴史的建造物の中で過ごすことの心地良さを堪能した。
この一角で3つのビデオが上映されていた。アジア系のグループによる無表情なのに滑稽な動きをし、民俗的なような現代的な映像作品、オーストラリアでの原住民への弾圧をダンスと映像で訴えた作品、そしてエステル・サラモンのシュールな映像がそれぞれのスペースで投影されていた。
エステル・サラモンは、独特な美学を持ったアーティストだ。今回上映された「ランドスケープ」はオレンジ色を基調としたビデオと緑を基調とした映像が並んで上映されていた。
身体中をオレンジ色の服やオブジェを纏った人たちが、崖や海に突き出す岩肌の上でかなり強い風に吹かれながら立っている。海や空の青と岩肌の茶色、そこにくっきりと映えるオレンジ色が美しい。一方の隣の映像は森の中。しっとりとした緑一色の中に黒いものがゆっくりと動いている。黒い陰が木々の間から現れ、そして静かに消えていく。森の精霊だろうか。
鮮やかなオレンジと緑の色彩が鮮烈だ。ワンシーンがかなり長く、動くものは少ないのに見入ってしまうのは、自然の美しさのせい?いや、何かが違う。後半でオレンジ色の服を纏った人たちのアップが映った。なんと、彼らが纏っていたのはゴム手袋とか道路工事に使われる標識やオブジェだったのだ。長い年月をかけて自然が作り出した地形と、短期間でそれらを壊して新しいものを作り上げる現代社会への批判ではないだろうか。そして緑の映像に映った黒い影は、黒い脳みその頭を持った人。自然を脅かす開発は、人間の頭脳が生み出したものだ。なんという社会批判!静かに、じわじわとメッセージが伝わってくる。
広い会場に二つの大画面。そこに大きなクッションが置かれていて、ゴロリと横たわって映像を見る。まるでミニシアターだ。映像の一部だけを見れば色彩が美しくダイナミックな映像でしかないが、全体を通してみるとたくさんのメッセージが見えてくる。映像と空間演出は見事に計算されていたのだ。さすがサラモン。

©Mattias Pollak

©Mattias Pollak
少し目眩を感じながら会場を出れば、新旧が混在したホールに出た。ここも歴史を感じさせる場所だ。この機会に建物内を回ってみた。

©Masumi

©Masumi
内部は近代的な装飾で、ショップ、レストラン、ホテルがある
いくつもある中庭は、それぞれの趣がある

©Masumi

©Masumi

©Masumi

©Masumi
昔の面影を残す装飾が歴史を感じさせる

©Masumi

©Masumi

©Masumi
余談になってしまったが、リヨンを訪れたら是非ともこの過去と現在が融合した場所に立ち寄られることをお勧めしたい。
最後にリヨンを見下ろすノートルダム大聖堂を!

©Masumi

©Masumi
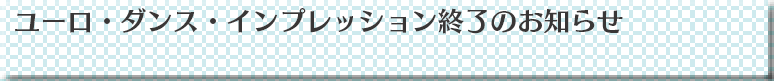
今回をもちまして、ユーロダンスインプレッションは終了いたします。が、「この感動を伝えたい!」とサプライズ登場があるかもしれません。
国籍を問わず、年齢や職業、熟練、アマチュアを問わず、ダンス好きは世界中にたくさんいます。そして舞台は素晴らしい。たくさんの人が関わって、協力しながら一つの作品を作り上げるからです。そして先人の開拓精神を忘れてはなりません。過去があるから現在があり、そしてこの先もどんどん変わっていくでしょう。
ダンスの本場と言われるフランスで、たくさんのことを,知りました。遠くから日本を見て、日本にいたら知り得なかったことも感じました。世界は広い!そしてその広い世界を見て、本誌創設者の故飯島篤が舞台芸術に魅了された気持ちを私なりに感じ取ることができました。
この場をお借りして、株式会社エー・アイの皆様と、そしてこのコラムを読んでくださっている方々に感謝しながら筆を置きます。ありがとうございました。
編集室より
2004年の連載開始から20年以上、貴重なインプレッションの数々をありがとうございました。
インターネットの普及で世界の“情報”の距離は近くなりました。高品質なライブ動画を遠隔地で見ることも容易になりました。便利な時代になり、その恩恵を有り難く享受し活用する一方、ナマモノである実際の舞台を、現場の空気を感じながら観たうえでのインプレッションは、私たちをより深く広い想像の世界に誘ってくれました。日本にいながらにして、フランスを中心としたヨーロッパのダンスの様相を楽しめたことを、筆者のMASUMIさんに改めて感謝!
本ページはもちろんこのまま存続します。インターネットに繋がる機械と、それを動かす電力がある限り、いつでもどこでも読んで、調べて、感じてください!
|

