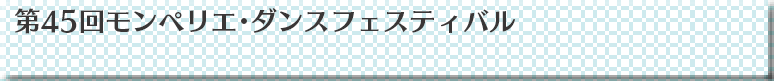
45回目を迎えた今年のフェスティバル・モンペリエダンスは、6月21日から7月5日まで開催された。今回の演目を決めたディレクターのジャン=ポール・モンタナリが4月に亡くなり、いまひとつ活気に欠ける感があったが、公演は大盛況で、43年に渡りフェスティバルを率いてきたモンタナリの精神は、しっかりと根付いているようだった。9月から始まる新シーズンからは、新たな4人のディレクターによる新生モンペリエダンスが始まる。
モンペリエにはアゴラダンス都市があり、モンペリエダンスとCCNの二つの異なる組織で運営されていたが、今後はこれらが合体して一つの組織としてダンスの開拓・発展に努める。それを担うのがドミニク・エルヴュ、ピエール・マルティネズ、ホフェッシュ・シェクター、ジャンヌ・ガロワの4人だ。ドミニク・エルヴュはパリのシャイヨー国立ダンス劇場、その後はリヨンのメゾン・ド・ラ・ダンスとダンス・ビエンナーレのディレクターを務め、2024年のパリオリンピックでは文化監督を務めた経歴を持つダンスを知り尽くした人で、ピエール・マルティネズも経験は豊かだ。多くのフェスティバルや劇場のディレクターを務め、特にディレクター交代時の橋渡し役として定評がある。この二人が全体を総括するとともにモンペリエダンスを引き継ぎ、世界的に注目を浴びている振付家のホフェッシュ・シェクターと新鋭振付家のジャンヌ・ガロワがダンサーの育成などのCCNの使命を受け持つことになるという。個性の強い4人がどのようなタッグを組むのかが気になるところだ。2025/26年のシーズンの上演演目は、モンタナリが決めたものと新たなディレクターが選んだ作品がミックスされたものになるそうだ。
モンタナリが43年かけて築き上げたモンペリエのダンス市場が、さらに発展することが期待されている。
さて今年の演目は、アクラム・カーン、カミーユ・ボワテル、エリック・ミン・クォン・カスタン、ピエール・ポンヴィアンヌ、NDT、フレンズ・オブ・フォーサイス、ダヴィッド・ヴァンパク、マチルド・モニエ、イスラエル・ガルヴァンなどで、ヒップホップの第一人者と言われるムラッド・メルズキが自身の作品も上演する他に、コメディ広場でのパフォーマンスでフェスティバルの幕を閉じる。オープニングにバットシェバ舞踊団が招待されていたが、イスラエルとパレスティナの戦争の影響で空港が閉鎖されたために渡仏できずに中止となったのは残念だった。何度もモンペリエダンスに招待されていたオハッド・ナハリンは、モンタナリへの追悼も込めて、予定の作品を変更しての上演を準備していたが、あいにくそれは叶わなかった。
アルジェリア生まれのモンタナリ。15歳でフランスに移住し、学生時代に演劇に興味を持ったことからダンスへと進み、ドミニク・バグエとの運命の出会いによって移り住んだモンペリエ。1983年から2024年までディレクターとしてモンペリエダンスを率いただけでなく、モンペリエ市の文化にも大きく貢献した。地中海に対する思いは深く、何度も地中海をテーマにしたフェスティバルを企画し、沿岸諸国のカンパニーを招待していた。
墓参をしたいと申し出たところ、遺灰は地中海に撒かれたと言うので海に行った。氏のことを思い出しながら泳いでいたら、前方にオレンジ色の浮遊物を見つけ、手に取ってみたら一輪の薔薇の花だった。氏に会えたような気がした。
では、6月26日から4日間に所見した作品を簡単に紹介しよう。
・Nederlands Dans Theater & Complicité
Crystal Pite & Simon McBurney ''Figure in extinction''
・Friends of Forsythe
・Israel Galvan & Michael Leonhart ''A new sketches of Spain''
・David Wampach ''Du Folie''
・Nadia Beugré ''ÉPIQUE ! (POUR YIKAKOU)''
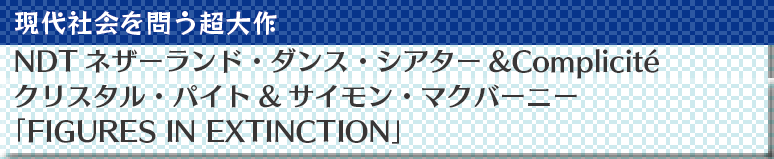

©Rahi Rezvani
辛辣なメッセージを送る作品が印象的なクリスタル・パイトが劇作家のサイモン・マクバーニー と組んで4年に渡って創った3作品が一挙に上演され、上演時間は休憩を入れて2時間超という大作だった。
全体を通して、環境問題を中心に現代社会が抱える問題を提起している。異常気象が様々な被害を自然界にもたらしていることを語る第1部。「動物は動物園でしか見られなくなるの?」このセリフが胸に刺さる。パソコンや携帯電話を見続け、上司の指示通りに働くスーツ姿の人たち。自然には触れない、考えない生活に慣れてしまった多くの人々を描いた第2部。「死」。それは生命を持つものが必ず迎えること。その一方で新たな生命が生まれ、歴史は続いていく。地球環境が悪化しても、だ。どこかに希望を求めるレクイエムの第3部。ダンスとセリフが見事に交差し、それを演じ切ったダンサーたちのエネルギーには圧倒された。
振付家がテーマを出して振り付けを始め、それに呼応する脚本と演出を手がけた第1部、第2部と第3部は先に台本とセリフがあり、それに対しての振り付けが行われたという。ダンサーは踊りながらセリフを語り、歌う。ジェスチャー的な動きが続く中の一場面で、バレエ的な動きが展開された時、空間が一気に広がった。エッジの効いた動きに見慣れていた目には、このふわ〜っとした動きに転換した瞬間の空気の変化が新鮮で、作品の広がりを感じるとともに、ダンサーのレベルの高さに釘付けになった。
現代社会を鋭い視線で分析し、そこに生きる人々の思惑が交差する。23人のダンサーが演じる現代社会の構造が、過去に起きた事件や問題を思い起こさせる。ブレのない鋭利な動きを綴りながら吐かれたセリフが心に刺さり、ふと立ち止まった時の感情に解される。そんな振り付けと演出が見事に融合し、それを的確に演じたダンサーたち。振付家、演出家、ダンサーのエネルギーが見事に融合した、見応え十分ではあったものの、休憩を含めて2時間強の間、台詞とダンスが息つく暇も無いほどの勢いで埋め尽くされていることが少し重く感じられ、その夜はなかなか寝付けなかった。(6月27日OPERA BERLIOZ / LE CORUM)

©Rahi Rezvani
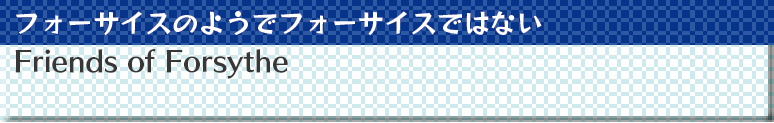

©Laurent Philippe
フォーサイスの名前がつくだけで、あっという間に完売になるのかと、改めて人気の程を知ったのだったが、公演を見て納得。キレの良い動きとシンプルながらも斬新な照明、そして密度の高い構成にはブラボーというしかない。
三方の客席に囲まれた四角い白いスペース。そこで男二人が座った姿勢で絡まっている。お互いの手足が絡まって動けないのか動かないのか、かなりの時間その姿勢は続いた。それが崩れて動き出すも、二人の体の一部は常に絡まったままだ。パンと手を打つ音で一瞬にして暗転となり、すぐに明かりがついてまた動きが始まる。体がくねり、ねじれ、回転して相手の体に滑り込む。その連鎖が面白くて目が離せない。
手を叩く音とともに暗転になり、次のシーンが始まるという構成の第1部。そこに別のダンサー二人が現れて交代し、コンタクトをしたり並んで早い動きをしたり、テンポよく温度が変わり見ていて飽きない。今度は男女二人が出てきての踊りだ。ここで踊る男性ダンサーのブリゲル・Gjokaは、フォーサイス独特の動きが身についているダンサーで、フォーサイスのフランクフルト・バレエ時代の作品のファンとしては懐かしく、惚れ惚れとしてしまう。相手の女性ダンサー、ジュリア・ウェイスはパリ・オペラ座にも在籍したダンサーだが、ブリゲルのテンポに合わせようとしているのか、どこか伸びが感じられなかったのだが、その後のソロではすばらしい踊りを見せてくれた。ラストはこのプロジェクトを主催するラフ<RubberLegz Yasit>とブリゲル・Gjokaのデュエット。この二人は長年共に活動していて、2019年に創作した「Neighbours」を2021年のリヨン・ダンスビエンナーレで見たが、その時よりずっと綿密になっていた。ラフはどちらかと言うとヒップホップのダンサーで、Gjokaはフォーサイス節のバレエダンサーという色が濃く出ていたのだが、今回は両者の特徴を活かしながらも、ヒップホップでもバレエでもなく、その二つが融合したような滑らかな動きの連続になっていて、見応えがあった。
ラフはフォーサイスにメールで連絡を取り、ラフのプロジェクトにフォーサイスが興味を示して「Friends of Forsythe」ができあがったのだという。フォーサイスらしさの中に、別の要素が加わった新しいプロジェクト。第2作はあるのだろうか?(6月29日Théâtre Jean-Claude Carière Domeine d'O)

©Laurent Philippe
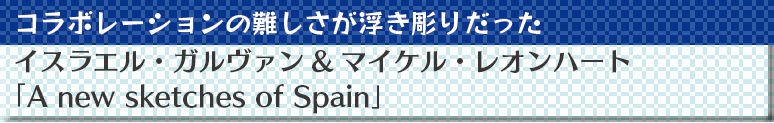

©Laurent Philippe
ジャズの巨匠マイルス・デヴィスが1960年に出したアルバム「sketches of Spain」にインスピレーションを得た二人によるコラボレーション。
イスラエル・ガルヴァンはフラメンコ界の一匹狼とも言える存在で、フラメンコ舞踊の常識を覆すようなアバンギャルドというかコンテンポラリーフラメンコ作品を創作している。一方のマイケル・レオンハートは17歳でグラミー賞を受賞したというジャズのトランペット奏者だ。この大物アーティストの共演に大いに期待したのだが…
アゴラの屋外劇場が夕闇に包まれ始め、舞台は赤く照らされていた。下手から3分の2はミュージシャンが位置し、上手側にイスラエルが登場する。そしてマイルス・デヴィスのアルバム同様に曲が始まった。ピアノ、チェロ、バイオリン、クラリネット、フルート、ドラム6人をトランペットを吹きながら指揮するレオンハート。そこにガルヴァンがカスタネットなどで参加しようとするのだが、演奏者は譜面とレオンハートの指揮を見るばかりで、ガルヴァンの存在など全く意識していない感。音楽は7人で完全に出来上がっているから、ガルヴァンが介入しても雑音としか聞こえない。サパテアードを踏んでも、パルマやカスタネットを叩いても、全く曲に入る余地がないのだ。なんとか中に入ろうとするも、一部の隙も見つけられず、上手の袖の階段を上り下りしてみたりして、地味に参加している。そのうち椅子に座って曲を聴いていた。コンファレンスでは、スペイン語しか話さないガルヴァンと、英語しか話さないニューヨーカーのレオンハートがどのように作品を詰めたのかという質問に、言葉はわからなくても、音楽とダンスで会話したと豪語していたのだが、いったい彼らはリハーサルをしたのだろうかと疑いたくなってしまう。唯一ドラム奏者がガルヴァンの動きを意識している以外は、誰もガルヴァンの存在さえ意識せず、コラボレーターのレオンハートもガルヴァンを見ることもなく、楽団の方を見て客席には背中を向けていたのに、コンサートのように一曲が終わればくるりと客席を向いてお辞儀をする。あら?これはコンサートだったのかしら? ダンスじゃなかったの?
しかし流石にガルヴァンも剛を煮やしたのか、次の曲が始まる直前にメタルを甲高く叩き始めたのだ。流石にこれでは次の演奏に入れない。ここでようやくレオンハートはガルヴァンを見、そこに突き刺さるようにガルヴァンが踊り始めたのだ。こうなったらガルヴァンの勝ち。ようやく二人の即興的コラボが始まった。これは素晴らしかった。これが見たかったのだ! ガルヴァンの食いつきを見事に受け入れ、それを返し、それにガルヴァンが答える。最初からガルヴァンに意識を持っていたドラムが即興で加わり、見事なコラボだった。一方の他の演奏者たちは、唖然と成り行きを見ているだけ。そこに加わることもなく、ここで初めてダンサーがいたのね、という感じで見ているだけ。最後の方になってようやく体がリズムを刻み始めた演奏家がいた程度。彼らはこの公演の趣旨を知らされていなかったのだろうか、あるいは即興演奏をしたことがないのだろうか?譜面ばかり見ていないで、全体を見てよ! と言いたくなった。
所見したのが初日だったので、翌日は最初から見事なコラボが見られたのではないかと信じたいが、ジャンルの異なるアーティストのコラボレーションの難しさが浮き彫りだった。(6月29日 Théâtre de l'Agora)

©Laurent Philippe
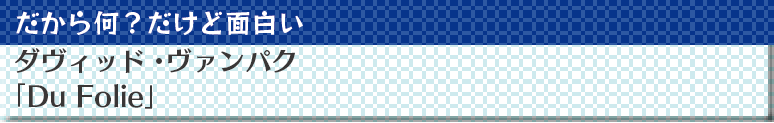

©Laurent Philippe
会場に入れば男3人が真っ赤な長椅子に寄りかかって座っている。 からだ半分が黒と白のレオタード姿という衣装に、どんなことが始まるのかと期待していたのだが、何も始まらない。だから観客はお友達とおしゃべりを始めたりしている。長すぎる、何も始まらない、と思いきや、あら? 3人の表情が少しずつ変わっているではないか。会場を見回しながら目を細めたり、見開いたり、微笑んだり、ぼーっとしたり。そしてずるずるっと動き始めた。隣の人に寄りかかったり、長椅子にのそのそとよじ登ったり、ずるずると動きながらも、時折ピシッとポーズが決まったりして、ただずるずるしているわけではないようだ。このずるずるのコンタクトをしているうちに、一人が台の後ろに消えて、しばらくして現れたらなんとゴールドのボールが5つくらい付いた顔になっていた。重ねた台を一気に崩すシーンは、ピナ・バウシュのパレルモパレルモを連想したが、規模が小さいので可愛らしい。そして最後は3人ともボールをくっつけた顔で登場して、震えたり、歩き回ったり、くっついたり離れたり。だから何? なのだけれど、ヴァンパクらしい。
以前に京都エクスペリメンタルで「Bascule」上演した時に馬鹿受けだったと聞いた。では、この作品を京都人はどう見るのだろうかなどと想像してしまった。(6月28日 Hangar Théâtre)

©Laurent Philippe
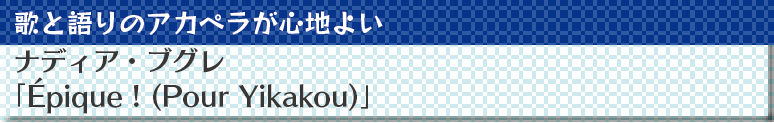

©Werner-Strouven-RhoK
遠くから聞こえてきた歌声。振り返れば客席の後ろから二人の女性が歌いながら舞台に向かっている。言葉はわからないけれど、歌と語りのようなアカペラが心地よい。そこに後から現れた振付家でこの作品を踊ったナディア・ブグレ。
プログラムに書いてあった彼女の言葉によると、コートジボワールの、今では消滅した自分が育った村への旅がこの作品のベースになっているという。雑草が生い茂る森の中で消滅した生家を探すということは、さぞかしむなしさや悲しみを訴えるのかと思ったら、明るい。歌手二人のリズミカルでハリのある元気な声のせいだろうか。
吊り下げられた木を連想するオブジェ、床に描かれる白い線、たくさんの棒を身体中に突き刺すように纏う。客にも配られるティッシュペーパーは、涙を拭うためというが、悲しみを誘う要素は感じられなかった。
なくなってしまったものは取り戻せない。でも、そこにはたくさんの想いや魂がある。それを糧に前に進んでいくこと、それが人生なのだ。生きることの強さを感じる作品だった。
それにしても、歌手の二人が素晴らしい。歌って良し、演技して良し、ブグレの作品の厚みを出すことを心得た演技が印象深かった。(6月26日アゴラ・バグエ・スタジオ)

©Laurent Philippe
私が注目している振付家のピエール・ポンヴィアンヌ。昨年に初めてモンペリエダンスに招待され、当時のディレクターのモンタナリが絶賛して今年も選出され、世界初演作品「La Liesse」を上演したのだが、あいにく所見日の本番2分前に劇場が停電して公演が中止となったのは非常に残念だった。好評だっただけに尚更悔やまれる。

©Laurent Philippe

©Laurent Philippe
|

