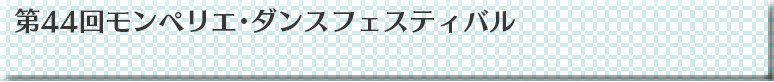

第44回モンペリエ・ダンスフェスティバルが6月22日から7月6日まで開催された。
昨年のフェスティバルではディレクターが引退を表明していたが、2025年のフェスティバルのプログラミングまで続投することになった。これはモンペリエ市などからの要請によるそうで、ディレクターのモンタナリ氏は市にはなくてはならない存在だということだ。
さて、今年の演目は、昨年すでに公表していた勅使川原三郎、クラウド・ゲイト・ダンスシアター、ミッシェル・ミュレイの他に、アンジュラン・プレルジョカージュ、ウェイン・マクレガー、ロビン・オーリン、ジョセフ・ナジ、アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルなどの錚々たる顔ぶれに加えて、若手振付家、実験的作品、そして過去を振り返る再演作品を織り込んだ豪華な演目だった。フェスティバルのオープニングを飾ったのは、勅使川原三郎、ロビン・オーリン、ウェイン・マクレガー。しかも全て世界初演!
日本人としてはなんとしても勅使川原三郎の世界初演作品を見たく、開幕から4日間滞在した。
所見した作品は以下の通り;
「Voice of desert」 Saburo Teshigawara
「..How in salts desert is it possible to blossom...」Robyn Orlin
「The cloud」 Arkadi Zaides
「Full Moon」 Josef Nadj
「Deepstaria」 Wayne McGregor
「Rush」 Mette Ingvartsen
「Roll」 Marta Izquierdo Muñoz
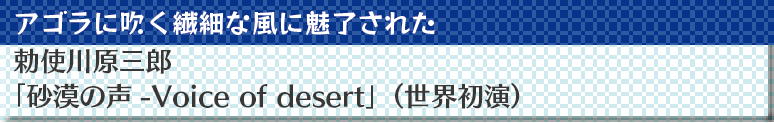

©Laurent Philippe
これまでにも何度かモンペリエダンスに招待されている勅使川原三郎。今回は初の屋外劇場での公演、しかもフェスティバルのオープニング演目であり、世界初演ともあって話題を呼び、その期待に応えるべく、会場には一筋の緊張感がみなぎっていた。
薄明かりの空の下、3人はゆっくりと歩いて出てきた。勅使川原、佐東、宮田だ。それぞれの場所に着き、同じ方向を向いた3人の黒い服が風に靡いている。そして聞こえる風の音。ゆっくりと勅使川原の腕が伸びる。そして舞台を横切る灯りが後ろに広がってはまた前に引き返す。
場面は転換し、中央に小さな丸い灯り。そしてそれを囲む丸い輪郭。バイオリンの優しい音色に勅使川原と佐東の体は揺れ、舞う。
勅使川原独特のスピーディーな動きの場面は以前より少なく感じたが、シャープさは以前と全く変わらない。そしてアブストラクトな動きの合間に見せる日常のたわいもない表情、それは不安であったり、希望や喜び。それらが声のない言葉になり、時に言葉になる以前の瞬時の感情が手に取るように見える。無機質に見える動きの中に、人の温かさが感じられて心がほぐれる。風がもたらすもの。そこにはたくさんの感情があるのだ。
佐東は風の流れが何かに当たって唐突に方向を変えたり渦を巻くように踊っている。以前より動きの高低差が明確になって面白くなった。
そして宮田。勅使川原が言っていたように昔と全く変わらない。15年間のブランクを感じさせないどころか、さらに存在感を増した感じだ。彼女はほとんど動かない。後ろの壁に沿ったところで、ゆっくりと揺れ、手を広げ、座って床を見つめる。その前で二人が激しく動いても、動きの少ない宮田の存在に目がいってしまう。なんという存在感!
この二人のミューズの間で踊る勅使川原。3人の共演を最後に見たのが、2003年の「Bones in pages」だった(クレテイユ・メゾン・デ・ザール)。これが宮田を見た最後で、同時に佐東を見た最初だった。そして20年後の今、再び3人の共演が見られたのは感慨深い。この二人の存在に触発された勅使川原のアーティストとしての歴史。KARAS創設から40年が経った。
二人のミューズが絡むシーンは、お互いを慈しむ家族のようだった。そして佐東が前に、その後ろに宮田が座って前を見つめた時、それは母(宮田)が娘(佐東)を優しく包み込んでいるように見えた。
突然飛び込んできた黒づくめの二人。加藤梨花と菰田いづみだが、顔は黒髪で覆われて見えず、素早く舞台を横切っては倒れる様子は不気味で滑稽で、作品の流れの大きなアクセントとなっていた。特に二人が揃いでステップを淡々と踏むシーンは、その速さと細かさと、クローンのように全くぶれない二人の踊りは驚異的とも言え、目が釘付けになったのは私だけではないだろう。このシーンにはヨーロッパのフォークロアダンスを連想したという人もいた。
そして突然鳴り響いた爆音。激しい攻撃の後の静けさ。瓦礫となった町。廃墟には誰一人としていない。ただ、そこには以前と変わらず風が吹いている。その風の中に誰かの声が織り込まれているのかもしれない。砂漠の声、人の声、風が運ぶもの…
フェスティバルオープニング日は、あいにく夕方から雨が降り出したが、開演20分前に雨は止み、肌寒い中ではあったが無事に初日を終え、私が所見した2日目は天候も良く、風が適度にあるベストな環境だったが、最終公演日の3日目は途中から雨が降り出し、3日間とも異なる雰囲気の作品になったと聞き、連日見るべきだったのかと後悔。この作品の日本での凱旋公演が実現することを祈らずにはいられない。(6月23日アゴラ劇場)

©Laurent Philippe
勅使川原三郎へのインタビュー記事は、セーヌ132号(2024年8月発売)に掲載しています
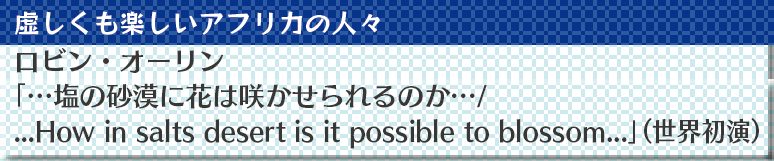

©Laurent Philippe
アフリカをテーマにした作品を作り続けているロビン・オーリン。直球のなかに変化球を入れたストライク。見事だった。
「ケープタウンから北へ向かった。ナミビアとの国境手前の街オキエプ。貧困が丸見えだ。
最初にここに住み着いた人たちは「有色」と呼ばれた。
1870年代、ここは鉱山の産出地で、世界で最もリッチな国だった。
鉱山は無くなったが、街は残った
冬には潮の花が舞う
昔の、鉱山で賑わった時代の前に戻った」
…塩の砂漠に花は咲かせられるのか…
ホリゾントに流れていた長いテロップが消えると、二人のミュージシャンと5人のパフォーマーが現れた。笑う。とにかく笑う。ゲラゲラ、ゲラゲラ。箸が転んでも笑う感じ。何がおかしいというのでもなく、笑顔と笑い声が絶えない人たち。その姿が多様な手法で加工されてホリゾントに映し出されている。オーリンの作品によく使われる小型カメラ。天井からのカメラに加えて、今回はスマホも登場。客席からは背中しか見えなくても、スマホで映せば正面から踊る姿が見える。オーリン得意の360度の実況中継だ。気がつけば舞台の左右にパソコンを前にした人がいる。カメラの操作と、捉えられた映像を加工する人たちなのだろう。最後には万華鏡のように体の一部が瞬時に形を変えて現れた。

©Laurent Philippe
二人のミュージシャンがいい。オペラ風、ファンキー風などと声色を変えて歌う女と、多様な楽器を演奏する男。5人のパフォーマーも個性的で、ダンサーとして、演劇人としても素晴らしい。特に年配の太っちょな女は偉大なる母という存在で味がある。彼らはガレージ・ダンス・アンサンブルというオキエプのグループで、今回初めてロビン・オーリンと組んだ。「過去のことなど話したくない。今の自分たちのこと、そして生きる喜びを語りたいだけだ」というグループの主張と、オーリンが見た街と人々、そして雨季の後の砂漠に咲く3,500種類もの野生のマーガレットの美しさ。これがこの作品のベースだという。
音楽とダンスだけでなく、映像も加わって、その瞬間にしかないエネルギーが会場を満たし、最後は観客総立ちの手拍子となって盛り上がった。盛り上がるからこそ、会場を出た後に残る虚しさ。
「…塩の砂漠に花は咲かせられるのか…」
明るく楽しい雰囲気の向こうに見える社会問題を、やんわりと、でも、きっちりと主張するオーリンの構成はさすがだ。
どんなに貧しくても、苦しくても、笑顔を絶やさない。笑いを忘れない。これを忘れてしまった人たちが世の中にはたくさんいるのではないか?会場を出る人の多くが明るい顔をしている。その笑顔をいつまでも。(6月22日Théâtre des 13 Vents Grammont)

©Laurent Philippe
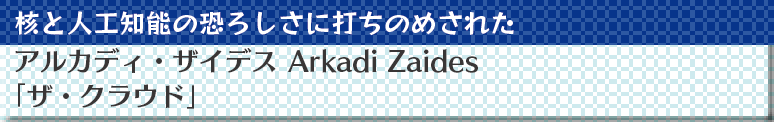

©Laurent Philippe
「ダンス作品にAI(人工知能)を取り入れてみました。」って、どうやって?
ベラルーシ出身のアルカディ・ザイデスが、7才の時にチェルノブイリ原発の事故で被爆した体験をもとに、ダンサー、IT技師、脚本家など国際色豊かなメンバーで作り上げた作品は、IT技術の発達によって我々の日常生活がどのような影響を受けるのかをテーマにしたディープな作品だった。
インターネットの普及により、多くの情報が氾濫し、さらにそれらが加工されて操作され、何が事実で何がフェイクかが見分けにくくなっている現代。そこに生きる我々の人間性は、人工知能によって変えられてしまうのか。クラウドってなんだ? クラウドに情報を記録させる、クラウドファウンディングって、空に浮かぶ雲と何が違う? 気候変動、環境破壊などと言うけれど、その全容が明確に見えているのだろうか。人工知能は日常にどのように関わってくるのだろうか。ドキュメンタリーは本当に事実を伝えているのだろうか。そんな疑問は、ロシアがウクライナに侵攻してチェルノブイリ原発を占領したことが、1986年のチェルノブイリ原発事故と繋がり、作品を作るきっかけになったという。
事故が起こった時、彼は7才でベラルーシのチェルノブイリ原発とはそう遠くないところにいた。第1部は彼が実際に経験したことを淡々と語る。その語りは、2面のホリゾントに映し出された映像によって増幅される。映像は次第に速度を増して変化する。小学校の集合写真は加工されて顔が歪み、写真や映像が目まぐるしく入れ変わる。事故が起こった時の町の様子、政府の対応、避難。体験者の言葉は私たちが知らない事実を語っている。加工することで何が事実かを混乱させる方法、そして核の脅威を知らずに推し進めたことへの恐ろしさを淡々と語っていた。
プルトニウムの寿命は2万4千年。健康な人の寿命は80年かもしれないけれど、被爆レベルによっては寿命はどんどん短くなり、数日ということもある。2万4千年対80年、60年、30年、10年、4年、1週間…。
2部では防護服を着たダンサーが踊る後ろで、チェルノブイリ原発爆発事故後の現場処理を撮影した映像が流れる。薄手の作業服に薄っぺらのマスクをつけただけの作業員が、シャベルで瓦礫を片付けている。国から表彰状をもらったところで、それは死と引き換えなのだ。事故処理に60万人が関わり、そんほとんどの人は亡くなり、生きているとしても障害を抱えているそうだ。そのことを誰も語らない。この映像は全く加工されていないそうで、これが事実だったのかと衝撃を受けた。
事実を伝えるドキュメンタリーとはいえ、厳密にはそれは事実の一部で、見た人の主観であり、別の角度から見た事とは異なることもあるし、加工されてフィクションになる事もあり、事実が人工知能で安易にフェイクになりやすい現在、何を信じたら良いのだろうかと思うとゾッとする。人工知能と核の脅威に打ちのめされて会場を後にした。
人工知能という機械で作り出されたものを、人間の体を通して表現したかったというザイデス。企画と構成は素晴らしかったが、ダンサーの表現に深みが足りなかったように感じたのが惜しい。(6月24日Studio Bagouet/Agora)

©Laurent Philippe
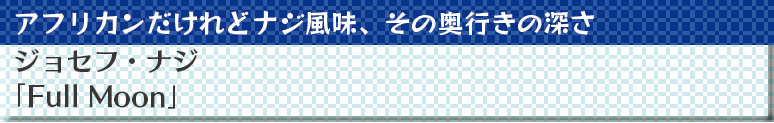

©Théo Schornstein
前回見た作品もアフリカだった。そして今回も。でも、似ていて全く違う作品「満月」。
暗闇の中に一筋のあかり。その中に入ってきた黒づくめの人。面をつけたその男の手のひらがひらひらと舞う。闇の神の手が消えると、後ろから男たちがゆっくりと出てきた。
全作品同様、男ばかりのダンス。なぜ男ばかり? それは、アフリカでも祖国でも、民俗舞踊でのソロや重要な役は男で踊られることが多く、伝統的に面を付けて踊るのは男であり、男のエネルギッシュな踊りで構成したかったからだという。ただ、前作と比べると、エネルギーの爆発度は抑えられていて、力強さの中に丸みのある人間性が見える優しい感じだった。それは、ナジがダンサーに、これまでに携えてきたものを全て脱ぎ去って、「無」になることを求めたからだろう。ゼロになって何を感じるのか。ダンスのテクニックではなく、何もないところに種を蒔いたらどう育つのか。草を刈る動きが自然に生まれたように、身体が発する純粋な動きを求めたという。
担ぎ上げられた勝者が天を仰ぎ、力強い踊りを見せたかと思うと、ふわっと優しい風を起こす。そしてストーリーテラーのように現れる謎の人物、ナジ。アフリカンダンスでも、ヒップホップダンスでもなく、でもそこにはアフリカの匂いがある。自分のスタイルは押し付けなかったと言っているが、アフロアメリカンの音楽に乗って、色とりどりのジャケットを着て、アフリカの面をつけた男たちがリズムを刻みながらゆっくりと退場するシーンがなんともナジらしく、微笑ましかった。

©Théo Schornstein
ユーゴスラビア(現セルビア)に生まれ、演劇作品を作り、見聞を広げるためにきたパリの図書館でフランスの作家を知り、ヌーボーシルクの人と出会い、音楽家や美術家とも知り合い、30ほどの作品を創った。それが1995年から2016年までのオルレアン国立振り付けセンター時代。そして、心機一転、何事にも束縛されないフリーランスになった。日本をはじめ様々な国を訪れた後に、アフリカの文化・生活に子供の頃に通じるものを見つけて今に至るが、頭の中には常に祖国がある。現在はハンガリーのブタペストに居を構えて5年になるそうだ。アフリカでありながらアフリカではなく、東欧でもないナジワールド。次の作品もアフリカなのか、あるいは別の国なのか、気になるところだ。(6月24日オペラ座コメディ劇場)
ジョセフ・ナジのプレスコンファレンスの模様は下記で見られます。
https://www.montpellierdanse.com/medias/conference-de-presse-avec-josef-nadj/
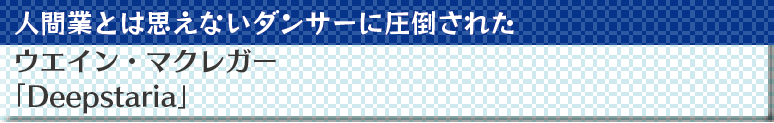
「ブラックホールの真髄に旅しよう、境界線を超えて落ちよう。もっともっと奥へ、宇宙の亀裂の中へだ。」カルロ・ロヴェッリ
夜の闇、海の底深く、人は神秘の世界に憧れる。そんなイメージを純粋にダンスで見せたかったという。
薄暗い舞台に交差する光の線の中をダンサーたちが激しく舞う。ソロ、デュエット、9人のダンサーは黒の水着のような衣装(女性はブラとショーツ、男性はショーツのみ)で 、目にも止まらぬ速さで踊っている。深い呼吸のような音に低音の雑音、そこに時折金属音が重なり、闇の世界を強調する。音楽は、2021年にオスカー賞を受賞した(映画「Sound of metal」)サウンドクリエーターのニコラ・ベッカーというのも興味深い。光と影のコントラストが神秘的で、ここはまさに宇宙空間。これがブラックホールか! ダンサーは次々と入れ替わり、息つく間もないほどの勢いで展開していく。圧倒され続けていると、今度はダンサーが白い衣装となり、赤い光のなかで荒い呼吸と心臓の鼓動のような音が響き、やがてそれは消えていった。次の青の世界では、ライトに映し出された手の動きが印象的だ。ラストは白い閃光の中での踊り。ダンサーたちは体力の消耗などはありえないかのように、鋭利な動きを最後までキープ。それはまるで人間を遥かに超えたサイボーグのようで、ブレることのない正確なポジション、かつスピーディでエネルギッシュ。完璧! というしかない。が、無機質な動きの連続に飽きてしまったというのが正直な感想。ただ、プログラムに書かれてあった冒頭のカルロ・ロヴェッリの「ホワイト・ホール」を事前に読んでいたら、別の印象を得たのかもしれない。本のように作品は進行し、我々はブラックホールからホワイトホールへ入っていたのだ。赤はマグマあるいは太陽だろうか、地球は青、そして最後はギャラクシーが勃発する宇宙全体を表していたのではないだろうか。機会があれば本を読んでから再度見たいと思う。宇宙への壮大な旅ではあったが、どこかに安らぎを感じるものが欲しかった。(6月23日Opéra Bérlioz Le Corum)

©Ravi Deepres
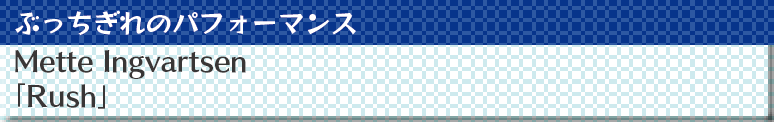
Mette Ingvartsenはデンマークの舞踊家で、今年初めに「スケートパーク」を見て面白かったので、今回も。ただ、この「Rush」は、いつもとはちょっと趣向が異なる。過去の作品の抜粋を、20年来作品に出演しているダンサーManon Santkinが解説しながら踊るドキュメンタリー風ダンスなのだ。
劇場の黒い壁に対して、真っ白な箱。白いリノに白いテーブル。シワシワのアルミの保温シートが5枚置かれている。中央のスピーカーから彼女の声。「こんばんわ。聞こえないけど、皆さんには聞こえているのかしら」。隠し事のないしゃべりに会場から笑いが漏れる。と、素っ裸で出てきた。なんの恥じらいもなく。そしておもむろに人の顔をしたマスクを後ろ前に被ってポーズ。後頭部に顔があるから、ポーズによっては不思議な生き物になる。一通り動いた後に作品の解説。そして別の作品へ。初演時は3人だったとか、汗をかいて滑ったとか、裏話が飛び交う。そして急に泣き出したり、笑ったり、叫んだり。
彼女は全くの女優なのだ。一人でしゃべり、目が語り、体が動く。瞬時にその場面、その感情になりきっているのがすごい。ここまでやるのは並大抵の技術ではなく、ただひたすら彼女の世界に引き摺り込まれた。アクション俳優如きにテーブルの上で、高層ビルの窓から落ちそうになりながらも必死で窓枠につかまっている様子は爆笑もの。観客を舞台に上げての演技も悪くない。ブロワバキュームで保温シートを舞い上がらせ、最後は身体中を振って叫びながら観客をけしかける。「みんなも私みたいに体を振って~!」たった一人でここまで盛り上がれるのだろうかと驚き、感動さえしてしまう。そして「2024年のラッシュはこうして終わる!」と叫んでカットアウト。彼女のエネルギーと演技力には脱帽。完全に飲み込まれた。(注;上演時間はその日のノリで変わると思われるので、終演後の予定を入れずに観ることを勧めます。)
彼女の作品を20年来見続けているデンマークの批評家は、懐かしくてたくさんのことを思い出したけれど、この作品を見ただけでは一つ一つの作品の良さが十分に伝わらない。特に面をつけた作品はめっちゃ面白かったそうで、ぜひアーカイブで見て、とのこと。(6月25日Hangar Théâtre)

©Bea Borgers
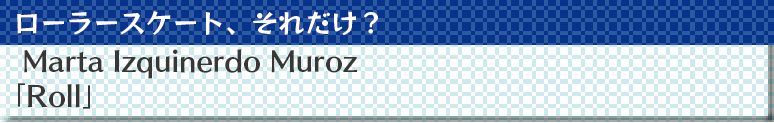
スポーツもダンス作品になりうるわけで、ローラースケートがどこまでダンスになるのか期待したが、残念ながら生かし切れていなかったように思った。
女優の太っちょおばさんのパワーはすごいけれど、ローラースケートとの関わりが見えず、スケーターたちが舞台を走り回るも、新鮮な動きも流れも感じられなかった。やりたいことはわかるのだが、構成と振り付けをもっと追求するべきだったのではないだろうか。
(6月25日Théâtre la Vignette)

©Laurent Philippe
|

