Dimitris Papaioannou ''Orientation Transversale''
L'Opéra national de Paris ''Hofesh Shechter-Uprising/In your rooms''
Acosta Danza -100% Cuban- ''Liberto'' ''Hybrid'' ''Paysage, Soudain, la nuit'' ''Impronta'' ''De Punta a Cabo''
Skopje Dance Theater / Risima Risimkin ''Identities- History of an extended dream''
Leïla Ka ''Se faire la belle''
Alexandre Roccoli '' Long Play (LP) avec Adam Shaalan et le Ballet national de Marseille
Delgado Fuchs '' Dos''
Smaïl Kanouté ''Utaki''
Johanny Bert ''Une Épopée''
Dada Masilo '' The sacrifice''
マリオン・バルボー主演映画「En corps」
公演情報
追悼 マリー=テレサ・アリエ死去
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
速報!
パリ・オペラ座バレエ団 フランソワ・アリュ、エトワールに任命
動画はこちら。
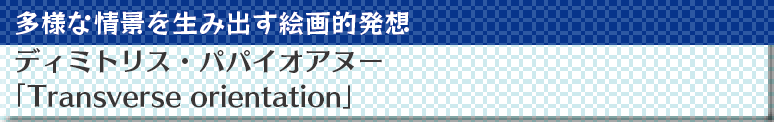
この作品はすでに昨年のフェスティバル・モンペリエダンスで批評を書いているので、ここではプログラムに掲載されていたインタビュー(リヨン・ダンスビエンナーレよりの抜粋)と、公演後のトークで語られたことについて書こうと思う。

©Julian Mommert
確かにこの作品はギリシャ神話やミノタウロス伝説を連想させる場面が多く、パパイオアヌーもトークでそれを語っていたが、ある観客からの「子供に戻ったように楽しめた」という感想に「そう感じてくれたのなら嬉しい」と喜んでいたことと、コメンテーターの作品解説に「深読みをしてくれてありがとう。そこまで考えていませんでした」という冗談めいた言葉から察すると、作品の意図を分析するよりも、ひとつひとつのシーンを楽しむことを望んでいるようなので、もし見る機会があったら、素直に受け止めるのが良いかと思う。
~創作過程について~
ひとつの作品を作るのに4ヶ月かかります。何を創作するか定めずに始めて、絵画・造形や動作、あるいは道具を使うことで身体がどう変化するかを見ながら出演者たちと組み立てていきます。そうするうちに次第に作品の趣旨が現れてきます。創作とは、直感とリハーサルとテーマを話したいと望むことだと思います。
~ダンサーとの仕事について~
私をワクワクさせるような動きができて、私が惚れ込むほどの個性を持っている人。自分自身が表現できるものをきっちり見せられる人。僕はダンサーたちに葉っぱをかけ、意見を言いながら考えをまとめていきます。
ダンサーたちに絵や紙やプラスチックや金属、ハシゴなど、自分たちで動かせるものを渡し、それで音を出したり動かしたりして、錯覚を起こすような視覚的演出を作ります。
~舞台美術について~
イメージなしでは作品は作れません。私は絵描きでした。プリズムの絵から世界を見る方法をとっていました。ダンサーを色とか形などのひとつの枠の中に入れて、それを変貌させます。
影響されるもの、それは人生そのもの。そして芸術の冒険。アートのプリズムに人生を見出します。私は一般的に芸術の仕事とは人生に意味を与えるものだと考えています。その存在そのものが私の創作意欲を掻き立てます。
~裸体について~
ひとつの表現方法としての裸体をよく使います。それは美しからとか、自然だからということではなく、単純に身体の提示、裸体の美化で、自分の原点でもあります。ギリシャ彫刻から自分が影響を受けたことのひとつは、性的なものではなく、官能的で裸体の絶対的な神秘性で、感性に触れるものです。これは私の考え方ですが、見た人がどう感じるかはそれぞれに任せます。
観客を交えたトークは大変に興味深かった。この作品は、ギリシャ神話を思い起こさせるが、オムニパスに流れる構成は独立していて、それがコミカルだったり、シュールだったり、風刺だったりする。それらは太古から現代までの歴史につながるとも言え、つまりはここには人類の歴史とそこに生きる人が描かれているということになるのだと思う。(3月4日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)
なお、本作品はロームシアター京都にて6月23~25日に公演が予定されている。
アドレスはこちら。

©Julian Mommert
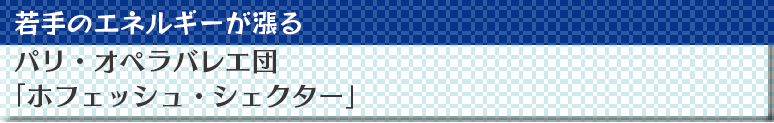
パリ・オペラ座のコンテンポラリーダンスここまできたか! というのが率直な印象。
今世界で最も注目されている振付家のひとり、ホフェッシュ・シェクターの2作品「アップライジング」と「イン・ユア・ルームス」がレパートリーに入った。このダブルビルでの一夜に、エトワールは出演していない。それでもガルニエ宮を満席にし、新作でなくとも鳴り止まないカーテンコールが続き、観客を熱狂させる公演が打てることに、パリ・オペラ座の新たな方針がくっきりと浮かぶ。
「アップライジング」は2006年にホフェッシュカンパニーで世界初演された作品で、男7人が激しく踊る。バーンという音と共に照明がつき、 闇の中から現れた男たちは無言でパッセをして止まる。そんな一風変わった始まりの後は、上からのスポットが作る光と影の中で走り、踊り、揺れる。バオーン、バオーンと響く金属音の中での優しさと暴力、主と従の駆け引きによる力関係が刻々と変わる。15年前の作品とはいえ、政治的な意味合いをも感じさせるシーンは現代にもつながる。いや、この構図はいつの時代にもどこにでも存在していることなのだ。それに慣れてしまっているから、こうして改めて客観的に見ると新鮮に見えるということか。明暗を作り出す照明がミステリアスに奥行きを出している。
7人とも素晴らしくホフェッシュ独特のムーブメントを踊りこなしていたが、特にシモン・ル・ボルニュの動きに目が離せない。骨や関節のひとつひとつが動いているのだ。しなやかでもあるが、体の芯から動いているので動きに残像が出るゆえに大きく見える。それがどんなに小さな動きであってもだ。そこがすごい。また、タケル・コストも、次の作品でもそうだが、ソロなどで踊る場面が多く、シャープで無駄のない良い動きをしている。それなのに彼はまだカドリーユでしかないというのが驚きだ。アントナン・モニエも素敵だ。さすがホフェッシュ、ダンサーの良さを的確に引き出している。とんとん拍子に昇進しているジャック・ガシュトゥットは黒髪を金髪に抜いていて、めちゃかっこいい。パリ・オペラ座の有色人種で髪を金髪にしたダンサーが過去にいただろうか。バレエ団には白人しかいないと思っている人がいるかもしれないが、それは違う。世界各国から集まったダンサーたちの国際色豊かなバレエ団なのだ。日本人だって有色人種だし、エトワールのセウン・パクは韓国人だ。人種や肌の色を問わないと宣言したオペラ座は進化し続ける。そのうちタトゥーを入れた王子様が出るかもしれない。パリ・オペラ座のコンテンポラリーダンスがこの先どこまで精鋭されるのかが大いに期待できる。

「アップライジング」©Julien Benhamou/Opera national de Paris
そして休憩後の「イン・ユア・ルームス」で更なるパンチを食らったのだ。女9人、男10人のうち、最高位のクラスに所属しているのはプルミエールのマリオン・バルボーだけで、それ以外はスジェとコリフェとカドリーユ。ダンサーはオペラ座バレエ学校などでクラシックバレエの基礎を叩き込まれたダンサーばかりだ。もちろん彼らの身体能力は非常に高いし、バレエ学校でもコンテンポラリーダンスのクラスを受けていて、体の使い方が根本から違うバレエとコンテンポラリーを体得している。しかしここまでハイレベルで踊りこなし、圧倒的な存在を見せつけたことに驚きを隠せなかった。ここでもマリオン・バルボーは光っていた。ベージュの地味な色のワンピース姿でも、自然と目が行ってしまう。ボルニュと同じく背骨のひとつひとつが動いているのだ。そしてマリオン・ゴティエ・ドゥ・シャルナッセ、エロイーズ・ジャックヴィエル、クレマンス・グロスなどの動きの大きいこと! もちろんどのダンサーもそれぞれに個性があり、優劣つけ難い。全員が同じ振りをしても、微妙に違う。違って良いのだ。それが個性だから。作品を踊る方向性が同じなら、それで良いのだ。
パリ・オペラ座は古典バレエ作品でなくとも、トウシューズを履かなくとも、エトワールが出演していなくても、会場を満席にし、観客を十分に興奮させるだけの実力のあるバレエ団だと実感した。こうなると、30年前にレパートリーに入ったドミニク・バグエの「ソ・シュネル」が見たくなり、もし、オリヴィア・グランヴィル(現CCNラ・ロシェルの芸術監督)が30年遅く生まれてパリ・オペラ座にいたら、どんな踊りを見せてくれただろうかなどと想像しながら、オペラ座ガルニエ宮をあとにした。(3月15日パリ・オペラ座ガルニエ宮)

「イン・ユア・ルームス」©Julien Benhamou/Opera national de Paris
パリ・オペラ座のホームページに載っていたシェクターのインタビューが面白いので、興味のある方はどうぞ。
アドレスはこちら。
なお、次号のセーヌ(5月下旬発行予定)ではパリ・オペラ座のコンテンポラリーダンスの歴史を振り返る。
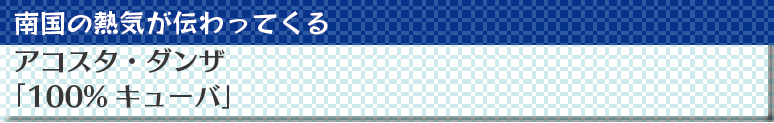
カルロス・アコスタ率いるアコスタ・ダンザ。パリのシャイヨー宮での公演は、5人のキューバに縁の深い振付家に依頼しての5作品を上演した。
「リベルト」(Raúl Reínoso振付)は、奴隷制度反対のふたつのキューバの小説にインスピレーションを得たデュエットで、頭を剃り上げた背の高い女と男が出会い、やがて奴隷として縄で捉えられた男が、女神となった女と共に去ると言う物語。ふたりの身体能力の高さは非常に高く、特に女性の存在感は他に類を見ないものがあった。
「ハイブリッド」(Norge Cedeño &Thais Suárez振付)は、シシューポスの伝説をもとに、人間愛と自由を謳う。近未来的な衣装と装置の中、ヒップホップやジャズ的な動きを取り入れ、繋がれた太いロープは、シシューポスのように逃れられない運命を意味しているのだろうが、少しテーマが散漫になったように感じた。
「Paysage, Soudain, la nuit/風景、不意に、夜」(Pontus Lidberg振付)は、キューバの原風景の中で生きる人々の日常を感じた。テンポ良く変化する構成は自由で明るいキューバ人をイメージさせ、見ていてとても気持ちがよかった。音楽はキューバ人のレオ・ブルーワー。

「Paysage, Soudain, la nuit/風景、不意に、夜」©KIKE
「Impronta」(María Rovira振付)は、ゼレディ・クレスポのソロ。最初の作品「リベルト」で圧倒的な存在感を見せたダンサーだ。上からのスポットの中で鮮やかな水色のドレスが舞う。キューバの伝統的な踊りとコンテンポラリーダンスを混ぜ合わせた動きで、ドレスの裾が揺れる様子は蝶が舞うようで美しかった。
「De Punta a Cabo」(Alexis Fernandez (Maca) & Yaday Ponce振付 )は、最後を飾るにはふさわしい、若さ溢れる作品だった。海辺で若者たちが語り踊る映像がホリゾントに映し出され、その前で同じ衣装のダンサーたちがエネルギッシュに踊る。まさに彼らの日常がそこにある。トウシューズを履いての踊りもあり、カンパニーのレベルの高さに見惚れた。
100%キューバ。まさにキューバのさまざまな面を見せてくれた一夜だった。(3月17日シャイヨー国立舞踊劇場)

「De Punta a Cabo」©YURIS NÓRIDO


©Risima Risimkin, Ohrid 2020
スコピエ・ダンスシアターは、北マケドニアの北部に位置するスコピエを本拠地としている。北マケドニアは、ギリシャの北側で、アルバニア、コソボ、ブルガリアに囲まれた国で、スコピエは北マケドニア最大の都市であり、首都である。
ダンスカンパニー、スコピエ・ダンスシアターの「アイデンティティ」は色々と考えさせられた作品だった。
脈略のない夢を見ているような構成展開で、奇抜な衣装と着想は面白い。大きなボールの後ろに立って、規則的な腕の動きをする人の元に人々が集まり、作品が始まった。顔と頭まで縦縞の布で覆われた服に着替え、小さめのボールに座る彼らの、それぞれの動きがいつの間にか群衆と個人になり、そしてやがて個人は群衆に埋もれていく。顔の見えない個人、多数に同調する風習は、現代社会への批判だろうか。コンピューター音楽がメロディーのある曲に変わると、赤いドレスの女のソロになる。スカートの先には赤いボールがつながっていて、それは臍の緒で繋がった子供にも見えた。ボールを抱き締めるのか、捨てるのか。今度は黄色いチュチュを変形させた衣装に、縁の太い眼鏡とポニーテールのそっくり3人女の登場。腕を90度に動かしながら移動するアンドロイド人形みたいだ。その間を透ける生地の上着と幅の広いズボン姿の男3人が彼女たちの間を縫うように踊り、男女の関係を問う。ピアノ曲に変われば女のソロ。これが女としての喜びと苦悩を表しているように感じられた。するとその後ろにラメの白いドレスの女現れて踊り、その姿をお立ち台の女を崇めるかのように囲んだ人たちが手持ちのライトで照らし出す。その横で一人自分の足にライトを当てる男。その足にはハイヒール。そして、これまでの出来事が走馬灯のように逆戻りして、最初の場面のボールが人々の間で行き来するという流れだった。
各シーンの衣装は素晴らしく、ダンサーたちの身体能力は高く、社会風刺を交えて練り上げられていたが、なぜその動きになるのかという疑問が頭をかすめることが何度かあった。なぜここで脚を高く上げるのか、なぜここで体操選手のようなアクロバットが入るのか…。それがなくても十分だったように思うのだが。少し消化不良を起こしてしまった。(3月16日シャイヨー国立舞踊劇場)

©Risima Risimkin, Ohrid 2020
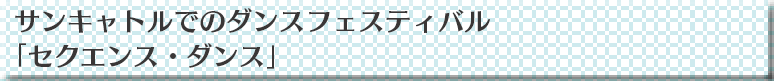
オーベルヴィリエ通り104番地の19世紀の葬儀場は、今や文化施設サンキャトルとして、人気の場所。番地の104をフランス語で発音すると「サンキャトル」となり、番地がそのまま名称となった。公演や展示などのイベントのほかに、アーティストのレジデンス、そして若いアーティストにありがたいのが、解放された場所で誰もが自由に体を動かせること。多くの若者たちがリハーサルやダンスなどをして利用している。カフェも売店もある。
アドレスはこちら。
ここで毎年行われるフェスティバル「セクエンス・ダンス」は10回目を迎え、3月13日から4月21日まで、新人から中堅の25作品が上演された。
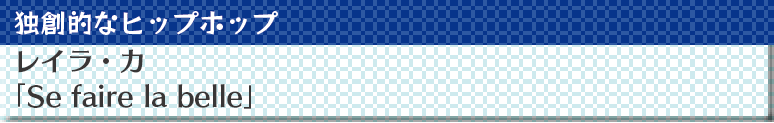
注目の新人で、サンキャトルをレジデンスとするレイラ・カのソロ2作。
まずは「Pode ser/たぶん」。レトロなランプシェードが丸いスポットを照らし出す。その中で薄いオレンジ色のドレスを着て、肩幅に足を開いて立つ女。広く開いた胸元のドレスをつかみ、強い視線を投げながら肘が激しく動く。それは、まるで音楽を言葉にして肘で伝えているかのようだ。上体の動きが加わり、ドレスの下の黒いズボンとズックが見えてくると足を中心とした動きに変わる。床に伏せ、体をくねらせスカートをたくしながら、時折見せる何かを求めるような表情。そしてその心の迷いを振り切るかのように再び激しく動く。すると突然ノイズ音に変わり、ロボットまがいに動いたのちにリズムカルな音と共にヒップホップ風のダンスになるが、再び元の曲に戻りくるくると回転する。
伝統に縛られながらも新しいものを求める自分の中のふたつの意識の戦いのように見えた。
動画はこちら。
続く「Se faire la belle/おしゃれをする」は、先ほどのとは形が異なるレトロなランプシェードが吊り下げられた部屋の中で、水色のゆったりした服を着て体をくねらせる動きが続く。緩急の動きで変化をつけ、それが夢と現を行き来するように見える。先ほどの「Pode ser」よりアブストラクトな印象を受けたが、他に類を見ない独創的な振り付けが面白い。
まだ作品を作り始めて間もないようだが、期待される新人のひとりで、これからどこまで伸びていくかが楽しみだ。(3月19日104)

©Kaita de Sagazan
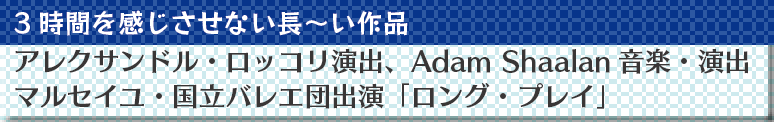
上演時間3時間、21時開演で、22時と23時にも入場可能という案内から予想していたが、約1時間の作品を少しずつ変化させながら3回踊るというものだった。
椅子席と座布団が置かれた席の中からダンサーたちが立ち上がり、舞台に集まった。舞台中央奥には大きなスピーカーが鎮座している。ダンサーたちは床に横たわり、塊になってゆっくりと舞台後方に移動していく。体をくねらせ、頭を振り、ゆっくりとトランスに入るかのようだ。円になり、列になり、ひとりの動きが隣に連鎖し、増幅される。風を起こし、風になり、地の底から沸くエネルギーに突き動かされるように流れていく。途中でホリゾントの幕が開き、サンキャトルの中庭と奥の建物が現れ、その大きさに圧倒される。人間のなんと小さいことか。再び幕は閉じ、我々は閉ざされた空間に戻る。大きな変化はこのくらいで、淡々と流れていく。そしてこの1時間のシーンが少しずつ変化しながら2回目3回目と繰り返される。
同じことの繰り返しだし、公演終了が24時なので、途中で帰るつもりだったのだが、はまった。次に何が起こるかわかっているのに目が離せない。もう一度見たくなるような特別なムーブメントもなければ、陶酔しているわけでもないのに、だ。なんとも不思議な時空間だった。(3月18日104)

©JacobKhrist
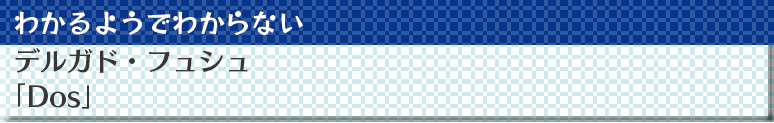
タイトルがフランス語なら「背中」という意味になる。ポスター写真もふたりが絡んで背中を見せているので、勝手にコミカルな作品かと思い込んで見たのだが、少し違うようだった。やはり先入観を持ってみてはいけないのだ。
体の大きい男とやせっぽちの男がポーズをしている。時々位置やポーズを変えるだけで何の変化もないのだが、かすかに聞こえる音程の高い唸り声は何なのだろう。ふたりの間に関係があるのかないのか、それぞれが勝手に動いている。それがやがて一緒に絡まり始め、リフトをしたり、一緒にステップを踏んだり、転がったり。その動きが発展するでもなく、あっと驚くようなアクロバットがあるわけでもなく、新鮮にも見えず、何をしたかったのかわからなかった。(3月18日104)

©Delfado Fuchs
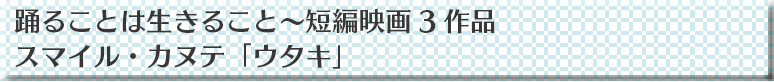
偶然に入った部屋で見た短編映画3本が素晴らしかった。
「NEVER TWENTY ONE」
アメリカはブロンクス。黒人の男の肌には白い文字がびっしりと書かれている。アパートの廊下、駅、公園で踊り、その体は汗で光っている。彼は言う、「この廊下で友達は殺された。やってきた男に妹は病気なので出られないと伝えたが、廊下に出され、そこで撃たれて死んだ。まだ14歳だった。」「ここで知り合いが殺された。彼は黒人だった。」「殺された友達の名前を体に刻むことにした。そうすれば僕といつも一緒にいられる。」黒人差別が激しいアメリカ社会の問題に心が痛む。そして、身体中に白い刺青を入れて踊っているのが、スマイル・カヌテ本人なのだ。
「YASUKE KUROSAN」
「ヤスケ 黒さん」これはもしかして…、「黒侍」という日本語のタイトルが現れて、やっぱりもしかしたら…。その通り、黒人が侍になるというストーリーなのだ。プログラムには「モザンビークの奴隷が侍になるという物語」と書いてある。笑ってしまいそうになったのだが、これがよくできていた。実際に日本で撮影するという力の入れよう。鎌倉の茶室で侘びを感じ、侍から剣の心得を受け、夜の繁華街で踊る。旅館かどこかの大広間で指導を受けるが、日本の武道の精神を受けているはずが、なぜかヒップホップで盛り上がるシーンは微笑ましく、真面目でマンガチックな短編映画。クレルモン=フェランの短編映画祭に出展を勧めたい。
「SO AVA」(編集過程)
ベナン共和国のノコエ湖に浮かぶ水草に中で踊る少年。川に張り出した住居に人は住み、船が日常の移動手段の村。少しの場所を見つけては踊り、村での祭りで踊り、踊ることが日常で、踊ることに喜びと自由を感じる少年の姿が眩しい。自然、自由、ダンス。踊りは人の営みの中から自然発生したものなのだ。こんなに自由に踊れたら、さぞかし気持ちの良いことだろうと思う。
以上の3本の映画を演じたのは、 スマイル・カヌテ本人。独特の感性に興味が湧いた。(3月18日104/ソンキャトル)

©Smaïl Kanouté
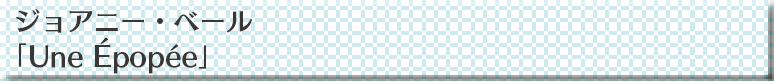
1日を子供と一緒に劇場で過ごせる作品を作りたかったというマリオネット師で演出家のジョアニー・ベール。6時間を子供たちがどんなふうに過ごすのかに興味を持って見にいった。プログラムには休憩を入れた4部構成で、休憩と1時間の昼食時間を含みますとの書いてある。お弁当持ち込みでも良いし、予約すれば劇場のレストランがお弁当を用意しますよとも。
これは、仲の良い4人家族の物語。両親と姉と弟は高い塀に囲まれた家で自給自足的な生活をしている。とってもエコロ。ある日飛んできたスーパーのレジ袋、これがただのレジ袋なのか、誘惑なのか、「壁の向こうには別の世界があるかも?」と気づいた姉は弟を誘って、レジ袋を追うように壁を登った。冒険にワクワクしてどんどん先に進もうとする姉と、臆病で家に戻ろうとする弟。そういえばこの弟、まだ小学生のなのに髭が生えている…。こうして外の世界で見るもの全てが驚きだ。見たこともないものばかりだから。携帯電話って何? なんで家に閉じ込めた? 両親への不信感が募るころ、魔法の力で子供たちを必死で探す両親に出会う。子供たちを外界の危険から守るためだったという両親をなじるうちに、両親はだんだん小さくなってとうとう豆粒になってしまった。どうしよう。大きな鳥に出会って、その子供の死を体験して、親の悲しむ姿と生きることの大切さを知ったふたりは、親を元の姿に戻す方法を見つける旅に出る。種だから植えればいいんじゃない?じゃあ、それだけの質の良い土がある場所を見つけなきゃ。
迷い込んだ家は四大元素の家だった。「土」はベッドに横たわって声を出すのもやっとな状態。風も火も水も地球が荒れているからみんな年老いてボロボロだ。車椅子に乗っているのもいる。子供たちは地球の改善を約束し、「土」のお腹に両親の種を蒔くと、あらあら、お腹から両親が元通りの姿になって出てきた。
両親は、子供たちを愛する故に外界との交流を遮断したことを謝り、子供たちは家に戻って今まで通り4人仲良く暮らしましたとさ。
4つのパートは4人の演出家によって作られ、それをベールが総監督としてまとめたという構成で、休憩を入れて6時間。それぞれのパートは約1時間という長さだったが、ほとんどの子供たちは最後まで楽しんで見ていた。
パート間の休憩中は、場面転換のために20分ほど会場の外に出て待たなくてはならなかったが、この間に何かイベントがあればもっと良かったのではないかと思った。多くの出演者、特にメインの子供と両親は(両親は3役をこなしていた)ほとんど出ずっぱりなので、休憩中にも演じるのは酷な話だと思うので、例えばベールの作品の写真やオブジェを廊下に展示するとか、スクリーンがあるのでプロジェクションを行うなどがあればとは思ったものの、ホールで親子が遊ぶ様子を見て、待ち時間は家族の会話の時間と考えれば、イベントがなくても良かったのかもしれない。ランチタイムには劇場のホールや会議室にテーブルが用意されて、思い思いの場所で食事ができるというのも微笑ましい。

©Christophe Raynaud de Lage
週末2日間は一般公開で、平日には学校専用の会もある。こうして劇場で1日を過ごせば、劇場が日常の一部になり、劇場に公演を見にいくことが「わざわざ」ではなくなるわけだ。コロナ禍でホームシアター配信に慣れてしまったけれど、実際に劇場に来れば画面では味わえないものに出会える。劇場に足を運ぶことの楽しみが子供たちに伝わった公演だったと思う。(3月20日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)
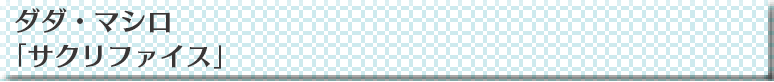

©DR
これまでにも「白鳥の湖」「カルメン」「ジゼル」などを独自の解釈で創作していたので、今回もタイトルから「春の祭典」ダダ・マシロ版かと思っていたら、死を受け入れることへのオマージュだった。
手を動かしながらゆっくりと前に進むマシロ。腰を少し前にかがめ、時折上体を回したりするだけの簡単な動きだけれど、その速さや明確な動きに彼女の身体能力の高さが窺える。
そこへドレスに身を包んだ歌手が登場し、ミュージシャン4人が上手前に位置した。歌手、バイオリン、シンセサイザー、そしてパーカッション。ストラビンスキーの「春の祭典」は流れず、彼らの音楽で進んでいく。この後はダンサーたちによる踊りで、ミュージシャンたちに「もっと元気な曲を」とか「ゆったり気持ちの良い曲にしてくれないかなあ」などと注文を付けながらの元気な踊りが続く。ダンスと音楽が掛け合いのように一致しているし、歌手の歌声が素晴らしい。これがアフリカでの彼らの日常なのかも。そしてマシロに渡された1本の白い花。それが何を意味するのか、死を宣告されたのだ。戸惑いながらも踊りつづけ、恐れる彼女を抱きしめ、そこに向かわせる人。
春の祭典からインスピレーションを得て、「死」を宣告された人の気持ちを描いたのだろう。アフリカンダンスとコンテンポラリーダンスを融合させ、生きる楽しさとそれを終わらせなくてはならない悲しみを描いている。以前のいくつかの作品で得たような衝撃的な印象はなかったが、これまでとは違う方向性を出したかったのかもしれない。ストラビンスキーの「春の祭典」を意識せずに見る方が楽しめるように思う。
2021年のアヴィニヨン・フェスティバル・インなど、何度かフランス公演が予定されていたのに関係者にコロナ陽性者が出て中止が続いていた。今年3月になてようやくフランス公演が実現して、エクサン・プロヴァンス、シャトネイ=マラブリー(Câtenay-Malabry)、クレルモン=フェラン、リモージュで公演し、今年夏のアヴィニヨン・フェスティバルにも予定されている。(3月24日クレルモン=フェラン・ラ・コメディ劇場)

©DR

パリ・オペラ座バレエ団のプルミエダンサー、マリオン・バルボー主演のバレエ映画が3月30日から上映されている。ホフェッシュ・シェクターも出演していて、ダンスの場面がふんだんにある。お見逃しなく! 詳しくは来月号で。

マリオン・バルボーがシャトレ劇場の屋根の上で踊るビデオが素敵です。シャトレ劇場のホームページより。
動画はこちら。

夏時間に変わる頃になると、夏のフェスティバルや来シーズンの劇場プログラム発表の時期。
~フェスティバル~
ランコントル・コレグラフィック・アンテルナショナル・ドゥ・セーヌ=サン・ドニ(5月13日~6月18日)
新ディレクターのフレデリック・ラテュはどんな作品を選んだのか。前ディレクターのアニタ・マチュー路線か否か、それは見てのお楽しみ
ジュン・イヴェンツ(5月30日~6月18日)
ヴァンセンヌの森の中のアトリエ・ド・パリ主催のフェスティバル。若手の個性的な振付家の名前がずらり。劇場ではなく、ヴァンセンヌの森の中での公演もある。
フェスティバル・モンペリエダンス(6月17日~7月3日)
ひとりのディレクターが42回ものフェスティバルを行うという快挙には全く恐れ入る。そして今年も国際色豊かで新人からベテランまで幅広い演目となっている。昨年亡くなったライムント・ホーゲへの追悼公演には、活動を共にした上野天志も出演する
フェスティバル・リヨン・フルヴィエールの夜
リヨンの古代劇場でのフェスティバル。
演劇とコンサート中心のフェスティバルだが、ダンスも4演目あり、シャロン・エイアル「チャプター3」、バンジャマン・ミルピエの「ロミオとジュリエット組曲」が気になるところ。ミルピエの新作「ロミオとジュリエット組曲」はコロナ禍で延期されていたのがようやく実現する。その他、アコーディオンに合わせてのヒップホップとダンスと音楽を交えた作品が上演される。
アヴィニヨン・フェスティバル(7月7日~7月26日)
インのダンスは8作品。昨年関係者にコロナ陽性者が出たために中止となったダダ・マシロの「ザ・サクリファイス」、今年で3年連続招待のアリ・シャルゥが気になるが、なんと言ってもヤン・マルテンスが法王庁の中庭での公演というのは見逃したくない。
オフのプログラムはまだ公式には発表されていないが、参加劇団のホームページには掲載されて始めている。
~来シーズンの劇場公演~
パリ・オペラ座
来シーズンは、オペラが18演目、バレエが13演目。
バレエで世界初演となるのが、アラン・ルシアン・オイエンと、ボビー・ジェーン・スミスの作品だ。両者とも今回初めてパリ・オペラ座に登場する若手の振付家で、両作品ともタイトルはまだ発表されていない。オーエンは、小島章司が出演した作品で日本公演を行なっているのでご覧になった方のいると思うし、ヴッパタール舞踊団に振り付けするなど、すでに多くの作品を創作している。作品は架空と現実を交えた構成で、21人のダンサーが出演する。
オーエンのインタビューはこちら。
また、ボビー・ジェーン・スミスはバットシェバ舞踊団にダンサーとして活躍したのちに、祖国アメリカに戻って活動している。
スミスのインタビューはこちら。
若い振付家が、パリにどんな新風を送ってくれるのかが注目される。
新しくレパートリー入りするのが、ケネス・マクミランの「マイヤリング(うたかたの恋)」、ピナ・バウシュの「コンタクトホーフ」、ジョージ・バランシンの「バレエ・インペリアル」と「フー・ケアーズ?」、ウェイン・マクレガーの「ザ・ダンテ・プロジェクト」だ。マクレガーはこれで3度目のオペラ座とのコラボレーションとなる。
その他では、ヌレエフ版「白鳥の湖」、モーリス・ベジャールのトリプルビルで「火の鳥」「Le Chant du compagnon errantさすらう若者の歌」「ボレロ」、マクミランの「マノン」、カロリン・カールソンの「シーニュ」。そして昨年3月に亡くなったパトリック・デュポンへのオマージュの昨夜がある。バレエ団のデフィレに続き、ベジャールの「Le Chant du compagnon errant」、ジョン・ノイマイヤーの「ヴァスラフ」、ハラルド・ランダーの「エチュード」が上演される。3日間しか上演されないので予約は早めに。
恒例のオペラ座バレエ学校公演は、12月と4月。
招待カンパニーはピーピング・トム。コロナ禍で延期になっていたのがようなく実現する。
なお、オペラ座にもさまざまな割引があるので、大いに利用してみよう。
年間割引では、青春パス、家族パス、デュオパス、アカデミーパスがあり、特に28歳以下(1994年1月1日以降の誕生日)の人にはいくつかの公演(オペラ作品6公演、バレエ作品6公演)の初日前日のアヴァン・プルミエ公演には10ユーロのチケットがある。2席まで購入可能。ただし販売開始数分で完売になるそうなので、1秒を争って予約してくださいと。また、入場時に身分証明書などで年齢を確認するので、生年月日が表示された証明書を持参のこと。子供の付き添いとして入場しようとした母親が入場を拒否されたという話を聞いたことがある。
また、15~18歳対象のカルチャーパスもあるので、インターネットで検索してみてください。
シャンゼリゼ劇場
オペラやコンサートが主だが、ダンスももちろんある。
アクラム・カーン振り付けイングリッシュ・ナショナル・バレエ団による「ジゼル」、キーウ(キエフ)国立オペラ座バレエ団「くるみ割り人形」、もとパリ・オペラ座エトワールのカデル・ベラルビが舞踊芸術監督を務めるトゥールーズ・キャピトルバレエ団「トゥールーズ-ロートレック」(カデール・ベラルビー振付)、前パリ・オペラ座バレエ団芸術監督のバンジャマン・ミルピエとピアニストのアレクサンドル・タローによる「デュオ」の4作品が予定されている。
その他の主な劇場の情報は、発表されたらお知らせします。
追悼
ダンススタジオ、メナジュリ・ド・ヴェールMénqgerie de verre創設者マリー=テレサ・アリエ氏死去
パリに住む多くのダンサーが一度は通ったことのあるダンススタジオ、そしてノンダンス系のフェスティバルなどを開催して若手育成に大きく貢献したマリー=テレサ・アリエ氏が3月26日91歳で亡くなった。葬儀は31日で、ペール・ラシェーズに埋葬された。
このダンススタジオはマリオン・バルボー主演映画「En corps」にも登場する。
時に周りの反対を押し切って主張を貫き、気狂い扱いされたこともあるほどの意志の強い人で、ダンスを心から愛し、ダンサーを愛し、新たなことに挑戦する人を応援した。広くて明るいダンススタジオは気持ちよく、しかもパリでは考えられない格安料金でオープンクラスを受けられた。クラスは主にコンテンポラリーダンスで、週単位で講師を招き、コンテンポラリーダンスに必要であればパリ・オペラ座のエトワールだったウイルフリード・ピオレ氏や、吉田矩夫氏などのバレエ講師を招き、時に定員オーバーになることもあった。多くの体験ができたことを感謝し、冥福を祈ります。
|

