Dominique Bagouet ''So Schnell''
Gisèle Vienne ''L'Etang''
Christophe Béranger/ Jonathan Pranlas-Descours ''Nos désirs font désordre''
La Veronal / Marcos Morau ''SONOMA''
Théâtre de Suresnes ''Suresnes Cités Danse''
Lyon Maison de la danse ''Sens Dessus Dessous''
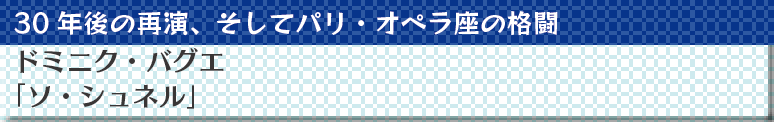
ドミニク・バグエと言われてピンとくる人は少ないと思う。1992年に41歳の若さで亡くなったフランスの振付家で、1980年代のフランス・ヌーベルダンスの騎手のひとり。そしてモンペリエダンスの創設者でもある。亡くなって30年経った今でもそのレジェンドは語り継がれ、舞踊学校では必ずと言っていいほどレパートリーを学ぶというフランスでは神様みたいな存在の人だ。亡くなった後はカンパニーメンバーが「レ・カルネ・バグエ」というグループを設立して、その意志を継いで活動を続けている。
そして今回、1990年に初演された「ソ・シュネル」の、1992年に亡くなる前に再構築されたバージョンがリバイバルされた。そして、この公演前日にパリ・オペラ座がこの作品をレパートリーに取り入れたときのドキュメンタリー映画が上映されたのは、非常に良いタイミングで、作品とカンパニーをより深く知ることができた。
これは1998年、当時のブリジット・ルフェーブル・パリ・オペラ座バレエ団芸術監督のもとにレパートリーに入った時のリハーサル風景を、マリー=エレーヌ・ルボワ映画監督(ダンスに関するドキュメンタリー映画の制作で有名)が収録し、翌年1999年に映画化されたものだ。
当時のパリ・オペラ座バレエ団はまだコンテンポラリーダンスには慣れていなくて、バグエの独特の動きを踊りこなすのは至難の業だったようだ。新しいことへの挑戦はしたいが、身体が思うように動かない。「レ・カルネ・バグエ」から何人ものダンサーが指導にあたり、「公演初日までバレエクラスのレッスンは受けないでね」とダンサーに言ったのが印象的だった。バレエとコンテンポラリーでは体の使い方が異なるからだ。背中を丸める、腰を曲げる、脱力する。頭でわかっていても体はいつものバレエのポジションになってしまう。しかし、リハーサルを重ねるうちにダンサーの動きがどんどんと変わっていく。できなかったことができるようになる喜びが自由な発想につながり、バグエカンパニーとは異なる「ソ・シュネル」が出来上がっていく。身体の可能性は未知なのだ。
この時に指導にあたったオリヴィア・グランヴィル(現ラ・ロシェル国立振付センター芸術監督)の踊りが素晴らしい。彼女はパリ・オペラ座学校出身で、バレエ団に入団後スジェまで上り詰めたけれど、チュチュを着る自分に疑問を抱いてコンテンポラリーダンスに転向したダンサー。だから古巣のオペラ座で教えることは適役だったと思う。
映画の中には、マリ=アニエス・ジロやクレールマリ・オスタ、ジェレミー・ベランガールの顔も見られて懐かしい。現在のパリ・オペラ座バレエ団は、バレエとコンテンポラリーを瞬時に使い分けられる技術を持っており、そこに至るまでの歴史が感じられた。また、1980年代にブレイクしたフランスのコンテンポラリーダンスのルーツを垣間見られる貴重な資料でもあるので、機会があればぜひと勧めたい。
ほんの4分だが、下記URLでこの映画の一部が見られる。グランヴィルの解放された身体は何度見ても素晴らしい。完全版の映画では、指導にあたったダンサーたちの言葉から、バレエとコンテンポラリーの考え方の違いなどが垣間見れるのも興味深い。
リンクはこちら。

©Caroline ABLAIN
さて、翌日所見したカトリーヌ・ルグランの再構築版は、オペラ座版とはかなり異なる印象だった。主を失った多くのカンパニーが遺作を後世に残すために厳格な規定を設けるのに対し、バグエの継承者たちは基本は守るものの、ダンサーに合わせて振り付けを変えることを認めたため、ニュアンスの違う作品が生まれるのだ。音楽は初演時と同じだが、衣装と装置は変えたという。ドキュメンタリー映画では、衣装なしのリハーサル風景で作品の一部しか映っていないので比較はできないが、バグエが言っていた「楽しく踊ること」はあまり感じられなかった。というか、ひとりの若い男性ダンサーが楽しそうに踊っているのに対して、他のダンサーがほとんどリアクションせず、ただ振りをこなしているようにしか見えなかった。常に楽しそうに踊る必要はないけれど、踊るエネルギーが感じられなかったのだ。バグエの生前に見た公演の印象とも違っていたように思う。これは私の思い込みかもしれないが…。また、初演時のダンサーと、バグウエイを知らない若い世代のダンサーとの混合メンバーだからこそ生まれる「何か新しいもの」が感じられなかったのが残念だった。現在のパリ・オペラ座バレエ団ならどう踊りこなすのだろうか、と思いながら会場を後にした。(1月10日映画上映ラ・ジュッテ/1月11日公演クレルモン=フェラン・ラ・コメディ劇場)

©Caroline ABLAIN
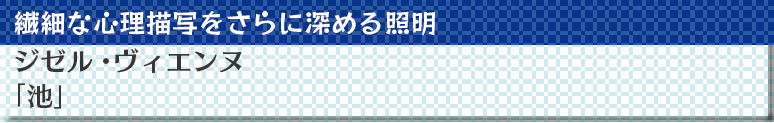

©Estelle Hanania
マリオネットを使い、シュールに演出して独特の世界感を表すジゼル・ヴィエンヌ。生や死、社会問題などを取り上げた台本などをベースにすることが多く、今回はスイスの詩人ローベルト・ヴァルザー/Robert Walserの同名の脚本を元にしている。原作は読んでいないが、ワルサーも納得の演出だったのではないかと思う。
真っ白い子供部屋。中央のベッドの周りには飴、ジュースの缶、ラジオや本が無造作に転がっている。そしてベッドに横たわる人、床に座ったり寝転がったり、壁に寄りかかったり、夜通し続いたパーティーの疲れか、だらりとした子供たち。上手後方の壁が少し開いて出てきた男は、そこにいる子供たちを一体ずつ丁寧に抱き上げて片付けていく。彼らは人形だったのだ。そして誰もいなくなった時、帽子を深く被って背を丸めた少年が現れた。小声で喋り続け、床を這う少年の背後には母親がいる。そのゆったりとした動きは威圧的で冷淡だ。舞台にはこのふたりしかいないが、姉や友達、そして父親も登場する。いや、登場はしないが声が聞こえる。ふたりが声色を変えて演じているのだが、彼らの言葉なのか、あるいはこのふたりの頭の中の言葉なのかわからない。ただはっきりとしていることは、この少年が悩み、傷つき、ひたすらに母の愛を求めているということ。そして母親の気を引くには池で自殺するしかないということ。その「池」、これがタイトル。
ジゼル・ヴィエンヌの描く世界はシュールだ。社会や家族などの身近な問題や事件を取り上げることが多いが、現実と仮想が交差し、観客をラビリンスに引き込む。少年が姉と友達を、母親が父親のセリフを声色を変えて演じているゆえに、本人以外の言葉が実際に放たれた言葉なのか、思いこみの中で発せられたのかが明確にならないことが、人間関係を交差させ、複雑な家族の心境を表すことに成功している。かつらを取り、突然に明るく陽気に話し始める母親。これは少年の理想の母親像なのか、それともこれが真の母親の姿なのか。何が現実で、何が仮想なのか。先の見えない狭い通路を歩くような感覚に陥った。それは多感な思春期の子供と現実に疲れた親のギャップなのかもしれない。
スローモーションと日常ではあり得ないポーズを取り入れた動きは言葉がなくとも心理を表し、それを深めるイヴ・ゴダンの照明が素晴らしい。微妙にトーンや色を変えるシンプルな照明は、登場人物の心の移り変わりを的確に演出し、わかり合えることのないふたりの関係が浮き立つ。
いつものことだが、ヴィエンヌの作品を見た後はずっしり重くなる。そこには表立って触れたくない現実、負の現実があるからだろう。決して良い気分ではないけれど、この現実と紙一重の架空の世界を体験したくて、再び彼女の作品を見に行くのだ。(1月19日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

©Estelle Hanania
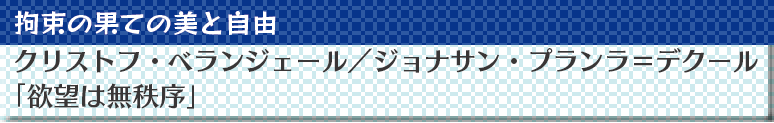

©Xavier Leoty
事前チェックでプロモーションビデオを見て、う~と固まってしまった。体を紐で巻かれ、後ろ手に縛られた裸の人たちが激しく踊っている。ネットではカラフルな花を纏った人たちの写真。読めない、予想がつかない。悪趣味だったら嫌だなあと思いながらも何かの予感がして見に行った。果たして…
フード付きのジャケットでウオーミングアップしていたダンサーたちが、客席に背を向けて並んでから中央に向かい服を脱いだ。そこには紐で縛られた体があった。円形になり、白い布の上に立ち、リズムを刻むように腰を振り、欲望を表すような動作をしながら移動する。それが崩れて自由に移動していたダンサーたちがひとつの塊となって転がる中から、ひとりが離れ、ふたりの黒服のスタッフによって後ろ手に縛られると、ゆっくりと群衆に向かって歩いていく。彼は特別なのか、皆に持ち上げられ、様々なポーズをとる。このように自らの意思でひとりずつ腕を縛られ、彼らは持ち上げられ、やがて両手の自由を失った彼らはかえって激しく踊りまくる。そんな彼らはまたひとりずつ拘束される。ひとりが足や腕にさらに紐を巻き付け、もうひとりが頭と体に花を生ける。生きる人間に花を生ける、これが見事。花は大輪の蘭やゆり、シダやススキのような大きな観葉植物もあり、生花の匂いが会場を包んだ。花の精と化したダンサーたちは絡み、マスクをつけて客席へと向かった。後ろ手に縛られていた手はいつの間にか自由になり、客に花を配り、コロナ禍で手渡しはできないから、通路に置き、あるいは客に取らせ、裸体となって舞台に戻った。そしてダンサーたちは、ひたすら自由を謳歌する。体を飾っていた紐を解きほぐして捨て、花をぶちまけ、花器の水が飛ぶ。床を滑り、自由に踊りまくるダンサーたち。そのエネルギーに観客は興奮し、酔う。舞台奥のドアが開けば、熱帯林を思わせるような大型の草木が生い茂っている。ここはパラダイスか。
裸体に巻き付けられた紐というのがSM的な印象を与えるが、想像を絶する舞台美術の美しさ、そして自由を謳歌する喜びとエネルギーの爆発に飲み込まれた。(1月20日シャイヨー国立舞踊劇場)

©Xavier Leoty
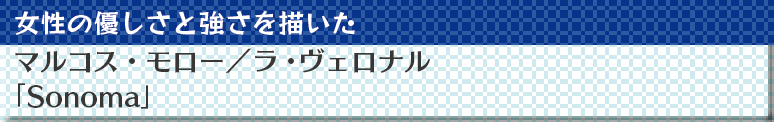

©Anna FÖbrega
男が女を描くとき、宇宙的な「美」と「強さ」を感じることがある。 「ソノマ」とはギリシャ語の「身体」とラテン語の「音」を合わせた造語。つまり「身体の音」ということになるのだろう。マルコス・モローは、同郷のスペインの映画監督でもあるルイス・ブニュエルのシュルレアリズムを背景に、自由を勝ち取る女性を描いたという。とはいえ、この作品から感じたのは、女性の優しさと強さだった。
ローラースケートを履いた人形が走るように、早い速度でスルスルと移動する女たち。ブニュエルが生まれたスペインのカランダの伝統的な衣装を着て、ひとつ屋根の下に集まり、大きな十字架の周りで、リズミカルな音に合わせて女たちのお喋りが始まり、平穏な1日が描かれる。その十字架が取り除かれると、モノトーンの服に着替えたダンサーたちは、天井から吊るされた大きな白い光を放つ板の下に座る。顔のない女たちの激しい踊りは、心の葛藤を表しているのだろうか。そして白いドレスに着替え、祝賀の行事に参列するかのようにたくさんの白い花をつける女たちの美しいこと。小さな灯りはこれから生まれる子供の命だろうか。女たちは喋り、歌い、踊る。ラストの太鼓を抱えての歌の力強く、天に向かって、それは神への祝辞でもあるかのようだった。
ブニュエルのシュルレアリズムというより、女が母になる強さ、生きることは人生を開拓することであり、その先にある希望に向かうような力強さが印象に残った。この作品は、昨年のアヴィニヨン・フェスティバル・インで、法王庁の中庭で上演されている。(1月21日シャイヨー国立舞踊劇場)

©Simone Cargnoni
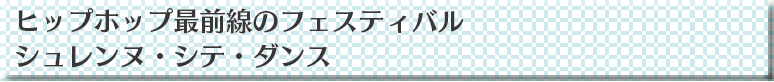

30回目を迎えたヒップホップフェスティバル シュレンヌ・シテ・ダンスは、1月7日から2月13日まで開催された。このフェスティバルはヒップホップとコンテンポラリーダンスをコラボレーションさせることで、ヒップホップの新たな可能性を広げた注目のフェスティバルだ。
ヒップホップは絶対にブレイクするし、ストリートで頑張っている若者をプロのダンサーとして育てるためにも、この企画は絶対に必要! とこのフェスティバルを1993年に立ち上げたのが、パリ郊外のシュレンヌ劇場の現ディレクター、オリヴィエ・メイエ氏。あらゆるジャンルのダンスと音楽が混ざり合ったアメリカ人のダグ・エルキンズの踊りに驚愕したのが、ここに至る最初の一歩だったという。まだヒップホップダンスが普及していなかったフランスで、フェスティバルを成功させるのは容易なことではなかったが、コンテンポラリーダンスの振付家にヒップホップダンサーを選ばせて作品を創作するなどの斬新な企画をたてるうち、フランス中からダンサーが集まった。現在フランスのヒップホップ界を率いる著名な振り付け家たちの多くがこのフェスティバルで踊り、創作している。現在のフランスヒップホップ作品がコンテンポラリーに近いと言われるのは、このシュレンヌ・シテ・ダンスゆえと言っても過言ではないと思う。
30回目の誕生日を迎えるにあたって、20回目のオープニングプログラムがテレビでリプライされた。10年前だが今見ても興奮する画期的な企画で、コンテンポラリーの振付家がヒップホップ作品を作るというもので、第1部がジョゼ・モンタルヴォとシルヴァン・グルド(プレルジョカージュのカンパニーでメインダンサーとして長年踊り、現在はバレエ・デュ・ノールCNDルーベの芸術監督)、第2部がロビン・オーリンとアンジュラン・プレルジョカージュ、第3部がファリド・ベルキ、モニカ・カサデル、ブランカ・リーがそれぞれ監修。ダンサーが入り混じってひとつの作品を作る構成で、まさにコンテンポラリーとヒップホップの融合だった。しかも出演していたダンサーのほとんどが、10年後の今活躍中のアーティストで、このフェスティバルは登竜門でもあるのだ。
残念ながらコロナ禍ゆえに30年目の誕生日を祝う大イベントは行われなかったが、バラエティに富んだ演目はこれからのヒップホップの可能性を広げている。そんな中で注目されたのがブランカ・リーのヒップホップ版「くるみ割り人形」だろう。見逃したのは残念だったけれど、きっとまたどこかで出会えると信じている。
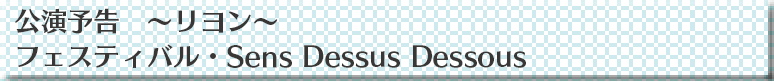
3月1日から12日までリヨンのメゾンドラダンスは10回目となるフェスティバルSens Dessus Dessousを開催する。ダンスにおける言葉との関係を問い、身体の可能性を追求する若手の作品が選ばれており、伊藤郁女と笈田ヨシの「絹の太鼓」が3月11~12日に上演される。
こちらのリンクから作品の一部が見られます。
|

