

コロナ第4波到来が懸念される中、75回目を迎えたアヴィニヨンのフェスティバル・インが予定通り7月5日から25日まで開催された。大まかに分けて演劇23公演、ダンス5作品、ジャンル分けできない部門7演目、語り1作品、展示が1という内容で、演劇の中には音楽やサーカス的作品も含まれている。このうちダダ・マシロの「Le Sacrifice」とディミトリス・パパイオアヌーの「INK」が中止になった以外の45作品が上演された。
フランスへの入国制限のためか、コロナ感染を恐れてか、例年より人通りは少なく感じられたが、7月14日の建国記念日前後は街を歩く人も増え、賑わいを見せた。
インの公演は人気が高く、この状況でもほとんどの公演は完売で、インの本拠地内の中庭でのアーティストの対談は活発な討論に大勢の人が詰めかけ盛況だった。
所見した公演で特に印象に残ったのが、エマ・ダンテ(イタリア人演出家)の2作品とアリス・ラロワ(フランス人演出家)、そしてヤン・マルテンス(ベルギー人振付家)の作品。
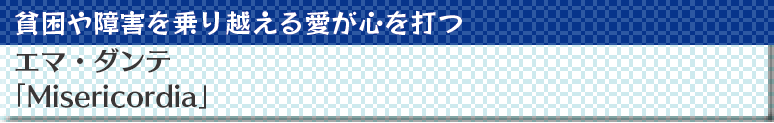
カチカチとリズミカルな音が聞こえる。それは3人の女性の竹の編み棒がぶつかる音だった。横一列に並んだ椅子に座る3人と頭をゆすり続ける男の子。ここは生活のために体を売る女3人が暮らす部屋で、仕事仲間が産んだ子供を育てている。女は夫の暴力により7ヶ月の早産、そして死んだ。生まれた子供には知能に障害が残ったという設定。
貧しいながらにも愛情を込めて育てているが、限界はある。3人それぞれの想いや対立もある。服を買う金がなく、ゴミ箱に捨ててあった女物の服を男の子に着せたことをなじるふたり。わざとわかるようなひそひそ話の光景は、ママ友いじめみたい。こんないざこざの間で無邪気に、でもなんとなく様子を察している男の子。この子がいるから3人は苦しい生活にも耐えられるのだ。
でも、暖房もなく、食事も十分に与えられないような環境にこの子を置き続けることが良いのだろうか。体格は立派になったけれど、知能的にはまだ子供だ。3人の女の悩みをよそに、ブラスバンドの行進にはしゃぎ、おもちゃをぶちまける。その行為は時に3人を苛立たせる。でも、彼に悪意はない。彼は全く自然体なのだ。
そして彼女たちは決意する、この子を施設に送ることを。新しい服に着替えさせ、母親の形見を持たせ、近づくブラスバンドの音楽に合わせてトランペットを吹く真似をしてはしゃぐ男の子に、「それ行け~」と声援を送る。その別れの瞬間、男の子は3人に向かって「ママ!」と叫んだ。実の母ではなくとも、彼にとっては3人が母親なのだ。

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
愛情という、何においても屈しない暖かさをベースに、いじめや貧困、家庭内暴力、障害者などの社会の暗い部分を取り入れ、家族の在り方を問う。血は繋がっていなくとも、絆はできる。この絆が「家族」なのではないだろうか。障害者自身は幸せなのか。そう、愛情を注がれているものは、皆幸せなのだ。では、障害者を施設に送ることは、見捨てることになるのだろうか。3人はここで葛藤する。愛している、でもどうすることもできない。見捨てるのではない、きっとよくなる。きっとみんなが幸せになる。そう自分に言い聞かせて見送る三人三様の複雑な表情に胸が締め付けられる。
社会問題を提示しつつ、それを大きな愛情で包み込む。ダンテは心優しい人なのだろう。言葉が分からずとも理解できる演出は、豊富な身体表現と出演者の演技によるものだ。登場した3人の女優とダンサーの男性。皆個性的だった。特にダンサーのシモン・ザンベリが素晴らしい。本当に障害を持っているのではないかと見間違えるほどの演技。ダンサーだった母親譲りで踊りがうまいという役柄で、素人っぽく踊っているものの、所々にチラリと素性が見えて、本当にダンスが上手い人なのだと確信。(7月17日ミストラル高校の体育館)

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
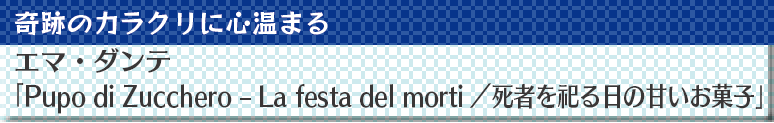
イタリア語、しかもほとんどが中世の言葉で綴られる演劇なのに、すんなり作品に入れる。今までに見たダンテの演劇は皆そうだった。言葉の壁がない演劇作品、そして日常の身近な要素を取り入れているから共感できるのだろう。
11月2日は、死者たちが家に戻ってくる日、つまり、アメリカではハロウイン、日本では夏のお盆に当たる日だ。南イタリアでは、小麦粉と砂糖と水で作る甘いパンを焼いて死者の霊を迎える古い習慣がある。それを元にエマ・ダンテは、貧しく孤独な老人に心温まる一日を送った。

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
チーンという鐘の音。3人の女性と子供に囲まれた老人は、パン生地を前に困り果てている。パンが膨らまないのだ。これができなくては明日精霊たちを迎えることができない。独り言を言ったかと思うと、ガクンと頭が落ちて寝てしまう。そしてはっと目が覚めていくつかの言葉を発したかと思うと、突然パン生地に顔を突っ込み、いびきをかいて寝始める。そんな老人を優しく見守るのは、死んだ3人の姉たちとその娘だったのだ。そして思い出が走馬灯のように舞台を駆け巡る。
発疹チフスで死んだ3人姉妹、子供の頃は枕投げをしてベッドではしゃいでいたっけ、フランス人の母は、海難事故で若くして死んだ夫が、死者を祀る日には帰ってこないと悲しんでいたっけ、愛と暴力の見境がつかないスペイン人の夫を持った姉、諍いの絶えない叔父と叔母、そして快活な養子のパスカリノ。それぞれの役柄がフィジカルで的確に描かれ、軽快なテンポで展開する。
中世のイタリア語を話すのは老人だけで、他の出演者のセリフは少なく、身体表現を多く取り入れているので、フランス語の字幕スーパーを読まなくても状況が把握できる。ダンスの要素が多く、3人の姉たちの踊りは蝶のように軽やか。一度だけ天から降りてきた父親は見事なヒップホップを披露して、腰が曲がった母親がいきなり服を脱ぎ捨てて若返り、ダンスパーティーに興じる姿など、暗転なしで時空間を一瞬のうちに変える演出は、作品の流れを止めない。そして思い出から醒めた時、老人の前には発酵しないパン生地が置かれているのだ。砂糖を加えたら膨らむかもしれないとテーブルを離れた隙に、そのパンをこねる死者たち。そして老人が戻ったときには見事な菓子パンができているのだった。
そしてその日になり、十字架の前に並んだ柱に死者たちは自分そっくりの人形を吊るし、老人は一つ一つ丁寧に蝋燭を灯す。老人はこの日だけは孤独ではない。家族に囲まれているから。そして独り言を呟く老人の首がガックリ落ち、両腕もそれに続いた。寝ているのだろうか、それとも。。。
消えつつある伝統に、孤独な老人や家庭内暴力などの社会問題を絡め、寂しくも、家族の優しさに心温る秀作。

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
以上イタリアの演出家エマ・ダンテの2作品とも、社会問題を背景に家族愛を描いている。生きるということの意味、幸せかどうかは他人が判断するのではなく、本人がどう感じるかということが大切だということ、そして思い出が生きる喜びともなりうるということ、そして何より「愛すること」の大切さ、家族の在り方を問うている。ダンテの優しさに会場全てが包み込まれた感じだった。(7月16日ミストラル高校の体育館)
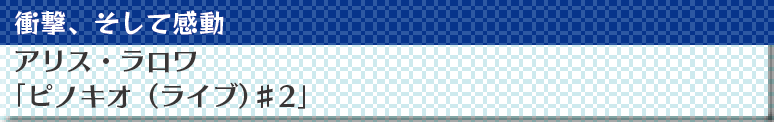

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
子供の歓声が聞こえ、無邪気に遊ぶ子供達。配られた桶をもらって大喜びで去っていった。こんな微笑ましい光景の後、号令の太鼓を叩く男女の後に続いたグレーの一団。各人がワゴンのようなものを引っ張りながら無表情で歩いている。服も、運ぶ資材も全てグレーで、一列になっての入場はまるで強制労働に連行される一団だ。そして、ホイッスルと太鼓の音に合わせて一斉に資材を組み立て始めた。ロボットのように全く同じ速度で同じ部分を組み立てる。手際悪く出遅れようものなら即刻拷問が待っているかのような雰囲気だ。そして出来上がったのは作業台。そこへ髪を白い布で覆い、白い服を着た子供たちがひとりずつ台に運ばれる。さっきの元気さは全くない。そして作業員たちは作業台に横たわった子供たちに白いスプレーをかけ始めたのだ。これからいったい何が起こるのだろうか。響き渡る太鼓の規則的な音、スプレーのシューっという音の中、作業員たちは黙々と作業を続け、だらりとした子供達の体はどんどん白くなっていく。そして目を描き、唇を赤く塗り、服を着せて手足に糸を縫い付けてピノキオ操り人形が出来上がった。
目の前でだらりとしているのは生きた子供たちだろうか、それともいつの間にか人形とすり替わったのかもしれない。全然動かないし、だらりとして生命感がなく、されるがままだ。作業員たちは命令通りに、そして遅れないように作業を続けるだけで、会話も感情もない。そしてこの人間を人形に作り替える冷酷な過程をひとり楽しんでいるのがリーダーらしき女性で、拡声器で作業員の士気を上げるべくまくし立て、「ピノキオの出来上がり~! これがピノキオライブ! さあみんな、写真を撮ってSNSで拡散しよう!」などと客を煽る。
生きた子供が人形に作り替えられるシーンは衝撃的で、退場する人も出たほどだった。
出来上がった人形を作業員が立たせたり、ポーズを取らせたり。そして中央に円形状に人形を並べた。すると、少しずつ人形たちが動き始めた。動いてはだらりと倒れ、また動いてはぺたりと座る。作業員たちは自分が作った人形がちゃんと動くかどうか心配そうに見ている。こうして少しずつ生を受け始めた人形たちが、パッと目を開けて元の子供たちに戻ると、作業員たちが駆け寄って抱きしめた。人形たちは元の子供に戻ったのだ。この瞬間に客席からは大歓声が上がった。子供たちが無事だったことにほっとすると同時に、その演技の素晴らしさに感動したのだ。
フランス東部のストラスブールの振付センターの子供達とコルマールの演劇コンセルバトワールの生徒たちが、週末と学校休暇を利用して1年かけてリハーサルしたという。つまりプロはひとりもいないことになるが、そのレベルはプロ並みだった。
グローバル化し、大量生産で物がどんどん作り上げられるのが当たり前な現代を背景に、生きていることの喜びをこのような形で再発見させる演出をしたラロワ。子供達の気持ちになっての指導が成果を表したのに違いない。
なお、2019にはピノキオ(ライブ)♯1を発表していて、これはパリ近郊のコンセルヴァトワールの生徒と若者が出演したそうだ。(7月12日サン・ジョセフ高校の体育館にて)

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
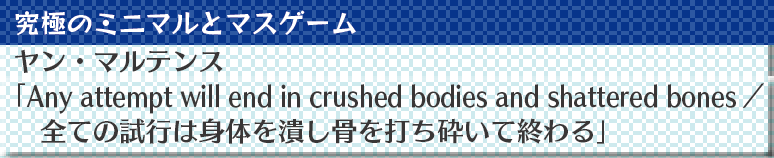

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
ヤン・マルテンスは頭の切れる人だと思っている。鋭い観察力とユーモアのセンスで、これまでの「常識」を覆す印象がある。このマルテンスがアヴィニヨン・インの大舞台で何をしでかすのかとワクワクしながら見に行き、予想をはるかに超えた出来栄えに彼の思考の奥深さに敬服。
サン・ジョセフ高校の中庭側の校舎の壁って、こんなにダイナミックな模様があったっけ? というのが会場に入った最初の印象。出入りは舞台奥中央の扉1箇所のみ。そこからソロやデュエットの少人数のシーンが展開する。今までにこの建物を美術の一部として使った振付家が他にいただろうか、と考えていたところに、若い男が登場して中央に位置するとヘンリク・ミコワイ・グレツキのチェンバロ協奏曲Op.40が流れた。この曲を使ったことにも驚いたが、まるでこの作品のために作曲されたかのような一体感のある振り付けに目が離せない。このソロは1箇所から動かず、上体と手を動かすだけの振り付けで、しかも音楽同様同じ動きが何度となく繰り返される。それだけなのに食い入る様に見入ってしまう。曲が終わるとスタスタと歩いて舞台を去り、入れ替わりにデュエットが始まる。このように数分のシーンが次々と展開する構成なのだが、その合間にすでに登場したグループが再登場して動きを送り返したり、中央で踊るグループの周りを別のグループが移動したりと、振り付けだけでなく構成までもが繰り返される。音楽は先のチェンバロ協奏曲とケイト・テンペストのピープルズ・フェイス、そしてマックス・ローチのTriptych:Prayer / Protest / Peaceの3曲しか使われていないのに、それを感じさせないのは、場面によって全く違う印象を得るからだ。それは、ひとつの曲を多方面から分析して異なる振り付けをしているからだろう。そしてラストで全員が同時にこれまでの動きを繰り返すと、これが混沌ではなく、太陽の周りを惑星が回る様なひとつの宇宙が見えてくるのだ。そしてその動きにダンスの歴史が刻まれている。カニンガム、ニコライス、チャイルズ、ブラウン、ローザス、ガロッタ…。どこかで見たことのあるような動きが懐かしい。
16歳から69歳までの17人のダンサーによる究極のミニマルダンスのなかに、マスゲーム的な大衆の動きと、個人を際立たせるシーンを組み込み、さらに社会問題を提起する。
劇場の舞台とは異なる会場の特徴を生かし、それぞれの個性を生かし、曲を綿密に分析した繰り返しの多い振り付けと、構成自体をミニマルに組み立て、そこにダンスの歴史まで織り込んでしまうという壮大なミニマル作品を作るとは、恐るべき才能の持ち主だ。(7月18日サン・ジョセフ高校の中庭)

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

舞踊作品からどんどん遠ざかる感じのマギー・マラン。ダンスではなくジャンル分けできない部門に振り分けられていたので少々不安だったが、見事に踊りのない作品だった。
舞台は所狭しとオブジェが置かれ、その間に原始的な仮面と槍の様なものを持った4人が登場。仮面を外してそれぞれの位置に着いたら、その後の1時間半はひたすらセリフのオンパレードだった。しかも内容は紀元前431年に始まったペロポネソス戦争。スパルタとアテナイ間の戦争に同盟国が加担し、ギリシャ全域を巻き込んだ大戦争だ。まさかの展開に驚いたが、図解説明による戦略や裏切りによる大混乱劇は分かりやすく聞き入った。しかし、少しでも踊る場面があるのではないかという期待は完全に裏切られ、かろうじて出演者たちが大きく移動したのは、夏の浜辺で日光浴をするシーンだけ。だが、マランの哲学は何事もなさそうに見えて最後に大パンチがある。この戦争解説が我々の記憶に新しい戦争の醜さに繋がるのだ。
「虐殺、殺戮、エゴ。これまでの戦争がどれだけの平和をもたらしただろうか。たとえ平和が訪れたとしても、その裏には多くの犠牲がある。人はそのことを知っている。知っていながら戦争は止むことなく今現在も続いている。」
そんな言葉とともに石を台に叩きつける4人の後ろ姿に、愚かな人間への憎しみと悲しみが見えた。(7月13日ブノワXII劇場)

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
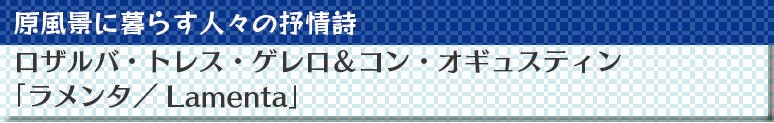
黒い服に身を包んだ男女が、吹き抜ける風の中で踊っている。ギリシャの民俗舞踊をベースにした作品で、独特の細かい足の動きや、コンテンポラリーの流れる動きなどを織り交ぜながらの踊りが、ひとつのコミュニティーで暮らす人々の日常を描く。同調、対立、喜怒哀楽。日々の光景や感情が歌声とともに流れ、広大な自然の風景と古い民家が立ち並ぶ村に生きる人々を連想させた。残念なことに後半の盛り上がりが始まった頃に雨が降り始めて中断し、そのまま中止となってしまい、最後まで見られなかった。歌詞はわからずとも、それぞれの場面の情景は伝わるが、強い印象が残らなかった。もしかしたら見られなかった最後の10分の群舞に凝縮されていたのかもしれないが。(7月12日アヴィニヨン大学)

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
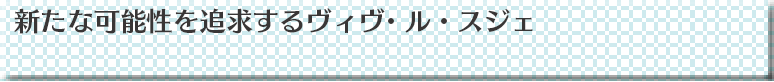
SACDが主催するシリーズで、出演者が振付家や演出家を指名するヴィフ・ドゥ・スジェとして1997年に誕生し、これがジャンルを超えた組み合わせにするル・スジェ・ア・ヴィフになり、それがさらにスジェ・ア・ヴィフとなり、2019年からヴィヴ・ル・スジェと名前を変えながら、新たな試みに挑戦するアーティストに30分の作品を依頼するもの。ちなみにSACDとは、Société des Auteur et Compositeurs Dramatiquesの略で、アーティストを保護する会社です。
フェスティバルの前半と後半に6日間、11時と18時の会にそれぞれ2団体がサン・ジョセフ高校のマリア像のある中庭で上演するのが恒例となっている。世界初演、しかもここでしか見られない作品が多いので人気が高いのに、会場が小さいのであっという間に完売になることが多い。それでも諦めきれない人は、早めに行ってウエイティングリストに名前を書けば、入れる可能性がある。
今回は8作品のうち4作品を所見。
期待を裏切らず、驚きの連続で爆笑だったのが演出家で人形師のジョアニー・ベールの「Làoùtesyeuxseposent」。言葉を全部くっつけてしまったタイトルで、「Là où tes yeux se posent」で、そのタイトル通り目は中央に置かれた台から飛び出るものに釘付け。この台から木が生え、根っこが台をぶち破り、小動物が走り回り、ダッチワイフも飛び出す。そしてマリア像が出たところで気がついた。この台はこの中庭の舞台の縮小版なのだ。そのマリア像が爆破され、神父らしき人形がぞろぞろ出てくるという手品まがいの演出に驚きと笑いの連続。ここまでの登場人物は全て人形で、最後に生身の女性が現れ、神父がそこにすがるというパロディ。さすがアイディアマンで、笑いの中にチラリと皮肉を込めるところがベールらしく大喝采。また、この作品を盛り上げたのがトマ・キナールの演奏。サクソフォーンを吹きながら木の影に潜んだり、舞台を転げ回ったり。音楽があまりにもピッタシで、作品と完全に一体化している。中央に躍り出てきて、おお、そうだった、これは生演奏なのだと感心すると同時に、そのパフォーマンスも見逃せない。舞台効果を知っているミュージシャンだ。

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
この後に行われたロイック・トゥゼの「プチ・トラフィック」は、ふたりの男性の無意味な会話がテーマ。1959年にロサンジェルスでジャック・タチとバスター・キートンがたった一度だけ、ひとつの椅子を使った4時間に渡るパフォーマンスを行ったことにインスピレーションを得ての創作。これだけ見れば面白かったのかもしれないけれど、ジョアニー・ベールの強烈な印象の後では物足りなく感じてしまった。(以上2作品7月11日サン・ジョセフ高校のマリア像のある中庭にて)

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
後半は、ポールアクロバットのジュグレールと、クランプのナッシュ。
ジュグレール(Juglair)の登場には度肝を抜かれた。身体中をラップで包み、しかも男女が合体した状態で出てきたのだ。両者の片足を一緒に包んでいるから、3本足の異様な物体が正面からひょこひょこと歩いて出てきたので、一瞬何がどうなっているのかさっぱりわからず。顔だってラップに強く巻かれてひん曲がっているし。その状態で私はこっちに行きたい、俺はあっちみたいな(口が開かないから、唸り声しか聞こえない)ぶつかり合いがあって、このままじゃあ皮膚呼吸ができないからどうするのだろうとの心配をし始めた頃に、ラップを取り外したので一安心。女のような男と男のようにたくましい女の組み合わせが面白いけれど、登場の衝撃が強すぎて、この後の展開のパンチが弱く感じられたのが残念。でも、ジュグラーのゆったりとしたポールダンスは魅力的だった。フランス版だるまさんがころんだで遊んだ後は、空気ビニール人形の馬に乗って駆け回り去っていった。タイトルは「プラスティック・プラトン」。

ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
そしてナッシュ。注目のクランプダンサーは、ラス・ローゼンタールが奏でる電子音楽に合わせてのパフォーマンス「7 vies /7つの生き方」。シンセサイザーやコンピューターで音質を変えて音を出したり歌ったりするのに合わせてナッシュが掛け合う。彼女のクランプは日常の感情を舞踊化していて、怒りというより楽しいダンスで、豊かな表情に好感が持てる。アドリブの掛け合いなどを交えて夏の屋外劇場を楽しんでいる感じだった。「人生、内面、青空は自分の中にあり、それぞれに歴史がある」そんな言葉が印象に残った。ただ、ふたりの会話はあっても、それが客席をも巻き込むような共感が得られなかったのが残念。
彼女はアヴィニヨン・オフにも参加していて、クランプダンスをわかりやすく説明しながらの「コンファレンス・ダンス」は上演日程が少なく、会場も小さかったことからあっという間に完売という人気ぶり。(7月18日サン・ジョセフ高校のマリア像のある中庭にて)

「7 vies」ⒸChristophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
この他、ダンスでは唯一法王庁の中庭で上演されたマルコス・モローの作品が見られなかったのは残念だったが、2022年1月のシャイヨー国立舞踊劇場で上演が予定されているので、そこで是非。
また、現ディレクターのオリヴィエ・ピイの後を継いで、ポルトガル人演出家のティアゴ・ロドリゲス(44)が2022年秋よりフェスティバルのトップとなる。2023年夏の演目が注目される。
|

