ようやく新シーズンが始まって活気が戻ってきたのも束の間、10月末には再び外出禁止令が出て劇場は閉鎖した。今回はリハーサル可能なので、解除されればすぐにでも上演ができるはずなのだが、「外出禁止令は少なくとも12月1日まで」。この「少なくとも」と言う言葉に不安感は拭えない。禁止令発令後に24時間以内のコロナ新規感染者が6万人と発表され、その後少しずつ減少しているものの、重症者は増えているとの報道。学校での授業は行われており、実感のない子供たちは顎マスクで街を闊歩している。ワクチンが開発されたという朗報と、最大の祝日であるクリスマス前には解除されるという見方もあるが、まだ先が見えない状態だ。
ランコントルは1作品を除いて全て延期、来年度のプログラムに組み入れることを決定した。
今月は、規制前に見た6本の作品の紹介を見た順に。
・Société en chantier/シュテファン・ケーギ
・白鳥の湖/アンジュラン・プレルジョカージュ
・Chotto Xenos/アクラム・カーン
・ルドルフ・ヌレエフ/パリ・オペラ座バレエ団
・オペラ座のエトワールたち/パリ・オペラ座バレエ団
・Le tambour de soie/伊藤郁女、生田ヨシ
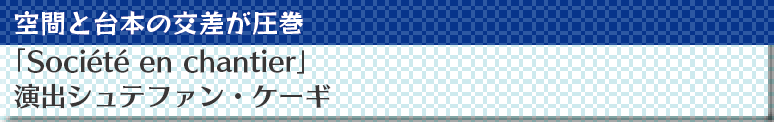
クレルモン・フェランの新劇場ラ・コメディ。落成オープン最初の公演が「Société en chantier」、直訳すれば「建設現場の社会」だけれど、「建設現場の実態」と訳したい。ゼネコンにまつわる談合や裏取引は世界中で行われている。その実態を、スイス人の演出家シュテファン・ケーギが鋭く暴く。内容も興味深かったが、その演出が見事。劇場空間をくまなく使い、時間と台本を交差させる。アートプロジェクトユニットのリミニ・プロトコルとしての名の方が通っているかもしれない。日本では2013年、第17回文化庁メディアアーツ祭のアート部門で優秀賞を受賞し、09年より何度もフェスティバル/トーキョーに招へいされている。話題の演出家の鋭い切り込みは、あっぱれであった。
開場して中に入るや否や「ここは工事現場ですから大変に危険です。ヘアーキャップを被り、軍手をつけてください。もちろんマスクも! 途中で体調を崩した場合は、すぐにオレンジ色のジャケットを着た係員に知らせてください」の呼びかけにワクワクするやらビクビクするやら。梯子が置かれ、ビニールシートで覆われた廊下を進むと舞台に出た。ど真ん中にプレハブ小屋があり、資材は山積み、ヘルメットがゴロゴロ。「劇場はまだできてないのでは?」と思いながら狭い通路を通って客席に。8つの小グループに分けられた観客は、舞台、客席、ホリゾント上の通路に位置してヘッドホーンをつけるように指示された。

©Jean Louis Fernandez
私のグループは客席から舞台を見下ろす形で、蟻の習性についての講義だった。何で蟻? 実は蟻は合理的な社会生活を営んでいるのだと蟻の生態を10年研究していると自称する研究者の話。自然の材料で巣を作り、簡単に増築変更ができる。これが現代人との大きな違い。また、年齢による仕事の分担がはっきりしていて、年寄りは巣の手入れでもするのかと思ったら戦闘要員。若者が巣の守りに入るのだそうで、合理的だけれど、爺さん婆さんが外での労働と敵との戦いとは、ちょっときついかも。説明員が舞台上で移動する人に話しかけて流れを止めれば、それが蟻の行動と重なり情報伝達の乱れを起こすとの説明。ふ〜んなるほど。

©Jean Louis Fernandez
蟻の講義が終わると今度は舞台のホリゾント上の照明通路へ。裏方さんのいる場所から舞台を見下ろす経験など滅多にできるものではないからワクワク。ここではアフリカの大規模工場への道路を封鎖され、稼働を続けるためにダーイッシュに通行料を払った結果、イスラム過激派協力者のレッテルを貼られることになった企業の話を聞き、見下ろせば舞台のあちこちで人が動いている。プレハブ小屋にばらまかれた金を慌ててかき集める談合中の人たちが滑稽に見える。その周りを足早に歩く人たちは、地下鉄の通路を移動する人たちで、地下通路で問題が起こればパニックとなる危険性を訴える。他のグループの動きが係員の説明にピタリと合うのが見事で、聞いて目で見て納得ガッテンの説明なのだ。

©Jean Louis Fernandez
舞台に降りてプレハブ小屋に入れば、先ほど上から眺めた談合会場。札束が降ってきた。「早く集めて!」解説員の言葉に素直に動く私たちを、別のグループの人たちは上から見ているのだろうなあ。ここは談合というより投資についての解説だった。
移動してヘルメットをかぶれば裏取引などの事例を挙げて、デモの参加者に早変わり。
大臣のゴリ押しで推薦した人に建設を依頼し、多額の資金を投入したにもかかわらず、空調施設不備のために使えないベルリンの飛行場。数日後にこのベルリン空港がようやくオープンしたとの報道をラジオで聞き、演劇の台本が偽りのないものだったことを確信。タイムリーな上演だった。中国人の役者は、中国の労働実態と、フランスへ移民としてやってきて、その違いに驚き戸惑う生活が語られ、ポルトガル人は、建設現場で働く労働者のほとんどが、不当に安い賃金と過酷な労働環境で働いている実態を明かす。それでは、このコメディ劇場はちゃんと賃金を支払ったのかなと思ったりしてしまった。設計者はポルトガル人だし、、、。
解説ごとに場所を移動し、資材を運び、ダンスまでさせてくれるフィジカルな構成にあっという間の2時間。そして何より素晴らしいと思ったのは、8つのグループが異なる内容を説明しているのに、別のグループの行動がその解説と絶妙なタイミングでバッティングし、説明通りの状況が見える演出。それがわかっていても、自分がその場に行けばすっかりハマって解説に納得している。
シュテファン・ケーギ。今後の活動を追いたい演出家だ。(10月1日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)
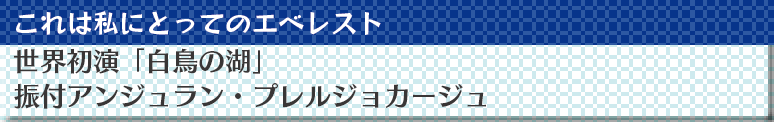

©Jean Claude Carbonne
「これは私にとってのエベレスト登頂」と意欲を見せたアンジュラン・プレルジョカージュ。マリウス・プティパとレフ・イワノフ版をベースに、チャイコフスキーの曲に音楽集団79Dの曲を組み入れながら、映像とともに現代社会と環境問題に言及した2時間の大作だ。
一言で言えば、コンテンポラリーダンスの強みと弱みが見えたと言うのが第一印象。世界に名だたるバレエ団の、トウシューズの先まで神経が行き届いたダンサーを見慣れた目には、足捌きの粗雑さが気になった。バレエ的なリフトも、細かい捌きがいまいち洗練されていない。とは言え、プレルジョカージュ独特のムーブメントとそれを見事にこなすダンサーたちに引き込まれた場面も多い。例えば、全員が黒い衣装に身を包み、椅子に座ったままシンプルな動きを連ねるシーンは、まさに鳥の館。4羽の白鳥は、プレルジョカージュのセンスが凝縮された絶品。そして、ラストで白鳥がジークフリートをなじる仕草。小さくて短い動きになのに、切なさ、寂しさ、後悔などオデットのやるせ無い気持ちが凝縮されている。プレルジョカージュ独特のムーブメント、そのボキャブラリーの豊かさにはつくづく感心する。
プレルジョカージュは、チャイコフスキーの素晴らしい音楽と、作品に溢れる「愛」に触発され、環境汚染で将来絶滅するかもしれない特異な形をした白鳥を描いたという。また古典作品との違いは、ジークフリートの両親にスポットを当てて踊る場面を多くし、物語の要としたことだ。
白いドレスの女が森を散歩中に、3人の黒服の男によって白鳥にされてしまう。服を剥がれ、スカートをたくし上げて白鳥になるのだが、この衣装が可愛らしく、悲劇よりも衣装に感心してしまった。
場面は変わり、高層ビルの一角のパーティ会場。ホリゾントにはニョキニョキと高層ビルが伸びていく。この街の権力者とその妻が、高層ビル建設計画の披露パーティに招待客を呼んだのだ。野心を燃やす夫と、贅沢な服に身を包んだ妻の踊り。息子のジークフリートは父親とは反りが合わず、自然を愛するナイーブな青年として描かれている。個性が足りないという批評があったが、いやいや、このくらい軟弱な性格というか、人混みに紛れたら見当たらなくなってしまうような個性のなさ、世間知らずでまだ乳離れしていないような成金のおぼっちゃまの方がこの作品には合っているのではないかと思う。
森を散歩中に暴漢に襲われたジークフリートを介抱したのがオデットだ。こうしてふたりは出会い、愛し合う。
一方、ロットバルトはジークフリートの父親に近づき、契約を取り付ける。そしてそのパーティ会場に戻ったジークフリートは黒鳥のオディールをオデットと勘違いして結婚を誓ってしまう。そして父親も、オディールの父ロットバルトが差し出した契約書にサインをしてしまい、騙されたことを知るのだった。
森に戻ったジークフリートをなじるオデット。「なぜ? なぜオディールと婚約してしまったの? なぜ私を捨てたの?」そんな会話が聞こえてきそうなムーブメント。小さく速い動きなのに、オデットの悲しみに満ちた動きが突き刺さる。巨大な工場が湖畔に建設される映像が映し出され、排水汚染で白鳥たちは次々と死んでいく。その中にはオデットの姿もあった。
背丈の揃った白鳥の群舞に見慣れていると、体型の違う白鳥たちのユニゾンがしっくりこないのだが、これもプレルジョカージュの目的のひとつ。森の中で見る白鳥は皆大きさが違うように、人間だって皆違う。綺麗に揃えることより、ありのままを見せることの方が自然だと。
バレエとコンテンポラリーの認識の違いを再確認させられた、少し不思議な「白鳥の湖」だった。(10月9日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

©Jean Claude Carbonne
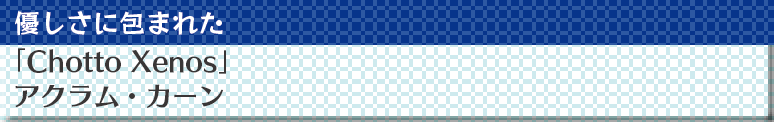

©Jean Louis Fernandez
アクラム・カーンのソロ「クセノス/Xenos」を見ていたので、「チョット・クセノス」はダンサーを変えただけだと思っていたのだが、全く違う作品なのだった。もちろん、設定は同じで、戦争に駆り出された一市民の男を描いている。カーンが踊る「クセノス」は、宮廷ダンサーだった彼がいきなり徴兵されて戦場に送り込まれ、武器の使い方もままならぬまま前線に立たされる姿を描いた重い作品だった。「チョット」シリーズは、「チョット・デッシュ」に続く2作目で、どちらも少し短縮して子供にもわかりやすいように作り替えられている。「チョット・クセノス」はマリオネットのスー・バックマスターの演出によって、戦争の恐ろしさを描きながら、愛に包まれて生まれ育ち、そして天国に向かうひとつの人生を描いていた。
大きな手が映し出される。次々と形を変えていく手の中に土が見え、やがてそこに現れたひとつの命。大きな手に守られながら、灯された火を取り込んで地上に降り立つ。生命の誕生だ。無垢な子供が見つけた迷彩服と防毒マスク。遊び道具のひとつだったものが、それに身を包み、自分を守る唯一の道具となり、戦場に送られる。常に監視され、砲弾にさらされ、仲間の死を目の当たりにする恐怖の毎日。故郷を思い、防毒マスクを愛犬に見立てて遊ぶことが唯一の心の安らぎ。しかし、目が覚めれば死と隣り合わせの前線にいる。大きな手が再び現れ、自分を包んでくれた。横たわった体からフゥッと魂が抜け、天国に旅立っていった。
アクラム・カーンの「クセノス」より柔らかく、戦争の惨たらしさより大きな愛情に守られていることを前面に出した作品だった。カーン版より社会性は失われているが、見やすい作品になっている。演出変わればここまで変わるのかと。(2020年10月23日テアトル・ド・ラ・ヴィル/エスパス・カルダン)

©Jean Louis Fernandez
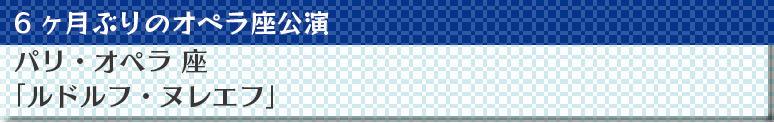
工事のため12月末まで閉鎖予定だったガルニエ宮は、新総裁の就任後予定を変更して、オーケストラピットを塞いだ幕前のスペースで9月から演奏会を、10月からバレエ公演を行っている。作品の抜粋、録音済の音楽、一部のダンサーしか踊らないという条件ではあるものの、観客の前で踊りたいダンサーと、バレエが観たい観客の気持ちがひとつになったソワレだった。たとえそれがソシアルディスタンスを取り、両隣1〜2席空けてのスカスカの客席ではあったけれど。天井桟敷席も埋まり、50%の入りで満席なのだ。
さて舞台は、貴賓席以外の舞台横のボックス席にはスピーカーや照明機材が置かれ、ダンサーは舞台に一番近い客席の出入口から入って舞台に上るか、舞台とオーケストラピットの間の隙間からの出入り。もちろん装置はない。条件悪くとも、オペラ座のダンサーが間近で見られるというのは、感慨深いものだ。
ヌレエフ振付の6作品の抜粋のソワレ。まずは「くるみ割り人形」1幕のアダジオをドロテ・ジルベールとポール・マルク。少し後にこのふたりは第2幕のアダジオで再登場する。ジルベールは安定して非の付け所がない。対するマルクは、よく踊っていたが、少し緊張した面持ちで、リフト時のスカート捌きとサポートに少々乱れがあり、若さを感じてしまった。エトワールに昇進するにはもう少し時間がかかるかもしれない。とはいえ、次のエトワールと期待している。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
「サンドリヨン/シンデレラ」はアリス・ルナヴァンとフロリアン・マニュネ。コンテンポラリーに定評のあるルナヴァンだが、古典ものも任しておけ! とばかりに、マニュネと息の合ったデュエットを見せた。ヌレエフの振付は難易度が高い。卒なくこなし、難しそうに見せないところは流石だ。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
ソロ「マンフレッド」は、プルミエダンサーのフランチェスコ・ムーラ(ミュラとも表記される。イタリア人なので、イタリア式にムーラ)によって力強く踊られた。舞台が狭く、客席に近いことも、彼のエネルギーがダイレクトに伝わる効果を増幅していたと思う。この後ラストの「ドン・キホーテ」でも見事な踊りを披露し、オペラ 座期待のダンサーであることを示唆した。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
ジルベールとマルクの「くるみ割り人形」第2幕のアダジオに続き、「ロミオとジュリエット」をミリアム・ウルド=ブラームとマチアス・エイマンのコンビで。これは本当に素晴らしかった。恋にときめくふたりからは、片時も離れがたく、愛する気持ちが溢れでていて、見ている側まで幸せになってしまうほどだった。ほんの10分の踊りだけれど、これだけで今夜はすばらしい公演を見たという気分にさせてくれた。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
写真はミリアム・ウルド=ブラームとジェルマン・ルーヴェ
アマンディーヌ・アルビッソンとオードリック・ベザールの「白鳥の湖」2幕のパ・ド・ドゥを見て思ったのは、「抜粋」はむずかしいということだ。物語があればその流れから状況を組み取れるのだが、作品の一部だけを取り上げる場合は、全幕を通して踊るのとは異なり、その状況、特に心理描写を明確に表さなくてはならないのではないだろうか。客席には生まれて初めてバレエを見る人もいるわけだし(親子連れの姿が多かった)、全ての人がストーリーを知っているとは限らない。「白鳥の湖」の物語も音楽も知らないという人に出会って驚いた事があったが、「ジゼル」となれば作品の存在さえ知らないフランス人が多くいるということに亜然とした記憶がある。つまり、バレエ作品を知っていて当たり前ではなく、知らない人にもなんとなくその状況がわかるように踊らなくてはいけないのではないだろうか。このふたりは確かによく踊っているけれど、そこからは「悲しい」「辛い」というような感情しか見られず、「悲しい運命」の中にも、ふたりの中に芽生えた愛情とか気持ちの変化が見られると良かったのではないだろうか。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
ラストはヴァランティーヌ・コラサントと再登場のフランチェスコ・ムーラによる「ドン・キホーテ」。今夜はムーラ大活躍。コラサントはオペラ座のお気に入りという印象がある。かつての昇進試験もエトワール任命の時も予想外の昇進と言われながら上り詰めた人で、個人的にはそのどっしり感が気に入っている。今宵のキトリ役はぴったりな上、3幕のパ・ド・ドゥは公演を盛り上げるには最適の演目だ。ムーラの溌剌とした踊り、コラサントの存在感、そしてラストはダブルを交えたグランフェッテ。少々軸がずれたものの、オーラで乗り切り、拍手喝采を浴びた。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
ジェルマン・ルーヴェとレオノール・ボラックの「眠れる森の美女」がダンサー降板で見られなかったのは残念。(11月26日オペラ座ガルニエ宮)
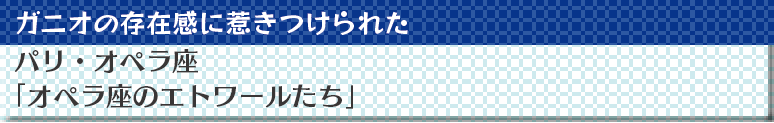
絶賛を浴びていたオニール八菜とヴァンサン・シャイエの「ヘルマン・シュメルマン」(ウイリアム・フォーサイス振付)はダンサー降板により上演されず、これが目的でもあったので全く残念だった。前回の23日までは踊っていたので尚更悔しい。ホームページの配役表では上演された形跡さえ消されている。
さて、幕開きはマチュー・ガニオのソロ、アラステア・マリオット振付の「月光/Claire de lune」。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
月明かりを浴びて佇むガニオ。やはりこの人のオーラは只者ではない。手を上げるだけで吸い込まれてしまう。オーラだけではなく、ダンサーとしての域をさらに深めたのだろう、たった7分のソロだが、見応え十分。サラブレッドではあるけれど、追及なしではその地位を保つことはできない。
次はエリック・サティの曲にハンス・ファン・マーネンが振付けた「3つのグノシエンヌ」をリュドミラ・パリエロとユーゴ・マルシャンが踊った。絶対安定のパリエロを卒なくサポートするマルシャン。あまりにも完璧すぎてかえって印象が薄くなってしまった。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
マーサ・グラハムの「ラメンテーション」は、伸縮性のある服を身につけて、椅子に座った状態で踊る作品。不自由な環境は社会批判でもあり、グラハムの著名な作品のひとつではあるが、セ・ウン・パクのように踊れるダンサーが踊らないというのが残念に思えた。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
初日にすでにキャストミスと酷評された「椿姫」は、ローラ・エケとマチュー・ガニオ或いはステファン・ビュリオンのコンビ。所見の日はエケとビュリオンで、残念ながら既読の批評通りだった。ジョン・ノイマイヤーの振り付けは、高度なテクニックが求められる。ステージが狭いからなのか、至近距離から見たせいなのか、単に振り付けを追っていて、目が合った時だけにこりと微笑むだけではふたりの関係を連想することすらできない。エケの感情表現には以前から疑問を持っていたが、身体から発するものが見えず、退屈な12分だった。これを見るにつけ、前日に見たミリアム・ウルド=ブラームとマチアス・エイマンの「ロミオとジュリエット」が思い出される。恋に浮かれ、片時も相手を思う気持ちが途切れない。どんなに難しいリフトをしていてもだ。もちろん作品が違うので簡単に比較することは出来ないのだが。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
「瀕死の白鳥」は、リュドミラ・パリエロとセ・ウン・パクのダブルキャスト。パリエロ版は優雅に朽ちていく白鳥で美しく、品位がある。しかし、何か一味足りないと感じたのは、死を目前にして、それでももう一度羽ばたきたいという生への渇望が弱かったからかもしれない。パクの白鳥も評判よく、いつか見る機会があればと思う。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
そしてユーゴ・マルシャンの「ダンス組曲」(ジェローム・ロビンス振付)で締めくくる。

©Svetlana Lobof / Opéra national de Paris
チェロ奏者のオフェリー・ガイヤールがステージに上り、マルシャンと駆け引きしながら踊る様子が微笑ましい。ただ、190cmの体格には舞台は少し狭かったからなのか、こじんまりと終わった感があったのは、一晩の締めとしては少し印象が弱かったように思う。(1月27日オペラ座ガルニエ宮)
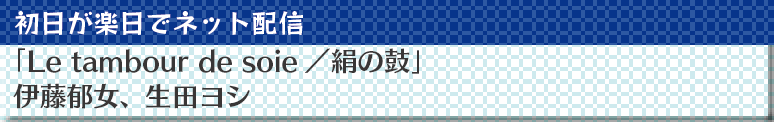

©Christophe Raynaud de Lage
伊藤郁女の提案で始まった新作「絹の鼓」。「90歳近い自分がまさか今になって舞台で踊るとは」と謙遜気味の生田だが、さすがの舞台人、ぴしりと舞台を締めている。
能の「綾鼓」と三島由紀夫の戯曲「綾の鼓」をベースに、日本人ならではの阿吽の呼吸を追求したという伊藤。舞台でリハーサルをするダンサーに一目惚れした掃除婦という筋書きだ。
演奏家の矢吹誠に上から目線で指示を出すダンサー。その様子を見ていた掃除係の老人に気づき、からかうように踊りに誘う。「絹の鼓の音を出せたら私はあなたのものよ」と老人をたぶらかす。幻想の世界に入り、優雅に舞う伊藤の後に、血がべったりとついた生田が鼓を叩き、伊藤に迫る。現実に戻り、伊藤はリハーサルを終えて去り、生田がひとり残るが、ダンサーと踊ったことが忘れられず、ひとりで楽しそうに踊って仕事を終える。踊ることは生きることの証なのだと、明るいラストに心が和む。
残念ながら外出禁止令が発令されたため、10月29日の初日が楽日になってしまい、翌日無観客のライブをネットで見た。画面ではダンサーのエネルギーは伝わりにくい。実際に観たかったと、コロナを恨むのみ。アクセスは予想以上に多く、伊藤と生田の人気ぶりが窺える。(10月30日テアトル・ド・ラ・ヴィルネット配信)

©Christophe Raynaud de Lage
ちょっとフランス語
外出禁止・都市閉鎖を日本では英語の「ロックダウン」という言葉を使っているが、フランス語は違う。
5月に発令された外出禁止令は「Confinement/コンフィヌモン」。閉じ込める、隔離の意味。
10月初めの夜間外出禁止令は「Couvre-feu/クーヴル・フゥ」。中世に夜中の火事を防ぐために発令されて、鋳鉄の蓋で覆って火を消せ、つまり「暖炉の火を落とせ」のこと。第二次世界大戦中にも使われた言葉。
そして10月末に再発令された外出禁止令もコンフィヌモンだけれど、2度目の登場なので「Reconfinement/リコンフィヌモン」と言われることが多い。REは再びの意味。
パリではコンフィヌモンに加えて11月6日以降、夜10時から朝6時までの食事のデリバリーとアルコール類の購入禁止のダブルパンチ。
外出禁止令解除は「déconfinement/デコンフィヌモン。この日が来るのが待ち遠しい。
※全て男性名詞です。
|

