
モー・ブランデル「LIGNES DE CONDUITE」
シモン・タンギー「FIN ET SUITE」
アクラム・カーン「OUTWITTING THE DEVIL」
国際ダンスプラットフォーム
杉本博司/アレッシオ・シルヴェストラン「鷹の井戸/AT THE HAWK'S WELL」
ウイリアム・フォーサイス「BLAKE WORKS 1/ブレイク・ワークス1」
フィリップ・ドゥクフレ「TOUT DOIT DISPARAITRE」
シーズンが開幕した9月。今年は早々と10日からボリス・シャルマッツの「INFINI」(見逃した)に始まり、バラエティに富んだ演目が続いた。では、見た順に。
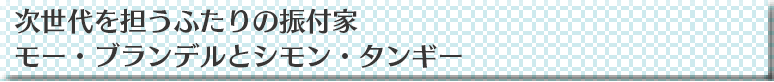
テアトル・ド・ラ・ヴィル主催で行われている振り付けコンクールダンス・エラルジーで、入賞あるいはファイナルに残った振付家のソワレが、アベス劇場で行われた。第1プログラムは、10分の抜粋を7作品上演するソワレ、第2プログラムは、モー・ブランデルとシモン・タンギーがそれぞれ1時間ほどの作品を上演する休憩を入れて2時間半のソワレだった。2018年に1位を受賞したKwame Asafo-Adjeiの「Family Honor」は、強く印象に残っていたが、ホールピースではないのでパスして、第2プログラムを見に行った。
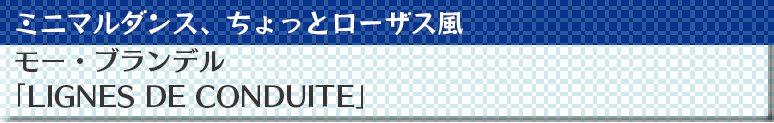
舞台奥にうっすらと見える大きな教会の鐘。舞台手前には天井から4本のロープが張られている。黒い衣装の女性4人がそれぞれのロープを引っ張ると、鐘はゆっくりと持ち上がり、そこからやんわりとした光とスモークが舞台に注がれた。鐘を上まで釣り上げて紐を固定すると、4人は輪になって向き合い、軽くステップを踏み、両腕を振りながらスルスルと移動している。鐘の音が音楽を奏で、それが風に揺らぐかのように、あるいは、木の葉が舞うかのように、4人は輪になったまま、少し向きを変えたりしながら移動している。曲が終われば、あっさりと動きをやめてロープのところに戻り、今度はゆっくりと鐘を下ろし始めた。少し下げたところで固定して、また先ほどのように輪になり、ステップを踏みながら不規則に移動する。しばらくして音がやむと、再び鐘を下げ、また踊り出す。鐘が下がるたびに照明は変わり、ホリゾントに大きな影を落とし、ダンサーも光と陰の中を行き来している。鐘を床すれすれに下ろした後は、4人揃っての前後の動きになるが、軽いステップから、少し飛び上がる動きや、回転、そして動きの速さを変えることで、同じような動きが少しずつ変化していくのがわかる。
簡単なステップだけれど、45分間ほとんど動き続けで、踊りをやめるたびに、大きな息遣いが聞こえてくる。これが私には、作品の流れを壊すように感じられたのだが、これもひとつの時間の経過と身体の変化を表す表現なのだろう。
長い髪と黒い衣装のミニマルダンスは、ローザスのいくつかの作品を連想してしまい、ブランデルらしさが薄かったのが残念。2016年のダンスエラルジーのファイナリストで、ボレロの曲に合わせて5人のチアーガールがサッカー場で踊るミニマルな動きの「タッチダウン」が印象に残っている。
ダンスだけでなく、演劇や、デザイン、写真の勉強もし、ローザンヌを中心に活躍する若い振付家の将来を期待したい。(2019年9月19日アベス劇場)

ⒸMargaux Vendassi
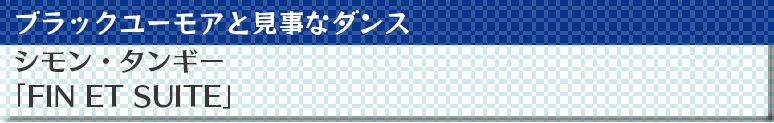
やっぱり好きだ~、シモン・タンギー! 見事なダンステアトルの爆笑もの。下調べしたプロモーションビデオでは感じられなかったが、しょっぱなから吹き出すほど面白かった。ナンセンスなブラックユーモアをセンス良く演出し、それをダンスの基礎がきっちり体に入っているダンサーに、ちゃんと振り付けして踊らせ、しかも豊富な知識による独自の言い回しで、納得ガッテンのセリフでまとめる。ジェローム・ベルとも、ピーピング・トム、デイヴ・サンピエールやジャン・マルタンとも違う、シモン・タンギー独特のセンスが好きなのだが、これを一言でどう表現したら良いのか、いまだに言葉がみつからない。

ⒸKonstantin Lipatov
若い4人が集まって飲み会をした秋の夜に起こった幻想? 現実? がテーマ。異様な空の色に不安を感じる人、ほろ酔い気分で呑気なことをつぶやく人、シェークスピアやドストエフスキーの文章を持ち出して、ヒューマニズムを語る人、ちぐはぐな会話と奇妙な行動。突き飛ばしたかと思うと、夢の世界に入り、別の人と抱き合い、踊り出したかと思うとぼーっとしたり、不安を叫びながらも、そのセリフとはどう考えても結びつかないような動きをしたりして、全く予想のつかない動きが飛び交っている。はちゃめちゃのようだけれど、ものすごくきっちり計算されていて、転がった先にスタッと別の人が飛び込んできて、見事なタイミングでのコンタクト。こっちで絡んでいたのが弾けると、別のところで絡む。セリフも既知に富んでいて、地球環境からモリエールまでと幅広い。ダンスだって、バレエからジャズ、コンテンポラリーから春の祭典までなんでもありだ。そこにブラックユーモアやパロディを入れているから、会場内は笑いが絶えず、時に爆笑の渦となる。ダンサーとしても、役者としてもレベルはバッチリの4人が、地球滅亡に怯え、そして滅亡を迎える。で、滅亡って何? みたいな終わり方がまたいい。
セリフが多いので、フランス語がわからないと腹の底から笑えないのだが、そこは野田演劇を日本語を理解しないフランス人が見た時の感覚と同じで、セリフは完全に理解できなくとも、テンポ良い展開と構成のや振付の面白さに驚くこと間違いなし。シモン・タンギーならではの風刺が見事。(9月19日アベス劇場)

ⒸKonstantin Lipatov
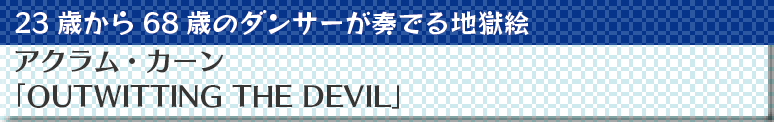

ⒸJean Louis Fernandez
カーンの最後のソロ「XENOS」で世界ツアーをする傍ら、英国ナショナルバレエ団に振り付けた「ジゼル」も世界ツアー中。そして、今年7月にシュトゥットガルトで初演の後、アヴィニヨン ・フェスティバルでは法王庁の庭で上演して話題となった「OUTWITTING THE DEVIL」が、パリの市立劇場テアトル・ド・ラ・ヴィル主催により、パリの新しい劇場トレージエーム・アート(13ème ART)で上演された。この作品もこれから世界を回る。
これは、メソポタミア時代の叙事詩「ギルガメシュ」を素に、死を間近にした過去の英雄王を描いている。
暗く、黒いオブジェが積み重ねられ、レンガが置かれた出口のない部屋を、よろよろと歩く男は、突然の大きな音に怯え縮こまる。昔の英雄の面影もない。シルエットとなっていた人たちがゆっくりと踊り始めた。女は髪を振り乱し、男たちは老人を威圧するかのように立ちふさがる。悪夢なのか現実なのかわからぬままに、震える手を差し伸べる老人の周りを、嘲るように踊り狂う集団は、地獄からの使者なのか。狂気の祭典に怯え、天を仰ぎ呟く男は、仲間割れから生じた殺人現場を目の当たりにして凍りつく。これは自分の過去だったのか。後悔、そして死への恐怖。しかし、心を落ち着け、人間としての優しさを伝えようと彼らに向かい、手を差し出す。神との静かな対話。そして見せられた石版。これはこの物語が描かれていたものだろう。それをうなだれた頭に乗せ、老人は静かに死の床に向かう。
インド舞踊をベースにした振り付けがシャーマニズム的な作風を盛り上げ、その一方でヒップホップの高度なテクニックや、小気味よいほどにシャープな動きをするダンサーに目をみはる。激しく踊るだけでなく、じっと見据えるだけで相手を恐怖で縛りあげるような迫力に、見ている方まで息を飲む。死を前にした王ギルガメシュを、68歳のフランス人ドミニク・プティが好演。現役時代はダンサーとしてカロリン・カールソンなどの作品を踊る一方で創作活動も行い、その後はコンセルバトワールで教鞭をとっていたが、その間も舞踊家としての活動を続け、演劇作品にも出演。退職後も踊ることから遠ざかることはなかったという。ふと目にしたオーディションの広告に興味をもった末が、今年のアヴィニヨンフェスティバルで法王庁の庭で再びダンサーとして踊ることになった。68歳という年齢とは思えない踊りは、その背中の筋肉を見ればわかる。
今年のアヴィニヨンフェスティバルでは、公演中にダンサーのひとりがアキレス腱を切断するアクシデントにみまわれたが、翌日ロンドンから急遽駆けつけたダンサーによって、最終日まで無事に公演を終えている。
その年齢でこの作品を踊る(かなり激しい動きもしている)ことについてドミニク・プティは、決して無理をしないこと、自分の体に合ったウォーミングアップをし、痛みが出たらすぐにケアーをするようにしているとのこと。これは全てのダンサーに言えることだと思う。
今回上演されたトレージエーム・アート(13ème art)は、パリ13区のプラス・ド・イタリー駅前の商業施設(丹下健三建築)にあった映画館を改築してできた劇場で、左岸では最大級の劇場という触れ込みだ。客席の段差が少ないため、見づらいと早くも不満の声が聞かれたが、中劇場ゆえに舞台が近く感じられるのは良いと思った。(9月20日Théâtre de la Ville/ Le 13ème Art)

ⒸJean Louis Fernandez
振付:アクラム・カーン
ドラマトゥルギー:Ruth Little
照明: Aideen Malone
ヴィジュアルコンセプト:Tom Scutt
音楽、音響:Vincenzo Lamagna
衣装:ナカノキミエ
台本: Jordan Tannahill
出演:Ching-Ying Chien, Joshua Jasper Narvaez, Dominique Petit, James Vu Anh Pham Mythili Prakash, Sam ASA Pratt,
ナレーション : Dominique Petit


このところ大劇場にばかり足を運んでいたのだが、振付センターや小劇場での若い才能も見逃してはいけない。有名じゃないから面白くないということはあり得ない。彼らがこれからのダンスを担っていくのだから。
パリの東隣の94県ヴァル=ド=マルヌの国立振付開発センターCDCNブリケトリーでは、毎年9月にレ・プラトーという国際ダンスプラットフォームを開催している。今年は、現代美術館MAC VALとジャン・ヴィラー劇場でも行われたが、岩渕貞太のパフォーマンスを見に、本拠地のブリケトリーへ。
この国際見本市は、無料公演の他、12ユーロまでの入場料と格安で、特にこの日は1日券15ユーロ、しかも最後までいればブリケトリーで採れた蜂蜜がくじ引きで当たるというおまけ付き。くじ運の悪い私でもゲットできました!

「We can be heros」ⒸLaurent Philippe
まず14時からの一般人参加のカラオケダンス「We can be heros/ウイ・キャン・ビー・ヒーロー」(コンセプトArnaud Pirault)。電源につながっていないマイクスタンドを前にした約30人が、30分間歌手になりきって一斉に歌い踊る。それぞれの思いを込めて熱唱する姿はピュアで、大受け。
この後が「Museum of Human E-motion」という日本、イタリア、フランス、台湾の4カ国から選ばれたアーティストが、各国でレジデンスをしながら作品を発表するという企画だ。ちょうどこの日が歴史的建造物公開日に当たり、元ライター工場だった建物を回って歴史を聞き、ダンスを見るという1時間のツアーガイド付き公演だった。アーティストはオブジェをひとつ持ってくるのが条件で、台湾のMing-Hwa Yehは、薄手の白い防護服を着て、ずるずると大きな紙を引きずって登場。そこからたくさんの写真を出し、レオタード姿になっての踊りだった。1967と書かれた数字や写真が何を意味するのか、もう少し明快に見えると良かったのではないかと思う。
簡単な内部見学とガイディングの後は、建物の外に出て、シンボルの煙突がある通路へと進んだ。石畳の外廊下の上に置かれた、黒い紐で編んだオブジェに気が付いた。するとその向こうで、ジーンズにダボダボの上着を着た女性が、もうひとつのオブジェを持ってゆっくりと石畳の上を移動している。日本とイタリアのハーフ、松下マサコだ。石の上に丁寧に素足を置きながら進んで、私たちを促すようにしながら前に進んで、煙突と外構の柵にかけられた緑のロープに体を委ねて揺れている。ロープにうまく体がかみ合わなかったようで、ぎこちなかったのが残念。
さらに進んで、正面入り口から再度建物に入ると、Ming-Hwa Yehがレンガを床に並べていた。その先の庭に抜けると、庭の奥の竹林からゆっくりと人が歩いてくる。先ほどの松下が黒いロープを持って進み、Ming-Hwa Yehが置いたレンガの隙間に下駄を脱ぎ、去っていった。下駄とレンガと、それを飾る細い笹の枝がいい感じ。するとバコバコと大きな金属音。見れば岩渕貞太が大きな金属の板を顔の前において、こちらに向かって歩いてきた。倒れ、起き上がり、踊り、竹林の中に飛び込み、走り、そして1本の竹と戯れ、静かに竹林の中に消えた。
Museum of Human E-motionは、日本、イタリア、フランス、台湾の4カ国のダンス交流事業で、身体とオブジェをテーマに、各国でレジデンスをしながらパフォーマンスを行う企画。2年目の今年は、8月イタリア、9月フランス、12月日本、そして年末年始にかけて最終地の台湾で終わる。東京公演では、今回参加しなかったフランス在住のイラン人Sorour Darabiも出演するだろう。時間の経過と場所の変化によって、それぞれのコンセプトがどう変化していくのか、興味がわく。詳細は、セゾン文化財団ホームページへ。 http://www.saison.or.jp

「Museum of Human E-motion」

「Museum of Human E-motion」 松下マサコ

「Museum of Human E-motion」 岩渕貞太
このあと別室に移動し、ジュリー・サルグの「De si loin, j'arrive(とても遠くから、来る)」を。完全に閉じていない光る円の中でのソロで、最後に開脚をすると円がつながるという趣向。座席を移動して、今度は四角いステージを「アン、ドゥ、トロワ…」と数を数えながらの踊り。動きを連ねただけの踊りから、もう少し感じるものが欲しかった。
最後は、アンドレア・サルストリの「マテリア」。扇風機を使ってボールや板が宙に浮いたりひとりでに動く作品で、オブジェの不思議な動きは、種明かしされていても見入ってしまう。制作途中なので、これからどう発展していくかが楽しみだ。

「マテリア」ⒸLaurent Philippe
ブリケトリーでの3日間に渡っての見本市では、2日目のレイラ・カ、ヌリア・グイウ・サガラ、チョイ・カファイの3作品が面白かったそうで、見逃した~。(9月21日ラ・ブリケトリー。https://www.alabriqueterie.com/fr/)


「鷹の井戸」ⒸAnn Rey / Opéra national de Paris
今年350年目を迎えるパリ・オペラ座は、杉本博司演出による「鷹の井戸」とウイリアム・フォーサイスの「ブレイク・ワークス1」で幕を開けた。
350周年のオープニングプログラム、しかもオペラ座に初登場、世界的に有名な杉本博司が「鷹の井戸」を演出するとあって、前評判は高かった。テレビのニュースでは初日の終演後の観客の感動の声を交えて大きく取り上げていたので、期待に胸を膨らませてガルニエ宮へ。
能とケルト神話の融合とも言えるイエイツの戯曲を、杉本博司の演出の下、イタリア人のアレッシオ・シルヴェストリンの振り付け、アメリカ人リック・オウエンスが衣装を、そして池田亮司の音楽に合わせてオペラ座のダンサーが踊るという、国際色豊か、かつ錚々たるアーティストの結集と期待したのだが、あいにく杉本が思い描いたイエイツの魂を感じることはできなかった。
会場に入って真っ先に目にしたのが、オーケストラピットに張り出した能舞台。ホリゾントには緩やかに弧を描いたスクリーンが張られ、その中央から客席に1本の白木の道が、まっすぐに能舞台へと通じている。ナポレオン時代の豪華な装飾と、白木の能舞台。この対照的な美術が印象的だ。
ホリゾントの色が変わるだけの照明と映像による美術(杉本、池田)は、ガルニエ宮の舞台の高さを強調し、効果的だった。衣装は、コールドが黒、若者と老人が銀あるいは金色、鷹姫が赤で、大きく穴の空いたレオタードにブーツというパンク調がかっこいい。男女の差なく全員がストレートヘアのかつらをつけていて、オウエンスの分身が踊っているようだった。しかし、斬新に見えた衣装は、踊るのに適していたかどうかは疑問だ。まず、老人と若者の衣装の違いはほとんどなく、ヒゲをつけているかどうかだけ。ふたりの長いマントは、ごわごわした素材の光るもので、その扱いがサラッと行かない上に、顔の横まで立ち上がる大きな襟は首の動きを隠し、それを脱げば前後に布を当てただけのアダムのような衣装で、老人とは思えない肉体からの動きは、若者との違いをさらにぼかしている。鷹姫の大きな羽も時にぎこちなく動き、夢から叩き起こされたような思いを何度かした。
振り付けに関しては、冒頭の濃いブルーのホリゾントの中、シルエットとなって現れたコールドの、キビキビした踊りも悪くないように思われたのだが、しばらくすると揃わない群舞が気になり始めた。この日は第2キャストの初日で、老人役のオードリック・べザールの美しい上半身とシャープな踊りからは、老人をイメージさせない。スジェのアクセル・マリアーノは、急遽代役が立ったのかと思うほど冴えず、鷹姫のアマンディーヌ・アルビッソンとのデュエットは、リフトを失敗したのかと心配するような場面もあり、コンビネーションがしっくり行かない。3人の関係も会話も感じられないまま、群舞の踊りとなったが、フォーサイスまがいの振り付けは、意味がなく冗長だった。そして、突然の能楽師の登場。これをデウス・エクス・マキナと解釈した人はどのくらいいただろうか。私にはあまりにも唐突に見えた。しかし、着物に白髪、面をつけ、マイクもつけずに歌う声が響くと、会場は一瞬にして緊張感に包まれた。杖をつきながらゆっくりと能舞台に上がり、あたりを制するように踊る観世銕之丞。小さな動きだが、会場を震わせるほどの存在感に圧倒される。このシーンで作品は締まったが、同時にそれまでの能を真似た動きが偽物だったことを浮き立たせてしまった。真似事は本物になりえず、伝統はそう簡単に身につくものではない。物語が見えないまま、能楽師と若者が静かに舞台を後にした。
第1キャスト(鷹姫リュドミラ・パリエロ、若者ユーゴ・マルシャン、老人アレッシオ・カルボルヌ)ならと思ったが、あまり大差はなかったようで、ビジュアル的には美しくとも、オペラ座のダンサーの価値が生かされなければ、ファンとして納得がいかない。
世界で活躍するアーティストが集結し、それぞれの構想は悪くないが、それらがひとつになって「杉本版 鷹の井戸」を作り上げたとは感じられなかったことを残念に思う。

「鷹の井戸」ⒸAnn Rey / Opéra national de Paris
その一方で、休憩後のウイリアム・フォーサイスが2016年に振り付けた「ブレイク・ワークス1」は素晴らしかった。これぞダンス、見る側が踊る喜びを分かち合えるのは、ムーブメントの面白さに加えて、ダンサーが踊ることを心から楽しみ、そのエネルギーが伝わってくるからだ。軽快な作品だから身体が喜ぶのではない。動きを身体が理解して、空間と重力の駆け引きをしながら、高度なテクニックを難解に見せず、さらりとこなしているから、流れが途切れず心地よい。

「ブレイク・ワークス1」ⒸJulien Benhamou / Opéra national de Paris
メインで踊ったレオノール・ボラックはシャープでいながらしなやかさを失わず、ユーゴ・マルシャンも軽快なステップで観客を沸かせ、エトワールとして安定した踊りを見せた。最初の場面では、ビアンカ・スクダモアが伸びのある動きと安定したバランスでひときわ目立ち、マリオン・バルボー、シルヴィア・サン=マルタン、ポール・マルクも良い踊りをしていて、シーズン幕開きにふさわしい作品だった。(9月25日オペラ座ガルニエ宮)
「鷹の井戸」
原作:ウイリアム・バトラー・イエイツ
演出、美術、照明:杉本博司
音楽:池田亮司
振付:アレッシオ・シルヴェストリン
衣装:リック・オウエンス
映像:杉本博司、池田亮司
能楽師、振付;観世銕之丞
能楽師:梅若紀彰


ⒸSigrid Colomyes
さすがドゥクフレ、エンターテイメント性十分の超楽しい公演だった。普段は見ることのない場所も解放されて、建物見学+公演+展示+映画+飲食+休憩の充実の半日。土曜日だったので15時半開場で、終了が20時半。最初から最後までいても、全部は見られない仕組みになっているとの説明に、欲を抑えながら劇場内を回るも、あちこちでパフォーマンスやインスタレーションを見て回っていたら、あっという間に時間が経つ。休憩をする暇はなかった。
まずは小グループに分かれて、ダンサー扮する仮装ガイドの説明を聞きながら、ホール、地下のホールを訪れる。木のエスカレーターは、パリ最古のものだそうで、1937年にできたとか言っていた。違ったかな。その階段で、ドミニク・ボワヴァンとパスカル・オーバンのデュエット。エスカレーターの方向を係員が変えながらの、サンパティックな作品。この階段で、誰かがジャン・ギャバンと出会ったとか。
そのあとスタジオ形式の小劇場ベジャールで30分ほどのパフォーマンス。男性のデュエットの後、ビデオダンスで有名な「ル・プティ・バル/Le P’tit Bal」の上映を懐かしく見ていたら、机がさっと出てきて、なんとドゥクフレとオーバンが実際に踊ったのだ。ビデオでしか見られない作品だと思っていたので感激。1994年の初演だから、25年ぶり。髪に白いものがまじり、昔のようには踊れないし、草原もないけれど、いい味出していた。そのあとに放映されたカンパニーメンバーのビデオも25年前に撮影されたデュエットで、これまた当時踊ったふたりが実際に踊った。時が流れて、容姿は変わっても、まだまだ踊れる。
ここからは劇場内をふらふらと見て歩くことになった。
そして、中劇場フィルマン・ジェミエ劇場へ。ミュージシャンが両脇にいて、中央の机では黒人のがっしりした男が机を磨いたり、その上で三点倒立をしている。そのうちにパフォーマンスが始まった。歌って踊って、いくつかの作品の抜粋が続く。ここでも「Le P’tit Bal」の実演。30分ほどのパフォーマンスの後は、また場内放浪。
ダンサーが映った画面をこすると素っ裸になるインスタレーションとか、ある場所に入ると自分の顔と背中が合体するとか、ラジオ放送の横で踊るとか、虫の面をつけたダンサーたちが場内を踊りながら移動するとか、映画もあって、気をつけないと大事な公演を見逃してしまいそうになる。慌てて大劇場ジャン・ヴィラールへ。ここでは1時間ほどの公演だ。
最初の「Tranche de cake」は1984年の作品で、浸水被害で資料が消失して、写真が数枚と音楽だけしか残っていなかったと。それを当時のダンサーの記憶を元に復刻したのだと、ドミニク・ボワヴァンは解説しながら踊っての大活躍。ドゥクフレ、パスカル・エンロ、ベンジャマン・ラマルシュ、シルヴィー・ジロン、60才を超えたか超えないかの5人が踊るから、ちょっと勢いはないけれど、同窓会風で微笑ましい。3曲目からはもう少し若いダンサーたちが出てきて、歌手のノスフェル(Nosfell)も加わって、 オケピの楽団との熱唱。抜粋ばかりだけれど、懐かしい~。ドゥクフレはかなり前からビデオとのコラボや、空中芸を取り入れていて、時代の先端を先取りしていた人なのだ。ダンスあり、エンターテイメントありの1時間を楽しみ、最後はダンサー総出で踊り、ドゥクフレのソロで締めて、観客大喜び。彼はやっぱりスターなのだ。
30分ほどの異なる演目が6つほどあったスタジオ・ベジャールの最終回は、豪華に1時間。ダンスあり、レクチャーあり、歌ありビデオありでバラエティに富んでいた。それにしてもここのダンサーは多才で、踊ってよし、歌ってよし、楽器もOK。ラストの男性ダンサーによる影絵劇と花火の音が面白くて、笑いが絶えない。
階段を客席に、廊下の壁をスクリーンにした映画上映では、アルベールビル冬季オリンピックの開会式のリハーサル風景とか、フランス2チャンネルの広告や、電話の地域番号が変わる案内のコマーシャル映像(超カワイイ)など、今までに見たこともなかった映像に出会えたのが収穫。
20時半に締めがあると聞いて、ホールで待てば、おじおさんおばさんになったオリジナルメンバーによる抜粋作品に続いて、観客交えて踊って歌って、これで終わりかと思ったら、最後は出演者全員の指鳴らしパフォーマンス(ソンブレロの一部だと思う)で締めた。
新作はなくとも、構成のうまさに、古いものを見たという感覚がなく、楽しい1日を過ごした。あちこち移動しながら5時間パフォーマンスしているダンサーは大変だろうけれど、みんな楽しんでいたようだった。遊び心たっぷりで、でもちゃんとダンスで、サーカスもあって、音楽も生演奏で、ノスフェルの歌と演奏がかっこよかったなあ。楽しいことは、いいことだ! でも、タイトル通り、全ては消えゆくものなのだが、「Tout doit continuer!/もっと続けろ!」と叫んでいる人もいる。同感!(9月28日シャイヨ国立舞踊劇場)

ⒸSigrid Colomyes
|

