| 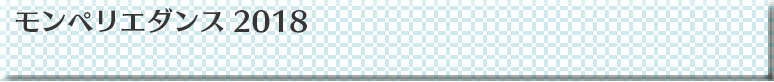
38回目となったフェスティバル・モンペリエダンスが、6月22日から7月7日まで行われた。
バットシェバ・ダンスカンパニー、NDT、ローザス、アクラム・カーンなどの名だたる名前が連なる中、スペイン国立ダンスカンパニー(カンパニア・ナショナル・ドゥ・ダンサ)とバレエ・デュ・キャピトルの、パリ・オペラ座元エトワール、ジョゼ・マルティネズとカデル・ベラルビ率いるバレエ団や、独特な作風のシルヴァン・ウク、ヒップホップ界を代表するカデル・アトゥ(ラ・ロシェル国立振付センター芸術監督)+ムラド・メルズキ(クレテイユ-ヴァル・ドゥ・マルヌ国立振付センター芸術監督 )2人のコラボ作品、その演出には定評のあるオーレリアン・ボリーとフィア・メナール、モード・ル・プラデック(オルレアン国立振り付けセンター芸術監督)など、注目の振付家が名前を連ねる豪華版。さすがモンタナリ氏の手腕が光るプログラミングだ。
オープニングは、フォーサイスの後を引き継いだ、ヤコボ・ゴダニ率いるドレスデン・フランクフルト・ダンスカンパニーと、ラ・ザンパ。地元で活動するカンパニーを押し出すことは大事なことだ。また、フェスティバルの期間中、トリシャ・ブラウンの回顧展が開かれていた。
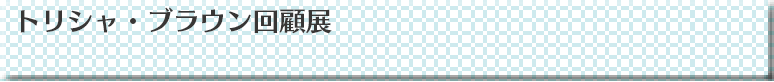

ⒸMasumi
シャペルだったベジャール会場は、天井が高くて雰囲気がある。中に入ると、中央の円形状の展示が目を引いた。写真が螺旋階段のように空に浮き、それをたどっていくと床に置かれたブラウンが描いた絵にたどり着く。
モンペリエが大好きで、1982年から2013年まで、何度もモンペリエダンスで踊っているブラウン。踊りながらデッサンをした「イッツ・ア・ドロー/It’s a draw」(2002年)が展示されていて、その時のことを思い出した。客に媚を売るでもなくウオーミングアップをし、遊んでいるように踊っていたブラウン。 梯子をいじり、ロールを引っ張って白いリノリウムを広げ、黒いクレヨンで足の形を描き、転がりながら描いていく。時々遠くからデッサンを眺めては、満足げだったり、気に入らなければやり直したり。全く自由な精神とその体に、戸惑いさえ覚えたものだ。奥ではインタビューやダンスの映像が大画面とモニターから流れている。一方の壁には、ブラウン直筆の手紙やデッサンが展示され、温もりを感じさせる展示だった。

ⒸMasumi
では、6月27日から29日までに見た公演評を見た順に。
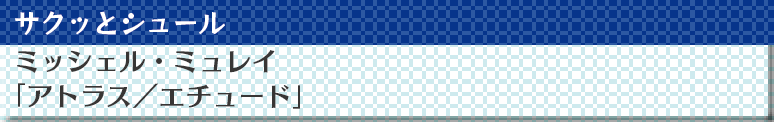

ⒸPAUL LECLAIRE & LAURENT PAILLIER
午後4時と10時の2回で完結する作品。それぞれが1時間強ある。昼の部は、「アトラス/エチュード」の5番、9番、10番、3番、2番、1番の順番、夜の部は、6、10、7、8、4という順番になっていて、それぞれが15分前後。どの章も、装置も何もない舞台に、下手奥から出てきて位置して始まる。
最前列の客のすぐ前で、エアロビのように腕を振り、奇声を時々あげるのが最初の作品「5番」。ミニマルダンスのようにひとつの動きの繰り返しが少しずつ変化していくスタイルだが、その暴力的とも言えるエネルギーの強さに、身を引いてしまった。しかし、怯まずに見ているうちに、バイクで突っ走る若者に見えてきた。面白くなりかけた頃に、彼らはさっと動きをやめて、スタスタと舞台から出て行ってしまった。すれ違うように出てきた男女4人は輪になって座り、大きな動きもなく、寝転んだり、遠くを見たり。公園でくつろぐ暇な集団に見えた。最初とその次の作品のあまりの違いに戸惑ったというのが正直な感想。しかし、作品は私の驚きとは関係なく続き、ひとつの集団が去ると、別の人が出てきて動き始めるというように、連結のないシーンが展開する。走ったり転がったり、モデルのようにポーズの連続をしたり、横にいる相手と目を合わせないカップルだったり。日常の動きだけれど、何か変な感覚が残る演出だ。音楽はリズムの強いハウスや、騒音、無音と、シーンによって全く異なる。消化不良感が残りながら夜の部を見たのだが、これが面白かった。時間を空けて見たことで、自分の中で何かが消化されたのだろう、日常の仕草の中の違和感を見つけるのが面白くなってきた。よくありそうなのに何か変、冷え切った関係に見えるけれど、実は信頼しているからこそできる行動だったり。ありそうでありえない、軽めのシュールな感覚にハマった。
翌日行われたダンスクラスでは、この作品の一部を紹介。踊ってみるとなかなか気持ちが良いし、関わりがなさそうで、実は密に相手を意識する感覚を体験できたのは、興味深いことだった。(6月26日アゴラ・スタジオ・バグウエイ)

ⒸLAURENT PAILLIER
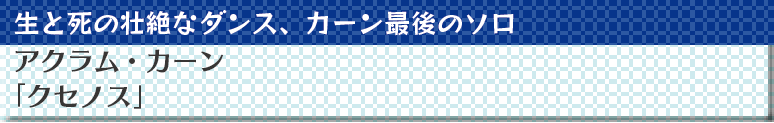

ⒸNicol Vizioli. Interprète / Dancer Akram Khan
速い回転と静止、リズミカルなインドのカタックダンス、あるいはシャーマニズムのような幻想世界を期待していたら、どん底に突き落とされたかのような重い情景に目を見張った。
開場時から舞台ではミュージシャンがカタック音楽を奏で、ゆったりとした心地よい雰囲気。客電が消えると、アクラム・カーンの小気味好い踊りが始まった。新作もカタックダンスかと思った途端に、まるで嵐が襲来したかのように様相が一変した。暗闇の中に灯されたマッチの明かり。目の前にせり上がった壁と太い綱。よろめきながら登り、転がり落ちる。この急激な変化を飲み込むことができなかったが、そこが戦場だということがわかってきた。その何本もの太い綱は、武器を運ぶための道具であり、同時にカーンがそこに縛り付けられていることも示している。時に転がり落ちる体を支えているようにも見えたのは、痛烈な皮肉だった。銃声に倒れ、号令に慌てて直立する。そしてまた銃声。伏せては起き上がり、進んでは倒れ、それでも必死に起き上がる。敵の銃弾に倒れるだけでなく、絶対服従しなくてはならない司令官への恐怖だけでなく、天候にかかわらず、道なき道を進み、土砂崩れなどで命を落とすものもいる。生き延びることへのかすかな希望だけを頼りに、前へ進み、死と隣り合わせの日々を重ねていく。
この作品は、第一次世界大戦に英国兵として駆り出されたインド人たちの話をベースにしている。彼らのほとんどは北部と北東部の貧しい農民で、1,500万人が異国で命を失ったという。「クセノス」とは「外国人」という意味のギリシャ語で、宮廷舞踊家が、突然兵士として戦場へ送られたという設定だ。
バングラデッシュの両親の元、ロンドンに生まれ、コンテンポラリーダンスと特にカタックダンスを学んだカーン。イギリスに住む上で自分を外国人だと感じることはないというが、これまでにも自身のルーツを感じさせるような、アジア的な精神世界を描いた作品を何本も創作している。この作品では、史実に基づいた悲惨な出来事、忘れてはならない事実、しかも語られることがほとんどなかったインド兵士を取り上げ、戦争の愚かさをダイレクトな表現法で描いたことに、ある種の驚きを感じた。そこには、これがソロで踊る最後の作品という思いも込められているように感じた。
土まみれになって踊るカーン。転がり落ちたたくさんの石は、戦争によって破壊された瓦礫、あるいは人骨、それとも砕けた心だろうか。救いのない世界に見えたが、そのひとつを取って土の上に落としたのは、一粒の種が地に落ちれば、そこから新たな生命が育つという希望を失いたくなかったからだろう。ベルリオーズ・オペラ劇場という広大な舞台は緊張で満たされ、カーンの存在感の大きさは、必見の価値がある。モンペリエのあと世界ツアーに出て、パリは1年後の上演になるそうだ。(6月26日オペラ・ベルリオーズ)

ⒸJean-Louis Fernandez. Interprète Akram Khan.21
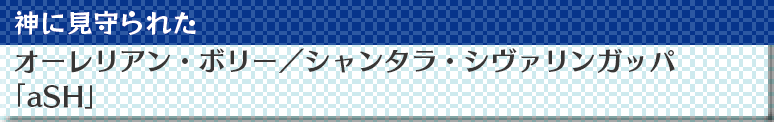

ⒸAgale Bory
自身のカンパニーを持ちながらも、多くのアーティストの演出を手がけ、意表をつく演出で人気のオーレリアン・ボリー。新作は、インド舞踊のシャンタラ・シヴァリンガッパへの作品。
薄暗い中でのパーカッションの響きと、揺れるホリゾントの模様。鋼鉄のような質感なのに、ぐにゃりとくねるその不思議な幕は、重いものを引きずるような音とともに激しく揺れた。それはまるで神が怒っているようだった。そして、不思議な模様は2本の線になり消え、静けさだけが残った。天井までの大きな幕の前にじっと立つシヴァリンガッパは、その全てをじっと受け止めているようだった。そして踊りだす。動きは少ないが、キレのある踊りに見惚れる。神の化身のような巨大な幕が波のように押し寄せ、そこに埋れ、抱かれるシヴァリンガッパ。神が宿った。幕は叩かれ、パーカッションは高揚する。
それが一段落すると、大きな盆から灰を撒き、出来上がった渦を巻くような円模様の上で踊り始めた。足の動きが円を描き、すでにできた渦を消し、新たな模様が浮き上がる。灰が服につき、汚れていく体。しかし、そこには力強くて新しい何かが宿っているのを感じた。
オーレリアン・ボリーの演出と、シヴァリンガッパの振り付け、そしてパーカッションのロイック・シルド。3人の戦いが神を制したようだった。(6月28日グラモン劇場)

ⒸAgale Bory
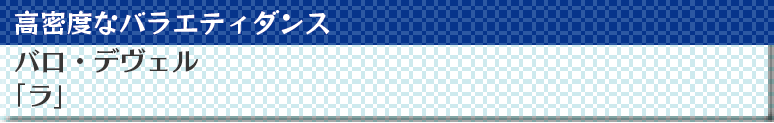

ⒸFrançois Passerini
「それ」というタイトル。ビデオを見れば、男女の頭の上を鳥が行ったり来たりするだけ。ふうむ、これしかないのなら、見にいくのは時間の無駄か。でもせっかくモンペリエにいて、時間もあるから、じゃあ見にいくか。と全く期待しなかったのが良かったのかもしれない。めっちゃ面白かったのだ。
確かに鳥も出演する。すごく賢くて、鳥なのに立派な役者で、司会者が読むべきメモを取り上げて引きちぎったりする。でもこれはほんの数分の出来事。残りの1時間は、カミーユ・ドゥクールティとブライ・マトゥのサーカスみたいなダンステアトル風。でも、ほとんど言葉はない。
司会者なのに言葉が出ない男、足から真横になって出てきた女。グネグネに柔らかい体が作り出す不思議な形にアクロバット。このふたりの予想がつかない行動に、驚き笑い、あっという間の1時間。ダンスに演劇(身体表現のボケとツッコミが絶妙)、鳥に(別の作品では馬も使うらしい)映像にノイズ音と、たくさんの要素とオリジナリティ溢れるアイディアいっぱいで、テンポよく展開する。デジタル技術を使っているのに、それを感じさせないところが良い。ホームページで動画が見られるけれど、実際に見に行くほうがはるかに面白いと思う。(6月29日ヴィニェット劇場)

ⒸFrançois Passerini
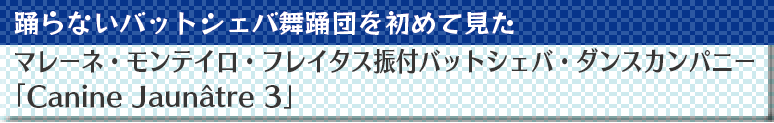

ⒸAscaf
マレーネ・モンテイロ・フレイタスの作品は見ていたし(バッコスの信女−浄化へのプレリュード)、この作品の情報を得ていたこともあり、困惑することなくスッと作品に入れた。これなしには、1時間半を耐えられなかったと思う。つまり、ナハリンの作品を踊るバットシェバ舞踊団を期待すると、あまりの違いに愕然とするはずだから。アバンギャルドで風変わりな作品を作るフレイタスと、バットシェバ舞踊団。どう考えても接点が見つからないこのコラボレーションを、非常に楽しみにして見にいった。
開場して客が席に着くまでの間に、2回ほどダンサーが出てきて、舞台中央で輪になり、ステップを踏みながら歌う。楽しくもなんともないといった感じだし、少年兵という歌詞も聞こえてきてくる。しかし彼らの出で立ちは、黒の短パンにTシャツ、白い靴下にバスケットシューズというスポーツをする出で立ちだ。しかも舞台全面にはテニスのネットが張られている。客電が消えて、再度同じことが繰り返され、今度は袖に入る代わりに、それぞれが位置についた。電光掲示板に数字が現れ、顎の下にガムテープを貼って、いかにもこれからラグビーの試合に臨むかのような様子を見せるものの、ラグビーをするわけでもなく、電光掲示板の数字が何と連結しているのかもはっきりしないまま、舞台の端に座ってボーッとする人、よだれを吐き続ける人など、ひとりから数人のグループが、意味のなさそうな動きを繰り返している。人形振りのようにカクカク動いたり、目をキョロキョロさせたり、大口開けながら変な形をしたり。奇声をあげる人もいれば、ボサノバに合わせて腕を振り続ける人もいる。チャイコフスキーから007まで無秩序とも思える音楽構成、バレエのパの真似事から見事なタップダンスまで、あまりにもたくさんのことがアトランダムに起こるので、何を言いたいのかさっぱりわからないのだが、面白い。だいたい、高度なダンステクニックを持ったダンサーたちを踊らせないところがすごい。2016年になるまでバットシェバ舞踊団を見たことがないという先入観のなさゆえに、できたことなのかもしれない。
3ヶ月のリハーサルで初演にこぎつけ、フレイタスの動きを消化仕切れないダンサーがいたらしいが、モンペリエでは全員が見事に「ちょっと風変わりな人」になりきっていた。舞台と客席を仕切っていたテニスのネットが最後に取り払われ、大声で自由に歌い、踊るダンサーたちの開放感は、もしかしたらフレイタスの動きから解放された喜びが全身に現れているようにも見えて、これを皮肉と取るのか、あるいはフレイタスの計算によるものなのか、ダンサーに聞こうかと思ったが、聞かずに想像する方が面白いと思って、そのまま会場を出た。
作品の目的をフレイタスは、「素晴らしい笑顔から、汚い歯が見えるような感覚」だという。ふうむ、わかったようなわからないような。でもそれで良いのだ。(6月29日アゴラ劇場)

ⒸAscaf
この独特というか非常に変わったマレーネ・モンテイロ・フレイタスの作品が、京都エクスペリメント2018でまもなく見られる。さすが京都国際舞台芸術祭。こちらで話題になっているものを新鮮味が失われないうちにサクッと呼ぶ。もう終わってしまったが、ジゼル・ヴィエンヌの「CROWD」も上演されていた。これもフランスで話題になった作品だった。
マレーネ・モンテイロ・フレイタス「バッコスの信女-浄化へのプレリュード」は、アイディアがいっぱい詰まった、めちゃめちゃに面白い作品です。10月20〜21日、ロームシアター京都サウスホールにて。是非!
詳細は下記アドレスでご確認ください。
https://kyoto-ex.jp/2018/program/marlene-monteiro-freitas/
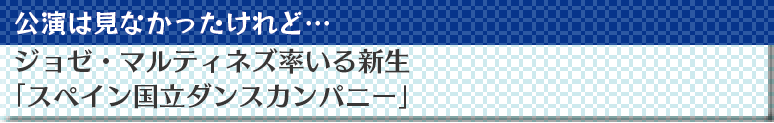
フォーサイスレパートリーに食指が動かず、予定に入れなかったスペイン国立ダンスカンパニー公演。しかし、芸術監督のジョゼ・マルティネズのトークを聞いて、後悔。
ジョゼ・マルティネズといえば、パリ・オペラ座の元エトワールで、作品も残している超エリート。オペラ座退団後に祖国スペインの国立ダンスカンパニーの芸術監督になって安泰かと思っていたら、実はイバラの道だったらしい。
ナチョ・デュアトを継いで就任したものの、なんとカンパニーにはレパートリーが1曲もなく、次年度の公演予定もなく、聞けば年間の公演数がたったの36回しかなかったという。パリのオペラ座で長年踊った経験からは想像もできず、国立の舞踊団とは思えない状態。しかもダンサーはトウシューズを7年間はいたことがないという。運営に対しても、ダンサー育成も、まさにゼロからの出発だったそうだ。ソリストを作り、給料を上げ、フランスのバレエを紹介したくて、くるみ割り人形やドンキホーテをレパートリーに入れ、フォーサイスにビデオを送って作品をレパートリーに入れる許可をもらい、スペインの若手振付家やイスラエルのシャロン・エイアルなどにも作品を依頼たという。 前任者のナチョ・デュアトが就任したときも、同じようなことをデュアトが話していて、スペインのバレエ事情の難しさを感じた。
マルティネズが2011年に芸術監督に就任した後の2014年には、フォーサイスの夕べで日本公演を行なっているが、このような裏話を知って見るのと、知らずに見るのでは、意味合いが違う。今回のモンペリエでのフォーサイスの夕べは、4年前とは違ったものになっていたと思う。
祖国スペインでの名前を加えてジョゼ・カルロス・マルティネズとなり、年間の公演数も倍になった。残念ながら、忙しすぎて作品を作ることもできないし、5年間踊っていないので、ダンサーとして舞台に立つこともないだろうというが、スペインのバレエ界に大きな改革をもたらすだろうと確信している。(プレス・コンファレンスにて)

ⒸMasumi
|

