今年のセーヌ・サンドニ県主催国際ランコントル・コレグラフィックは、5月16日から1ヶ月にわたり、17カ国から選ばれた30作品が、13の会場で上演された。開幕作品は、奇想天外な作品で有名なマルコ・ベレッティーニと、ヤン・ファーブルの滴るオリーブオイルにまみれて熱演して一躍有名になった経歴を持つリスベット・グルウェーズ。
こんなことを言っては失礼なのだが、「振り付けとの出会い」というフェスティバルなのに、ダンスの動きというより、超アバンギャルド、或いは、見終わった後にクエスチョンマークが頭の中で踊りまくるのに、数年後にはその作品が世界ツアーをするほど売れる事が度々あるこのフェスティバル。今年は何が飛び出すのだろう。
私は中盤から所見。見た順に、一言。
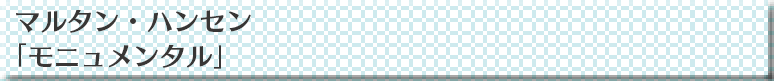
バスケットシューズを履いて、体をくねらせて踊っていた男が、不朽の名作「瀕死の白鳥」を踊る。これが素敵だった。どう頑張ったって、アンナ・パヴロワのようには踊れないのを承知で踊る。いまにも力尽きそうな白鳥というより、パヴロワへのオマージュで、彼女が残したものは、不朽なのだと、これがタイトルにつながった。そして、この名作を真似するのではなく、ハンセンの感覚で踊り直す。過去のものは時に別の解釈によって受け継がれ、元の意味をなくすこともある。人も物も、生きているものと死んだもの、現在あるものと過去のもの、それらがある接点を持ちながら変化していく、そんな時代の流れを感じた。

ⒸNick Haffner
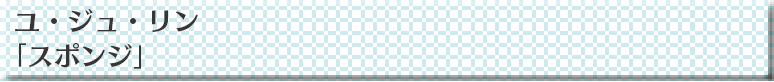
学生時代に先生から「スポンジのように多くのことを吸収しなさい」と言われたことが広がって、海水が世界を回るように、自分の体内に流れるものによって養われ、必要のないものを吐き出す。そんな自然体の体を表現したかったのだと思う。繊細なダンサーだと思うが、薄暗い舞台に浮かび上がるドレスの女性が、ノイズ音とともにゆったり動く姿は、心地よいイメージというより、何かドロドロとしたものを感じてしまった。作品が始まってすぐに始まった雷雨、劇場の屋根を叩く激しい雨音と雷が使用曲のノイズ音にかぶさったためにそう感じたのかもしれないが、この作品の間だけ雷雨に見舞われ、これが相乗効果を出していたような印象を受け、妙に不思議な気分だった。


ひゅるひゅると強い風が隙間を通り抜けるような音の後、リズミカルな音が続く。そこに響く女の声。ゆっくりと明かりが入ると、それはひとりの女性が縄跳びをしながら喋っているのだった。
縄が床を打つ音と、軽快に体が上下するシルエット、スカートのフリンジが形を変えながら揺れている。祖国がチェコスロバキアからチェコになったこと、家族のこと、自分のこと、思い出が語られる。時に鋭く、時に優しく。縄跳びという単調な動きがちっとも飽きないのは、40分間喋りながら飛び続けた体力もさることながら、縄の回し方や飛び方、体の向きを変えること、そして照明を微妙に変化させることで次元を変えたからだろう。人生は、この作品のようにリズムを変えながら常に動き続けるものなのだ。(以上3作品5月25日 ル・コロンビエ)

ⒸVojtech Brtnicky
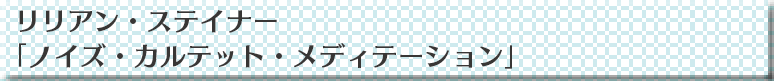
白い衣装を着た4人が円形に向き合っている。ゆっくりと手を合わせた後、ふたりの男がそこから離れてパーカションの前に移動し、女ふたりが短いフレーズを繰り返しながら双子のように踊っている。少しずつ場所を移動し、ある地点まで来ると動きを変えて動き続ける。シンバルをこするようにして出る金属の音からドラムを叩く激しい音まで、タイトル通り、ノイジーな音とトランスに入れそうな単調な動きの、4人による作品だった。

ⒸJames Wright
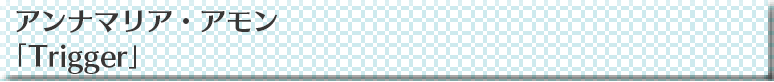
「ノイズ・カルテット・メディテーション」がステージを挟んだ形の客席だったのに対し、アンナマリア・アモン「Trigger」は客席を三角形にした。その内側と外側で、なんとも不思議な動きが展開する。一方向の客に向かって鳥が羽を広げるように腕を広げ、それから片腕を勢いよく回す。これを三方向に繰り返した後は、最前列の客のすぐ脇や、席の後ろの空いたスペースで、コンテンポラリーのようなヒップホップのような、独特の動きをする。日常の動きを取り入れているが、次の動きが予想できないのが面白い。この流れなら次は右へ行くだろうと思っていると、いきなり下に向かったり、手とは反対の方向に足が動いたり。鳥や動物の鳴き声が聞こえて来て、瞬時に様々な動物に化身しているようにも見える。独特な動きが面白いのだが、後半が冗長になってしまった。作品の意図がもう少し深められればぐっと面白くなるように思った。よく鍛えられたダンサーなので、期待を込めて。

ⒸAndrea Macchia

このような作品が「振り付け」フェスティバルで見られるのは、ディレクターのアニタ・マチューだからだ。踊りの部分は全くない。踊らない。だけれど面白い。青いバスケットシューズの上にオレンジ色のバスケットシューズを重ねて履いて、まるで西洋の花魁みたいに、客の間を歩き回る。喋り、歌い、口をひしゃげ、歯をむき出し、舌を出す。高く澄んだ歌声で歌ったかと思うと、いきなりがなりごえで怒鳴り散らすし、 同時にふたつの声がでる。口がひとつとは思えないような、ありとあらゆる音が出る。踊るシーンがある作品ではないけれど、観客相手のパフォーマンスとしては非常に興味深かった。(以上3作品5月29日ル・コロンビエ)

ⒸJule Flierl
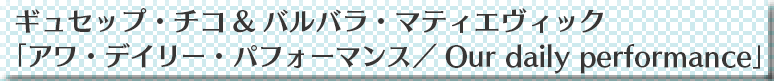
プログラムに掲載された、プロレスラーのマスクをつけて椅子に座る写真に躊躇したが、蓋を開けてみれば、日常の動きを極限まで広げた動きの連続で、こんなことはあり得ないと思いながらも、ありうるかもと妙に納得してしまうパフォーマンスで、タイトルが嘘でない。正直でよろしい。まあ、これだけのことを毎日する人はいないと思うけど。
いかにして倒れるかを真面目に解説し、カエル跳びやカニ歩き、ジムに通わなくてもできるエクササイズ、運送用の保護シートをロール状にしたもので合気道ごときの技を見せ、家庭でできる運動だったか痩せるためだったか、一時流行った大きな丸いボールに飛び乗ったりと、バカバカしくも新発見の連続だった。ふたりで組んでのエクササイズがひとつ間違えば強姦体勢になるわけで、女性には役に立つかもしれない。すると今度は、強姦を避ける方法が紹介される。本当に役立つのだろうかと思いつつも、食い入るように見てしまった。ひとりで音楽を作るのも簡単で、基本のリズムさえインプットして従えば、それに声や音を重ねて、あっという間に1曲が出来上がる。くだらないとは思いつつも、吹き出してしまうことばかり。アイディア勝ち。

ⒸMatthieu Edet


ⒸLouise Roy
「アワ・デイリー・パフォーマンス」のフィジカルでバカバカしくも目からウロコの作品を見た後に、シンディ・ファン・アッカーの背筋がピンと張るほどのインテリジェントな作品を見た驚きは、新鮮だった。彼女は、ミニマリスト、或いはゆっくりとした動きの多い作品を作るという印象があったのだが、生と死、そして人間への尊厳を感じさせる重厚な作品だった。とはいえ、気難しい作風ではない。淡々と動きで語る。
真っ暗中にぼんやりと浮かび上がる白い線。それが人の腕や足だということに気づくのに、少し時間を要した。布の波の上をゆっくりと歩く人たち。彼らが後ろに吸い込まれるように消えると、目が眩むような白い線が現れた。その線は徐々に広がり、面積を拡大していく。それは、大きな光の面で、ゆっくりと斜めに持ち上がり、白いリノリウムを照らしている。ひとりがもうひとりを気絶させるように倒し、その体を引きずり、転がし、無造作に形を変えている。赤いホリゾントは、真っ赤に染まる夕焼けか、それとも戦火?
天井が高くなり、空間が広がると、布や細い棒が整然と置かれ、その布を広げたり畳んだりしながら、淡々と人が動いている。そしてアッカーの娘の淡々としたナレーションが続く。
イタリアの作曲家ルイジ・ノーノの「死の間近な時 ポーランド日記第2番」にインスピレーションを得て作られている。この曲と詩を語る声、淡々と作業を進めるダンサーたち。状況に関係なく時が流れるように、人の歴史も流れていく。生があり、死があり、それは繰り返されていく。3部構成の最初が暗闇に浮かぶ白い骨と、黄泉の国をさまよう精霊をイメージさせた死の世界、目がくらむような白い天井に照らされた2部が生と死、むき出しの舞台に敷かれた白いリノリウムの上に、整然と置かれた布を広げてはたたむ作業が、輪廻転生をイメージさせ、奥の深い作品に仕上がっていた。(以上2作品6月1日MC93)

ⒸLouise Roy
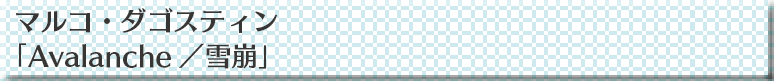
前作「Everything is ok」の印象を引きずってはいけなかったのだ。クールによく踊ることを期待していたし、崩れた大きな岩の上にだらりと引っかかったような体が写っているプログラムの写真を見て、勝手に期待を膨らましていたら、目をキョロキョロさせ、手探りで進むような、ゆっくりとした動きだったからだ。タイトルの「Avalanche」を「雪崩」と解釈していたのだが、雪崩に巻き込まれて遭難したにしては、寒さを感じさせない。後から資料を読めば、自然災害で一命をとりとめて、真っ暗な洞窟かどこかに入り込んでしまって、相手の気配はするものの、どこにいるのかはっきり見えない状況を描いていたようだ。予想と大幅に違っていたとしても、なぜか頭を切り替えられなかったのは、デュエットでいながら、ふたりの関係や状況が明確に見えてこなかったからなのではないかな。最初から最後まで同じような感じで、ふたりの関係も見えず、ストーリーの発展性が感じられなかった。(2018年6月5日モントルイユ市ベルテロ劇場)

ⒸAlice Brazzit
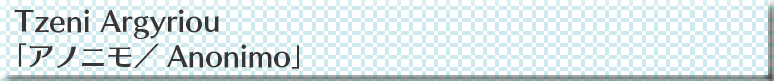
これはなかなか面白かった。ヴーという音が開場時から聞こえている。黒服の人たちが横に1列。髪の毛で顔を隠している人もいる。ひとりずつ腕と手で形を作る。黒服に白い肌だから、それがTの字に見えたり、鳥の形に見えたり。少しずつ動きが加わって、それが個人だったり団体だったりしながら、服の黒と肌の白を生かした形を見せる。手拍子足拍子でリズムを叩き出し、猿の真似やら犬の遠吠えも飛び出す。ニジンスキーの「春の祭典」のような、儀式的な動きがあったり、ノイズ音とリズムが混ざり合ったり、アイディアいっぱいの、テンポの良い展開が心地よい。泥臭くもなく、かといって機械の冷たさもなく、ちょうど良い体温を感じさせる。自然界の中で起こる出来事と、それを元に発展させた人の文化が、リズミカルに混在している感じが好きだった。(2018年6月5日モントルイユ市ベルテロ劇場)

ⒸLila-Sotiriou
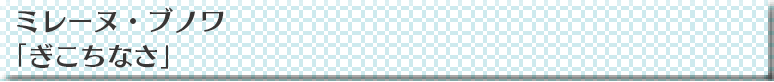
京都のヴィラ九条山に滞在して、そこで受けた新たな感覚を基にして作ったという。寺の鐘の音を聞きながら、能や歌舞伎に興味を持ち、滞在を楽しんだようだ。ただ、作品からは「ぎこちなさ」を感じることはなかった。
日本舞踊とコンテンポラリーダンスの振付家兼ダンサーの日置あつしが、ソロで踊る。踊ったのは、「三番叟」と「鶴の声」だが、なんと無音。衣装は白のワイシャツに黒のズボンと現代風。踊り終わると舞台後方の壇上に音楽家が位置して、セリア・ゴンドルが踊る。生演奏のノイズ音や、遠くに聞こえる鐘の音をバックに、いわゆるフランス版コンテンポラリーダンスをしながら時折歌う。公演後のトークで、この発声法は日本の伝統芸能から学んだもので、溜め込んだ空気をパッと吐き出すようにして出し、それを澄んだ声で伸ばしているそうだが、声楽に疎い私には、公演中にそこまで感じられない。
「ぎこちなさ」を感じずに見終わってしまったのだが、日置氏曰く、日本舞踊は、歌にぴったりと動きがはまっているものなので、今回のように無音で踊ると、どこまで溜め込んだり、流したりして良いのか、ふと迷うことがあるという。この迷いが、ぎこちなさなのかも。後半は、流れるような動きとノイズ音の組み合わせがしっくり行かないことを目的としたのかしら。見ている側には、すべてがすんなり入っているように見えてしまったのだけれど…。(6月15日モントルイユ・ヌーヴォーテアトル)

ⒸVeronique Baudoux
どこがダンスだ、さっぱりわからんなどといいう批評批判があるけれど、このフェスティバルから排出されたカンパニーが、数年後には世界で活躍する振付家になっているのは事実。アニタ・マチューは我々一般市民の何年も先を読めるディレクターなのだと確信している。さて、今回紹介された中から、どれだけのカンパニーが世界に羽ばたいていくのだろうか、楽しみだ。
|

