

日本とフランスの外交160周年を記念して行われた文化交流イベント「ジャポニズム2018」でシーズンの幕を開けたパリ・シャイヨー国立舞踊劇場。9月13日には、皇太子殿下(今上天皇)を迎えて、エッフェル塔の特別ライトアップに続き、松竹歌舞伎が上演された。
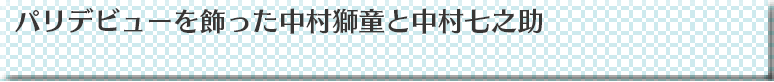
中村獅童と中村七之助演じる「色彩間刈豆かさね(いろもようちょっとかりまめかさね)」「鳴神(なるかみ)」は、テンポの良い展開ゆえに、フランス人にはわかりやすかったように思った。また、「色彩間刈豆かさね」での中村七之助の女形には、男が演じているとは思えない女らしい仕草に感嘆とも言えるため息があちこちで漏れ、これが怨霊となっておどろおどろしくなると、その変身ぶりに驚くといった感じで、楽しく観劇できたように見受けられた。
「鳴神」は、歌舞伎は美しく真面目なものと思い込んでいたフランス人を裏切り、小坊主の出で立ちに笑い、美女に惑わされる鳴神上人に人間の性を見出し、ちょっとしたアクロバットと鳴神上人の変身ぶりを大いに楽しんだようだった。
これまでにも歌舞伎は何作もフランスで上演されているが、今までとは異なる趣向の作品に、歌舞伎の奥の深さに感心しているような印象を受けた。
(9月13日シャイヨー国立舞踊劇場)

「色彩間刈豆かさね」ⒸPatrick Berger

「鳴神」ⒸPatrick Berger
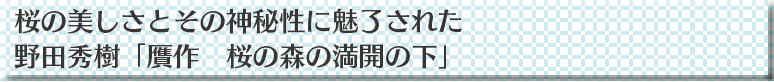

ⒸKishin Shinoyama
2014年の「The Bee」、2015年の「エッグ」に続き、3作品目の上演となった「贋作 桜の森の満開の下」。これまでの作品上演で、私の不満だった「説明不足」はだいぶ改善されたように思った。つまり、日本では当たり前のことでも、文化が違う国では理解できないことがあるわけで、作者の意図や、時代背景などの説明がプログラムに書かれていないことが、いまいちちゃんと理解してもらえない原因なのではないかと懸念していた。今回大まかなストーリーが書かれていたのでわかりやすかったが、日本人にとって「桜」が何を意味するものなのか、その神秘性などを説明して欲しかった。とはいえ、紙面には限度があるし、そのようなことは作品を見て感じれば良いことなのかもしれない。
ところで、30年前に初演された作品の再演とは興味深い。作品が使い捨てにならず、年月を経て成長していくのは、とても良いことだと思う。
野田の演出は、さすがにうまい。客席最前列の前に作られた出入り口、大人数による動きの構成のうまさ、テンポの良さ。字幕スーパーを追わなくて済んだのは幸いだった。フランス人の知人は、途中から字幕を追うのを諦めたとか。言葉が多いため、字幕を追っていたら舞台の動きを逃してしまう。字幕を追わなくても、それなりに理解できたというから、成功裏に終わったと言えるのだろう。演劇を外国で上演することの難しさは、言葉にあるが、セリフが完全に理解できなくても、何かしらの感動を与えられる作品はあり、それがゆえにシャイヨー国立舞踊劇場は、3度も野田演劇を招待しているのだ。
今回は特に装置の桜の美しさが際立ち、長いカーテンコールが終わり、ほとんどの客がはけても、美術の桜の美しさに見とれる人多数。これが日本の桜じゃい! と叫びそうになった。(10月3日シャイヨー国立舞踊劇場)

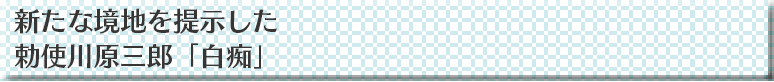
ドストエフスキーの原作を追うのではなく、主人公をひとつの象徴として描いたという勅使川原三郎版「白痴」。今までずっとシャイヨーの大劇場での上演だったのが、今回は中劇場となったことに少々の不満を抱いているようだったが、同時にアップデイトと同じく8回公演ができることを喜んでいた勅使川原。この作品は、小劇場が似合う。初演はアップデイトダンスだったというから、踊り込んでいるとはいえ、微妙に変化していくだろうと、最終日の前日に所見。
クラシックからノイズ音に近いレミックスまで、バラエティに富んだ音楽構成。ただこれが、普通ではない。心地よい曲だと思っていると、別の曲がかぶってきて、居心地が悪くなる。スポットの明かりが不安定なのも、主人公の微妙な心の移り変わりを表しているのだろう。
ストーリーを追わないと言っても、やはりそこには物語がある。出会い、希望、失恋、破壊。大きな装置もなく、たったふたりの出演者しかいないけれど、時の流れ、感情の移り変わりが明確で、白痴の物語が浮き上がっているが、同時に「白痴」に限らず、これは誰にでもありうる事で、ひとりの男の、本人にとっては普通でも、他人から異常だとレッテルを貼られてしまった男の悲しい物語とも理解できる。
勅使川原の感情の微妙な変化は見事だったし、佐東利穂子の、いつもの素早い動きとは違う質のダンスが新鮮で、さらに奥行きが深まったと思った。(10月4日シャイヨー国立舞踊劇場)

ⒸAbe Akihito


ⒸThéâtre de la Ville
ヨーロッパで好評を得ていた川口隆夫の「大野一雄について」が、ようやくパリ上演となった。大野一雄はフランスでも伝説の人だが、実際に踊る姿を見た人は少ないから、この作品がどう受け止められるのかに興味を持った。舞踏に関心を持つ人が増えた現在、大野一雄のコピーをどう受け止めるのだろうか。
公演はまず屋外から始まった。カルダン劇場の横には、シャンゼリゼ大通りに面した公園があり、川口隆夫は劇場からずるずると引きずるように歩き、植木に頭を突っ込み、青いブルーシートを引きずって転がったりよろよろしながら、オブジェが置かれた芝生へと向かった。しかし、すでにパフォーマンスは始まっていることに誰も気がつかない。川口隆夫の顔はまだよく知られていないから、路上パフォーマンスをする怪しい男とみられていたように思う。芝生の会場に待機していた観客は、なかなか出てこないダンサーに少しイライラしていたようだが、芝生に転がり込んだ途端、待ってましたとばかりの期待感が投げ込まれた。芝生の上をふらふらと、あるいはオブジェと絡み、気が向くままに動く川口。イサドラ・ダンカンを思い出した。自然の中で自由に踊る姿は、踊りの根本なのだ。日没となり、あたりが次第に暗くなると、さすがテアトル・ド・ラ・ヴィルの照明係、屋根の上に見たこともないほどの大きなスポットを用意していて、それで見事に照らし出す。川口に誘導されて、劇場内に入る。観客が席に落ち着いた頃、川口はゆっくりと客席から舞台に上がった。
体を白塗りにし、ハンガーにかけられた衣装を選んでゆっくりと着る。靴下を履き、髪を整え、帽子をかぶり、そして踊り出す。この着替えの時間が長く感じられた人は多いと思うが、これが川口が言いたかったことの大きな要素なのではないかと思う。丁寧にかけられた衣装への愛着、次に踊る作品に見合った衣装を選び、それをゆっくり纏う。その瞬間から大野一雄は作品に入り込んでいたのではないか。確かに、川口の踊りは大野一雄の名作のコピーなので、大野一雄のようで大野一雄ではないし、懐かしいような、ものまねのような、よく言えば新たな解釈によるダンスだったと思う。ただそこに、舞台の表側では見られなかった大野一雄がいた。ビデオや写真では見られない、舞台裏の大野一雄。それがこの作品の面白さのひとつなのだと思う。 (10月5日エスパス・ピエール・カルダン/テアトル・ド・ラ・ヴィル/フェスティバル・ドトンヌ・ア・パリ)

ⒸThéâtre de la Ville
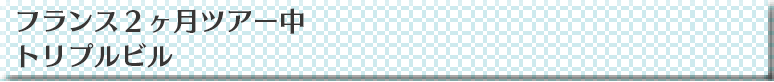
ダンスダンスダンス@横浜で上演された後に始まった、フランス2ヶ月ツアー中のトリプルビル。ダンスダンスダンス@横浜のフランス側の芸術監督ドミニク・エルヴュ氏は、このトリプルビルで、日本とフランスのヒップホップダンスの違い、そのコントラストを見せたかったという。そして私は、エルヴュ氏が望んだもの以上の違いを発見することになった。
9月2日に横浜赤レンガ倉庫で見てから約1ヶ月。この間すでにフランス各地をツアーしている。パリのシャイヨー国立舞踊劇場では、東京ゲゲゲイのメンバーが客席を走り回ったりして、派手なパフォーマンスをしていたようだ。横浜公演ではダンスというより歌のシーンが印象に残ったので、それについてリヨンでビエンナーレのディレクターのドミニク・エルヴュ氏に問うと、「ちょっと方向性が違ったわね。でも、フランス公演ではほとんど歌がなかったわよ」という。一方で、パリ公演を見た人は、「横浜と変わらなかったですよ」。ではいったいどちらなのだ? というわけで、パリ郊外のナンテール・メゾン・ド・ラ・ミュージックへ。
頭で床を這う動きが面白かったジャンヌ・ガロワの「リバース」と、テクニックと動きの面白さで見せたカデル・アトゥの「要素」を踊った男子5人組。ジャンヌ・ガロワもカデル・アトゥもこれまでに日本との交流はなく、いきなりコラボしろと言われても、深みのある作品は生まれるわけがないというのが、フランスの批評家の間の会話だったが、私には短期間のリハーサルとは思えないほどよくできていたと思う。しかも、初演から1ヶ月が経って、3日に1回舞台を踏んでいるだけのことはある。横浜で見たときのぎこちなさが消えて、随分踊り込んでいて、良くなったと思った。やはり1回の舞台は100回のレッスンにも勝るわけで、舞台で踊ることがどれだけ成長を促すかを改めて感じた。

「リバース」 ⒸMichel Cavalca

ダンスダンスダンス@横浜「リバース」ⒸKota Sugawara

「要素」 ⒸMichel Cavalca

ダンスダンスダンス@横浜「要素」ⒸKota Sugawara
一方の東京ゲゲゲイは、客席に飛び出すこともなく、あっという間に終わってしまった感じだった。奇抜な衣装と、キレのあるダンス、ビシバシ変わる照明に、観客はノリノリで、その雰囲気ゆえに短く感じたのか、実際に公演時間が短かったのかはわからないが、何か尻切れとんぼのようにあっさり終わってしまった感が残ったのは、もっと見たいと思ったからなのかもしれないが。また、エルヴュ氏が言っていたのとは違って、横浜同様に歌のシーンが多い。一般客には受けていたようだが、ダンス関係者の間では、これはダンスではなくキャバレーのショー(リドやムーラン・ルージュで上演される類の作品)だという意見が多かった。

東京ゲゲゲイ ⒸMichel Cavalca

ダンスダンスダンス@横浜 東京ゲゲゲイⒸKota Sugawara
では、このフランスツアーで何を感じ始めているのかを、5人のダンサーに聞いてみた。
フランスでの印象については、「観客が家族連れだったり、ダンスとは全く縁がないような普通の人や年配の人がほとんどなことに驚いた」ことと、リヨンのビエンナーレでいくつかの公演を見た印象として、「盛り上がりもなく、同じようなことの繰り返しのダンスに、観客が喜ぶ理由がわからない」と。これにはハッとさせられた。アカデミックな舞台芸術に長年浸っていたし、フランスのコンテンポラリーダンスばかりを見ている私には、想像もしなかった意見だったからだ。私が知る20年前の現代舞踊界の意識でいたのもいけなかった。「普通なら、最後に盛り上がってパーンと終わるでしょ」という言葉に、ショーとコンテンポラリーダンスの違いと、日本とフランスのヒップホップの質の違いを感じずにはいられなかった。もちろんフランスにもテクニックを競うヒップホップもミュージカルもあるけれど、私はいわゆる大劇場で演じられるアカデミックなヒップホップを念頭に置いていたために、ショーダンスやミュージカルなどの、ショービジネスの世界でのダンスを考えていなかった。思い込みで質問したことを反省するとともに、ダンサーたちは「盛り上がりのない作品」を2ヶ月踊り続けることが苦痛なのではないか、楽しんで踊っていないのではないかと思ったが、どんな状況でも、観客を納得させるだけのレベルを提供できるプロのダンサーなのだろうから、この質問は失礼にあたると思い、口を閉じてしまった。
客席に一般人が多いのは、多くの劇場にアボンヌマンという、前売り割引制度があることや、親や学校が舞台鑑賞を企画して、あらゆるジャンルの作品を見せる習慣をつけているので、年に何回かは劇場に行って、大人と同じ作品を見ることが習慣となっているからだ。「文化は人を豊かにする」という考え方がフランスでは一般的で、見に行くだけでなく、体験させる教育制度ゆえに、文化が身近にある。
5人のダンサーが持った疑問を、疑問で終わらせずに、もう一息踏み込んで、なぜそうなのかを問えば、フランス人の気質や文化が見えてきて、 このツアーに参加した意味が出てくるのではないかと思う。
さて、東京ゲゲゲイには事前にインタビューを申し込み、劇場側がお膳立てしてくれ、MIKEYさんも受け入れてくれたようだったのに、 事務所の社長さんに遮られ、すぐ横にいるMIKEYさんに声をかけることも許されず、断られてしまった。社長さんは、私がこれまでに書いた記事と、今回のインタビュー記事の検閲を断ったことが気に入らなかったらしい。もう帰ったとの見え透いた嘘と、私が劇場から完全に離れるまで監視する態度にも恐れ入った。これが舞踊界(私が知る限りの)と芸能界の違いなのかもしれない。一方の劇場側は、この成り行きに唖然。「事前にインタビュー内容は伝わっているし、10分だけのインタビューで芸能生活を脅かす記事が書けるわけがないのは明らかなこと。しかも記事を検閲するとは! 批評は個人的な見解であって、それを検閲することは、表現の自由を脅かすもので、フランスでは考えられないことだ」とのコメント。私は単純にフランスの印象と、素敵なクリップ撮影に関してと、作品が初演から変わったかどうかを聞きたかっただけなんですけどね。
ダンスには多様なスタイルがあり、それぞれのやり方があること、そして自分の常識は他人には通じないことを思い知らされ、それを認識しなくてはいけないのだと反省。そして、フランスと日本の考え方の違いを改めて感じた。
フランスで重要なことは「再来仏」。つまり、2回、3回と呼ばれるかどうかが重要。1回来ただけでは、あっという間に忘れ去られてしまう。今回のメンバーがフランスツアーで何かしらの収穫を得たと感じ、再びフランスで踊ってくれることを期待したい。(9月2日横浜赤レンガ倉庫・ダンスダンスダンス@横浜、10月12日ナンテール・メゾンドラ・ミュージック)
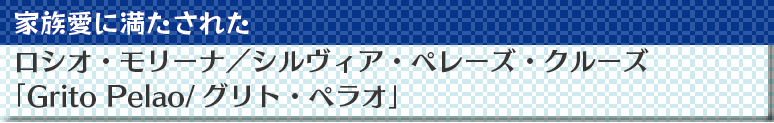

ⒸLorenzo Carnero
新たな切り口、男勝りの弾けるようなフラメンコで人気の、シャイヨー国立舞踊劇場提携アーティストのロシオ・モリーナの新作は、これまでの作品とは異なる趣向で、女性歌手シルヴィア・ペレーズ・クルーズの歌をメインに、彼女を育て上げた舞踊家の母を舞台に上げての私小説的な作品だった。エネルギッシュな踊りを期待していたファンにとっては意外な方向性だったが、大きなお腹で踊る姿は、ダンサーとしてだけでなく、これから母になるひとりの女性の姿と、ずっと彼女を支え続けた母への思いがひしひしと感じられ、ほっくりする作品に仕上がっていた。ミュージシャン達は、いつもと同様に、モリーナに対する尊敬と愛情を持って作品を盛り上げ、それに答えて踊り、走り回り、水に飛び込むモリーナとの掛け合いが良く、アットホームな雰囲気が始終漂っていた。この雰囲気は、今しか見られないだろう。数年先にこの作品が再演されるときには、また別の印象を受けるだろう。でも、それでいい。こうしてひとりのダンサーが出産を経て変わっていくことも成長のひとつ。今後、彼女がどのような作品を生み出すのか、伝統的なフラメンコのしきたりを超えた作品を作り続けていくこと、それが楽しみだ。(10月9日シャイヨー国立舞踊劇場)

ⒸLorenzo Carnero
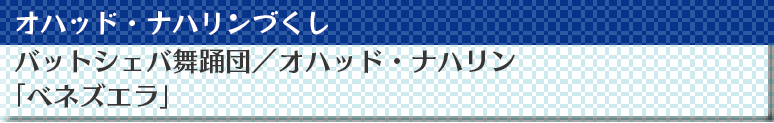

ⒸAscaf
ジャポニズムの後は、オハッド・ナハリンオンパレードとなったシャイヨー国立舞踊劇場。カンパニーが「ベネズエラ」と「Mamootot(ヘブライ語でマンモスの意)」の2作品、若手カンパニーのヤング・アンサンブルが「Décalé(隔たり)」と「Sadeh21」の2作上演、しかも、昼が若手で夜がカンパニー、その合間にガガのワークショップと「ミスターガガ」の映画上演と、ナハリンづくしの2週間となった。ナハリンは政治をダイレクトに挑発するような作品を作っているとは思えない(現状を描写する表現は確かにあるが)のに、イスラエルのアーティストというだけで標的になるため、劇場のセキュリティーは異常なほどだ。いくつかの都市では、公演中に反対勢力が妨害をしたらしい。文化に国境はないはずなのに、残念なことだと思う。「ラスト・ワーク」の上演にあたり、ナハリン自身が「国の状況から、いつ死んでもおかしくないから、もしかしたらこれが最後の作品になるかもしれない」と言っていたことと、若いダンサーが一日兵士として駆り出されている状況を聞くにつけ、困難な状況の中でもダンスを続けている人たちに敬服。平和な世界に生きている自分は幸せ者だとつくづく思う。
さて、2017年に初演された「ベネズエラ」は、てっきりベネズエラという国をイメージして作られたものと思っていたが、「単純にこの名前が気に入って」というナハリンのコメントに肩透かしを食らった感じだったが、テンポよく展開するシーンのひとつひとつに、生きることのメッセージが感じられた。ものすごくエネルギッシュなシーンと、とてもゆっくりしたシーンが交差するが、このゆったりとシーンが人間の根本的な欲求や苦痛を表しているようで、印象に強く残った。ここには様々な場所での人の姿がある。国旗を1枚1枚落としながらゆっくり進む人たち、そしてそれらを叩きつける人たち。国境なんて糞食らえとでも言わんばかりだ。
ナハリンが発信し続けるメッセージを、18人のダンサーたちはエネルギーを惜しむことなく発揮して表現する。この見事なコラボレーションに浸りきった1時間20分。(10月19日シャイヨー国立舞踊劇場)

ⒸAscaf
|

