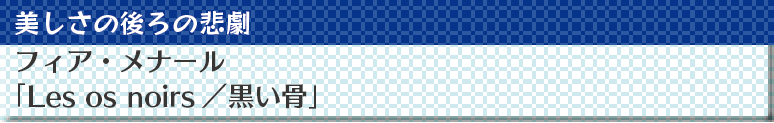

©Jean-Luc Beaujault
19歳でジャグリングを始め、エルヴェ・ディアスナスとの出会いからコンテンポラリーダンスに傾倒し、氷のボールでのジャグリング作品や、一晩かけて凍らせたコートがゆっくりと崩れ、その後は水浸しのシーンとなる作品や、スーパーのビニール袋を飛ばして夢の世界を作るなど、意表をつく作品で評判の高いフィア・メナール。新作「Les os noirs/黒い骨」は、4つの後味の悪い夢を見るような、でもそこに人の本質があるような作品だった。
さざなみに足を浸していたはずが、波は次第に高くなり、なすすべもなく波に飲まれた娘の話。広がったスカートが波間に浮かぶ一輪の花のように綺麗だっただけに、自然の前には無力な人間の小ささが虚しい。少女を襲った黒い波が、凄まじい勢いで上手にはけたら、今度は後ろから黒い波が押し寄せてきた。いきなり林立した黒いもの。海底の森か、地上なのか、四つ足の動物が動いている。やがて二本足になり、走り、逃げ、そして威嚇するように、あるいは高くそびえる木になるかのように、両手を上に突き出し、一本の線になった。そして全ては一瞬にして崩れ落ちた。慌ただしく照らされるサーチライトが消えると、床下を這う獣が、ガザゴソ、パンパンという鋭い音と共に動き回っている。その怪物が奇妙な叫び声をあげながら覆われたシートをひっくり返すと、そこには女がひとり。可愛らしい容姿とは裏腹に、キャパシティを顧みずに暴れる女は、今度はムキになってひとりでワルツを踊り始め、ニヤリと笑って白いスモークが漂う夜の街に飛び降りた。と同時に壁が倒れた。青春真っ只中の女の子は、その存在そのものが壁を壊すほどの嵐なのかも。海底火山が爆発するような映像の後は、黒い袋に覆われたロボットの無骨な動き。しかし、そのロボットが袋を破り、ひとりの女性に姿を変えると、そこは戦場だったことがわかる。煙がくすぶる中、真っ黒になった人を掘り出し、愛撫する。黒い骨とはこのことか。
世界のあちこちで起こる戦争や災害、そして歪んだ心をテーマにした、フィア・メナール独自の世界観。いつも通りビジュアル的に綺麗なだけに、人の愚かさや弱さが虚しく響いた。(4月3日Le Monfort/Théâtre de la Ville)

©Jean-Luc Beaujault

フェスティバル・コンコールダンスは、振付家と作家のコラボレーション。身体表現と、言語表現という、ふたつの異なる表現を求めるアーティストが初めましてと出会って、ひとつの作品を仕上げる。舞台もフュージョンだけれど、客席も負けない。本を読むのは好きだし、演劇も好きだけれど、ダンスはちょっと…という人と、頭でっかちの言葉で制限されるのが嫌いだという舞踊ファンを交える企画は成功を収め、今年もさらに規模を拡大して、会期は1ヶ月以上となった。去年の作品のリクエストまである。パリだけでなく、パリ郊外からボルドーまで、劇場もあれば図書館での上演もあって、面白い展開をしている。言葉の壁はあるけれど、そこは舞台作品。何かを感じればそれで良い。
今回は、パリのメゾン・ド・ラ・ポエジーでの公演を観に行った。
イヴァン・アレクサンドル(振付家)+ シルヴァン・パテュ(作家)「EN ARMES」
心象風景の描写が上手い振付家イヴァン・アレクサンドルと、作家シルヴァン・パテュの「En Armes」。人間、生きていくのに、何が武器なのだろうというのが主題。リドのレビューみたいな、ブルーの羽の衣装を着けて出てきたアレクサンドルには驚いたが、これは確かに舞台のダンサーの武器でもあるね。作家のパテュは言葉で押してくる。うん、確かにこれが作家の武器。トマトを並べて、ビジュアル的にも綺麗だけれど、私にはちょっと言葉が多すぎたかも。

©delphine micheli
パスカル・ウバン(振付家)+キャロル・マルティネズ(作家)「ENTRE NOS MAINS ENTRE NOS JAMBES」
パスカル・ウバンといえば、フィリップ・ドゥクフレとのビデオダンス「ル・プティ・バル/Le P’tit Bal」を思い出す。だだっ広い草原に置かれたテーブルに座ったふたりが、音楽に合わせてジェスチャーのようなダンスをするビデオ。1994年に作られた作品は、未だに人気がある。
舞台に現れて、ゆっくりと腕を回した。それだけなのに、空気が変わった。天井を見上げれば、そこには空が見える。小さな舞台なのに、まるでそこは屋外と感じさせる。黒いコートに触れれば、そこは部屋の中。空間を自由自在に変えられる人なのだ。その存在感に見とれていると、白い布がかかったテーブルの下から、いきなり女性が飛び出した。それが作家のキャロル・マルティネズ。無言でゆったりと動くウバンと、威勢の良い声で喋りまくるマルティネズの凸凹コンビ。これがいい味を出している。全く違うふたりだけれど、お互いの接点を見つけようと、主張と妥協をしながら進んでいく。シーツのたたみ方も置き方も違うふたりのやりとりを見ながら、ああ、自分の主張ばかりしないで、相手のいうことを聞いて、その中でお互いに妥協点を見つけていくことが、世の中を丸くおさめる方法なのではないかと、トゲトゲした心がほくっとするのを感じながら見ていた。(2018年4月4日メゾン・ド・ラ・ポエジー/フェスティバル・コンコールダンス)

©delphine micheli
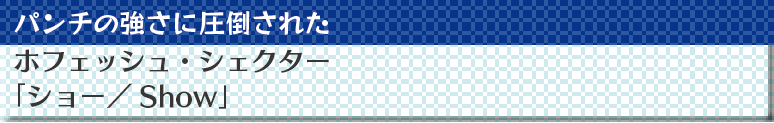

©Gabriele Zucca
ホフェッシュ独特の、儀式を思わせる太鼓のシンプルな音の繰り返しとステップ。ブラックユーモアを交えたエネルギッシュな作風は、鋭く肌に突き刺さってくる。今回上演された「ショー」は、2016年にNDT1に振り付けた「Clown」を、18から25歳までのジュニアカンパニーに再構築して振り付け、カーテンコールの短い「続き」を加えている。
煙る会場にゴーという低い音、1列に並んで手を繋いだ人たちがゆっくりと正面を向き、軽いステップを踏んでいる。真っ赤なホリゾントの幕、吊り下げられた小型電球、そうここは芝居小屋なのだ。激しく踊り、殺しあっても、これはあくまでも「ショー」なのだ。白い道化のような服を着た人たちは、やがてそれぞれの職業や階級を象徴する服に着替えた。博識者もいれば、モヒカンもいて、それなりの振る舞いをしている。にこやかな会話は、裏切りに変わり、喉を掻き切り、頭を撃ち抜き、首を絞める。無事でいることが不思議なくらい殺しあう。殺して小躍りしていた人たちは、今度は別の人に殺される。ISの横暴ぶりを思いうかべたが、人類の歴史が始まった頃から、人々は人を殺して喜んでいたのだ。命はこんなにも軽いものなのだろうか。全ては一瞬の出来事で、記憶の彼方に消えてしまうことなのだろうか。情報が溢れ、人が死ぬことにさほど驚きを感じなくなってしまった現代を皮肉っているようだった。そして、突然鳴り響いたコンチェルトとバレエのパ。全てが本物で、同時にバーチャルな世界。
延々と続く殺し合いのシーンに嫌気がさした終盤、死体を抱いて悲しむ人の姿に救われた。(4月6日アベス劇場)

©Gabriele Zucca
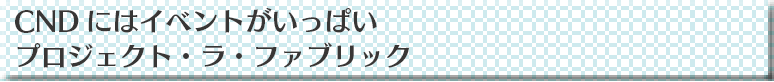
パリのCNDは国外の若手振付家の作品を上演することが多くて面白い。ラ・ファブリックというプロジェクトでは、毎年ひとつのカンパニーを招いて、公演、ワークショップ、展示などを行なっている。今年はベルリンからダンス・オン・アンサンブルを招いての3日間の日替わりメニュー。展示があり、ダンサーも振付家も日替わりの小品+本公演の3本立て。ダンス・オン・アンサンブルは、元フォーサイスカンパニーのクリストファー・ロマンを芸術監督にして構成された、40歳以上のダンサー集団で、私が観た日は、ノエ・スリエの小品と、フォーサイス、ジャン・マルテン、ラビア・ムルエによるトリプルビル。
全体的に、どの作品も形の変化や面白さを見せる作品という意味で似通っていたのが気になったが、ジャン・マルテンの「マン・メイド」が特に面白かった。円陣になって、それぞれが単純な動きを繰り返しながら、形や方向を変えていく。それだけなのだが、各自時差のあるミニマルダンスに個性を見えて、ロボットみたいだけれど、ロボットでは出来ないマン・メイドなニュアンスを打ち出しているのが、マルテンらしいなと思った。

「マン・メイド」©Dorothea Tuch
ウイリアム・フォーサイスの「カタログ」は、男女のデュエットで、ふたりが同じような動きを微妙なズレで綴っていく。ひとつの動きが少しずつ変化し、方向を変え、移動し、一連のフレーズになる。形の面白さと、その連鎖が面白い。
ラビア・ムルエは、ベルリン在住のレバノン人の演出家。鬼才と言われるアーティストが作るダンス作品は、ダンステアトル風な男女のデュエット。光の通路を往復するたびに変わる表情で状況を提示する。ただ、なぜタイトルが「エレファント」なのか深読みできず。タイトルにとらわれすぎたのがいけないのか、鬼才を理解できない自分の凡才さがいけないのか、ちょっと反省。
カンパニー存続のための資金面での苦労が多いのはドイツも同じことらしい。今後はどうなるかわからないというが、活動を続けて欲しいと思う。(4月5日CNDパリ)

「カタログ」©Dorothea Tuch
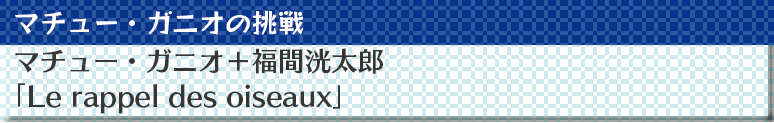
マチュー・ガニオと福間洸太郎の共演という豪華な企画。パリ日本文化会館に感謝! どんなコラボかと期待した人は多かったはず。ただ、この勝手な期待は少し裏切られたかも。というのは、踊るガニオを期待していたら、ずっと喋り続けている。しかし、流石のエトワール、その存在感はすごいし、何より、エトワールという最高位の称号にあぐらをかかず、常に自己の可能性を広げようと挑戦を続けるガニオの姿勢に感心した。勅使川原三郎が昨年オペラ座に「グラン・ミロワール」を振り付けた時、勅使川原は「ガニオはみっともないほどまでに自分をさらけ出していた」と語っていたと聞いたが、自身の可能性を広げるための努力は惜しまない人なのだ。
ロシアの作家ニコライ・ゴーゴリの「狂人日記」の主人公ポプリシチンをガニオが演じ、福間洸太郎がバッハやラモーの作品を弾く構成だ。狂人にしては美しすぎる感があったたが、不安定な感情を表し、オペラ座では見られない一面が見られたのは収穫だった。
一方、福間の透き通るような音色は、音の一つ一つが舞いながら、空気に溶け込んでいくような印象だった。バッハとラモーという、誰もが知っている曲を流すことで、見る側に自由な発想をさせる演出を狙ったという、演出家のオリンヌ・モレッティの狙い通り、演技と音楽がしっくり流れているように感じた。ただ、せっかくのこの黄金コンビなら、福間が伴奏にとどまらず、ガニオとの掛け合いがあっても良かったのではないかと思った。(4月7日パリ日本文化会館)

©Stéphane Audran
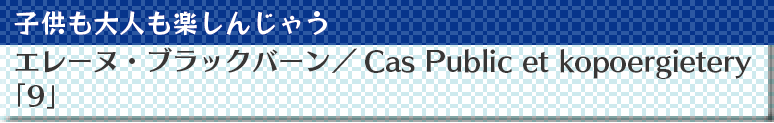

©Phile Deprez
エレーヌ・ブラックバーン率いる 「カ・ピュブリック」は、何度もオペラ座の子供向け公演に招かれている人気のカンパニー。今回も大いに楽しませてもらった。感心したのは、見に来た子供を舞台に上げ、すぐに子供の性格を見抜いて、臨機応変に対応したダンサーたちのこと。踊りながらそこまでできるとは!
開演10分前にダンサーたちが出て来て、客席に座る子供達の前や横に座ってニコニコしている。手応えがありそうな子供を舞台に上げて、椅子に座らせて、何かを指示している。舞台にはたくさんの子供サイズの白い椅子。同じ形の10センチくらいのものから、もっと小さい5センチくらいのものまで、たくさん置いてある。それらで遊び始めたのだ。椅子を積み上げたり、椅子取りゲームをしたり。勘の良い子供は、ダンサーのちょっとしたリアクションに反応して、舞台を駆けずり回っている。恥ずかしがり屋だったり、反応しない子には、多くを要求せず、自由にさせる。ほんの数分で子供の性格を見抜くダンサーたち。ちょっとした動きに反応しているうちに、それが椅子取りゲームになったり、追いかけっこになったり。打ち合わせ無しとは思えない子供達の反応には感心する。ダンサーは子供達の相手をするだけでなく、ビシバシと踊っていて、紅一点の女性は、ハイヒールからトウシューズまで難なく履きこなして、ものすごいスピードで踊りまくるし、男性もアクロバットもリフトもなんでもこなす。このカンパニーは踊るだけでなく、公演を打つことの意味、観客との無言の会話をちゃんと心得ているのだ。そこがすごいと思う。毎回思うことなのだが。
というわけで、ベートーベンの第九の「9」にインスピレーションを受けた「9」。この作品に限らず、ブラックバーンの作品は絶対にオススメです!(4月7日アンフィテアトル・バスティーユ)

©Phile Deprez


©Korea Natinail Contemporary Dance Company
CNDのフェスティバル・キャンピング
キャンプする感覚でダンスを楽しんじゃおうというCNDの企画は、今年も元気で4回目になる。パリとリヨンのCNDの、プロからアマチュアまでをも巻き込んでの大イベントは、公演はもちろんの事、ワークショップ、シンポジウム、映画にパーティまであるし、子連れで参加できるワークショップもある。
ブノワ・ラシャンブルやグザヴィエ・ル・ロワなどの異色アーティストに交じって、松音充和の名前を発見! ウイーン在住のダンサーだ。 2016年に京都国際芸術祭にも招待された作品「踊れ、入国したければ」を上演する。
フェスティバルは、6月18日から29日まで。
https://www.cnd.fr/fr/page/33-camping
ワークショップ一覧
プログラム一覧
|

