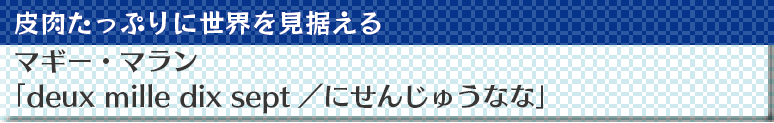
社会を批判する作品を作った振付家はたくさんいるが、ここまであからさまに世界の歪みを皮肉るダンス作品を作れるのは、マギー・マランくらいだろう。
ブランド名の入った大きな紙袋をいくつも手にして、にこやかに振る舞う人たち。頭には家を、足には車を履き、偽の鼻がぴーんと伸びている。一方で、建設現場の作業員は、ロボットのように皆同じスピードで黙々と柱を立て続ける。整然と並ぶ立方体の群れは、団地にも墓石にも見えた。そこを一瞬で覆ったのは、国旗のパッチワーク。イギリス、オランダ、イラン、ミャンマー、ブルキナファソ…そこからニョキニョキと人が現れて、大口開けて叫んでいる。しかし、彼らが手を繋ぐことはない。今度は独裁政権を敷いた国家元首の写真をつけた人が次々と現れた。ブラジルのブランコ、ハイチのパパ・ドクことデュヴァリエ、チリのピノチェト、インドネシアのスハルトなど、国名、名前に顔写真つきだから、それが誰だか一目瞭然。彼らは手渡された紙幣を躊躇することなく懐に入れ、その一方で小銭を撒く。民には情けばかりの慈悲ということか。舞台の片隅では、ひたすら神に祈りを捧げている人がいる。術を知らぬ民は神に頼るしかないのだ。金持ちと貧乏人の対比が見事に描かれているなあと感心していたら、ワイシャツ姿の男が祈る2人に文句を言っている。どうやら演技に文句をつける現場監督らしい。ということは、ここは撮影現場で、ヤラセということ? 整然と並んでいる台の上に、黙々とテーブルセッティングするウエイトレス。全て同じように、少しでも違えば店長に怒鳴られる。老人の体を洗う女も、上司に怒られ、老人を残したまま去っていった。男に執拗に追いかけられる女。パワハラ、セクハラ、家庭内暴力、そして老人問題。大きなアメリカの国旗とスイスの国旗が強風になびいている。建設現場の作業員は、無言でさらにビルを建て、積み重ねた。ちらりとその側面に見えた$の文字。ビルの谷間をライトを照らしながらさまよう人々。その明かりが消えた時、轟音とともに台が崩れた。ドミノ倒しだ。舞台は一瞬にして瓦礫の山となった。暗がりの中、人々が歩く音がする。せわしなく動いている。復興! しかし、明かりが入って私たちが目にしたものは、たくさんの名前が書かれた高い壁。国境の壁だ。この壁を越えようとして、どれだけ多くの人が命を失ったことだろう。
貧富の差は開き、人々は個性と自由を失い、力のあるものは弱いものを支配し、人々の心は荒んでいく。それが2017年の現実なのだ。
耳栓をしてちょうど良いほどの音量のノイズ音の中にわずかに聞き取れる百万、一千万という声。大地を揺るがすような大音量の音が切れた時、耳にはキーンとした音が残り、誰もいない舞台にそびえ立つ壁をただ眺めるだけだった。(12月9日MACクレテイユ/Théâtre de la Ville/Festival d’Automne)

©DEUX MILLE DIX SEPT -® David Mambouch
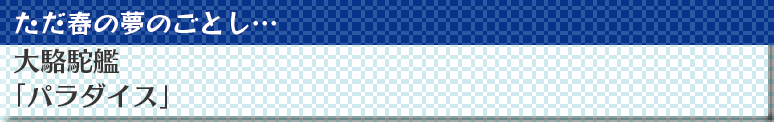

©Hiroyuki Kawashima
大駱駝艦は今秋1ヶ月に渡るフランスツアーを行った。アバンギャルドな大駱駝艦ワールドが受けているのだろう。ポワチエで「パラダイス」、パリでは「パラダイス」と、鉾久奈緒美振付の「阿修羅」(2016年舞踊批評家協会賞の新人賞受賞作品)、そしてパリ郊外のナンテールにて「クレージーキャメル」と続いた。「阿修羅」を見逃したのは残念だったが、「パラダイス」の緻密な演出構成に、さすが麿赤兒!
闇夜のカラスではなく、雪原のうさぎのように、真っ白な舞台でうごめく白い衣装に白塗りのダンサーたち。その目と髪の黒、口の赤のコントラストがひどく生々しい。首を小刻みに動かす鳥を思わせる集団の間からにょっきりと現れた大木、麿。人が繋がれているのか、木が繋がれているのか、太くて重い鎖の鈍い音が響き、身勝手な行動をする人を体を張ってつなぎとめているようにも、老木をいじめるために鎖を引っ張って遊んでいるようにも見えた。ひとり、またひとりと鎖を外して去り、やっと自由を取り戻した老木は、背中を丸め、重い鎖を引きずりながら、時々後ろを振り返り、あてもなく彷徨う。それはまるで人生の過去を振り返っているようだった。そこへ登場したふたりの蛇の化身は、体をくねらせ、赤い舌を出しながら、りんご、バナナ、ぶどうを木から取り出した。捧げ物と言わんばかりに3組の男女にうやうやしく捧げた。赤、黄、青のカツラを被った女と、3人の男は、供え物を前に楽しそうに踊っていた、1組がリンゴをかじるまでは。黒いカツラの女達は大きな箱の上で逆さになり、男は背中に黒い人をしょって絡む。けたたましい笑いと、ローラースケートで走り回る3組の男女。強烈な音楽に合わせてノリノリの若者たち。ここは天下のパラダイス! 陳腐で下世話で奇妙な宴会が続く。しかし、赤い花が撒かれた美しい世界は、いつの間にか消えた。蛇の化身が着ていた服は、首吊り死体のように宙に浮き、南国の楽園は消えて、元の白い壁になっている。「存在してなかった?」という麿のつぶやきが虚しく響く。
麿の世界は色彩が艶やかだ。純白の壁に現れた南国を思わせる木々と動物。袖と一体化していた白い箱が動き、派手なパフォーマンスに真っ赤な花びらが撒かれ、そしてまた無の世界に戻る。パーティは終わったのだ。人は生まれ、死んで行く。永遠の楽園など、夢のまた夢。平家物語の冒頭の一節が浮かび、人生の儚さを考えさせられたと同時に、「生」を受けた以上は、十分に楽しもう! という元気もくれた。(12月7日パリ日本文化会館)

©Hiroyuki Kawashima
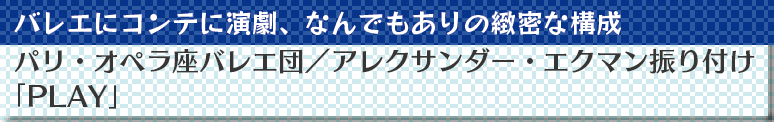

©play Ann Ray/Opéra national de Paris
オペラ座のダンサーがここまでコンテンポラリーダンスを踊りこなしたか! という驚きと、アレクサンダー・エクマンの隙のない構成と演出にを楽しんだ。振り付けを始めた12年前にいつかパリ・オペラ座に作品を振り付けるんだと語った夢は、現実のものとなり、大きな拍手で受け入れられた。
白いテニスウエアーを着た4人の演奏者が、幕前に置かれた4つの管楽器を取って軽快な演奏を始めると、緞帳には「アレクサンダー・エクマン『PLAY』」の堂々たるタイトル。出演者とスタッフの名前が映し出された後は、道路に落ちた新聞や、行き交う人の足をアップにした映像が流れ、一味違った始まりが新鮮だ。緞帳が開けば目の覚めるような真っ白な舞台。白いリノリウム、白い壁、白い衣装の36人のダンサーたちが、1人の動きを真似しながら走り回り、最前列の客と手を合わせるなど、遊び感覚的な幕開き。黒い風船を飛ばしている男と、白い台の上で踊る男。そんな中で落ち着きなく身だしなみを整えているインテリ女。この一団が去ると、マリオン・バルボーが高い台の上に立ち、上手に向かって挑戦的とも言えるシャープな足さばきで進んで行く。トウシューズの音は、上手で迎えるシモン・ル・ボーニュがマイクで音を出し、アンドレア・サリが、もうひとつの台をパズルのように動かしてバルボーがボーニュに向かう道を作っている。ふたつの台が音を立てて接合した瞬間に始まった、ヴァンサン・シャイエとシルヴィア・サン・マルタンのパ・ド・ドゥ。そして、フランソワ・アリュとアンドレア・サリの声を発しながらの掛け合いダンス。この間をオーレリアン・ウエットが大きく膨らんだスカートを履いてさまよい、宇宙服の人が旗を振り、長い白髪で顔を覆った人が歩き、カーリーヘアーの人が舞台横のボックス席に転がり込む。舞台のあちこちで、様々なことが同時進行している。ソロ、デュエット、小グループにユニゾン。ダンサーたちは舞台奥のたくさんの白い扉を出入りし、奥の高いところでは、ミュージシャンが演奏をしている。ヘルメットに鹿の角のようなものを生やした女たちのシュールな行進、トランポリンやボール遊び、天井に吊り下げられていた白いキューブが降りてきたりと、次々と予想もしないことが起こっている。コンテンポラリーにバレエに演劇を交えて、タイトル通りの「遊び」が続く。脈略がないように見えるけれど、緻密に計算されているというパラドックス。ここにグリーンのボールの雨が降り、ボールを蹴飛ばしながら踊るダンサーたち。1人残ったグレーのスーツのインテリ女(カロリーヌ・オスモン)はため息をつきながらゴミ袋にボールを入れて片付けている。あと先考えずに遊ぶ子供達の面倒をみる教師は大変なのだ。

Vincent Chaillet、Silvia Saint-Martin
©play Ann Ray/Opéra national de Paris
ここで幕が降りて休憩となり、2幕の用意で、緞帳の隙間から大量の緑のボールがオケピットになだれ込んできた。
緑のボールの海となったオケピットに、グレーの長いコートと黒縁メガネの男たちが無表情で立っている。一部の子供時代から、大人の時代へ移ったのだ。ゆっくりと腕をひねり、勢いよく体を回して半回転する度に、ボールが擦れてざっという音が響く。ボールの海に倒れ、埋もれ、挙げ句の果てはボールを蹴散らして激しく動く男たち。グレー系の衣装となった群衆が踊る中、台の上では男が白鳥の湖の王子をひとりで踊っている。やがて探し求めていた黒鳥と出会い、パ・ド・ドゥに。その対比として、ステファン・ブリヨンとミュリエル・ズスペルギーの男女の微妙な関係を描いたデュエットが大人の味を出している。その一方で、整然と並べられていた白い台で、規則的な動きをし続ける人たち。グローバル化され、規格一辺倒の流れに疑問を持たない人々と、その間で自分の居場所を見つけようとする人々。不可能なことはないと思わせる現代社会同様、ダンスもコンテとバレエがアトランダムに入り混じって当然なのかもしれない。台が一斉に釣り上げられた。床の上では大きかった台は、天井で小さく揺れている。人の感覚などあてにならない。何が本当で、何が錯覚なのか。ここにあるもの全てが、偽りの世界なのかもしれない。服を脱ぎ捨て、最後にメガネを落とした男は、サバサバした様子で舞台を後にした。
「パーティは終わったよ」そんなフレーズが頭をかすめたが、それはカーテンコールでぶっ飛んだ。歌手のCalesta<Callie> Dayが中央に立ち、その歌に合わせて、白い大きな風船が場内を飛び、ダンサーが黄色いボールを投げ入れての大フィーバー。年末にふさわしい、終わり良ければ全て良し的な明るい印象で終わったが、振り返ればいくつかのシーンはどこかで見たような感じを受けた。ただ、階級にとらわれずにダンサーの個性を活かしていたことが新鮮さをもたらしていたと思う。エトワールは、ステファン・ブリヨンのみの若手中心の配役で、プルミエダンサーのミュリエル・ズスペルギーのシャープな踊りが際立っていたし、ブリヨンとのデュエットも大人の味をきっちり見せた。ヴァンサン・シャイエとフランソワ・アリュが個性をさらに引き延ばしていたように思ったし、まだカドリーユのシモン・ル・ボーニュが全編を通してメインで踊り、マリオン・バルボーとシルヴィア・サン=マルタンが非常に良い踊りをしていたのが印象的だった。これは、外部の振付家の視点ならではだろう。また、変化に富んだミカエル・カールソンの音楽もよく、一味違った年末作品を楽しんだことは確か。(12月12日オペラ・ガルニエ宮)

©play Ann Ray/Opéra national de Paris
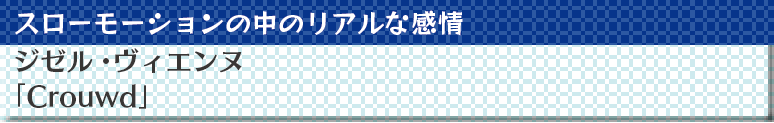
人形を使わない、しかも若者ばかり15人が出演という、今までとは異なる傾向の作品に興味を持って、デファンスの先ナンテールにあるアマンディーヌ劇場へ。広大な公園の中に位置する気持ちの良い劇場だ。平日は無料送迎バスがあり、夜の公演後はパリ中心地まで送ってくれるそうなので、ぜひ利用したい。
土が敷かれ、プラスチックのコップやボトルが散らかる舞台に、ゆっくりと現れた女の子。高校生くらいか、黄色いパーカーのフードをかぶり、ジュースを飲みながら歩いている。後から数人のグループや、誰とも交わらずにタバコをふかす黒服の男などが現れ、喋ったり、ふざけあったり、どこにでもありそうな日常が描かれる。これが全てスローモーション。空気もスローモーションで、白いスモークが空中に滞っている。このスローモーションが時々ストップモーションになったり、ひとりだけが早く動いたりして、大勢の中の個を浮き立たせる。
私が今までに見た作品は、 死や暴力をテーマに、時には猟奇的殺人などかなりグロテスクで直接的な表現が見られたが、この作品では誰も死なない。けれど、日常の小さな暴力が見える。それは身体的なこともあるし、精神的なこともある。学校のクラスメイトという小さな集団の日常の中で起こる些細な出来事。仲間に入りたくない人、入れない人、ふざけた行為がいつの間にか別の意味を持ち、相手を傷つける。それが大事には至らないし、ほんの短い間の出来事だけれど、大人社会で起これば、事件にもなりうることかもしれない。一言も声を発しないけれど、たくさんの会話が聞こえてくるようだった。スローモーションだからこそ、微妙な感情の移り変わりが見えるのだろう。普通の速度なら一瞬で過ぎ去ってしまうことが拡大される。若者たちが出てきて、お祭り騒ぎをして去って行く。それだけなのに、重い。馬鹿騒ぎをして笑っているけれど、その裏に潜む心の動きが見える。
それにしても、全く見事なスローモーションだった。歩き、肩を組み、笑い、水を掛け合って騒ぐ。口や目の動き、手の動き表情がゆっくりと変わって行く。スローモーションは、一瞬視線が飛んだだけで、動きの流れが途切れてしまう難しいムーブメントだが、まだ若いダンサーたちがここまで完璧に、感情を途切れさせることなく、1時間半を演じきったことは、特筆すべきだろう。そしてそれを指導し、作品に仕上げたジゼル・ヴィエンヌの演出力。さすがだ。(12月10日Nanterre Amandiers/Festival d’Automne)

©Estelle Hanania
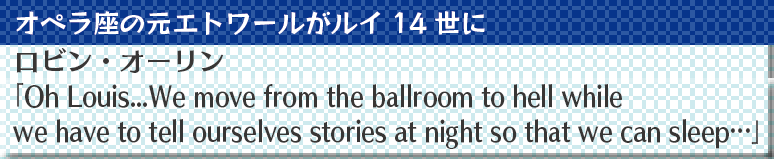

©Robyn Orlin
オペラ座のエトワールを踊らせないなんて、オーリンはなんて失礼なことをしたんだ! と怒っていた人もいたけれど、いやいや、さすがバンジャマン・ペッシュ、踊る以外にもこんなにアドリブができて表現が豊かな人だったのかと感心した。生身の人間が演じる舞台の面白さを、十分に楽しませてもらった。
会場に入るなり、何やら騒がしい。珍しく座席指定だったので、右往左往する人の交通整理をする係員の声かと思ったら、バンジャマン・ペッシュがひとりでペラペラ喋っているのだった。「どの席? ああ、それならここ。」「あ~ナタリー、見に来てくれてありがとう。招待なのになんでそんな後ろの席なの? もっと前にくれば?」「チョコレートいる? カカオ85%。僕、チョコだーい好き!」取り出した手鏡のようなものは、オーリンお得意の小型カメラ。舞台に吊られた月のような大きな円形のオブジェは、鏡になって最前列の席に座るバンジャマンの姿を映し出したり、小型カメラの映像を映し出したり、ひとつで3役の大事な美術。隣の女性に舞台上のルイ王朝風の靴で1番から5番の足のポジションを作らせて、ルイ14世がバレエの基礎を築いたことを説明する傍で、チェンバロ奏者は奴隷法を読み上げる。「脱走した奴隷は、鼻と耳を切り落とし、肩に百合の刻印をする。もう一度脱走すればもう一方の肩に刻印し、3度目は死罪とする」。 そう、ルイ14世はバレエを発展させ、芸術を愛する王として有名だけれど、奴隷法を制定した人でもある。このパラドックスを南アフリカ出身のオーリンは描いたのだ。
バンジャマン・ペッシュはルイ14世の生まれ変わりで、300年後にアフリカから戻って来た。でも、パスポートをなくしたという想定。舞台一面に金色のシートが敷かれ、客席最前列ど真ん中に座ったペッシュも、その黄金に包まれ、両腕に女をはびこらせている。ちなみに、両隣の女性は一般の観客で、運が良いのか悪いのか、最後までペッシュの演技に巻き込まれていた。実は、この2人を選ぶために、開場時にあっちに座れこっちに座れとわめいていたのだった。ルイ王朝風金色の靴を履いてダンスを踊り、オレンジをチューチュー吸って食べてゲップして、高貴なんだか下品なんだかわからない王の生まれ変わりは、皮肉を込めて歴史を語る。愛人ではなく、王妃を求め、客席から見つけ出したのは50代の男性。あら、ゲイだったの? 金色のチュチュをまとい、サンサーンスの「瀕死の白鳥」に合わせて踊り、金色の波にもまれ、沈んでいった。
踊らないペッシュだけれど、さすがプロの舞台人で、アドリブを交えての演技に1時間笑いっぱなしだった。また、チェンバロ奏者のロリス・バルコンも、ペッシュに負けない演技力で盛り上げる。それにしても、人間が人間を同等に扱わない奴隷制度への批判を、面白おかしく、でも辛辣に描くオーリンの演出はさすがだ。ちなみにルイ王朝が定めた奴隷法は、奴隷の最低限の生活を保護するものでもあったらしいけれど…。(Théâtre de la cité international/Théâtre de la Ville)

©studio habeas corpus
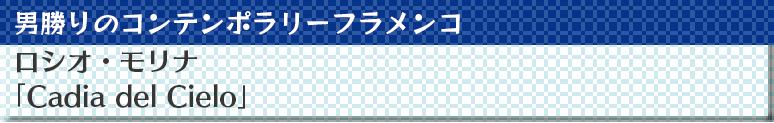

©djfrat
コンテンポラリーフラメンコとわかっていても、まさかロックコンサート風に始まるとは思ってもいなかった。しかも1曲終わると、演奏者はさっさと引っ込んでしまう。この騒音とは対極的に、白いドレスのモリナは無音の中で静かに佇み、やがてゆっくりと崩れた。フラメンコでは見たことのないフロアーの動きが続く。ホリゾントには大きな月が映し出されている。肩ひもをずらし、ストンと落ちたドレス。ミュージシャンがそっと服を着せた。男の歌声が響き、それはアカペラで、鉄琴のようなポロンポロンという音がBGM。生演奏だけれど、伝統的フラメンコの音楽とは全く違う。パソコンで音をミックスし、エレキギターと正方形の箱のような太鼓で押しまくる。マタドール風の衣装を着たモリナの、男並みの早くて力強いサパテアードに眼を見張る。膝をついて、多様なフロアーの動きに、フラメンコもここまできたかと感心していたら、セクシーなパンティを重ねて、おふざけが始まった。ギタリストはポテチを食べ、空になったパンティの前に貼りつけて踊り出した。その品の無さをテクニックでカバーし、4人のミュージシャンとの掛け合いで盛り上げる。これがめちゃめちゃ面白い。ミュージシャンはモリナのことが大好きで、モリナはそれに応えるべくどうだとばかりに踊る。この関係が素敵なのだ。靴を投げ捨て、男どもが用意した衣装や小道具を手に取り、差し出された花を身に飾り、ぶどうを食べ、その姿は怖いもの無しの女王様。客席を駆け上がって通路で踊り、1時間半踊りっぱなしのパワーには恐れ入った。次代を担うアーティストとして注目を集めている理由がよくわかる。(12月5日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

©djfrat
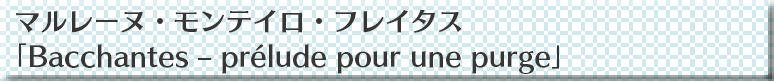
辞書によると、「Bacchantes」とは、バッカスの巫女、酔いしれた女、淫乱な女、複数形で口髭とある。Bacchanaleとなるとバッカス祭り、あるいは乱痴気騒ぎ。副題にあるune purgeとは、下痢、排水、粛清、追放。まさにこれらの言葉が全部舞台の上にあった。
会場の入り口からプープーとトランペットの響き。音楽というよりは、ただ吹いているだけで、騒々しい。短パン姿のトランペッター5人はその後、簡単な動きをしながら会場に入ってきた。少々遅れて来た観客は、このゆったり行進とともに入場するわけで、規則的な動きをする軍団の中で、キョロキョロしながら空席を見つける姿は滑稽とも言える。一方の舞台も騒がしく、目と口に白いものを貼り付けた女がキーキー言いながら譜面台を突き立てているし、好き勝手に踊る人もいれば、うろうろする人など様々。お尻を顔に見立てた歌手のコンサートが始まり、サイレンは鳴るわ、トランペットはぷーぷー鳴るわでやかましい。シャワーヘッドとチューブはただの小道具かと思ったら、これもトランペット並みに音が出る。コンテにヒップホップに人形振りに芝居に、コーラスに自転車競走と、なんでもあり。ふと気づけば昔ながらのタイプライターが並んだ事務所になっている。掃除夫もいる。その小道具が譜面台。口を大きく塗り、ヒゲを描き、金色のスカーフで頭を覆った女性たち、青のビニール袋を装飾品にして着飾る人たち。5人のトランペッターも役者で、突拍子もない演技で迫る。ダンサー対トランペッターの掛け合いは爆笑だった。2時間にわたる饗宴は、混乱極めた馬鹿騒ぎで、笑いっぱなしだったけれど、さらりと描かれた日常の風刺があちこちに隠れていて、これが後からじわーっとくる。人気上昇中の振付家だけのことはある。(12月15日ポンピドゥーセンター)

©Filipe Ferreira
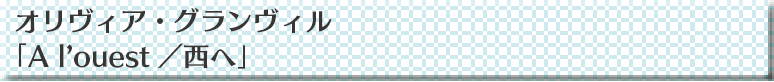
旅する心は、渡り鳥。振付家のオリヴィア・グランヴィルが、ケベックからニューメキシコまでの旅をしてできた作品で、水量の多い川、滝、何もない草原、川の横を走る列車からの映像がバックに流れている。鳥のさえずり、虫の音が聞こえる中、単調なリズムを刻むパーカッション。軍隊の隊長か誰かの過去と、笑いと、自分の歴史。壮大な景色は、短い人生のつながりで形成される歴史と重なったのだろう。ブーツを履いて、雪を踏むように歩く女達は、袋に入った雪をイメージした綿をばら撒いた。黒い上着にフードをかぶり、首を垂れて、スラリとした肌色の足でステップを踏むのは、カラスのようだった。単純な音と単純な動きをぶち破るように、突然ひとりがブギウギのようなステップをスピーディに踊り始めた。その解放的なこと! プラネタリウムかかまくらを連想する半円形の骨組みに、薄いシートを被せて家に見立てる。
ケベックからニューメキシコ、その長距離の旅を直接感じることはなかったが、ミニマル系の単純な動きとリズムが心地よかった。(12月8日 Ménagerie de verre/フェスティバルInaccoutumés)
下記リンク先で動画をご覧いただけます。
https://vimeo.com/242724220

©Marc Domage
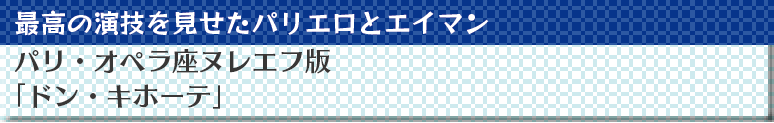

リュドミラ・パリエロ、 マチアス・エイマン
©Svetlana Loboff/Opéra national de Paris
オペラバスティーユ劇場での年末年始演目は「ドン・キホーテ」。明るく楽しい作品は、1年の鬱憤を晴らすにはちょうどいい。配役は、キトリがリュドミラ・パリエロ、レオノール・ボーラック、ミリアム・ウルド=ブラームがメインキャストで、これにドロテ・ジルベール、ABTのイザベラ・ボイルストンがゲストアーティストとして年末に2回踊り、年明けにはアマンディーヌ・アルビッソン、アリス・ルナヴァンで締める。バジリオは、マチアス・エイマン、ジェルマン・ルーヴェ、カール・パケット、マチュー・ガニオ、ジョシュア・オファルトとエトワールがずらりと並ぶ中、スジェのポール・マルクが2回、コリフェのパブロ・レガサが1回という大抜擢が注目を集めた。将来を期待する2人が抜擢されたことを嬉しく思うが、今回は堅実なところで、パリエロとエイマンコンビを所見。
この日は何と言ってもパリエロとエイマンの最高の出来を褒めるしかない。全くの期待通り、いやそれ以上の出来栄えで、踊って良し、演技して良しのふたりはさすがエトワールと言わざるを得ない。パリエロは、まさしくキトリそのもので、パリエロが舞台に飛び出した途端にパッと花が開いたように舞台が明るくなり、お茶目で明るいキトリを見ていると、こちらの顔までほころんでくる。かつてのオーレリー・デュポンを彷彿とさせる安定したバランスは見事で、結婚の場面では、サポートなしのアチチュードをかなりの時間保っていたし、グランフェッテは扇子を開いたり閉じたりしながらダブルを入れて余裕を見せる。一方、バジル役のエイマンは、髭を生やして精悍になり、以前と変わらぬ柔軟な踊り、高い跳躍と正確な着地、綺麗に伸びたつま先の細かいバッチュにため息が出る。美しい~! このゴールデンカップルを固めた周りのダンサーたちも悪くない。
エスパーダのオードリック・べザールは、自分の美貌を見せつけて派手に踊り、キトリのふたりの友達オニール八奈とセウン・パクをナンパしている。オニールはなかなかの役者で、演技が細かくお茶目で愛らしい。パクは演技が地味に見えたものの、踊りの余韻が残る動きが広がりを持たせている。街の踊り子ヴァレンティーヌ・コラザントは、彼女独特のどっしりさが適役で、色気を振りまきながらの踊りは見応えがあった。(後日キトリを踊ってエトワールに任命された)

Hannah O’Niell、Sae Eun Park
©Svetlana Loboff/Opéra national de Paris
第2幕では、ジタンのポール・マルクが若さ溢れる踊りを見せ、ドン・キホーテの夢に出てくるドゥルシネア姫にアマンディーヌ・アルビッソン、キューピットにドロテ・ジルベールとエトワールが貫禄を見せた。パリエロとエイマンは、最後まで安定した踊りを見せ、余裕の演技で一夜を盛り上げた。(12月14日オペラバスティーユ)

年明け早々の1月5日、ドン・キホーテのキトリ役を踊って、エトワールに任命されたヴァランティーヌ・コラザント。怪我で降板したアマンディーヌ・アルビッソンに代わって、急遽3日前にキトリ役を踊ることが決まり、その日たった1回の公演でエトワールに任命されたことに、誰もが驚いた。プルミエール・ダンスーズに昇進した時も予想外と言われたが、今回もまた予期せぬ任命と感じた人は多かったはず。
ただ、私が所見した12月14日のコラザント(街の踊り子役)は、はっとするほど光り輝き、オーラが出ていたので、この任命には納得するものがあった。ただし、エトワールとなれば、多様な役を踊りこなす技量が求められるので、さらなるスキルを期待したい。

©Svetlana Loboff/Opéra national de Paris
|

