Nomination Étoile : François ALU
Olivier Dubois ''Pour sortir au jour''
Alexandre Fandard ''Comme une symbole''
Thomas Lebrun ''Mille et une danse''
Opéra national de Paris ''La bayadère''
Christian Rizzo '' Miramar''
Concordan(s)e
Carlotta Sagna & Olivia Rosenthal '' On a jeté le bébé avec l'eau du bain''
Edmond Russo et Shlomi Tuizer & Bertrand Schefer '' Insomnie''
Joanne Leighton & Camille Laurens ''L&L''
En corps film avec Marion Barbeau


©Julien Benhamou/Opera national de Paris
フランソワ・アリュが「ラ・バヤデール」のソロルを踊ってエトワールに任命された。
何年か前に「ラ・バヤデール」の黄金のアイドル役で、舞台から飛び出すのではないかと思われるほどの高くて伸びのある跳躍に息を呑んだのが強く印象に残っている。この後、ヌレエフ版の「白鳥の湖」の家庭教師役(ロッドバルトでもある)では、王子を罠に嵌めようとする細やかな演技に、テクニックだけでなく内面も着実に域を深めていると思っていたのだが、その後オペラ座の舞台で見る機会が減り、近年では個人活動で大きな反響を呼んでいるとの記事が目立っていた。そして今回久々にオペラ座の舞台で踊り、エトワールに任命された。出演が予定されていた4日のうち、最終日の「初めてのオペラ座」という親と子供が格安料金で入場できる特別な日に任命日したのは、オペラ座の粋な計らいで、初めて訪れたガルニエ宮の美しさだけでなく、エトワール任命の儀式に立ち会えたことに興奮した子供たちの姿が目に浮かぶ。
1993年生まれの28歳、バレエ教師の母のクラスで踊り始め、9歳の時にパトリック・デュポンが踊るドンキホーテをテレビで見た時、「全く動かずに食い入るように画面を見ていたのを見て、バレエを続けると確信しました」とは母親のコメント。彼女は現在でもバレエ教室で教え、ヒップホップダンサーとして活躍する弟や従兄弟もいるダンス一家。
アリュは10歳でオペラ座バレエ学校に入り、17歳でバレエ団に入団。毎年昇進して2013年にはすでにプルミエダンサーになっているのだが、その後の最終昇進には長い年月を要したことになる。しかし、その間に着実に域を広げるべく活動していたのだ。オペラ座バレエ団のダンサーで結成されたトロワジエーム・エタージュなどで舞台に立ち、コンテンポラリーダンスやヒップホップも習得し、現在は声楽も訓練して、映画出演にも興味があるという。2021にはテレビの「ダンス・アヴェック・レ・スター」での審査員を務めていて、それは彼に影響を与えたデュポンと重なる。
近年オペラ座で踊ることが少なかったにも拘らずエトワールに任命されたことは、個人活動も含めてダンサーとしての資質を評価したことになるのではないだろうか。これからはエトワールとしてパリ・オペラ座の舞台で見る機会が増えることを期待したい。
次の公演は6月25~26日、パリのトリアノン劇場にて。
詳細はこちら。
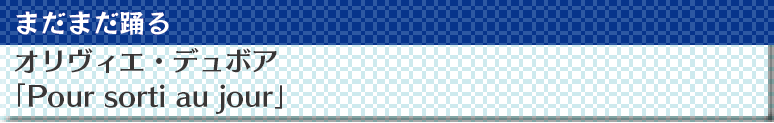
ホールに入るなり、賑やかな声が響いている。デュボアが客と話しているのだ。「何でそんなに後ろに座るの? 最前列がこんなに空いてるのに。ここは素晴らしい席だよ」「あ~久しぶり、元気?」知り合いとビズ。「シャンパン欲しい人~。え、そんなにいるの? グラスが足りないから、みんなで回し飲みしてね」見知らぬ人と回し飲みしたら、コロナとかうつるんじゃないのか? と野暮なことは考えない。そんなことをしていたらこの作品は楽しめない。「タバコもあるよ」え? 屋根のあるところでの喫煙って禁止じゃないの? そんなことも言ってはいけない。スタッフが慌てて灰皿を届けてくれる。なんでもあり、とにかく楽しめ! なのだ。酒を飲み、タバコをふかしてリラックス風のデュボア、「そろそろ始めるか」。
パソコンを開いて、ダンスのレクチャーをサクッとしてから、ゲームが始まった。3人を椅子に座らせ、ひとりに封筒を引かせる。60枚の封筒の中身は、彼が今までに踊った作品の名前が書いてあるのだ。もうひとりにはその曲が書かれた封筒を選ばせる。そしてくじで引かれた作品をデュボアが踊るのだ。作品も曲もくじ引きだからしっくりこないこともあって、そのうち「作品の曲にする、それともくじでひいた曲?」などと選択の余地を広くする。その作品にまつわる話をしてから踊るのだが、ソロ作品ばかりではないから、踊りながら別のダンサーが何をするのか解説するのでなんとも慌ただしい(笑)。3人目の人には踊り終わった後にどの服を脱がせるかを決めてもらう。このパターンがいくつも繰り広げられ、カイロで買ったお気に入りの黒のスーツは、まず背広、次にズボンと脱がされてなくなり、そしてワイシャツ、靴、靴下、ベルトがなくなって、とうとうパンツ1枚となった。途中では客からの質問を受けたり、客と踊るのだが、さすがフランス人。一般人も役者なのだ。パンツ1枚のデュボアと踊る羽目になった男の客が選んだ曲はなんと愛のデュエット。抱き合ってセクシーに踊る作品で、キスを迫るデュボアを、顔の位置を変えてさりげなく避け、デュボアが彼のお尻をさすれば、負けじとさすり返すリアクションに会場は爆笑の渦。フランス人ってユーモアたっぷり!
別のシーンでは、引き当てた作品を客に演じさせたり、デュボアが踊る作品を、客全員の多数決で決めたりと、エンターテイメントに溢れた構成だ。最後は「今までに踊ったことのない踊り」でディスコ風に、観客も舞台に上がっての大フィーバー。まさに1日の終わりにはもってこいの作品だ。フォーサイス、ヤン・ファーブル、プレルジョカージュなどとの仕事裏話も交えて、濃厚なソワレとなった。
息切れしたりして、昔のようにはいかないけれど、10年以上前の作品をちゃんと覚えているところがすごい。決して美形なダンサーではないけれど(失礼)、味のあるダンサーだから、多くの振付家からオファーがあったのだ。ボリショイバレエ団から頼まれて踊ったというライモンダのバリエーションは必見。(2022年4月6日サンキャトル104)

©Pierre Gondard
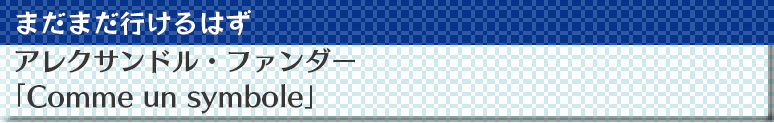
開場時から時折聞こえる叫び声やバコバコと板を叩く激しい音。これに期待していたのだが、多くのことを詰め込みすぎて、テーマが散漫になっていたのではないかと思う。
心地よい女の歌声が突然途切れて太鼓の音になり、デモ隊の最前列にいるかのように怒り、ものを投げるような動きがダンスになり、スピーディに形を変える。フラメンコの曲で踊り、フラッシュがたかれ、最後は自らが歌う。
パリ郊外の若者が語る日常がそこにあった。罵声が飛び交い、暴動や喧嘩が日常茶飯事。でも、それだけじゃない、多くの人種が入り混じれば、そこにそれぞれの文化がある。最後に服を脱ぎ歌を歌う。それは、人種という皮を剥げば皆同じ人間、そしてその心の奥には愛や平和を願う気持ちがある。そんなことを言いたかったのではないだろうか。
まだまだ作品は煮詰められるはず。振り付けを始めて3作目という。次のプロジェクトは5人ダンサーに振り付ける作品だそうで、今後を期待したい。(2022年4月6日サンキャトル104)

©Raphaël Labouré
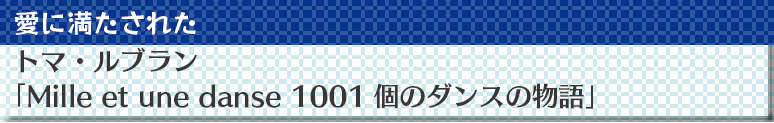
千一夜物語ならぬ、千一個のダンスの物語。そこにはたくさんの「愛」があった。
最も強く影響を受けた振付家や教師の作品を思いながらのフレーズをダンサーに創らせ、それをベースに再構築。そこには著名な作家もいれば、子供の頃に習ったダンス教師の作品もある。ニジンスキーやイサドラ・ダンカンをイメージした人もいるのだろう。多くのダンスシーンを思い起こさせてくれる。15人のダンサーの思いをまとめたルブランの構成力は繊細かつ緻密で、短いシーンが次々に流れ、音楽も突然変わるのだが、それが全く気にならない。まるで雨粒が水面に落ちて波紋が広がり、それが別の波紋とぶつかって新たな波紋を作る、あるいは川の流れが岩や倒木にぶつかって流れの方向が変わるような、そんな構成で綴られるのだ。ひとつのソロの横で大きな流れを作るグループが舞台を横切り、その流れがふうっと消えてまるで石が投じられたかのように一変する。次々と変わる構成は、多くの振付家の作品を思い起こさせながら残像として脳裏に記憶される。目の前で起こっていることと記憶がさらなる連想を呼び起こすのだ。そしてたくさんの音楽が流れては消えていく。時折ホリゾントに映し出される雲や色は控えめなのに奥行きを感じさせ、むき出しの何もない舞台なのに、空間は満たされていた。

©Frédéric Iovino
作品の途中で宮沢賢治の「アメニモマケズ」がカットされずに流れたことに感謝したい。これは出演していた梶原暁子が恩師高澤加代子氏が振り付けた作品をベースにした踊りで、ジャンルを問わずに流れていく音楽の中に現れたナレーションがアクセントとなり、また、日本人の私には忘れていた大切なことを思い出させてくれた瞬間だった。プログラムには出演者の他に、出演者が影響を受けた人の名前も印刷されていて、出演者の環境にも尊敬の念を表すルブランの優しさを垣間見た気がした。冒頭のカロリン・カールソン自身がこの作品のために吹き込んだナレーションは、彼女の人生と踊りへの愛に満ちていて、心が洗われるようだった。
この作品には日替わりで5人のゲストダンサーが登場する。ダンサー、カップル、劇場関係者など、現地在住の人が出演するので、このゲストによっても作品の風味が毎回変わるという。2回見たうち、クレルモン=フェランの方が好きだったかな。ゲストのせいだけではなく、何度見ても楽しめるのは、ここにたくさんのダンスと、それを思う心があるから。とても温かいものに包まれた一夜だった。(4月7日パリ・シャイヨー国立舞踊劇場、4月14日クレルモン=フェラン・ラ・コメディ劇場)

©Frédéric Iovino
余談だが、パリ公演の後のトークで、ルブランが「子供の頃は太っていると言う理由でうまくいかなかった」と言っていたが、先のオリヴィエ・デュボアもどちらかと言うと太め。でも、ふたりとも多くの振付家の下でダンサーとして活躍し、現在は振付家として確固たる地位を築いている。個性を磨いて突き進めば道は開けるのだと自信を持ちたい。
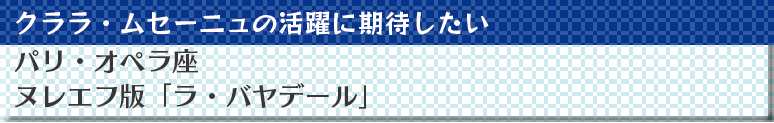
エトワールの主役を差し置いて、コリフェのクララ・ムセーニュの名前を先に出すのも何だが、無意識に目がいく先がいつも彼女なのだ。所見した日は、1幕第2場でジャンペの踊り、2幕ではインディアンダンス、3幕では聖霊を踊っていた。特に役がついているわけではないのだが、大勢の中にいても目に止まるのがいつも彼女だった。華やかな雰囲気を持ち、キレが良く正確なパ、そしてポールドブラが美しい。オペラ座のホームページの配役表では別の日に、壺の踊り、4人のソリスト、3幕のソリスト2のバリエーションを踊ることになっており、今後の活躍に注目したい。
さて、今年のニキヤ、ソロル、ガムザッティの配役は、初日がローラ・エケ、ジェルマン・ルーヴェ、エロイーズ・ブルドンで、セウン・パク、ポール・マルク、ヴァレンティーヌ・コラサントとの日替わり、中盤がドロテ・ジルベール、フランソワ・アリュ、ビアンカ・スクダモアで、出演4日目(最終日)にアリュはエトワールに任命された。後半は、ミリアム・ウルド=ブラーム、フランチェスコ・ムーラ、ブルーエン・バティストーニ組とヴァランティーヌ・コラサント、ジェレミー・ル=ケール、ロクサーヌ・ストヤノフ組が交代で踊った。黄金のアイドルは主にパブロ・レガサが踊り、そのほかではマーク・モロー、トマ・ドキール、 ジェレミー・ル=ケールとなっている。

セウン・パクとポール・マルク©Julien Benhamou/Opera national de Paris
ローラ・エケ、ジェルマン・ルーヴェ組を予定していたのだが、ダンサーにコロナ感染者が出たために、当日午後に急遽公演中止となってしまった。幸運にも翌日のチケットを手に入れることができたのでホッとしたが、日常生活が戻っているように見えても、コロナウイルスは蔓延しているのだと実感。劇場に行く前にホームページで最新情報を確認することを勧めたい。

ヴァレンティーヌ・コラサント©Julien Benhamou/Opera national de Paris
そこで所見したのがセウン・パク、ポール・マルク、ヴァレンティーヌ・コラサント組。セウン・パクとポール・マルクは相性が良いようで、最近はデュエットを組むことが多く、今回も密度の濃いデュエットを見せてくれた。マルクは以前より貫禄がついて、ひと回り大きくなった。しなやかで動きが柔らかく、ジャンプも回転も見事。これからのオペラ座を支える大黒柱となるだろう。ただ、2幕の婚約式で、ニキヤの踊りを見ている間の演技は、もう少し大袈裟にしても良かったのではないかと思った。パクとコラサントの存在そのものが対照的で、それぞれの役にぴたりとはまっている。華奢で控えめなニキヤのパクもよかったが、プライドが高く、身分の違いを表情ひとつで演じ切るコラサントは圧巻。もちろんテクニック的にも安定していて、回転ひとつを取ってもガムザッティそのものなのだ。
黄金のアイドルのマーク・モローのシャープで力強い踊リや、愛らしく壺の踊りを踊ったシルヴィア・サン=マルタンには大きな拍手が巻き起こった。3幕影の王国での3人のソリストのバリエーションのエロイーズ・ブルドン、シルヴィア・サン=マルタン、ロクサーヌ・ストヤノフは、悪くはないのだが印象が薄かった。その前に踊ったキャラクターダンスの印象が残っていたからだろうか。

シルヴィア・サン=マルタン©Julien Benhamou/Opera national de Paris
5通りの配役全てを見ることができないのは残念だが、多くの役を踊ることで成長するダンサーたち。次回はどこまで域を深めるのか楽しみになる。(4月9日オペラ座バスティーユ)
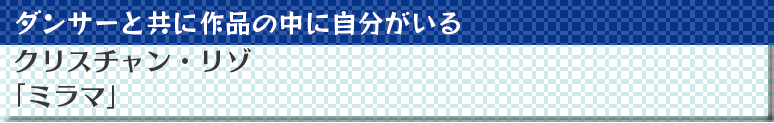
微妙な照明、ぼんやりとした映像、だけれど私たちは果てしのない海を見ている、そんな作品だった。
一瞬にしてできた1本の白い道。女はゆっくりと歩く。白い道は次第に後ろに広がり、女の歩みと共に舞台全体が明るくなった。女はひとりで踊る。時に激しく、時に遠くを見つめる。素人っぽさが残る踊りに、これまでのリゾの作品に出ていた優れた身体能力を持ったダンサーを起用しなかったのはなぜだろうと思って見ていたのだが、これはこの後に登場する10人のダンサーとの対比なのだと思った。この10人は明らかにプロのダンサーで、動きが滑らかでシャープで大人だ。それぞれで動き、組み、リフトし、され、倒れる。
淡々と踊るその向こうに広がる黒い永遠。彼らはほとんど後ろ向きで踊っている。観客に背を向けてホリゾントを見つめる。私たちも遠くを見る。ぼんやりと海。果てしない海。その向こうにあるのは、永遠。
10人のダンサーは最初のソロを踊ったダンサーとは明らかに違うが、だからこそフィードバックのように最初のソロが思い起こされる。ゆっくりと歩いていた少女が長い髪を振って回転し、倒れ、そしてまた激しく踊る。目に見えない不安に怯え、希望を求め、がむしゃらに体当たりしながら向かっていくような印象は、青春時代に覚えた感覚に似ている。
無垢の時代の原点に戻る。果てしない海を見ながら。
微妙に変化していく白い照明、ぼんやりとした映像という演出が、大きな想像を与えてくれる。リゾの美的感覚が好きだった。(4月11日104サンキャトル)

©Marc Domage

16回目を迎えたコンコール・ダンスフェスティバル。作家とダンサーが初めましてと出会って、30分の作品を作る人気のシリーズ。劇場だけでなく、博物館や図書館などでの公演が新鮮だし、時に無料というのが嬉しい。今回はディレクターのジャン=フランソワ・ムニエ氏の手腕に拍手。8演目がリバイバルで、時を経て再会したアーティストや作品が、今日どう映るかを試したのだ。これがなかなか興味深かった。作品は人と共に成長していて、作って終わるのではないのだ。
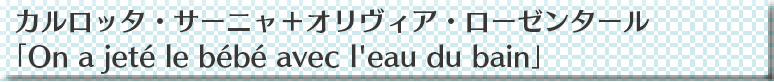
ダンサーとしても優れ、一風変わったダンステアトルを創作して人気のカルロッタ・サーニャと、小説と戯曲を手掛け、京都のヴィラ九条山にも滞在したオリヴィア・ローゼンタールの組み合わせは、個性がぶつかり合うバトルとなるかと思っていたし、「風呂の水と一緒に赤ん坊を捨てた」という残酷なタイトルに興味津々で行ったのだが、作品はちっとも残酷じゃない。ふたりの連想ゲーム的な会話が面白い。赤ん坊は「捨ててないよ」とサーニャがサラリと言っていた。
2009年初演のものを10年後の2019年に再構築したのだが、コロナ禍により中止。そこで今回ようやく上演の運びとなった。
小さな丸いテーブルの上のパソコンを見ながらおしゃべりをするふたり。パソコンの向きをくるりと変えて画面を覗き込むふたりのお尻を見ていたら、いきなり音楽がかかって慌てて中央に位置するふたり。そしてふたりの会話とダンスが始まる。
「2009年に何をした?」「2010年は…で、2011年、ああ、東北大震災。」「2013年は、忘れた」とカルロッタが言えば、オリヴィアがすかさず答える。その年に何が起こったか全部覚えていると。「風呂の水と一緒に赤ん坊を捨てた。」「違う、そんなことしてない。」
そしてふたりの揃いのダンス。手の動き、簡単なステップを踏むだけだけれど結構複雑で細かい。作家にとっては難しそうに見えるけれど、オリヴィアはさらりとこなす。たわいもない会話に仲の良さが感じられて好感が持てる。
パソコンの画面に流れていたのは2009年初演時のビデオ。「企画者のムニエ氏から10年前の作品を再演しないかと声をかけられて、練り直して完成したと思ったらコロナ禍で上演の機会を逃し、今年になってようやく上演することになったので、さらに練り直した」とは、講演後のトークで。「多分また10年後に再構築して上演するかも」と。10年後を期待してます。(4月9日パリ20区マルゲリト・デュラ図書館)

©Delphine Micheli
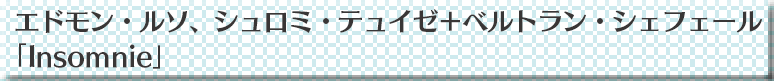
リヨンオペラ座バレエ団とバットシェバ舞踊団にいたふたりの踊りは、いつ見ても気持ちがいい。踊りがうまいから、見ているだけで気持ちが良いのだ。
このふたりのダンサーと作家のベルトランの組み合わせは2度目だ。前回はふたりが振り付けをして、別のダンサーが踊っていた。今回は、このふたりに実際に踊ってもらう企画。国立公文書館パリ館の円形の部屋での上演だった。
音楽が鳴って踊り始めたふたり。相手に時々目をやりながら、いくつかのフレーズを繰り返していくうちに、少しずつ接点が現れる。しかし触れることはなく、相手を意識しながらも、自分の世界の中にいる。背の高い髭面の男が話し始めた。「何か話さなくてはいけないんだと思う。別にこれといって大事なことではない、自分が何をして、何がしたいのかとか、ありきたりの日常のことだけど。」「車は買わない。公害を出すし」などと環境に優しい生活を考えているみたい。彼の独り言とは関係なく、男ふたりは踊り続ける。時々ひとりが作家の横に立つと、作家は腰を上げ、ダンサーは椅子を少し前に移動する。その椅子に座り直してまた話し続ける。ベルトランの声が心地よい。語りが踊りのBGMになっている感じ。ダンサーは語りの内容に関係なく踊りつづけているように見えるが、ふたりの関係は濃厚になっていく。ダンサーふたりと作家が少しずつ移動する場所を狭めて密になっていくけれど、やはり3人が絡むこともない。淡々と、それぞれの独り言のように過ぎていく。
「そろそろ空が白々としてきた。眠りにつこう」という言葉でサクッと終わる。何がどうと言うこともないけれど、気持ちの良い時を過ごした。(2022年4月10日国立公文書館パリ館)

©Delphine Micheli
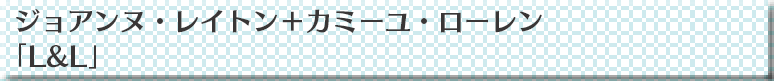
2019年に初演したものの、コロナ禍で公演は中止になった作品を再び。
四角く囲んだスペースの中で、ふたりは歩く。歩いては止まり、ローレンは語り、レイトンは踊る。そしてまた歩く。レイトンが踊ると言っても、それはステップをベースにした動きで、それは少しずつ変化を加えて繰り返される。金色に輝く面を付けて揃いのダンス。
歩くことは進むこと。たとえ元の場所に戻ったとしても、以前とは違う。時が経っているし、昔の自分とは違う。歩けばそこに何かが生まれる。そこにはふたりの心地よい存在があった。(4月11日ポンピドゥセンター)

©Delphine Micheli


ダンス大好きのセドリック・クラピッシュ監督の最新作「En corps」が3月30日から公開されて、ロングランしている。これは、26歳のソリストが公演中に怪我をして、医者の診断に絶望するものの、そこから立ち直る話だ。ダンサーに怪我はつきもの。再起不能と言われても、視点を変えれば再起できると、元気をくれる。しかも、パリのバレエ関係施設が映るシーンが多いし、ダンスのシーンは多いし、ホフェッシュカンパニーのリハーサル風景が見られるなど、ダンス好きにはおすすめの映画です。
ネタバレはしないけれど、見どころを少し。
最初のシーン「ラ・バヤデール」では、開幕直前の舞台裏風景が見られ、これはシャトレ劇場での撮影ではないかと思う。その後屋根に登ってセーヌ川を見下ろす夜景が美しい。レッスン見学をして、ホフェッシュ・シェクターと言葉を交わすのは、ダンススタジオ・メナジュリ・ドゥ・ヴェール。ヒップホップと将来の恋人と出会う場所が、パリ市が営む文化施設の104サンキャトル。ラストのホフェッシュ・カンパニーの公演会場はラ・ヴィレット。アパルトマンの廊下やベランダでのウオーミングアップ場面もあって、パリを散歩している気分。また、ノルマンディのレジデンスが素晴らしく、ホフェッシュ・カンパニーの「ポリティカル・マザー」のリハーサル風景や、海辺で踊るダンサーたちの解放された体に見惚れる。
出演は、マリオン・バルボーをはじめ、パリ・オペラ座からはマリオン・ゴティエ・ドゥ・シャルナッセ、ジェルマン・ルーヴェとミュリエル・ズスペルギー(踊らないのが残念だけれど、優しい笑顔が素敵)、そしてホフェッシュ・シェクターとヒップホップのメディ・バキなどがダンス関係で、ドニ・ポダリデスやミュリエル・ロバンなどの味のある役者揃い。
怪我をして踊ることを諦めざるを得なかった友達の言葉や、法律家の父の「ダンスなんて一生続けられるものじゃない。それみろ、怪我をすればおしまいだ。それに比べて法律は一生稼げる」と言うセリフ。「2年間の休養が必要です。足首の古傷もありますから」という医師の言葉に「以前に捻挫した時にちゃんと直さないまま踊り続けたから…」と答えるエリーズ。身につまされる思いがするセリフがたくさん出てくるのは、ダンサーの実体験をもとにした台本だからだ。
また、レジデンスのオーナーが「私はアーティストでもなんでもないけれど、場所があるから提供するだけ。それで今週はこれ」と聞こえてくるのは弦楽四重奏のグループのリハーサル。その次はダンスで、その後は歌。自然に囲まれ、週替わりで芸術を楽しめる生活が羨ましい。いや、彼女の精神が解放されているから人が集まるのだろう。
素敵なセリフとダンスづくしの2時間。もちろんバレエとコンテンポラリーを踊るバルボーの素敵なこと! 女優としての活躍も期待されている。
動画はこちら。
|

