Boris Charmatz 「Somnole」(NEXT Festival.eu)
Milo Rau 「Grief & beauty」(NEXT Festival.eu)
Mapa Teatro 「La luna en el Amazonas」(NEXT Festival.eu)
タニノクロウ「笑顔の砦」(Théâtre de Gennevilliers/Festival d'Automne)
Malandain Ballet Biarritz 「Programme Stravinski」(Théâtre national de danse Chaillot)
Giséle Vienne/ Étienne Bideau-Rey「 Showroomdummies ♯4」(Centre du Pompidou)
Vincent Dupont 「Attraction」(Les Abbesses)
シーズンが始まって3ヶ月目。劇場には客足が戻ってきた感じがする。どうぞこのままコロナが消滅してくれますようにと祈るばかりだったが、下旬になって近隣国では感染者が増えて、外出禁止令が出た国も。そして新型変異株オミクロン出現…
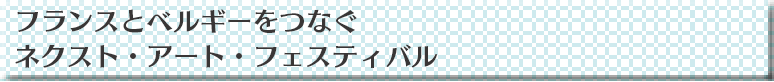
フランス北部とベルギーにまたがるフェスティバルNEXT(https://nextfestival.eu/fr)は、毎年秋に3週間催される。今年のオープニングの演目は、タニノクロウの「笑顔の砦」。言葉と文化の壁を超えて、日本の演劇作品が選ばれたことを誇らしく思う。パリでは名が知られていても、地方ではまだまだだが、初上陸の街での初演はスタンディングオベーションだったという。人間として、誰もが持つ感情に触れる作品はユニバーサルなのだ。フェスティバルについては、2022年冬号のセーヌで詳しく紹介しようと思う。
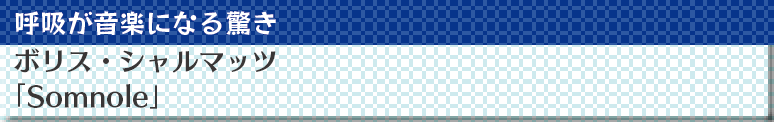
身体を追求し続けるシャルマッツのソロは、自身が口笛を吹きながら踊るという驚愕の舞台だった。
ホーホーという笛を吹くような音が近づいてきて、シャルマッツが両手を上げてゆっくりと舞台に入った。布を貼り合わせたような膝丈のスカート姿で、座ったり立ったり、ゆるゆると移動しながら動いている。外出禁止令ゆえに活動が停止状態だったときに思いついたアイディアで、夢と現を行き来するような踊りを目指したというように、これといったテーマはなく、赴くままに動いている感じだ。しばらくして、即興のような踊りが音と完璧にぴたりと合うのが気になった。あまりにもタイミングが合いすぎている。不思議に思っていたら、それはシャルマッツ自身が発している音なのだということがわかった。動きは次第に速くなり、時に激しく動くが、それでも音が止まることはない。ただの音ではなく、メロディーも奏でるのだ。バッハからバルバラ、そしてピンクパンサーの曲になって楽しそうに踊る姿は無邪気な子供のよう。どんなに呼吸が荒くなっても音楽はやまない。息を吹くだけでなく、吸い込む時にも音を出していたのだ。マイクを使っているかのようにはっきりと聞こえ、しかも軽くエコーがかかっているのはこの会場独特の効果らしい 。無機質なグレーの壁が、音を増幅させると音響効果をもたらしているのだ。カーテンコールの拍手が、メタル音の細かなエコーとして跳ね返ってきたのには驚いた。また、照明は彼を感知して自動で動くロボスポットひとつだけというシンプルな舞台で、シャルマッツそのものが見えてくる。2022年9月からピナ・バウシュが率いたヴッパタール舞踊団のディレクターになることが発表された。舞踊団に新たな風を送り込みたいと意欲を示すシャルマッツの今を知るための貴重な舞台だった。
なお、このスペースは、クリスティーヌ・バスタン、アラン・ブフォーなど、90年代から現在に至るまでの多くのコンテンポラリーダンサーがレジデンスとして作品を創作した伝説の劇場で、アーティストを惹きつけるパワースポットだったのだ。(11月18日ヴァランシエンヌ市エスパス・パッソリーニ)

ⒸMarc Domage

ⒸMarc Domage
このフェスティバルNEXTは、フランス側の3団体とベルギーの2団体がオーガナイズしているもので、演劇、ダンス、展示などを中心に、2国間の文化の交流を目的としている。
ベルギーにはフランス語圏とオランダ語圏があるため、字幕スーパーはオランダ語とフランス語で表示される。「笑顔の砦」も2か国語表示で、翻訳にはかなりの時間をかけたとスタッフの話。会場は広範囲にわたっているが、無料送迎バスがあり、コロナ禍にもかかわらず、集客は以前と変わらないという人気のフェスティバルだ。
滞在中にミロ・ラウの 「Grief & beauty」と、マパテアトロの「月はアマゾンに」を所見。
「Grief & beauty」は、死がテーマ。ダイニング、寝室、サロン、浴室がある一軒の家の中で、死んだ娘の思い出、子供の頃の思い出などが4人の出演者によって語られる。語る役者の顔を遠くからカメラで捉え、それを後方上部の画面に大写しに映す方法は、現在進行形で進む芝居とは別の次元、つまり人には語らなかった心の呟きや過去の思い出として捉えられる。映像が高い位置にあることが、現実の舞台との距離を置くことになるという演出だ。そして、ここには実際にはいないもうひとりの出演者がいる。ビデオだけに登場する人。屈託なく微笑むその人は動かないのに、なぜか後ろの柱時計の振り子は揺れている。実はこの人は安楽死を選んだのだ。難病を抱えているとは思えない初老の女性は、屈託なく笑って雑談している。「これから深くて長い眠りに入るのね」と言って、実際に死にゆく映像を流したことはショックだった。これが演技だったと信じたかった。時間をかけて話し合った結果の選択だったというが、このように死を選べるということが驚きで、このような映像を堂々と流す事には疑問を感じた。しかし、これがラウなのだ。タブー視されることをダイレクトに提示する。私には命の軽さを感じずにはいられず、後味は悪かった。(11月17日ルーベ・コンディシオン・ピュブリック「笑顔の砦」も同劇場で上演された)

「Grief & beauty」ⒸMichiel Devijver

「月はアマゾンに」Ⓒarchives Mapa Teatro
マパテアトロは、コロンビアを代表する演劇集団で、2016年に東京で公演をしている。アマゾンの無謀な森林開発によって生態系が破壊される事実を、ジャガーをメインに語るドキュメンタリー的な演劇作品だったが、主にスペイン語の会話でセリフが多く、遠くの字幕スーパーを読むのに苦労してしまい、奥深いメッセージを汲み取るには相当のエネルギーが必要だった。ダンス界の人間としては、言葉がわからなくても伝わるような演出はできなかったものだろうかと思ってしまう。(11月18日ヴァランシエンヌ市フェニックス劇場)
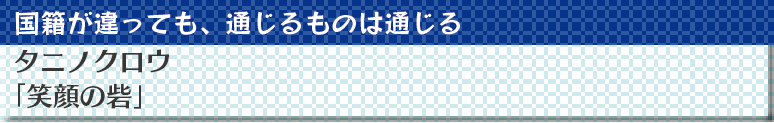
フェスティバルNEXTで見逃してしまったので、パリ公演を所見。
パリ北部にあるジュヌヴェイリエ劇場、略してT2G。国立演劇センターで、ここでは日本の演劇作品が上演されることが多い。岩井秀人はアソシエート・アーティストだし、ほぼ毎年のように岡田利規の作品が上演されていて、11月末から岡田利規と金氏徹平の「消しゴム山」が、12月には静岡のSPACとの共同制作の「桜の園」が予定されている。
タニノも今回が初めてではない。すでにファンがいて、パリでの8公演は完売。入り口にはチケットを求める人が何人もいた。
日本語での上演なので字幕スーパーがつくが、舞台両脇の目の高さに設置してあったのと、簡潔的確な翻訳ゆえに、セリフから間をおかずに客席の反応があったのは、良いことだと思う。字幕スーパーの位置は重要で、舞台との距離があると役者の動きを見ることなく終わってしまうことがあるからだ。もちろんこれは翻訳だけでなく、タニノのわかりやすく端的な演出にもよるところが大きい。家庭という日常は、生活様式は違っても人間のすることは同じだ。食べて、飲んで、テレビを見て、占いを信じて、寝て、悩んで。隣同士、異なる環境の2世帯だけれど、それぞれの心の底に流れているものは同じなのだ。思いやりという温かいもの。それが感じられるから共感できる。それと同時に家族とはなんなのかと問いかける。血が繋がっているから家族で、血が繋がっていなければ家族ではないのか。
印象に残った場面のひとつに、卵が転がる場面がある。ただそれだけなのに、そこにある「間」に笑いが起こった。海外では「間」が日本独特のもののように解釈されているように感じるが、セーヌ2021年秋号で紹介した堀川炎さんが、「それはフランスにも存在しているけれど、それを意識するかどうかの違いではないか」と言っていたが、日本では「間」を一瞬の空白として思いを伝えるのに対して、海外ではその一瞬を、動きや言葉で埋めることが多いのではないかと思った。転がった卵を見て「あ」と言った瞬間の「間」を、観客はちゃんと感じて反応していたように思った。
誰だって笑って楽しく生きたい。辛いことも苦しいこともあるけれど、笑顔でいられることが幸せにつながるのだと、親父さんを思い出しながら劇場を後にした。この作品はこの後、オルレアンのCDN 国立演劇センターで上演されてフランスツアーを終える。フランス語のタイトルはLa Forteresse du sourire。(11月20日ジュヌヴィリエ劇場)

ⒸTakashi Horikawa
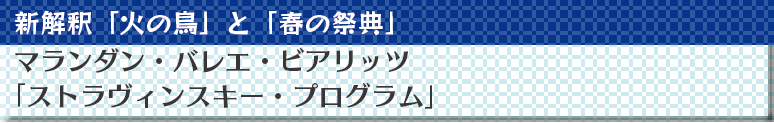

「火の鳥」ⒸOlivier Houeix
バレエ団でありながら、トウシューズは履かずにコンテンポラリー作品を創作しているビアリッツ・バレエ団。ディレクターで振り付け家のティエリー・マランダンは、独特な創作で人気がある。今回はストラビンスキーの「火の鳥」と「春の祭典」を上演。シャイヨー国立舞踊劇場での1週間にわたる公演を満席で終えた。
マランダンの作品はなぜ人気があるのかといえば、独特の解釈と細かい音楽の分析による振り付けが融合しているからだろう。また、抽象的な表現によって多くのことを連想できるという面白さがある。今回の「火の鳥」では、イワン王子も魔王カスチェイも出てこない。衣装は男女ともロングドレスで、男女の差がほとんどないユニセックスな振り付けだ。昔は女性ダンサーがたくましかったが、ここ数年は男性ダンサーが中性的な踊りをするようになったように感じる。

「火の鳥」ユーゴ・レイヤーⒸOlivier Houeix
まず、幕開きは男女とも黒のドレスのユニゾンで、横に移動する時にスカートの裾をサラッと広げる動きが鳥をイメージさせる以外に、鳥らしい動きはほとんどない。そこに真っ赤なレオタードの赤い鳥が現れる。これを踊ったのが男のユーゴ・レイヤーで、女のようにしなやかな踊りに目が離せない。体は柔らかく、高いアラセゴンが印象的。他に類を見ない彼の存在はバレエ団にとって貴重だ。ここにも鳥らしい動きの連続はなく、瞬間的に鳥をイメージさせる動きが散りばめられているだけだ。黄色いドレスに着替えた女性だけの群舞は軽快でかわいらしく、小鳥たちのおしゃべりが聞こえそうだ。これが黄金の木に留まる鳥たちの踊りだろう。そして赤い鳥と男女のカップルのトリオになる。王子と王女を連想させるが、群舞と同じシンプルな衣装で赤い鳥と穏やかに対話するような構成になっている。次の場面での黒の踊りは、音楽に合わせて激しい動きの連続で、それまでの流れを変える。衣装の色によって場面が変わり、きめ細かく計算された構成は、次々と形を変え、飽きさせない。赤い鳥は死を迎えるのだろうか、弱り果てている。白いドレスになった群舞は弔いの行進をするかのように列をなし、顔を覆い、泣く仕草をしながら歩いている。しかし、赤い鳥は黄金に輝き復活し、群れをなして大空を飛ぶかの如くの群舞には迫力がある。ひとり残った不死鳥のところへ男が光る卵型のオブジェを持って出てくるところで幕となった。魔王カスチェイの命が入った卵なのだ。これを壊すかどうかはそれぞれの想像に任せるということなのだろう。
これまでにもフォーキン、ベジャール、バランシン、バウシュなどがこの物語をベースにして創作しているが、ここに新たにマランダン版「火の鳥」が誕生したと言えよう。
先にも書いたように、以前と作風が変わりつつあるような印象を受けている。マランダンはダンサーの可能性を最大限に引き出すことで、新たな方向性を追求しているように見える。これからもバレエ団は変わりゆくだろう。非常に興味深いことだと思う。

「火の鳥」ⒸOlivier Houeix

「春の祭典」ⒸOlivier Houeix
さて、続く「春の祭典」は、マルタン・アリアーグの振り付けだ。周防正行監督の映画「ダンシング・チャップリン」に草刈民代とともに出演していたので、ご存じの方もいるだろう。19歳からバレエとコンテンポラリーダンスを始め、マランダン・バレエビアリッツ・ジュニアを経て、マルセイユバレエ団やキブツ・コンテンポラリーダンスカンパニーなど欧州のバレエ団で活躍したダンサーだ。また、多くのバレエ団に作品を提供しており、現在ビアリッツ・バレエ団のアソシエート振付家となっている。マランダンが選んだだけのことはある、これまた一風変わった解釈の「春の祭典」だった。
スタンドピアノが1台下手奥にあり、黒いスーツの男がポーンと一音を叩いた。それが春の祭典ピアノ版の始まりだった。生演奏の序曲が録音された曲に重なり始めたら、ピアノから手が出て頭が出て、なんと人が出てきた。そしてピアニストを乗り越えて次から次へと人が湧き出てきたのだ。最初に出てきたのが腰が曲がった老婆で、髪はボソボソ、ヨタヨタしている。ところが群衆を率いるリーダーのごとく、曲が激しくなって踊り始めたら、若いダンサーに劣らぬシャープな踊りを見せる。踊り終わればまたヨレヨレになる。そして消えていった。その後の群舞の踊りは曲を綿密に分析した振り付けで、戦いの踊りは男のバトル。その後に静かな曲になったら女の優しい踊りと、曲のイメージ通りの展開だが、シーンごとのメリハリがはっきりしているので新鮮に感じた。そして生贄を選ぶ場面では、白のゆったりとした上着にショートパンツだった女がクルクルと自転すると、一瞬にして白のロングドレスにブラジャー姿に変わったのだ。見事な衣装の変化に驚く。そして全員がスカートになり、倒れかけたところを男が受け止めてデュエットとなる。トランスに入った女を、さらに深いところに連れて行くような、決して暴力的ではないが優しくもなく、空中を浮遊するような振り付けで、各デュエットごとに異なる振り付けをしている。そしてついにひとりが選ばれる。呆然とする女を男たちは激しく操り、次から次へと人々の手に飛ばしていく。するとそこに腰が曲がった老人が現れた。村の長老だろうか、彼も髪はボザボサ、体はヨレヨレで、ほとんど歩けず、支えてもらってようやく立っているほどなのに、踊り出したらキレがいい。これまた踊り終わればヨタヨタしている。そして、神の光らしきものが爆発し、台の上に座らされた生贄の胸には血を思わせる赤い布。その周りで激しく踊る人々とは対照的に、ただ静かに前を見続ける生贄は、ゆっくりと空中に浮かび昇天する。そしてラストの曲は、またピアノの独奏になった。誰もいなくなった舞台に響くピアノの音。白昼夢を見ていたような気分になった。腰が曲がった老婆を踊ったクレール・ロンシャンと老人のフレデリック・ドゥベルドが素晴らしかったが、なぜここまでヨボヨボの老人役が必要だったのか、これをジョークと捉えて良いものなのか少し疑問だった。(11月12日最終日シャイヨー)

「春の祭典」ⒸOlivier Houeix
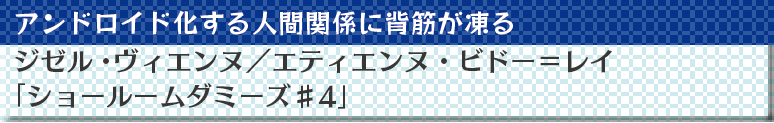
マリオネットと人間のシュールな世界を描くジゼル・ヴィエンヌ。残虐の中に人間の優しさを組み込んだ独特の作風は多くのファンを持つ。今年のフェスティバル・ドートンヌ (アドレスはこちら)では、彼女の6作品と展示を9月から来年1月まで特集。今回は京都のロームシアターとの共同企画による「ショールームダミーズ ♯4」をポンピドゥ・センターにて上演した。この作品は2001年に初演され、その後もツアーを続けており、2020年に4回目の改訂版として京都で日本人出演者により再構築された。
「2分前」「1分前」という舞台監督からの日本語のアナウンスが流れて始まった。薄いグレーの壁の部屋、隅には鉢植えの植木がある。壁に沿って置かれた椅子にだらりと座った女の子たち。中央には黒い椅子が並べられ、黄色いTシャツの女の子がポツンと座っている。何かの気配や音にびくりとしながら、落ち着きなく移動する中、面をつけたピンクの服にジーンズ、ハイヒールの女がまるでファッションショーのモデルのように歩き、ポーズをとる。黄色い服の少女がその女のポーズを変えても抵抗もせず、何もなかったようにモデルウォークを続ける。この女は人間か、それともアンドロイドか。ポツンと置かれた黒い靴を履いて動き始めた別の女は、立っていたかと想うと突然崩れ、また激しく踊る。少女に椅子に乱暴に座らされても、抵抗することなく動きを繰り返す。その後に出てきた女たちも同様で、人間とアンドロイドの二面を持つ人たちに見える。意思を持って動くときと、相手に動かされても抵抗せずに動かされる時があるからだ。それとも自分を偽り、仮面を被っている? もしかしたらこれが現実の学生の姿なのではないだろうかと思い始めた。後ろの壁に沿って並べられた椅子に座り、髪で顔を隠したり、だらりと頭を垂れたり、椅子の背もたれにうずくまるように座る14体の人形(リアルで人間と人形の区別がつかないほど)。学校という集団生活に疲れ、いじめ、抽象誹謗を逃れるために感情を表さず、本音を隠し、言われた通りに行動する。仮面をつけて初めて自分らしさを表せるけれど、仮面の下の顔は見せない。歪んだ世界に生きる高校生たち。
ひとつの空間に多くの人がいても、心から交わることはない冷めた関係。ただそこに人が存在するだけという空間。学校だけでなく、集団社会でも他人との距離をとることが多くなった。特にコロナ禍により人の意識は大きく変わりつつある。20年前に初演された作品は、現在の社会を予言していたのだろうか。それとも、20年前も今も変わらないということだろうか。ヴィエンヌの鋭い感性を改めて感じた公演だった。
出演は京都公演と同じで、朝倉千恵子、大石紗基子、高瀬瑶子、花島令、藤田彩佳、堀内恵。(11月14日ポンピドゥセンター/フェスティバル・ドートンヌ)

ⒸYuki Moriya
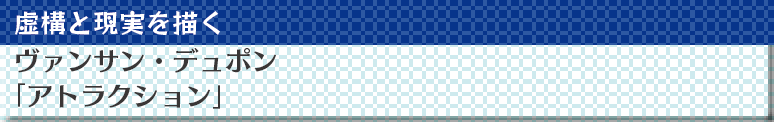
たくさんの白い線が交差する空間に4人。バイオリンの一音が長く響き、それに合わせてひとりが踊る。二音になればふたり、三音なら3人というように、それぞれが音のコードに反応して踊っているようだ。個人的に動いているように見えるけれど、どこかで交差する時がある。4人が重なった時、プシュッという音とともに線が弾けた。変化した空間の中にピアノの音が響く。場面によって変わる楽器に合わせて、まるで音符をダンスで表現するかのように踊るダンサーたち。ゴムでできた線を引っ張って空間形状を変えながら踊るダンサーを見ていたら、いつの間にか細かった白い紐が太くなっている。デュポンの手品が始まった。白いシャツがブルーに輝き、それまでの空間が別世界になった。そして次々と白い線が消え、ただの四角い黒い空間にダンサーたちが立っている。夢と現実が交差する瞬間だった。(11月19日アベス劇場)

ⒸMarc Domage
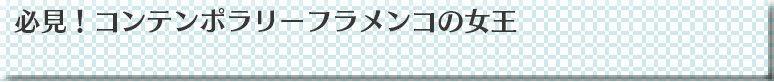
今回見逃してしまったのだが、もし機会があったら是非見てほしいダンサーがいる。コンテンポラリーフラメンコの女王と言われるロシオ・モリーナだ。日本公演もしているのでご存じの方もいると思うが、精力的な追求は止まることを知らない感じだ。母になり、奥行きを更に深めたようで、今回のパリ公演もパワーが爆発していた。ギタリスト相手のソロの見事な掛け合い。ふたりの無言の会話を見ているだけでワクワクする。そこには踊り、演じ、会話する喜びがあり、見ている側の心まで熱くしてくれる。衣装もバラエティに富み、伝統的なフラメンコの衣装を着ることもあるが、まるでモード雑誌に出てくるような衣装で踊る。これからどこまでフラメンコの伝統を守りながら新たな方向性を追求していくのか、目が離せない。
ホームページはこちら

ⒸÓscar Romero

ⒸÓscar Romero

ⒸÓscar Romero
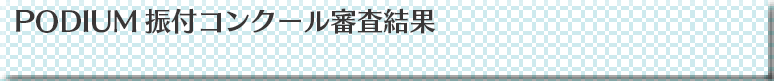
第2回目の振付コンクール・ポディウムの決選は、11月19~20日の2日に渡ってグルノーブルで行われ、厳選された9か国12団体の中から、審査員賞と観客賞の4作品が選ばれた。このコンクールの特徴は、入賞作品の上演を手配してくれることで、今回の受賞作品は、2022-23年のシーズンに26公演が予定されている。
結果は下記の通り
審査員賞ソロ/デュエット部門
メルセデス・ダッシー「B4 サマー」(ベルギー)
審査員賞団体部門
フローラ・デトラ「ミュイット・メーカー」(フランス)

「ミュイット・メーカー」ⒸBruno Simao
観客賞
19日 コレット・サドラー「ラーニング・フロム・ザ・フューチャー」(イギリス)
20日 レオ・レリュ「エントロピィ」(フランス/グアドループ)
ホームページはこちら。
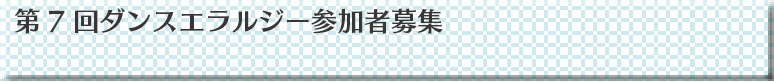
パリのテアトル・ド・ラ・ヴィルが主催する振り付けコンクール、ダンスエラルジー。ダンスの観念をどこまで広げられるかが求められるコンクールだ。とはいえ、何を基準にして「観念」というかは設定されていないので、選ばれた作品は非常に舞踊的であったり、踊りがほとんどなかったりと、自由な発想で参加できるコンクールと見ている。
参加条件は、10分以内の作品で、最低3人が舞台に出ること。それだけ。
来年2022年6月25、26日に決選が行われる。
参加希望者は2021年12月31日までにホームページでネット登録をすること。
|

