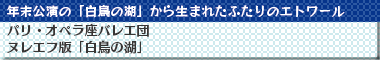

レオノール・ボーラックとマチアス・エイマン ©Svetiana Loboff / Opéra national de Paris
2016年の年末演目のひとつ「白鳥の湖」は、オペラ座に新しい風を送り込んだ。28日には、王子役を踊ったジェルマン・ルーヴェが、その3日後の大晦日には、オデット/オディールを踊ったレオノール・ボーラックがエトワールに任命され、オーレリー・デュポン監督になって初のエトワールが立て続けに誕生した。アメリカを意識したミルピエ前監督が選んだ今シーズンの演目を、フランスらしさを重視したいオーレリー・デュポン新監督が引き継ぐという歪みのあるシーズンが始まって最初の古典作品上演に、デュポン監督のオペラ座再改革の意気込みが感じられるようだった。
レオノール・ボーラックは金髪の愛らしい容姿で、ネオクラシックを得意とするものの、古典作品でも高い評価を受けている。12月31日にたった1回、しかも初めてオデット/オディールを踊ってエトワールに任命された。
一方のジェルマン・ルーヴェは、11月に行われた昇進試験で2017年1月1日からプルミエ・ダンスールへの昇格が決まっていたが、これを待たずに飛び級でエトワールになったことになる。ジークフリート王子にふさわしい、貴公子的な雰囲気を持つダンサーで、まさにパリ・オペラ座の雰囲気にぴったりの男女のエトワールが誕生したと言えよう。
さて、私はそのはるか前、12月8日のアマンディーヌ・アルビッソンとマチュー・ガニオの白鳥・黒鳥/王子コンビを見た。
今回は、アルビッソンとガニオのコンビがプレオープニング、本公演の初日はミリアム・ウルド=ブラームとマチアス・エイマンで、後半にリュドミラ・パリエロとジェルマン・ルーヴェという配役。その中に22日にオニール八菜/ファビアン・レヴィヨン、31日にレオノール・ボーラック/マチアス・エイマンのたった1日だけのキャストが組まれたのは、ジョシュア・オファルトの怪我による降板が理由で、結果として若手の起用とエトワールを生むことになった。オファルトの怪我のために相手役のローラ・エケも降板となり、その代わりにオニール/ファビアン組が22日に、31日にはボーラックがエイマンと踊ることになった。エトワールで主役を固めた当初の配役の中に当時まだスジェだったジェルマン・ルーヴェが起用されたのは、その才能を見抜いたデュポン監督の意向だったのだろう。その期待に応えた形で2回目に王子役を踊った28日にエトワールに昇格し、ボーラックが大晦日の公演でそれに続いた。
なお、ロットバルト役は、ステファン・ブリヨンとマチュー・ガニオが怪我で降板し、フランソワ・アリュ、カール・パケット、ファビアン・レヴィヨン、ジェレミー=ルー・ケールで、多くの会をカール・パケットが踊ることになった。ガニオのロットバルトは是非見たかったのだが、次回に期待しよう。
さて、オデット/オディールを踊ったアルビッソンは、柔軟な体を生かしたしなやかな動きで綺麗な印象を残したが、あいにく内面から出てくるものが弱く、感動を巻き起こすには至らなかった。白鳥でいる時と人間でいる時の差が曖昧で、例えば、ロットバルトに操られて白鳥に戻る瞬間に見せる、抜け殻のようなオデットを見ることはなかった。昨年エロイーズ・ブルドンがオデットを演じた時には、腕や首の動きが鳥そのもので、人間でいる時のしなやかな動きとの差異に、不運な王女の姿を見出したことが思い出される。オディールでは、オデットにはない強さを見せたものの、ロットバルトとの悪巧みを感じさせるようなしたたかさはなく、王子が愛を神に誓った瞬間に指をさしながら腹を抱えて笑う姿にようやく悪意を見いだしただけだった。グランフェッテはダブルを2回入れてこなし、会場から大きな拍手をもらっていたが、心に残るような感動は得られなかった。
マチュー・ガニオはここ数年内面の描き方が繊細になっていて、人を疑うことを知らない純情な青年を演じ、もちろんそのエレガントな貴公子ぶりはいつも通りで素敵だったのだが、バスティーユの大劇場の後方席までその繊細さが伝わったかどうかは疑問だった。遠くからでは繊細な演技を感じ取ることができず、得てして派手なテクニックで判断しがちだが、この日もそうで、ロットバルト役のフランソワ・アリュが、2幕の宮殿での短いバリエーションで、鳥人並みの高いジャンプ力と、ためがあり伸びがありそれでいてキレのある踊りを見せた途端に、6階席までの全ての観客の待ってましたとばかりの歓声を浴び、一躍本日のスター的存在になってしまった。もちろんアリュの身体能力の高さは誰もが認めるところだが、ダンスはそれだけではなく、特に物語のある作品では、どこまで感動を呼び起こすかが重要になってくる。アリュの演技に対しては、1幕のロットバルトの化身でもある家庭教師役でも、2幕のロットバルト役の時でも、もう少しはっきりと悪党さを露出しても良かったのではないかと思った。物語の面白さを見せるためには、小ぶりなガルニエ宮の方が似合っている。
日本人として気になるのは、やはりオニール八菜の存在だ。この日は1幕のパ・ド・トロワをレオノール・ボーラックとジェルマン・ルーヴェとともに踊り、若手ホープ3人組の期待は裏切られなかった。オニールはリズミカルで流れるような動きが素晴らしく、ボーラックは、コンテンポラリーも良し、古典も良しの逸材だと確信した。ジェルマン・ルーヴェもダイナミックで見応えがあり、この3人の共演は大きな花を添えた形になった。
王妃役はほとんど批評されない役だが、ステファニー・ロンベルグ演じた王妃は黒鳥に好意を持たず、王子が結婚相手として紹介した時、ほんの数秒の小さな演技だったが、困惑しながらも息子の愛を信じて渋々承諾した親の顔が現れていたのが印象に残った。
全体的に群舞が驚くほど綺麗に揃っていた上に、エレガントらしさが増し、デュポン監督の細やかな指導が着実に行き渡っているように感じた。(12月8日バスティーユオペラ座)

©Svetiana Loboff / Opéra national de Paris

©Svetiana Loboff / Opéra national de Paris

©Svetiana Loboff / Opéra national de Paris

©Svetiana Loboff / Opéra national de Paris

©Svetiana Loboff / Opéra national de Paris

©Svetiana Loboff / Opéra national de Paris
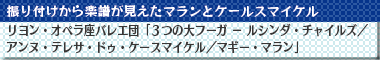
ベートーベンの大フーガを3人の振付家が料理する。1992年にローザスに振り付けたケースマイケル版、2001年に自身のカンパニーに振り付けたマギー・マラン版、そしてこの日のために振り付けたルシンダ・チャイルズ版の3作品が並んだが、同じ曲なのに全く違う印象を受け、振付と音楽への深い思慮に感動を覚えた一夜となった。

ルシンダ・チャイルズ ©Bertrand Stofleth
まず、ルシンダ・チャイルズがリヨン・オペラ座バレエ団に振り付けた新作から始まった。レースのような白い壁の向こうに男女が見える。ダンサーたちがひとり、またひとりと舞台に現れ位置につき、壁の向こうから出てきたふたりが中央に位置すると踊りが始まる。ソッテ、アラベスク、ソデシャなど、バレエの基本的なポジションをベースにした動きの連続で、シンプルなゆえに正確な位置に入らなければ面白みが出ない難しい作品だ。時々2組のデュエットとなり、他のダンサーは左右に流れ、しばらくするとまた合流してユニゾンとなる。シンプルだからこそ見える形式美からは、一貫してミニマルダンスを追求するチャイルズの姿勢がうかがえる。
アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル版は、モノトーンのイメージで、横のラインを描く照明の中を黒のジャケットと白いシャツのダンサーたちが踊るのだが、 そこには明と暗、高と低、調和と不調和、団体と個人、踊りと日常が混在している。ひとつの体なのに、見える部分と見えない部分ができる。上半身は明かりの中なのに、下半身は闇の中。男女共黒いスーツ姿なので照明の当たらない部分で黒い服で踊れば見えないが、体の一部が光に入れば、そこだけが浮き上がって見える。高い位置で踊った後に床に転がれば、一瞬にして消え、そしてふっと現れる。後半上着を脱いで白いシャツになると、踊りがさらに鮮明に見えてきて、躍動感あふれる豊富な動きのボキャブラリーに目が離せない。動きの面白さは、綿密な音楽の分析にもよるもので、不協和音の部分ではダンサーがバラバラになり、綺麗なメロディーになるとユニゾンになって流れるような構成になっており、音楽とダンスの一体化が非常に心地よく、この作品のためにこの曲が生まれたのではないかと思わせるほどだった。

アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル ©Bertrand Stofleth
ケースマイケルの才能に改めて感心していたが、マギー・マランにも度肝を抜かれた。かなりの間暗転の中で音楽が流れ、いきなり舞台全体が明るく照らされて目に飛び込んできたのが、真っ赤なドレスの女性4人。これでもかと自分をいじめるかのように激しく動いている。モノトーンで黒のイメージが強いケースマイケル版から、いきなり明るい照明に目の覚めるような真っ赤な衣装という差異に唖然としたが、同じ曲を3回立て続けに聞くと、演奏者の違いで曲の印象が変わることに気づかされる。2001年、まだマランがダンスのムーブメントを創っていた時代のものなので、動きは激しい。マランは、ベジャールの20世紀バレエ団のソリストとして活躍した後、出来上がった身体を壊すためにフランスに戻り、コンセルバトワールに入り直したという経歴の持ち主だということを忘れてはならない。この作品では、バレエのパをベースにしながらも、ダラダラのつま先で、膝も曲がり、決して美しいとはいえない動きが連続している。それなのに食い入るように見てしまう。洗練された美を求めたクラシックバレエに対抗するかのように、コンテンポラリーダンスのあり方を見せつけている感じだ。体型の違う体から生まれる動きのずれが面白く、体の心底から発せられるダンサーとしてのピュアーなエネルギーに引き込まれる。
なお、マランもケースマイケルとは別の角度からこの曲を分析している。弦楽四重奏の4人の演奏家のパートを各ダンサーに当てはめ、ひとりの演奏家が激しく弾けばそれに合わせてひとりのダンサーが激しく動き、ゆったりしたメロディーの担当ダンサーはゆったりと動き、不協和音となればそれぞれが違う速度でバラバラに動き、同じような旋律を奏でる時は似たような動きになるというような構成になっているので、動きから楽譜が読める感じだ。激しい動きの連続で、このままダンサーが倒れるのではないかと心配し始めた後半には、観客の期待に応えて(?)ダンサーがぐったりと床に横たわり、ダンスは疲れるものなのだという現実をはっきり見せる。 ここで観客は安心するとともに笑い、それでもでも踊り続けるダンサーに感動するのだった。踊る楽しさと苦しさを混ぜ込み、これがダンスだと言わんばかりにダンサーのありのままの姿を見せたマランからのメッセージに、会場は熱い拍手で覆われた。
形式美を追求したアメリカと、音楽を分析したヨーロッパの振付家。ここに各国のメンタリティーが見えたような気がして面白かった。
(12月2日MAC/Maison des arts de Créteil)

マギー・マラン ©Bertrand Stofleth

「蛙は正しかった」??? 気にしない、気にしない。蛙は夢を飲み込んでくれるから。2016年のジェームス・ティエレ新作は、地下で冬眠する蛙たちならぬ、奇妙な世界の住人たちの物語。赤い布を被って透き通るような声で歌う人が光を発しながら床に沈んでいくと、地下の世界が現れる。不安定な螺旋階段や傘を逆さまにしたようなオブジェは地上に繋がっているのかしら。中央の鳥かごのようなスペースでは、電気が体を通っているかのようにジェームス・ティエレがピリピリと震えるように動いているし、そこから抜け出してバイオリンを見事に演奏したまでは良かったが、それが手から離れなくなってしまったり、何度スプレーで固めても落ちてくる前髪に苛立って後ろに向かって投げれば、スプレー缶が顔に突き刺さった男が怒って出てくるし、ピアノの前にぐったりと座った女の手が伸びてピアノを弾くも、人が触ればその手がもげて落ち、髪を触ればごっそりと毛が抜ける。何が起こってもおかしくない世界なのだ。
この作品では、ジェームス・ティエレがメインで動いて、彼の魔術がたっぷり見られるのでファンとしては嬉しい。ステッキのダンスはステッキが空に浮いて独りでに動いているように見えるし、チャップリンみたいだなあと思ったが、ティエレはチャップリンの孫なのだから、似ているのは当たり前かも。ティエレの演技もさすがだが、もっと驚きなのはそこに住む女(ヴァレリー・ドゥセ)だ。中国雑技団顔負けのぐにゃぐにゃの体で、体を反らせば頭と足がくっついてゴムまりのようになって、バク転かと思ったらそのまま胸から着地してあっという間に立ち上がっている。並はずれた身体能力を巻き戻してスローモーションで確認したいところだが、あいにくこれは生の舞台なのでそれができない。そんなことは朝飯前とばかりに、床の上を転がり、奇妙な形でバランスを取り、水槽に沈む。このツッコミのふたりに、ボケ役のアシスタント的存在のおじさんと、訳もなく怒りながら出て来て恐怖を煽る大男が絡み、無人のピアノまでが鍵盤叩いて歯向かってくる。次から次へと事が起こる慌ただしい世界だ。
ここに異星人ティ・マイ・グエンが飛び込んで来たから、舞台はさらに大変な騒ぎ。すばしっこいから捕まえようたって捕まらない。ただでも騒がしい部屋がてんやわんやの大騒ぎ。食卓に並べようと持って来た皿は、どんどん増えて持ちきれなくなってしまうし、人はくっついて離れなくなったり動かなくなったり。結局歌手がカエルだったようで、最後は白い大きなカエルに飲み込まれていってしまう。カエルに悪い夢を食べてもらったのかも。
手品のような世界にあっけにとられるやら、笑うやらであっという間に終演となった。カーテンコールは全編を通して澄んだ歌声でストーリーテラー役をしたマリアマがティエレのピアノに合わせて歌を歌った。最後までおっしゃれ〜。演技よし、楽器演奏も上手いティエレにまた惚れ込んでしまった。(12月6日ロン・ポワン劇場にて/Théâtre de la Ville提携公演)

©Richard Haughton
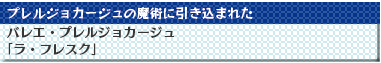
中国の民話をもとにしたアンジュラン・プレルジョカージュの新作。シュウとメンというふたりの旅人が、風と雨の嵐の日に小さな寺の前で雨宿りをしていると、年老いた僧が素晴らしい壁画を見せてあげようと言う。若い女性達が描かれ、そのうちのひとりは花を摘んでいる。かすかに微笑み、その唇はさくらんぼの実のように生き生きと赤く、瞳は輝いていた。シュウは未婚で自由の身であることを示す長い黒髪の女に惹かれた。長いこと見つめていると、その絵の中に吸い込まれて行った。何年かが過ぎ、戦士によってつまみ出されるまで、幸せな日々は続いた。シュウは現実の世界に戻り、メンを見つけた。メンは数分前からシュウを探していたのだった。ふたりが改めて壁画を見つめると、先ほどまで長い黒髪をしていた少女は、髷を結っている。それは既婚者の髪型なのだった、というお話。そして私たちも、プレルジョカージュの魔術にかかって、そのおとぎの話の中に吸い込まれた。
白い半円形のものがゆったりと舞い、雲のようにふわっと伸びる。白い幻想に包まれるようにこの物語は始まった。 ふたりの旅人に、黒い服の僧がからみ、やがて若い女性達の美しい壁画が現れる。四角い台の上に座った女性達は、長い髪を激しく振りながら踊る。それは女性の象徴でもある長い黒髪の美しさと神秘さ、そして内面からの女性としてのフェロモンを惜しみなく振りまいている。その中の白いワンピースの女性に惹かれたシュンが近づき、惹かれ合った男女の踊りになる。
込み入った要素のない物語ゆえに、いかに観客をその世界に引き込むかが作品の良し悪しになるのだが、変化に富んだ振付のコンビネーションと構成のうまさが、1時間20分という長さの作品を、あっという間に過ぎさせた。プレルジョカージュは振り付けにこだわる。どんな細部に渡っても、全て踊りで見せる。演劇的な要素も全てが踊りの振り付けなのだ。どんな囁きも、全てがダンサーの体を通した踊りで表現される。髪を結うのも踊りの一部。決して演技ではない。これがプレルジョカージュの価値なのだ。ラストを迎え、我々観客がプレルジョカージュの描いた壁画に吸い込まれ、官能な愛の世界に酔い、シュンとともに壁画の世界から出て、ポーズを取る女性たちの中に先ほどとは違う髪型の女性を見出し、現実に戻るのだった。
主役の女性を踊ったのは津川友利江で、華奢な体からは想像もできないほどのエネルギッシュな踊りを見せてくれた。しなやかでかつシャープ。これからバレエ団を支えていくダンサーのひとりになるだろう。そして、白井渚。彼女はプレルジョカージュのこと、そして彼の描く作品を深く理解して踊っている。カンパニーにとってなくてはならない存在のダンサーなのだといつも思う。
エクサンプロヴァンスのパヴィヨン・ノワールに本拠地を置いて10年、振付家として30年のキャリアを持つプレルジョカージュ。見るたびに作品の傾向が違い、アーティストとしての奥の深さには脱帽する。そして舞台作品だけでなく、「ポリナ」という舞踊映画まで作ってしまった。無尽蔵の才能を、まだまだ楽しめる。(12月9日La Comédie de Ckermont-Ferrand)

©Studio Constance Guisset / Jean-Claude Carbonne
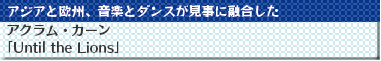
ラ・ヴィレットの広い会場の中央に円形の舞台。それを囲むようにして客席が設けられている。青い首が転がり、竹が突き刺さる舞台から白いスモークが時々上がり、ゴーという地響きのような音が聞こえている。飢えた獣のように舞台に近づく女は、警戒しながら何かを探している。時々立ち上がって人のようにもなるし、ググッとしゃがんで動物にもなる。竹を大地から抜き取り、首を拾い、そこに出てきた男に渡し、首は竹に突き刺される。生首だ。すると男(アクラム・カーン)が女を肩に担いで走り出てきた。舞台に下ろされた女は平静を装うかのように優雅にインド舞踊を始めた。しかし、カーンが舞台に上がると女は激しく頭を振り、上体を振って抵抗し、一気に緊張感が高まった。
これは、マハーバーラタの一部を題材にした物語で、女は王女で誘拐されてここに連れてこられ、生首は女の愛する人だったのだ。男カーンとの激しいやり取りは、舞台四隅に位置した4人のミュージシャンによる演奏と歌と、叫び声と、舞台を激しく叩く音でまくし立てられる。最初にひとり出てきた女は動物になり人になり、その間に入る。男と王女は決して抱き合うことなく、それでも女の情は移りつつある。円形の舞台が割れ、煙が吹き出し、盛り上がり、人を殺した罪なのか、男は女に竹を突き立てられ殺され、王女はただ無心に踊り続けるのだった。
3人のダンサーの高い身体能力とミュージシャンの激しくも美しい旋律は、効果的に場面を語り盛り上げ、終始一貫した緊張感に片時も目が離せない。コンテンポラリーダンスとインド舞踊、東洋と西洋の音楽が混じり合い、アクラム独特の壮大な世界に飲み込まれた感じだった。(12月5日ラ・ヴィレット/Théâtre de la Ville提携公演)

©Jean Louis Fernandez
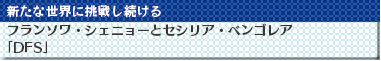
この1時間の中にどれだけたくさんのものを見たことだろう。経験したことや興味のあることすべてを作品にしたいと意気込むふたり。そのふたりが別々の場所でアンテナを広げてキャッチしたものをまとめたから、ポリフォニー、コンテンポラリーダンス、アフリカンダンスにアクロバット、トウシューズ、ダンスレッスン、そして犬まで、もうなんでも来いという感じ。演じる側もなんでもできちゃうしやってしまう。歌も上手ければ、ダンスも上手いし、女性3人がトウシューズを履いてスピーディにガンガン踊るのは、ブラボーと叫びたくなるほど。特に宮内エリカはフェッテ(もちろんトウシューズを履いて)は安定しているし、歌もうまいし、コンテもできる。透明な歌声にうっとりしたかと思うと、ハチャメチャパーティーが始まるし、客を舞台に上げてのダンスレッスンもあるし、その間を犬はチョロチョロするし。何が出てくるかわからないから、闇鍋ダンスとでも呼んでしまいたいくらいだ。
しかし、これらが何を意味するのか。体が引きあがらないまま無理矢理トウシューズで立っても美しくないし、ジャマイカから来たおばさんは何なのだろう。でも楽しい。ものすごく深く追求しているのに、とても安易に見えて、でもこの軽さが受けているのかも。(12月3日ポンピドゥー・センター)

©François Chaignaud
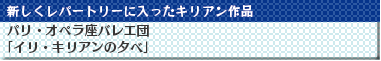
予定されていたチューダー/ミルピエ・プログラムがキャンセルになり、イリ・キリアンの夕べとなった。1995年初演の「ベラ・フィギュラ」は2001年にレパートリーに入っていたが、2006年の「Tar and Feathers」、そして1978年の「Symphonie de Psaumes」が新たにレパートリーに入った。
ガラスの箱に入った裸の人体が2つ空中に浮き、ダンサーたちがリハーサルをしている。これが開場時。そして急速に暗転になり「ベラ・フィギュラ」が始まった。
「レント」「グラーヴェ」「アンダンテ」「アダージオ」とタイトルがつけられた短いシーンが綴られていく。
黒幕に抱かれたアリス・ルナヴァンが、 前に出ては口に何かを入れるような仕草をしながらホリゾントに戻って黒幕に包まる官能的な幕開き。上手ではアレッシオ・カルボーネがシルエットで横たわり、次のシーンへと導く。「グラーヴェ」でのエレオノール・アバニャートのシャープな動きに見とれていると、上手から幕が閉まり始め、レティシア・ピュジョルとアレクシス・ルノーがだんだんと下手に追いやられていく。ピュジョルのしなやかな動きが素敵だ。サーッと幕が開くと、クリステル・グラニエとイヴォン・ドゥモルのアダージオ。グラニエはまだスジェだが、なかなか良い動きをしている。そして続くアンダンテでは、ドロテ・ジルベールとアレッシオ・カルボーネのデュエットとなる。ジルベールの踊りはしなやかで嫌味がなく、好感を持った。両サイドで、袖幕を掴んでは床に落ちる動きを繰り返すルナヴァンとピュジョル。ルナヴァンが幕を自分の体内に取り込もうとするのに対して、レティシアは幕を体全体で受け止めようとする。この違いが面白かった。そしてかの有名な赤いスカートのユニゾン「Stabat Masterの抜粋」となる。特にこのパートでは、女性の優しさと強さ、その神秘性を表現しているように思うが、ピュジョルが一番人間的で好きだった。ルナヴァンもアバニャートも悪くないが、強さがきつい動きに見えてしまう時があった。そしてラストの「静けさの中で」は、ジルベールとカルボーネのギクシャクしたような、それでいてコミカルなカップルを描き、相手の上がった片方の肩を優しく抑え合うふたり。カップルは、お互いの欠点を直し合いながら、支え合って生きていくものなのだと思った時に、男は両肩が上がってしまった女の肩を優しくおろし、何事もなかったようにスタスタと袖に入るところで幕となった。
音楽の使い方、動きの面白さ、幕を利用したシンプルながら衝撃的な美術、そして温かみを感じさせる作品に、キリアンの奥深さを感じずにはいられなかった。

「ベラ・フィギュラ」©Ann Ray/Opéra national de Paris
「Tar and Feathers」は、1枚の絵を見ているような美術に魅せられる。ごつごつした岩のような形の光を発するオブジェが上手前にあり、下手奥には長い脚のグランドピアノがそびえ立っている。微妙に変化する照明は、ピアノが靄の立つ湖面に置かれ、鏡のように反射したピアノの足が長く伸びているように錯覚させる。ここがガルニエ宮だと忘れさせるような美術の中、白く光る岩の後ろで女が口を開けたりしながら奇妙な動きをして前に進んでくる。女が隣の男のシルエットと重なった時、下手から足から現れた女が上手に進もうとするが下手に連れ戻され、再び現れた後は男とのデュエットになる。構成は綿密で、ひとつのシーンが終わる頃に別のシーンが始まり、時が過ぎ行くが如くシーンが変わっていく。そこに流れる音楽は複雑で、長い足のピアノを弾く向井山朋子のフリージャズ風の前衛的なピアノと、モーツアルトの録音されたピアノ協奏曲9番とが重なりながら綴られる。向井山朋子は即興演奏だが、ダンサーの動きにピタリと音を合わせ、この作品のために作曲された楽譜を追っているかのように溶け込んでいて素晴らしかった。ジャズとモーツアルトの高揚は、茶系のホリゾントに眩いばかりの光の筋がゆっくりと上下する中、幻想的な雰囲気を高めていた。
男女のデュエットの横で、白いロングチュチュをつけて、太い眉に真っ赤な口紅の男女が機械仕掛けの人形のような動きをしながら、「みんな死んだ」などと社会批判的なことを咳き込みどもりながら語るところで終わる。コールタールと羽、残虐な刑罰を連想させるタイトルのこの作品は、均整と奇異が混ざり合う不思議な世界を作り上げていた。なお、これを踊ったのは、ドロテ・ジルベール、オーレリア・ベレ、リディ・ヴァレイル、ジョシュア・オファルト、イヴォン・ドゥメル、アントニオ・コンフォルティの6人。

「Tar and Feathers」©Ann Ray/Opéra national de Paris

「Tar and Feathers」©Ann Ray/Opéra national de Paris
「Symphonie de Psaumes/詩篇交響曲」は、キリアン初期の作品で、宗教的な雰囲気を漂わせる作品だ。赤い絨毯が敷きつめられ、古びた椅子が並ぶ大広間のような場所での男女の踊りで、並べられた椅子に象徴されるかのように、ラインを生かした構成で、縦一列が斜めのラインになり、左右に流れ、横に広がり、群舞の構成の面白さを見せ、その中に男女の思いが絡む作品だ。マリー=アニエス・ジロのスケールの大きさを改めて感じたが、パブロ・レガサがキレのあるいい踊りをしていたのが特に印象に残った。(12月1日オペラ座ガルニエ宮)

「Symphonie de Psaumes/詩篇交響曲」©Ann Ray/Opéra national de Paris

フェスティバル・シューレーヌ・シテ・ダンス
25週年を迎えたシューレーヌ・シテ・ダンスフェスティバル。1月6日に25周年記念の開幕特別演目で幕を開けた。ヒップホップのフェスティバルだけれど、コンテンポラリーの振付家がヒッピホップダンサーに振り付けることもあるので、ひと味違った作品が見られるのが特徴だ。また、オーディションで選んだアマチュアダンサーを使った作品もあるので、若き才能の発見にもなるし、ここで育って羽ばたいていったダンサーも多い。2月5日まで開催しているので是非! 郊外はちょっと〜という事なかれ。パリから無料送迎バスが出ているので、安心して行けますよ〜。
http://www.suresnes-cites-danse.com

©Julien Benhamou / Adeline Goyet
勅使川原三郎 マルセイユとパリで世界初演
1月に東京荻窪の本拠地カラス・アパラタスで8日間のアップデートダンス「シェラザード」を公演したのちに、2つの異なる新作をマルセイユとパリで上演する勅使川原三郎。精力的に活動する勅使川原の世界初演をお見逃しなく!
2月9、10日にマルセイユのサラン劇場(Les Salins)で世界初演「Sleeping Water」を発表。
http://www.les-salins.net
そして、その後2月26日から3月3日までパリのシャイヨー劇場にて、同劇場用に新作「Flexible Silence」を上演する。音楽は武満徹とオリヴィエ・メシアンで、アンサンブル・アンテルコンタンポランによる演奏。アンサンブル・アンテルコンタンポランとは、2015年に藤倉大と勅使川原三郎によるハイブリッド・オペラ「ソラリス」以来の共演となる。
また、2月25日には「Jour de silence/静寂の一日」というイベントがあり、ドミニク・デュピュイらによるワークショップ(参加費12€)が行われるが、午後はジャン・ミッシェル・レイによる講習の後に勅使川原三郎のダンスが披露される。午後のパートは無料だが、要予約(01-5365-3000)
http://theatre-chaillot.fr/saburo-teshigawara-ensemble-intercontemporain-flexible-silence

「Sleeping Water」©Mariko Miura
3月のテアトル・ド・ラ・ヴィル
シャトレ広場の本劇場は2年間の改装工事中なので、アベス劇場以外は他の劇場との提携公演となっている。チケットは上演される劇場でも、テアトル・ド・ラ・ヴィルのホームページ、あるいはアベス劇場で購入できる。
3月3日〜7日 アベス劇場
イゴー & モレノ「Idiot-Syncrasy」
ベン・デューク「Paradise Lost」
ロンドン在住の異色アーティストによる2作品のソワレ。プレイスシアターでレジデントするイタリア出身のモレノ・サリナスとバスク出身のイゴー・ウルゼライは、それぞれのご当地ダンスの「飛び跳ねる」運動をいかに体力を消耗せずに作品にするかにトライ。
一方のベン・デュークは、大学で英文学を専攻していた時に、アラン・プラテルの作品を見て衝撃を受けてこの世界に入ったという。ミルトンの「失楽園」にインスピレーションを得て、ユーモアと言葉とダンスで綴るワンマンショー。
3月9日〜12日 パリ・フィルハーモニー
ロビン・オーリン「Beauty remained for just a moment, then returned gently to her starting position... 」
辛辣な社会風刺をユーモアたっぷりに描くことで人気のあるロビン・オーリン。ここでは一体何が飛び出すのか。しかも会場はフィルハーモニー。奇想天外な演出が期待される。なお、3月11日にはトークが企画されている。
3月15〜18日 アベス劇場
アンブラ・セナトール「Pièces」(仮題)
数年前にあちこちのコンクールで賞を取りまくり、一躍有名になったイタリア出身の若手振付家。1年前からナントのCCNのディレクターに任命されている。真面目なのにどこか抜けていて、現実とフィクションが混沌とした作品で人気がある。ナントでどんな活動をしているのか、興味津々。
3月25〜30日 104(ソン・キャトル)
エマニュエル・ガット
作品を毎公演ごとに改定してくから、作品がどんどん変わっていくので有名な振付家。今回上演される「Sacre」と「ゴールド」は再演ものだが、出演者も代わっているので、初演時とは全く違った印象を受けると思う。昔と変わっていなければ、「Sacre」はストラビンスキーの春の祭典の曲を使ったミニマルダンス。それなのにちゃんと生贄がいて衝撃的なラストを迎える。10年以上前に見たけれど、未だに忘れられない作品のひとつ。
3月29〜30日 MAC/Maison des arts de Créteil
タオ・ダンスシアター 「6/7」
テアトル・ド・ラ・ヴィルでは、過去にタオ・ダンスカンパニーの「4/5」と「6/7」を上演し、今回はクレテイユのMACで「6」と「7」を再演する。「6」は6人が出演し、「7」は7人が踊る作品で、列をなしての揃いのミニマル的な振り付けの中にトランスにも似たエネルギーを感じる作品。
http://www.theatredelaville-paris.com/discipline-danse-1
|

