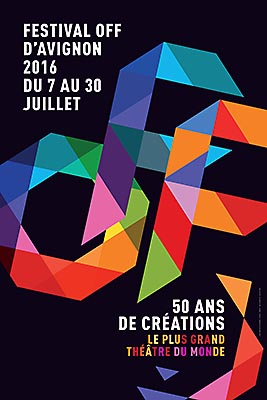
テロにもめげずに盛り上がるアヴィニヨン・オフ
インが70周年、オフは50周年。7月14日のニースのテロの翌日はキャンセルが相次いで、町はがらんとしていたというけれど、そんなことには負けていられない。自由と芸術を愛する者たちの祭典だぁ! でも、作品が売れなきゃどうしようもないアーティストの切実な叫びも聞こえてくる。見る方も体力勝負で、昨年ほどの暑さではないけれど、炎天下に列を作り、やっと開場かと思ったら入り口で荷物検査。大型トランクはどの劇場も持ち込み禁止だし、特にインは厳しくて、日焼け止めクリームはダメ、スプレーはダメ、保温魔法瓶はダメと、入り口はごった返している。入場にかなりの時間がかかるはずなのに、不思議に10分遅れ程度のいつもの状態で始まり、ほぼ予定通りに終演する。 いつもこのアバウトな開演ときっちり終わる終演には感心する。
今年のオフは7月7日から30日まで。年々上演数が増えていて、1,092団体による1,416公演が123劇場でと、この小さな町が人で溢れる世界最大規模のフェスティバル。1,416公演のうち、ダンスは55本、ダンステアトルが21本で、ヌーボーシルクが30本。演劇の数にはとても及ばないけれど、質の高い作品が多かったように思う。
日本からは3団体で、昨年に引き続き花柳衛菊が創作日舞を、井上まことがマイムを、桂サンシャインが落語を上演した。海外在住の日本人が出演している作品もあって、頑張れ〜!
これだけ数があるとどれを見てよいのか迷うが、劇場や地域圏からの推薦公演はあまり外れることはない。例えば、パリ郊外93県にあるルイ・アラゴン劇場がダンスと演劇作品をラ・パランテーズ劇場、ロワール地方はグルニエ・ア・セル、ランス国立舞台はカゼルネ・デ・ポンピエと提携している。これ以外にもセレクション・スイスがあるし、ダンス専門のCDCイヴェルナルやゴロヴィン劇場は要チェック。あとは公演前に長い列ができているかどうかも判断基準。口コミの力は強いからね。でもこればっかりは好みの問題でもあるから、その点はお手柔らかに。毎年朝10時に上質のダンス公演を上演していたコンディション・デ・ソワが提携の台湾のカンパニー以外は全て演劇になってしまったのは残念だったけれど、来年は新たな場所でダンスが盛り上がることを期待したい。
花柳衛菊「平家物語を語り継ぐ」
数年来、アヴィニヨンで自作の日舞を上演している花柳衛菊。毎年見ているとその成長が見えるのも頼もしい。日舞といえど伝統にとらわれず、モダンダンスのレッスンにも通ったという彼女自身の創作舞踊は、コンテンポラリーダンスと言ってよいだろう。一昨年と昨年は3つの小品の上演だったが、今年は1時間弱の「平家物語」で、日舞にも歴史文学にも精通していない私だが、「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の〜」くらいは知っているからどうにか理解できるかなと見に行ったのだが、篠笛と薩摩琵琶の演奏者ふたりを交えての5つのシーンから成り立った作品は、フランス人にも受け入れやすかったのではないかと思った。
「書」と題された最初のシーンは、手で空に文字を書くよう動きで見せ、続く「竹の唄」は、福原百之助作曲、福原道子の澄んだ篠笛の音に研ぎ澄まされる。打って変わって「手ぬ具衣」では、1枚の日本手ぬぐいがあっという間に形を変え、向きを変えただけの手ぬぐいで、花柳自身がおかめとひょっとこのような男女の会話を描く。手品のように形を変えていく1枚の布の面白さに加え、花柳のコミカルで軽快な動きが微笑ましい。ほくっとした後は、壇ノ浦の語りを薩摩琵琶の坂麗水がひとり小さなスポットの中で演じ、語る。まさかアヴィニヨンで琵琶の生演奏による壇ノ浦を聞くとは思わず、フランスどころか日本でも滅多に見られない琵琶の演奏と語りを聞けたのは貴重だった。入場時に手渡された紙に壇ノ浦の語りが簡単に説明してあったが、これはやはり字幕スーパーで語りの内容を訳して欲しかったが、何しろアヴィニヨン個人参加のレベルではそこまでの予算が出るはずもなく、どこかのプロデューサーが作品を買い上げてくれるのを期待するしかない。そして最後の章は「徳子」。平家一門で唯一生き残った女性を描き、悲しみの中にも平家の人として誇りを持って生きる姿が描かれていた。
踊りあり、演奏ありの変化に富んだ構成で、平家物語を知らずとも、着物の美しさに見とれ、篠笛の繊細な響きと薩摩琵琶の強い弦の響きと唸るような壇ノ浦の語り、そして日本舞踊独特の静かでありながらも強さを秘めた動きに感動した人は多いはず。
日本で創作日舞の活動を続けていくことは容易なことではないと思うが、コンテンポラリー日舞として海外で受け入れられる可能性を秘めた作品だと思った。(7月17日ガラージュ・アンテルナシオナル)

「平家物語を語り継ぐ」©Haruhisa Yamaguchi
ダンスを見るならやっぱりCDCイヴェルナル/Les Hivernales
ディレクターの辞任問題で揺れたイヴェルナルだけれど、セレクションは良かった。朝10時から2時間ごとに7団体が上演。その中で、台湾のポ・チェン・ツァイの「Floating Flowers」はよくできていたと思う。1時間ほとんど動きっぱなしのエネルギッシュな作品で、それでいて美的。これが多くの人の感想だった。確かに。男も女もロングチュチュを履いて、腕を揺らし、腰を振り、スカートを持ち上げて、スピーディーに動いたかと思うと、ゆらゆらと浮かぶように揺れている。ひとりで踊っているのかと思ったら、にょっきりと足が出て、2階建ての巨人になった。細身の女性の割には筋肉質の足だけれど、自由奔放に動く女性を支えながら踊るには、かなりの筋力が必要だろう。それにしても、ふたりで踊っているのにまるでひとりが踊っているように、上体と足の動きが一致している。お見事! このシーンがあちこちで取り上げられていたが、それ以外のシーンも見応えがある。似たような動きの連続なのに、構成を変え、スピードを変えてニュアンスをつけているから、作品にメリハリがあり、あっという間の1時間。これを踊りこなしたダンサー達もすごいが、振付家のポ・チェン・ツァイの活動をもっと知りたくなった。(7月18日)

「Floating Flowers」©jean Couturier
ただあっけにとられて見ていたのが、シルヴァン・ウクの「Boys don’t cry」。「クライ」というから悲しみに満ちた少年の物語かと思ったら大違い。
しょっぱなからハイテンションな男は、まるでボクサーのようにステップしながらジョブともヒップホップともつかない激しい動きをしている。これを3回立て続けにやったら、普通の人なら動けなくなるだろうと思うけれど、さすがプロのダンサー、ゼーゼー息を切らしながら続けている。見ている方が心配になる程だ。もうひとりが出てきてこれまた激しく動いている。なんなんだこのテンションは? ふたりはライバルなのか、いかに優位に立つかで競っていたが、それが取っ組み合いになり、その横でドラムを叩く男まで、まるで戦っているかのように激しく叩き、ドラムのバチを振りまき、もう舞台は混乱状態。体をぶつけ合い、叫び、何を好き好んでそんなに暴れまくっているのかわからないけれど、ここまでやってくればあっぱれだ。(7月18日)

「Boys don’t cry」©loran chourrau
独特な表現方法で注目されているペリーヌ・ヴァリは、セレクション・スイスに選ばれて「Une femme au soleil」を上演。ゆったりとしたリズムの中で、女性がふたり、四角く囲まれた緑の地でシンメトリーに動いている。タイトルから想像した夏の強い日差しを浴びる女性のイメージとは違い、暗いステージに落ちるスポットの中での踊りで、そこに感情があるわけでもなく、淡々とポジションを変えていくふたりの女性の姿がある。双子のような、あるいは鏡に映ったような、でも、別々のふたり。後半大柄な男性がふたり現れてのコンタクトとなる。
特定の物語があるわけでもなく、感情が露わになるわけでもなく、延々と繰り返されるリズムに乗って、止まることのないムーブメントが連なっていく。気だるいような、それでいて後腐れのない爽やかさ。ミニマルのようでミニマルではない動きと構成。ふたつの対照的な要素がひとつの空間に混在している。この微妙なニュアンスが好きだった。(7月18日)

「Une femme au soleil」©Dorothée Thébert
久々に見たクローディオ・ベルナルドは、表現者として一皮むけたように思った。踊りはうまいけれど、作品はインパクトに欠ける印象が残っていたのだが、今回見た「So20」は、回顧録的作風で、飾らない彼の今の姿に好感を持った。ブラジルで生まれ、決して裕福でなかった幼少時代、そしてベルギーのムードラへの留学。ベジャールが彼に言った一言がきっかけで振付を始めた…。自身の生い立ちを語る手法は観客の心を捉えやすいが、時折短いフレーズを踊りながら語る顔は明るかった。若いとは言えない年代になってしまったが、踊りのうまさは昔と変わらない。踊ることだけにとらわれず、ありのままの自分を肩肘張らずに表現する姿に好感を覚えながら、舞台で表現するということ、作品とは何なのかを考えさせられた。(7月18日)

「So20」©Jean-Luc Tanghe
ヒップホップは超人気で、簡単に客が呼べてしまうから、長蛇の列に頼らずに下調べをしてから見に行かないとガックリする羽目に。そんな中でブライム・ブシュラゲムの名前を目にした。2年前にイヴェルナルで見た作品は、ヒップホップといえど非常にエステティックで、イスマエラが舞踏のようなヒップホップを踊っていたのが印象に残っている。
今回の「What did you say ?」は、ビデオやシルエットを使いながらのソロだった。気がつかないほどのロースピードでズックが光の道を下手に流れ、上からは言葉と絵が描かれたモノクロの蒔絵がゆっくりと降りて、波のように床に溜まっていく。ストリート的なヒップホップを踊っていた人が通り過ぎ、床に浮き上がった白い文字に誘われて、ミステリアスな踊りが披露される。光に満ちたホリゾントの前でしなやかに踊る影ともうひとつの影。ソロなのにたくさんの人物像が描かれ、ブーシュラゲムの踊りの幅の広さが凝縮されている。
夢と現実、今と過去。淡々と過ぎる時の中で多くの人の人生が流れ、今を成す。ポエティックなヒップホップは、カロリン・カールソン自筆の絵と語りにもよるところが大きい。(7月18日)

「What did you say ?」©Frédéric Iovino
イヴェルナル劇場の夜10時からの公演はいつも強力なのだが、今年もやっぱりそうだった。ソル・ピコの「One-hit wonders」は、行く先知らずの飛行機に乗ってしまったピコの奇想天外な旅だった。しかし、そこに行くまでの冒頭の部分がすごい。まるで漫画。バレエとコンテンポラリーとフラメンコと中国武道とファッキングポーズと○△×が混ざった見たこともないようなダンス。あっけにとられていたら、今度はサボテンの植木鉢の間を目隠しして踊る。行き先不明の飛行機から降りたら、予想外の展開が待っていたのだ。アイディアがありすぎという感じがしたのは、ピコのピュアーなダンスを見たかったからかもしれない。まともにバレエを続けていたらプリンシパルになっていたと思うほど上手いけれど、その性格上、ひとつのところに収まらなくて、こうして独自の世界を作っているのだと思う。トウシューズでのスパニッシュは一見の価値あり。(7月18日)

「One-hit wonders」©rojobarcelona
ゴロヴィン劇場もダンスオンパレード
ダンス作品だけを上演しているので要チェックの劇場。今年はヒップホップ作品が多かったように思う。ここでは何と言ってもジュリー・ドサヴィ「La JUJU」が圧巻だった。
独創性のあるパフォーマーとして有名で、その押しの強さ、存在感の強さには定評があるが、こうして間近で見るとその迫力に改めて驚かされる。マジで半端じゃない。男を抱える後ろ姿に、ドサヴィの真似をした男かと思ったら本人だった幕開きに見られるように、体格も存在そのものもたくましいのだ。ミュージシャンのイヴァン・タルボの細身の体が潰されそうだが、彼もなかなかのやり手。ドサヴィの機嫌をとりながらも、うまくかわして自分のやりたいようにやってみせる。この駆け引きが面白い。そのくらいの度胸がなければドサヴィの相手はできないのだけれど。このふたりのトンチンカンなようで、まとまりのある50分を大いに楽しんだ。何がどうというより、舞台に立つということはどういうことなのか、作品に入り込むということの意味、それをピシリと見せてくれる。舞台に立つ人は絶対に見ておくべきパフォーマー。勉強になります。(7月21日Théâtre Golovine)

「La JUJU」 ©Grégory Brandel
ジャン・ガロワの「Compact」は既に見ていたけれど、せっかくだからと見に行ったら、前回とは違う印象を受けた。丸くなったというか。本人は変えたつもりはないと言っていたが、生身の人間が踊り続けるのだから、自然とニュアンスが変わるのは当然のこと。ふたつの体がくっついている最初の構図は、以前の未確認物体の形の面白さというより、くっついてしまったふたりのあーでもないこーでもないの会話で、仲が良いのに喧嘩をして、なんでこーなっちゃったの? これ、あんたの足? え、どこに行くの? ふ〜全くぅ! などの会話が聞こえてくるようだった。ラストは前回見た時のような衝撃性には欠けるけれど、丸く収まった微笑ましいラストだった。これからも各地をツアーして回るようだが、次に見るときはどんな展開になっているのかしら。(7月22日)

「Compact」©Laurent Paillier
「コンパクト」でジャン・ガロワの相手役をしているラファエル・スマジャも自作のデュエット「Domino」を上演。白いテープがいくつもの四角い枠を床に描いていて、迷路に入り込んだようなふたりの会話が始まる。ヒップホップベースだけれど、そのテクニックを使ってのコンテンポラリーダンスという感じ。最後にゴールに行き着くのかと思ったら、はがしたテープで人の顔を作ったオチがいい。(7月22日)

「Domino」©Stemutz
男女の物語、しかもコンタクト。ポスターのイメージに期待せずに見に行ったのだが、これがなかなか良かった。エマニュエル・グリヴェの「Duo 1」は、男女の行き違いを感情だけでなく、繊細な動きで表現していたのがいい。ひとり? それともふたり? お互いの距離が少しずつ離れていく。このまま背を向けてそれぞれの道を行くのか、あるいは受け入れながらふたりの道を進むのか。そんな男女を緻密なムーブメントで綴ることで、サラリとしていながらもドラマチック。これが、どこにもありそうだけれど、一味違う作品に仕上がっている理由だと思う。静かだけれど、とても印象に残った。
抱き合わせて上演されたのが、振付家のエマニュエル・グリヴェ自身のソロ「Résonnance(s)」。あいにく「Duo 1」の印象が残りすぎていたのと、ナレーションを理解するだけの余力がなく、作品に入るこむことができなかった。自作自演となると思いや感情が入り込みすぎるように感じたのと、私自身が「Duo 1」のようなクールな作品を期待していたからかもしれない。(7月21日)

「Duo 1」©Guillaume Fraysse

「Résonnance(s)」©Mihai Mangiulea
今年のゴロヴィン劇場はヒップホップ作品が多く、10作品中5作品がヒップホップだと、どうしても客が分散してしまうようで、ジュリアン・グロの「Mauvais rêve de bonheur」のような地味なヒップホップは、よくできているのに会場が埋まっていないのは残念だった。上演時間帯にもよるのか、作品紹介文が暗いからか。孤独の中で行き場を失った男を描いている作品だけれど、これといって暗くもなく、自己の存在を見つめようとする作品で、しっかりしたヒップホップのテクニックを織り込みながら、心情を淡々と語る。派手な展開がある作品ではないけれど、きちんと構成されていたのがいい。これからの独自の追求を期待したい。(7月20日)

「Mauvaise réve de bonheur」©caillou-photographie
マニアックなロワール地方のダンス グルニエ・ア・セル/Grenier à sel
ロワール地方のセレクションはマニアックというか、とっても真面目な作品が見られる。「真面目」というと変だが、地道に探究を続けているカンパニーが選ばれている感じがして気に入っている。
ダンサー・振付家として定評のあるダヴィド・ドルオーの「(F)AUNE」は、2メートル以上もある大きなクマのぬいぐるみに意表をつかれた始まりだった。ドビュッシーの牧神の午後の冒頭部分が流れるも、巷の「牧神」は出てこない。大きなクマのぬいぐるみがおどおどしたように歩き、強い光に当てられて後ずさりして倒れる様子は、餌を求めて里に下りたクマが無残にも撃ち殺されるようだった。ところがこの後に光り輝く生命の誕生をイメージするシーンに、牧神が現世に再生したような神秘的な印象を受けた。白く輝く物体から足が出て、頭が出て、生を受けてこの世に降りた無垢の生き物は、未知の世界に戸惑いながらも居場所を求めて突き進んでいく。服を着た後は、クマのぬいぐるみの腕を引きちぎり、傲慢で暴力的な動きに人間のエゴイズムを見出したのだが、本人は子供が大好きなぬいぐるみの中身を見たくて、興味半分で壊してしまうイメージだという。この解釈は意外だったが、生命の循環の中で生きる人間が、自然の法則を破壊していく現代を描写しているようだった。現代には優雅な牧神はもういないのだろうか。(7月17日)
身体のあり方を追求しているのが、ジュリー・クタン。2年前にもここで上演していたが、今年はソロとデュエットの2作品で参加。
ソロはアンヌ・モレルのコンセプションに振り付けして自演した「Trace Antigone」で、ジーンズに手を突っ込み、苛立たしそうに片足を引きずりながら歩き回っている。曲がらない膝の理由は、剣が入っていたから。取り出して自由になった体は、何かに憤るようにホリゾントに当てられた3枚の絵を見つめ、はげしく踊る。その姿がリュック・ベッソン監督の映画「ジャンヌ・ダルク」と重なったのは、使命を全うしなくてはならないという正義感を垣間見たからかもしれない。現実と理想、悩みや迷いを抱えながらも前へ進もうとする意思は、時に怒りのように燃え上がり、時に消え入りそうになる。生きることは戦いなのだろうか。
数日後に見たエリック・フェッセンメイエとのデュエット「Suite」は、出色だった。向き合う体、20センチほどの距離を置いているだろうか、そのふたつの体は決して触れ合うことはないが、身体から発せられるエネルギーがバイブレーションとなって相手に伝わり、跳ね返る。ふたりなのにひとつの輪の中にいるのがはっきりわかる。無言の会話だがその強さは半端じゃなかった。これはビデオでは感じられない。劇場で実際に見るからこそ伝わるエネルギー。20分ほどの濃厚な時間に満足。(7月21日・23日)

「Suite」©Xavier BOURDEREAU
ルイ・アラゴン劇場はラ・パランテーズ
パリの隣93県のルイ・アラゴン劇場が送り込んでいるのがラ・パランテーズ。ダンスは朝10時から、ダンステアトルと演劇は午後7時からで、30分ほどの作品が2〜3作品上演される。すでにパリで見た作品が再演されることもあるけれど、場所が変われば雰囲気も変わる。
「コンパクト」を夕方からゴロヴィン劇場で上演しているジャン・ガロワは、朝10時にはここで「Carte blanche」 を踊るというハードなスケジュールも難なくこなしている。「Carte blanche」 はアヴィニヨン特別版で、開放的なアヴィニヨンの雰囲気に合わせて、観客とやりとりしながらの遊び心たっぷりの作品。番号が書かれた紙とマイクを客席に回し、マイクを手にした人が数字を選び、その番号に当てられたフレーズを踊るというもの。3のフレーズを踊っている間に別の人が2と言えば、2の動きに即刻切り替える。途中でゴングが鳴った後は、名指しされたダンサーがその番号のフレーズを踊るわけで、三人三様の踊りが見られるという仕組みだ。短いフレーズといえど、30分踊り続けるわけで、これはかなりの体力がいるし、意地の悪い客に当たれば次々と変わる番号に混乱するやらハードな動きばかりを踊らされるやらで、見ている方は笑っていられるけれど、踊る方はかなり大変。ここで面白いのが、疲れてくると3人の素顔が見えてくるところ。最初は真面目に踊っているものの、観客に振り回されるうちに堪忍袋の緒が切れたのか、マリー・マルコンは落花生をばら撒き始めるし、アロイーズ・ソヴァージュは喉が渇いた〜、誰か水ちょうだい! と客席にまで上がってくる。振付したジャン・ガロワは責任上真面目に踊っている。この3人の個性が面白い。人間パニクるとこうなるこのかと。特にソヴァージュはアドリブがうまく、きついフレーズだと客席に向かって「ちょっと〜やめてよ〜」とか、お気に入りの楽なフレーズのリクエストには「こりゃいい!」。誰かが存在しない番号を言えば、しばらく考え込んだ後に「ま、こんなのもいいかもね、悪くないよ」と言いながら「マカレナ」を踊りだしたのには大爆笑。毎回何が飛び出すかわからない作品だから2回も見てしまった。アヴィニヨンだけのバージョンなのがもったいない。(7月22日)
数年ごとにここで上演しているエルマン・ディエフイスは、ダンサーの個性を引き出すことに長けている。「Prémix」では、すでにディエフイスの幾つかの作品に出ている太っちょおばさんのダリア・カティがいい味を出していた。
カティは歌手で、オペラ作品でも歌っているけれど、役者としても活躍している人。この強烈なおばさんに対抗するのが若きマルヴィン・クレック。今時の若者らしく、リズムに乗ってヒップホップを踊りまくる彼に、カティが食いかかる。あっけにとられるクレック。太っちょとやせっぽち、おばさんとガキ、チビ背高のっぽ。全く違うふたりがだんだんに歩み寄っていく様子が描かれた作品で、朝一番に見る作品として気持ちの良いものだった。(7月21日)

「Prémix」©Teilo Troncy
今年のダンス・エラルジーで1位になったミスカル・アルガー(Mithkal Alzghair)は「Déplacement」のソロバージョン。底の厚い編上げ靴を履いて、ドンドンと音を出しながらステップを踏み、手を後ろに組んで冷めた目を客席に向ける。上から誰かに押し付けられたように膝が折れて膝立てになったのは、囚われたのを意味することがはっきりわかる。それでも穏やかな表情で、時にうっすらと微笑見ながら客席を見渡している。しかし、目は絶え間なく動き、落ち着きがない。戦争状態のシリアで、時に強制的に、時に自主的に街から街へと移動を余儀なくされる人々の様子を描いた作品で、生き延びるために敵をカモフラージュしながら移動する難民の様子が伝わってくる。ただ歩くだけの30分だけれど、こうして間近で見ると、テアトル・ド・ラ・ヴィルで見たときとは違ってインパクトは強い。(7月22日)
ランスも真面目です
ランス国立舞台はカゼルヌ・デ・ポンピエと提携していて、幾つかの作品を送り込んでいる。マリネット・ドズヴィルは完全暗転になる劇場で照明効果をフルに利用した作品を2本。
暗闇の中にぼんやりと浮かび上がる赤い色。それが目の錯覚ではなく、毛皮のようなものが赤いライトに照らされて、しかもゆっくりと呼吸するように動いていることに気がつくまでにものすごい時間を要した。実際に長かったのか、長く感じたのかはわからないが、その不思議な光景に吸い込まれていくような感覚で、時間が経つのも忘れて見ていると、その毛皮はやがて起き上がり、そこにちょこんと乗った頭が動物の不気味さと相反してお茶目にも見えるのだが、空気を漂うように移動する姿は、殺された動物の霊が森の中をさまよっているようにも感じた。「Mu」。これは「無」でもある。
「Saison 1&2」は、「春の祭典」リメイク版に乗って体そのものにCGを投影した作品。装置はなく、白い全身タイツの彼女が踊るだけなのだが、前作の「Mu」同様、自然の中で踊っているような印象を受けた。木はないのに森を想像させ、川があり、草原がある。決して派手な作品ではないけれど、よく練られた作品は見応えがある。(7月20日Caserne des Pompiers)

「Mu」©DR

「Saison 1&2」 ©DR
もうひとつ、ランス国立舞台推薦作品のダンステアトル「La tête des porcs contre l’enclos」は、振付家のマリーヌ・マンの自叙伝的作品。家庭内暴力に耐えた幼少時代のことや、その後のことなど、決して明るい話題ではないが、生きる希望を失わない姿勢に救われる。この作品を見ようと思った理由は、ひとりのアーティストが台本を書き、動きを作り、それをどのように演出して作品に仕上げるかに興味があり、セリフと動きのバランスを見たかったから。想像していたよりセリフの量が多く、ダンスというより抽象的な動きで綴られる。暴力から逃れるために隠れた半透明の箱は、恐怖より肌の温かみを伝え、体に描かれた線は、傷跡というより身体の構造に見える。インパクトの強いセリフは、こうして動きと美術によって薄められ、淡々と綴られることで返って心にじっくりと伝わる。アヴィニヨンの暑さとお祭り的雰囲気とは程遠いが、こうして良質の作品を見られたことは大きな収穫だった。(7月20日Caserne des Pompiers)

「La tête des porcs contre l’enclos」©Caroline Ablain
ダンスがメインでない劇場も要チェック、美味しい作品がありますよ
口コミの強さを見たのが、アリス・キンとテオ=モガン・ギドンの「Lenso」だった。すれ違うのがやっとというほど狭い路地にあるローレッタ劇場の前が埋まっている。フェスティバル中盤までの上演で、しかもたった30分の作品なのに、噂はこれだけの人を集めてしまう。
さて、若いダンサーにはお金がないことが多く、若き頃のダニエル・ラリューがそうだったように、このふたりも公園や空き地をスタジオにしているらしい。
無音の30分のデュエットは、路上で作ったとは思えないほど綿密な構成になっている。男と女の関係を描いた作品は、よくありがちな愛の物語ではなく、ひとつの空間に存在して、空間と感情を分かち合う二人の素直な姿が描かれていたのに好感を持った。ぶつかり合い、手を引き合い、寄り添いながら前に進もうとする二人。男には男なりの、女には女なりのやり方がある。わかってもらえなくても、時間をかければわかってもらえる。そんなふたりの会話が聞こえるような作品だった。
ふたりとも基礎のしっかりしたダンサーで、ギドンの甘いマスクと力強い動きに見とれたが、キンのニュートラルな動きが心地よく、すっきりしたムーブメントの端々に見える微妙な感情の表し方に好感を持った。(7月18日Laurette Théâtre)

「Lenso」©Lizzie Hornshuh
アヴィニヨンの城壁の外に少し出るだけでも躊躇するのに、バスに乗って隣町まで行くのをためらう人は多いはず。バス停を探すのはややこしいし、時間はかかるし。しかし、行くだけの価値があるのがヴィルヌーヴ・レ・ザビニヨン/Villeneuve les AvignonでのフェスティバルVilleneuve en scène。アヴィニヨン・オフと提携しているけれど、独立したフェスティバルなので、詳細は直接問い合わせるのがよいようだ。川をふたつ渡り、坂を登ると中世の街並みに入る。アヴィニヨンのゴタゴタとは打って変わって、静かな時間が流れているのが新鮮だ。この小さな町のあちこちで演劇・ダンス・サーカスが行われている。今回の目的は、ジャンクロード・ガロッタの後を引き継いでグルノーブルのCCNに本拠地を置くヨアン・ブルジョワの公演「Tentative d’approches d’un point de suspension」で、会場はサン・アンドレ要塞。アヴィニヨンから川向こうの丘の上にそびえ立つお城のような建物が以前から気になっていたので、公演を見るついでに場内を見学できるのはラッキー。

「Tentative d’approches d’un point de suspension」©Cie Yoann Bourgeois / Villeneuve en scène
新作ではなくて、これまでの作品の抜粋だったけれど、14世紀の建物の中で見るのはひと味どころか二味以上も違う。広い敷地の中に11箇所のパフォーマンスが隠れているから、内部を見学しながら驚きの一場面に出くわすことになる。これはなかなか楽し。円筒形の大きな水槽の中で漂う人、トランポリンを使って壁をよじ登る人、空気に立てかけられたはしご、ひとりでに踊る椅子、戦いにも見える男女の無言の会話。眼の前で自分とは重力も重心も違う空間が広がっている不思議さ。そしてここは14世紀の建物。この異次元な世界が、アヴィニヨンの町から数キロのところで体験できる。しかも、ワークショップ付きなので、実際に無重力地点を体験できる。椅子に座ってできる簡単な動きに、見ている方からもほーという声。不思議が身近になった。最後に見学者全員が行き着いたのが、途切れる階段を登っては落ちる人のパフォーマンス「Cavale」。夕日をバックにシルエットになった二人の男が、何度も階段から落ちては戻り、最後は夕日に向かって消えるという印象深いラストで締めくくった。(7月17日Villeneuve en scène)
アヴィニヨン、特にオフはお祭り的なイメージがあって、その勢いで劇場に入ったら結構シリアスな作品で、ちょっとブルーになってしまうこともある。そんなときには深く考えずに楽しめる作品でリフレッシュするのもいい。オーレリアン・ケロの「Un petit pas de deux」はそんな作品だった。ダンスのオーディションになかなか受からない男女が出会って、運よくふたりを気に入ったプロデューサーの元で新作を作り始めるという物語。ヒップホップ系のふたりが、面白おかしく、ドタバタ劇も含めての1時間。3年前に見たニーチェの晩年を描いた作品が強く印象に残っていたので、このような楽しい作品を期待していなかったのだが、外の暑さも、秀作を求めてアンテナを張り巡らすストレスもぶっ飛んで、リフレッシュできたのはありがたい。大衆受けする作品を低く評価する人もいるけれど、老若男女多くの世代に受け入れられるということは、作る側にたくさんのアイディアとそれを表現する技術、そしてそれをまとめる力がなければできないのだとつくづく思った。(7月20日Théâtre des Luciore)

「Un petit pas de deux」©Compagnie De Fakto
3年前に見た「Le sacret de la petite chambre」の繊細さが忘れられないでいたが、今年は別の作品でアヴィニヨンに戻ってきてくれた。「L’Objet du Délice」、振付家のマーク・ティリエの自作自演のソロだ。ゆっくりと浮かび上がった円形のスポットの中でうずくまる男の背中。青いライトに浮かび上がった床の模様の中で、地からのエネルギーを吸い上げるように男の背中が揺れて、やがて立ち上がる。オーラを発し、トランスに入っているような動きは宗教儀式のよう。張り詰めた空気が伝わってくるのだが、濃厚過ぎて食傷気味になってしまった。エマニュエル・グリヴェの「Résonnance(s)」の時同様、自作自演となると感情が入り込みすぎるのかもしれない。(7月22日Théâtre du Girasole)

「L’Objet du Délice」©Collectif Zone libre
ダンステアトルを怖がることなかれ
ダンステアトルは言葉があるけれど、結構雰囲気でわかるもの。頭の中で3回転しそうなほどの難しい言葉は出てこないのが普通だから、ポスターを見て面白そうな「Happy Hour」を見に行った。
舞台に明かりが入ってから気がついたのだが、マウロ・パッカニェラとアレッサンドロ・ベルナルデシはカテリーナ・サーニャの作品に出ていた一風変わったおじさんたちだった。彼らのキャラクターが変わるわけはなく、やっぱりおかしなおじさんたちで、いい加減なようでちゃんと構成された作品は、「こんなシーンをやってみよう」と、会話の成り行きで短いシーンが演じられる。かつらをかぶり、布をまとって役になりきって演じるけれど、なにせ男ふたりだからどこか間が抜けている。意見が合わなければ喧嘩のようになってしまうし、話はぶっ飛んでしまうし、でもちゃんと踊って見せたりして、脈絡のない出来事が続いていく。イタリア語も出てくるのでさっぱりわからないけれど、なんだか可笑しい。暑くてやってられないよ〜とマウロが出て行った時には一瞬会場が真っ白になってしまったが、ビールを持って戻ってきたのには大笑い。ハッピーアワーの時間ではないけれど、こうしてふたりで楽しんで演じているのが、イタリア人らしくて好きだった。(7月20日Théâtre des Dôms)

「Happy Hour」©Alice Piemme
ここ数年興味を持っているのが、ダンステアトルと子供向けの作品。ダンステアトルは、ムーブメントとセリフのバランスがどのように取れているかを見たいし、子供向けの作品、つまり3歳以上などと書いてある作品は、忍耐力のない子供をいかに1時間集中させながらテーマを語るかという難題がついてくるわけで、そのためには綿密な構成と演出が必要になり、大人向けの作品とは異なる難しさがある。子供向けだから面白おかしくドタバタやれば良いというものではないわけだし。
ヤン・ジレドゥの「L’imaginarium」が良かったのは、見る側の想像力を刺激するところだった。2メートル四方の四角い枠の中で「昔むかし…」のナレーションで始まる物語。薄い布のむこうには小さなベッドがあり、眠りの森の美女のような寝顔が見えるのだが、ささっと布が丸められて出てきたのは男だった! と、ちょっと驚きの始まり。丸められた布は旅の荷物となり、ひもやスチールの枠の位置を変えれば、汽車が走るレールになるし、スルスルとオブジェが移動して、吊るされた帽子が上下する。ライトを利用して壁に色ガラスを投影したり、小さなミラーボールで星空を演出したり。最低限のスペースの中で、少ないオブジェがどんどん世界を変えていく。演じるヤン・ジレドゥは、きっちりとダンスの基礎のできた人で、オブジェを操る以外はダンスの振りで見せてくれる。演劇やマイムと違って、ダンス特有の抽象的なムーブメントなので、イマジネーションを駆使しながら見るのが楽しい。手の内や結果を見せてくれないと満足しない人が増えているように感じることが多いので、このような見る側の想像力を優しく刺激してくれる作品が嬉しかった。
制作がCCNバレエ・プレルジョカージュというのにも納得で、ヤン・ジレドゥからの手作りの贈り物に心が温まった。大事にしてほしい作品だ。(7月17日Artéphile)

「L’imaginarium」©Didier PHILISPART
ブリジット・ムニエ「フクシマ」
演劇だけれど、タイトルを目にして迷わず見に行った。東北大震災で大きな被害を受けた福島。そこに住んでいたフランス人ミカエル・フェリエの体験記を台本に、女優のブリジット・ムニエが演じる。
地震、津波、その後の3部構成で、当時の状況を作品として、美的しかも的確に表現していたのが見事だった。
激しい揺れに、本が落ちてくる中を右往左往する。この混乱の後に中央の障子が開けばそこは海。水の中の不気味な静けさの中を、生活用品や人が浮いたり沈んだりしている。濡れた髪を拭きながら出てきたムニエは、大きなお膳を出した。食卓の用意だ。椀、茶碗、湯飲み、皿。しかしそれらは被害にあった町の位置関係を示すもので、大きな水差しから水をこぼせば、あっという間に食器が倒れるように町も壊滅したと語る。そして原発センターの爆発。
フランスのメディアは当時たくさんの映像を流したから大体のことは知っているけれど、体験記をこうして目の前にさらされると、当時の恐怖や被害の大きさがより明確に実感できる。位置関係をお膳で表したのはうまいと思った。
文字という平坦なものを立体にしたムニエ。この作品が福島の未来を語るものではないけれど、起きてしまった事の重大さを示すには十分な作品だった。(7月24日Présence Pasteur)


