
5月下旬に公演予定だったのに、80歳の出演者が骨折したために9月に延期になっていた。80歳の出演者!? 骨折? 今回は、骨折した人とは別の出演者で再演。土に半分埋もれた地下に住む家族の日常を描く。山積みになった土の中から人が出入りしたり、アクロバットの連続など、このカンパニーらしい発想と構成。「庭」「サロン」に続くシリーズで、生と死を背景に社会問題を風刺している。ここでは、前作で出てきた子供は死んだようで、子を失った母親の異常な振る舞いと、老いた母親の面倒を見なくてはならない嫁の立場との二面性を持つ嫁と、現実をどこまで把握しているのかわからない夫、そしてこの家庭を冷ややかに見る看護婦が強烈な印象を残した。壊れかけた家族を描き、シニカル度は今まで以上のパンチ。新聞の三面記事に載る家庭内の問題を目の当たりにしたようで、ずっしり来てしまった。(9月12日アベス劇場)
 (C)Jean-Pierre Maurin (C)Jean-Pierre Maurin
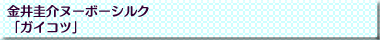
日本人でこの手のサーカスをする人がいるなんて! サーカスと言うと、動物芸とピエロをすぐに思い浮かべる人が多く、今こちらで流行のアクロバットダンスを想像する日本人なんかいないと確信していた私にとっては画期的な公演だった。シビアーに批評すれば、まだまだ上達の余地はあるものの、オープニングの奇妙な物体が変化していく様子は超面白かったし、せり出して見える装置が、実は非常に単純なものだったりとアイディアは素晴らしい。スタッフは、フランス人と日本人のコラボレートで、日仏の交流が微笑ましく、フランス人が金井さんの事を心からサポートしている感じがサンパ。金井さんが新しい風を起こしてくれる事を期待しています。(9月13日パリ日本文化会館)

(C)Alberto Pitozzi
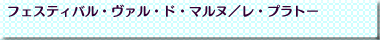
パリの東隣のヴァルド・マルヌ県で、若手を応援するフェスティバル「レ・プラトー」が催された。作品を買いにくるプロモーターのためなのか、多くの公演は平日の日中に行われる。私は一般公開された公演へ行ってみた。
ジョアンヌ・レイトン「5 EASY PIECES」(ベルギー)
今年の夏のアビニヨン演劇祭中に、スタジオ・イヴェルナルで彼女のソロを見たばかりだった。この作品は、レイトンを含む5人のダンサーによる短いシーンの連続。1人のダンサーが1~5の数字をトリック的に見せ、それでシーンが展開していくのはちょっとサスペンス風。ソロ、デュエット、トリオ…。状況は変わるし、ダンサーは素晴らしく良く動くし、コンタクトは面白い。なのに、30分が長く感じてしまうのは、動きに流れがないからではないか。つまり、短い踊り或は動きの連続で、そこから次につながるものがなく、途切れてしまうのが、作品に入れない原因だったように思う。振付家のレイトンが、観客とのコミュニケーションの取り方を知っている人だけに、ワクワクしなかったのがちょっと残念。

オディール・デュボック「PROJET DE LA MATIERE」
懐かしい93年の作品。出演者のほとんどが初演時のままで、ボリス・シャルマッツがいて、ペドロ・パウエルがいる。ほとんどの出演者が中堅として活躍している顔ぶれというところに、時間の流れを感じた。ちょと体型が変わり、求める方向が変わったからなのか、10年ほど前に見たときと印象が違ったが、よく出来ている作品というのは、どんな状況でも生彩を失わないという事を実感した。感情のない、物質的な動きの中にも、他との関わりがあり、質が変容していくのが感じられる。音楽があり、静止がある。見ているだけなのに、ダンサーが触れているものの温度や質が感じられ、不思議な感覚が残るのがこの作品の特徴だ。一つ気になったのが、体型をきれいに見せないだぶついた衣裳。妙な古くささが気になった。(9月20日クレテイユ・メゾン・デ・ザール)


2002年に初演された時は、あまり良い評判を聞かなかったが、個人的には結構気に入っていた。幕開きの、風になびくブルーのカーテンが不吉な予感をもたらし、さらにそれを助長するかのような使用人ジョセフと彼が落とす石の音。そして揺れる炎。その陰気な雰囲気を一瞬にして明るくしたのが、天から降ってきた大量の花。石でも降ってきたのかと思うような音にびっくりして瞬きをすると、そこは花の咲き乱れる楽園に変わっていた。そこで幼いキャサリンとヒースクリフが仲良く遊んでいる。まるで恋人のように。しかしその横には絶えずヒンドリーがつきまとう。風によってくの字型に曲がった木の下でうずくまるヒンドリーの影。絵柄的にはとても良く出来ているのだが、複雑な人間関係と感情のもつれをたった2時間で語るには無理があったのではないか。1幕はよくわかるのだが、2幕がストーリーを追うのに精一杯になっている感がある。その2幕では、ヒンドリーがヒースクリフと争って死に、ヒースクリフの息子が死に、最後にヒースクリフも死ぬという悲劇が続くのだが、瞬きしたら既に死んでいたという感じ。例えばヒンドリーとヒースクリフの争いは、長い棒を使って動きもコンビネーションもよく出来ているのだが、そのわりにヒンドリーの最後が余りにもあっけない。このようなあっけない死に方が続き、感情が揺さぶられる事はなく、一つの事実としてだけ記憶に残る程度なのが気になる。絵柄的に美しいシーンや、動きのコンビネーションの面白さがあるのに、物語を通しての感動がないのが非常に惜しい。メロドラマにしたくない気持ちはわかるが、ピントが絞り切れていない感じがした。この日の配役は、キャサリンにマリー=アニエス・ジロ、ヒースクリフにニコラ・ル・リッシュ、エドガーにジャン=ギヨーム・バール。(9月24日オペラ座・ガルニエ)

(C)Anne Deniau

今シーズンのテアトル・ド・ラ・ヴィルの幕開きは、注目株のシディ・ラルビ・チェルカウイ。日本でもアクラム・カーンとのデュエットで高評を得たと聞いた。新作「MYTH」は、14人のダンサーと役者にミュージシャンを加えての、3部構成2時間という大作。図書館のような設定で、書庫と長椅子があり、本を読む人が何人かいる。するとどこからともなく「影」が出てきて、閲覧室の人々につきまとうが、普通の人にはその影が見えないから、本が落ちてくるのもつまづくのも、よくある出来事としか思わない。この「影」のいたずらが小悪魔的でめちゃ面白いし、身体がぐねぐねに柔らかい人もいて、人間業には見えない。時には忍者のように身軽に飛んだりぶら下がったり。一方、音楽は中世のもの、しかも生演奏なので、心が和む。2階建てという立体構成の上、舞台のあちこちでいろんな事が起こっていて、全く隙のない綿密な構成。ダンサー、役者共に個性の強い人たちばかりで、刻々と変わる状況にワクワクしながら見ていた。ダンスと芝居と音楽の見事な融合。と、感心したのはよいが、これが延々と続くと飽きるもの。最後に3メートルはあるような大きな重い扉が開くのは感動的なはずなのだが、そこに行くまでに観客が疲れてしまったのは誠に残念。日本人ダンサーの工藤聡がシャープな動きでいい味を出していたが、立ち回りをしたり、日本語の神妙な台詞は、日本人から見るとありふれた東洋趣味に転じてしまい、ちょっと興ざめだった。(9月25日テアトル・ド・ラ・ヴィル)

(C)koenbroos
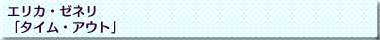
男3人が何やら騒がしく音を立てる。うまく歯車が合わず、待っていたものが来た時には既に時遅し、もう1人は別の行動に出ているといった動きの連続。このずれがテンポよく展開する。例えば組み立て式のテーブルの、脚を置いて、さて、上板を運んでくると、もう1人が脚を別の場所に移動していて、上板を乗せられないといった具合。次に面白かったのが、常に舞台に3人がいるという構図。それぞれが何かをしていて、1人が幕にはいると、すっと別の人がどこからともなく舞台に出てくる。この辺りのビミョーなタイミングが非常に良く出来ていて、漫才かコントを見ているよう。今度は女性3人が男性と同じ構図で動くのだが、、、、なぜか面白みに欠ける。後半は人の出入りやトリックではなく、舞台後方から前への直線の構成となる。それなりによく構成されているのだが、前半に比べると平坦になってしまったようだ。(9月27日エトワール・デュ・ノール)
 (C)DR (C)DR
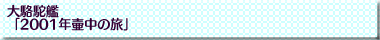
いやあ、久々に楽しい舞台を見ました。山海塾だけが舞踏だと思っている人は強烈なパンチを食らったようで、「あな恐ろしや~」と言っていたスノッブなフランス人のおばさんがいたが、ダンスの玄人と日本人は大喜び。幕開きの眠れる森の美女のパロディには腹を抱えて笑ったし(会場が静かだったので、そっと笑いましたが)、ちゃぶ台の踊りは、フランス人には到底わからないだろうなあと、ちょっと悲しいような優越感のような気持ちで見たし、素っ裸の電車ごっこに巨大◯◯◯◯には、度肝を抜かれた。麿赤兒は芸術監督になり、向雲太郎が振付けをするが、大駱駝艦の精神はしっかり受け継がれている事を実感。来年またフランスで、センセーショナルな公演をしてくれる事を心から待ち望んでおります。(10月4日パリ日本文化会館)

(C)Matsuda Junichi
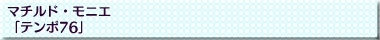
舞台全面に敷かれた芝生の緑と、薄暗い白っぽい明かりの中に人が浮かび上がる。ゆっくり辺りを見回し動き始める。どこからともなく出てきたもう1人が、その人と同じ動きをする。ふと気がつくと、3人目が同じ動きをしている。と、4人目…。いつの間にか同じ衣裳を着た人が何人もいて、皆同じ動きをしている。今夏のモンペリエダンスが初演で、その初日の前に催されたプレスコンフェランスで「ユニゾンをやってみた」という彼女の言葉に、「あなたにとってはユニゾンかもしれないが、傍から見ているとちっとも動きが揃っていませんが。」とジャーナリストに突っ込まれて爆笑したのを思い出した。ここ数年の彼女の作品の傾向は、集団の動きの中の個性だったと思う。その集団がこの作品では、本当にユニゾンになっていた。モニエの言葉は本当だったのだ。同じ衣裳に同じ動き。日本ではよくある傾向だが、ヨーロッパで、特にフランスでユニゾンというのは滅多にないため、確かに新鮮だった。揃って動いているうちに、1人がずれて別の動きが始まる。芝生をちぎったりくしゃみをしたり、泣いたり笑ったり。日常のシーンもある。その繰り返しを見ながら頭に浮かんだのは、踊りとは何か? という事。踊りと動きは違う。なぜダンサーが身体表現をするのか? 役者では出来ないのだろうか? ダンスとは何なのか? そんな疑問と同時に、多くのものがグローバル化され、他と同じ行動をしていれば、とりあえずは安全だという現代思考、それによる個性の抹消、日常の行動の形式化という構図が見えてきた。芝生の匂いが唯一改ざん出来ない自然の摂理に見えて、背筋が寒くなるのを感じた。モニエならではの社会批判か。芝生の間から顔を出す不思議な物体が、バクテリアのお化けみたいでかわいかった。(10月9日テアトル・ド・ラ・ヴィル)

(C)Marc Coudrais

噴水の回りで儀式の踊りのようなものが始まる。絶対的なものを求めるような視線が怪しくミステリアス。大きな鳥かごに入れられた男が落ちる。生まれたばかりの赤子のようだ。身体についた血を洗い、母のような女性に抱きしめられる男性。ちょっと宗教的で、内面の動きを求め、ミニマリズムになりがちな今のコンテンポラリーの流れに逆らったような作品。悪く言えば、90年代後半によくあったような作品だが、形ばかりを気にして中身の薄い作品が増えた現在において、振付、構成、テーマがはっきりしている点に好感を持った。前述のマチルド・モニエの作品で、踊りとは何ぞやという疑問にかられた直後だっただけに、久々にしっかり振付けされた舞踊作品を観たという満足感に浸った。今後も地道に続けてほしい。(10月11日エトワール・デュ・ノール)
 (C)Jef Rabillon (C)Jef Rabillon

日本人アーティストが活躍するカンパニー、クビライ・カーン・アンヴェスティガシオンは、今シーズン、クレルモン=フェラン(フランス中央部に位置し、ミネラルウオーターのヴォルヴィックの生産地)でレジデンスをしている。その活動を紹介するイベント「星座」が行われた。まず、芸術高等学校にて、カンパニーのリーダーのフランク・ミシュレッティのワークショップに参加した学生たちによるパフォーマンスと展示が、15分毎に学校内の場所を移動しながら行われた。面白かったのが、等身大の人形と女性のダンス。人形を身体の前にたすきがけでつけた女性が、人形に生を吹き込んだかのように操る様は、興味深かった。約3時間に渡り学校内でパフォーマンスが行われ、夜はコメディ劇場でカンパニーの作品が2本上演された。
「ソロー・ラブ・ソング」
村上春樹の「ねじまき鳥クロニクル」を題材とした作品で、私のお気に入り作品。しかし今回が最後の上演になるそうで、非常に残念。ダンサーの1人が、現在求めているものと、この作品を創作した時との隔たりがありすぎて、もう踊れないというのが理由のようだが、代役を立てず、初演メンバーの意志を尊重した決断は、なかなか出来るものではないと思う。この辺りの裏話に、またこの作品への思い入れが強くなってしまった。さて、作品は、大和田類が舞台上で音をミックスし、福島たくみが叫ぶ。彼女は本来はミュージシャンで、バイオリンをかき鳴らしたり奏でるのだが、舞台人としての素質があり、その存在感には一目を置いている。また、舞台上にミキサーを置き、客席に背中を向けて音をミックスする作品も珍しいが、大和田の作業を見ていると、音に舞台に広がっていくのが感じられ、音も作品の重要な一部である事が納得できる。際立って良かったのが、間宮千晴の踊り。ぶれがなく、明確でシャープな動きが小気味よく、そこに彼女ならではの「間」が入り、優しさと強さと、でも時々投げかける冷めた目が、1人の繊細な人物像として浮かび上がる。それに加えて、彼女の低いささやきと、細い歌声が作品に大きな意味をもたらす。装置はすっきりしているのに、立体的な構成で、照明の微妙な色使いが美しい。最後の公演に立ち会えたのは幸運だったが、またもう一度見たい気持ちに変わりはない。

(C)Laurent Thurin Nal
「MONDES、MONDE」
ミシュレッティは欲の深い人だ。ここ数年、作品ごとにがらりと傾向が変わっているように思う。この作品は、静かな幕開きだった。だだっ広い空間に、彫刻の様に存在する人。いや、ゆっくり動いているから、彫刻ではないか。下手端には何が起こっても微動だせずに寝ている人がいる。ふらふらと出てきたアフロヘアーの男性は、手をゆらゆらとなびかせながら時々アクロバットをする。静かな描写が続いたかと思うと、突然始まる暴力的な男女関係。奥に潜んでいたものが堰を切って出てきたよう。このように描写は変化に富んでいるのだが、各シーンが長く感じられたのは、振付けが平坦だったからだと思う。スタジオのような、観客とダンサーの距離が近い空間の方が良かったのではないか。(以上2作、10月13日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

(C)Pierre Vigna

ドイツの振付家サシャ・ワルツがオペラ座に振りつけると聞いて期待したのだが、古典版のロミジュリを念頭においてしまったからか、どうにもついていけなかった。この物語が、長い事語り継がれ、何度見ても感動するのは、憎しみあう事の愚かさと、愛の強さ、そして悲劇の引き金となる時のいたずらによるものだと思う。しかし、ワルツ版は、さらりと事が済んでしまう。まず、両家の憎しみが見えて来ない。白い衣裳の人々と、黒い衣裳の人々が混じり合い、何事もなく過ぎて行く。ロミオとジュリエットの出会いも、最初から仕組まれたようで、感動がない。バルコニーの場面は、2人の踊りより、ぐいーんと持ち上がる装置に目が行ってしまった。この装置はよく出来ていて、まず白い厚手の板が持ち上がり2階建てとなり、それがさらに持ち上がって壁のように立ちはだかる。シンプルなのに多くを語る。さて、ダンスに戻ろう。物語の登場人物はとりあえず全員出てくるが、象徴的すぎて具体的な行動がないため、ぼんやりしていると話がどこまで進んだかわからなくなってしまう。こう書くと、こきおろしているようだが、素晴らしいところも、もちろんある。立ちはだかる壁に何度もよじ上っては落下するロミオ。両家の隔たりを超えて、運命に立ち向かっているようだ。無音のため、壁にしがみつくように登る足音と、落下するときの擦れる音。やるせなさがダイレクトに伝わってくる。そして、ジュリエットが死んだと思い込んだロミオが毒を飲み(これももう少し劇的にしてほしかった)、小石に埋まったジュリエットをかき出し、接吻すると、なんとジュリエットの腕が動くではないか。そして息を吹き返したばかりのジュリエットを抱きしめ、再会を喜んだのもつかの間、毒が回ったロミオは息絶えてしまう。このタイミング、喜びから悲しみへ一瞬のうちに転落する描写には息をのんだ。そう、このような感動がもっと全面に欲しかった。あまりにもすっきりしすぎていたように思った。ダンスを観にきた私にとっては、たった1人の歌手の存在が、20人のダンサーより強いのが悔しかったが、自然と引き寄せられてしまうほどのオーラと存在感は確かに素晴らしいものだった。ちなみに音楽は、ベルリオーズ版ロミオとジュリエット。この日の出演は、ジュリエットにオーレリー・デュポン、ロミオにエルヴェ・モロー。古典作品と全く違う、ワルツならではの作品創りを体験出来た事は、ダンサー達にとって大きな収穫だったようだ。(10月15日オペラ・バスティーユ)

(C)Bernd Uhlig
エトワール・デュ・ノールの新企画、特定の地方と協力して、その地方のカンパニーを紹介するシリーズ。第1回目はロワール地方。
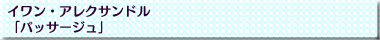
路上パフォーマンスで、車輪のついた買い物バッグを持ち、手首に小さなライトをつけた白い衣裳の女性が現れた。天使がいたずらして人間に化けたような印象を持った。ちょっとお茶目で、ちょっとフツーの人とは違って、もしかしたら空中にふわりと浮かんでしまうかもという雰囲気。犬の散歩に出た人に関わるも、その人が全く気がつかなかったのは、彼女が天使で人間の気配がなかったから? 横断歩道に立ち、走る車に関わろうとするのは、道を急ぎ、目的地しか見ない現代人への皮肉に見えた。

(C)DR

踊りのうまい男性3人を見るのは実に気持ちがよい。鈍角に曲がった棒が三本天井から下がり、これが速度差を付けて回転すると、思わぬところで空間が変化する。また、この棒の中にライトが仕込んであり、不思議な空間が浮かび上がるなど、アイディアは面白いし、踊りもうまいし、振付けも、特にコンタクトのコンビネーションがよく出来ている。なのに後半に飽きてしまう。もっと広い舞台が似合っていると言った人がいたので、再度見てみたい。

(C)DR
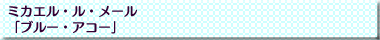
ヒップホップのストリート系の3人の若者。同じ男3人でも、上記の「五つ目の季節」の直後なので、レベルの差がはっきりと見えてしまったのは、運が悪いとしかいいようがない、と思っているうちに、どんどん引きつけられてしまった。まず、ビデオがよく出来ていて、3人をモチーフにしたいくつかのイメージに、映像の必然性が見える。踊りとマッチしているし、さりげなくコラボレーションするところが上手い。彼らが素直に得意な芸を見せ、それを楽しんでいるのも好感的。センスが良いので、今後も期待が出来る。(以上3作品、10月18日エトワール・デュ・ノール)
 (C)Cie S'poart.BYE ABDEL (C)Cie S'poart.BYE ABDEL
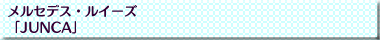
今注目の若手フラメンコダンサー。小柄なのにそれを感じさせない存在感の大きさが売り物だ。今回はタイプの違う2人の美男子ダンサー2人を従えての新作。私が好きなのは、中に入りすぎず、グッと集中した後に「どお? 良い動きでしょ?」と観客に投げかける瞬間。才能にあぐらをかかず、ちょっと謙虚に、でも確固たる自信を秘めて観客に見せる視線がたまらない。その一瞬、空気がふーっと流れ、彼女の人柄が見えてくる。今回も、最初は表情が硬かったが次第に柔らかくなり、やがて笑みがこぼれる。彼女は彼女の踊るダンスと会話しているようだ。それがとても心地よい。カーテンコールでのミュージシャンを交えての即興は何とも楽しく、メトロのストのストレスも忘れて足取り軽く家路についた。(10月19日レ・ジェモー)

(C)Frédéric Néry

何とも彼らしいユーモアたっぷりの作品だった。シモン・ラットル指揮のベルリン交響楽団が「春の祭典」を練習する風景からヒントを得たと言う。確かに指揮者の動きは、時に見ている方がびっくりするほどの動きをして、汗だくの人もいる。ロワもそんなところに目をつけてこの作品を創ったそうだ。赤いTシャツにジーンズというラフな格好で、何の装飾もない舞台の中央に、後ろ向きに立つ。かの有名な春祭の始まりを、まるで彼の間の前にオーケストラがいるかのように指揮し始める。あーん、後ろ向きじゃあ何も見えないよおと思っていたら、くるりと向きを変えてくれた。表情、手の動きが細やかに、激しく、大きく変わる。観客がオーケストラだというかのように、客席に指示を出す。かとおもうと、突然舞台隅に行ってしまいしばらく考え込んだりする。本物の指揮者が彼の動きを見たら、そんなのあり得ないと言うかもしれないが、指揮者をパロる点ではよく出来ている。ただ、ロワならではの毒が甘かったように思った。指揮者のパロディーが、演奏を超えて別の次元にまで行ってしまうのではないかと勝手に期待した方が悪かったのかな?(10月20日ポンピドー・センター/フェスティバル・ドートンヌ)

(C)Vincent Cavaroc

目の覚めるような色の花が一面にホリゾントを飾っている。次に出てきたのが、招き猫。電動で手がこまねく奴だ。土に埋もれて首だけが出ている女性が、ポップスに合わせて歌っているうちに、手が出る足が出る、さらにもう一人土の中から飛び出してくる。このパプニングと招き猫に魅せられたわけではないが、80分という長丁場があっという間。子供の遊び、家族を亡くした悲しみ、怒り、一人でいる事の不安、恋愛。。。次々と日常の断片の展開にぐいぐいと引き込まれる。「助け合うために皆がいるのさ」というタイトル通り、人との関係がよく見えるのが作品に入りやすい理由の一つだ。そして、歌あり、芝居あり。何より踊りの必然性がちゃんと見えるのがよい。出演者が、外観からは想像もしないような事を平気でやってしまうのも、意表をついて面白い。個性豊かな6人が織りなす人間模様、と言ってしまえば一言で済んでしまうが、見なくては個性の豊かさと展開の面白さを語る事は出来ない。(10月22日バンブ劇場)

(C)DR
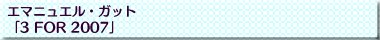
 イスラエルの新鋭振付家エマニュエル・ガットが3作品を携えてやっとパリにやってきた! と期待したのだが、何かを見失ったガットを見たようだった。ガットのソロの「マイ・フェヴォリット・シングス」は、前回見たときよりもメリハリがあり、とにかく彼が踊りがうまい人だというのを見せてくれる。テクニックを見せるわけでもないが、動きの節々に踊りのうまさが光っているのは誰が見ても明白。男性2人のデュオの「プティ・トーン・ド・ダンサ」と、ガットを含む8人に振りつけた「中央を通って、みんなが、同時にそして止まらないで」は、踊りとは何かという疑問を残した。素晴らしく上手いダンサー達が踊るので、全てがそつなく展開される。ただ、見終わった後、心に残るものがない。私にとっては「冬の旅」の緊張感、「春の祭典」の淡々とした展開の最後に見せる演出が衝撃的だったし、初演の「K626」での、今までに見た事のないものをどう評するかと言う、難しい課題に直面していただけに、今回の3作品、特にソロを除く2作品は、すっと身体を通り過ぎていったものでしかなかった。なぜか。おそらく、ダンサー同士の会話がない事と、このダンサーではなくてはダメだと言う、強烈な個性が感じられなかった事が原因なのではないかと思う。どんなに技術があって完璧に踊っても、そこにプラスされる何かが感じられなくては何も心に残らない。彼の中で何かが変わりつつあるのだと思うが、イスラエルからマルセイユに本拠地を移したとの事で、環境の変化があるのかもしれない。(10月25日クレテイユ・メゾン・デザール) イスラエルの新鋭振付家エマニュエル・ガットが3作品を携えてやっとパリにやってきた! と期待したのだが、何かを見失ったガットを見たようだった。ガットのソロの「マイ・フェヴォリット・シングス」は、前回見たときよりもメリハリがあり、とにかく彼が踊りがうまい人だというのを見せてくれる。テクニックを見せるわけでもないが、動きの節々に踊りのうまさが光っているのは誰が見ても明白。男性2人のデュオの「プティ・トーン・ド・ダンサ」と、ガットを含む8人に振りつけた「中央を通って、みんなが、同時にそして止まらないで」は、踊りとは何かという疑問を残した。素晴らしく上手いダンサー達が踊るので、全てがそつなく展開される。ただ、見終わった後、心に残るものがない。私にとっては「冬の旅」の緊張感、「春の祭典」の淡々とした展開の最後に見せる演出が衝撃的だったし、初演の「K626」での、今までに見た事のないものをどう評するかと言う、難しい課題に直面していただけに、今回の3作品、特にソロを除く2作品は、すっと身体を通り過ぎていったものでしかなかった。なぜか。おそらく、ダンサー同士の会話がない事と、このダンサーではなくてはダメだと言う、強烈な個性が感じられなかった事が原因なのではないかと思う。どんなに技術があって完璧に踊っても、そこにプラスされる何かが感じられなくては何も心に残らない。彼の中で何かが変わりつつあるのだと思うが、イスラエルからマルセイユに本拠地を移したとの事で、環境の変化があるのかもしれない。(10月25日クレテイユ・メゾン・デザール)

(C)Thomas Ammerpohl

彼女を見ていると、子供の頃から現在までの様々な時代の思い出が蘇ってくる。日常の描写と移り行く心情風景が丁寧に積み重ねられていく。それが自分の思い出と重なる。前半の現代舞踊的な振付けより、後半に見せる彼女ならではの動きが好きだった。(10月30日エスパス・ベルタン・ポワレ)
 (C)KôS (C)KôS
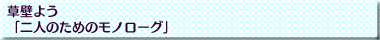
草壁よう振付けによる彼自身とフィリップ・デュクーのデュオ。暗闇の中でぼんやりと光が舞う。明るくなったりくもったり。時に身体を照らし、時にぼんやりと天井を照らすだけの不思議な光。それと対照的につけられたライターの現実味を帯びた炎。浮かび上がる男の顔。個性的な男2人が、子供のように元気に踊りまくる。極めつけは、突然客席で鳴った携帯電話にアドリブで答えた草壁のタイミングの良さ。これはなかなか出来るものではない。わざと携帯を鳴らしたのかと思ったほど。ダンサーとしてだけでなく、舞台人としての草壁が光っていた。最後、そうめんと青江三奈の歌には笑った。始まりのミステリアスな光から青江三奈。この落差が草壁らしいのかも。(10月30日エスパス・ベルタン・ポワレ)

|

